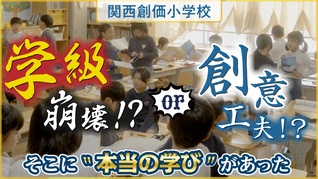〈SUAリポート〉 識者が語るアメリカ創価大学
〈SUAリポート〉 識者が語るアメリカ創価大学
2023年10月13日
SUA「地球的問題群研究センター」総合顧問
アンドレア・バルトリ博士
SUA「地球的問題群研究センター」総合顧問
アンドレア・バルトリ博士
人類貢献の人材を輩出し続けるアメリカ創価大学(SUA、カリフォルニア州・アリソビエホ市)。その発展を世界の識者はどう見ているのか。「平和と対話のための聖エジディオ財団」の会長で、昨年、SUAに設置された「地球的問題群研究センター」(テツシ・オガタセンター長)の総合顧問に就任した、アンドレア・バルトリ博士に語ってもらった。
人類貢献の人材を輩出し続けるアメリカ創価大学(SUA、カリフォルニア州・アリソビエホ市)。その発展を世界の識者はどう見ているのか。「平和と対話のための聖エジディオ財団」の会長で、昨年、SUAに設置された「地球的問題群研究センター」(テツシ・オガタセンター長)の総合顧問に就任した、アンドレア・バルトリ博士に語ってもらった。
◆世界市民の模範として 相互理解広げる挑戦を
◆世界市民の模範として 相互理解広げる挑戦を
――博士は現在、アメリカ創価大学(SUA)の理事を務められ、昨年、同大学に設置された「地球的問題群研究センター」の総合顧問に就任されました。
「地球的問題群研究センター」は、昨年、SUAに設置されたばかりの“新しい”研究所ですが、その起源をたどると、とても“歴史が深い”ことが分かります。
SUA創立者の池田大作SGI(創価学会インタナショナル)会長は、1987年に発表した第12回「SGIの日」記念提言で、「全地球的問題の解決に世界の英知を集め、科学的、総合的にアプローチするための研究施設」として、「地球的問題群研究センター」の設立を提案しました。
この時に示されたビジョンに基づいて、昨年、SUAに設置されたのが同センターです。
――博士は現在、アメリカ創価大学(SUA)の理事を務められ、昨年、同大学に設置された「地球的問題群研究センター」の総合顧問に就任されました。
「地球的問題群研究センター」は、昨年、SUAに設置されたばかりの“新しい”研究所ですが、その起源をたどると、とても“歴史が深い”ことが分かります。
SUA創立者の池田大作SGI(創価学会インタナショナル)会長は、1987年に発表した第12回「SGIの日」記念提言で、「全地球的問題の解決に世界の英知を集め、科学的、総合的にアプローチするための研究施設」として、「地球的問題群研究センター」の設立を提案しました。
この時に示されたビジョンに基づいて、昨年、SUAに設置されたのが同センターです。

世界市民を輩出する教育の殿堂として、発展を続けるアメリカ創価大学のキャンパス
世界市民を輩出する教育の殿堂として、発展を続けるアメリカ創価大学のキャンパス
偉大な仕事は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。
同センターが、提言の発表から、35年の歳月を経て設置されたという事実は、池田会長のアイデアが、一過性の小さなものではなく、長い時を経た今でも色あせることのない、極めて重大な提案であったことの証しだと思います。
また会長が、指示や命令ではなく、あくまで「提案」したことに対して、後継の人々が、その意思をくんで実現し、実践しているところに、同センターの限りない未来性が表れているのではないでしょうか。
どの地球課題も、若い世代が受け継ぎ、長期的に取り組むことが、解決策を得る唯一の方法だからです。
――具体的には、どのような取り組みをされているのですか。
主に「世界市民教育」と「核軍縮」を焦点にしています。
まず、「世界市民教育」では、池田会長が提言で言及した「世界市民教育の教科書」の作成を推進しています。今はその前段階として、幼児期から高校レベルまでの教育機関で活用できるカリキュラムの作成を進め、この取り組みに関心がある教育者の相互交流も促進しています。
また、「核軍縮」については、SUA同窓生の代表による、核廃絶のためのワーキンググループを結成し、学術界の専門家や研究者、市民社会、宗教団体等とのネットワークを広げます。学生や若手専門家を集めた多国間のワークショップも実施する予定です。本年6月には、SUAで、核軍縮教育の夏季セミナーを開催し、九つの大学・大学院から16人の学生らが集い、核なき世界に向けた課題などを学び合いました。
偉大な仕事は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。
同センターが、提言の発表から、35年の歳月を経て設置されたという事実は、池田会長のアイデアが、一過性の小さなものではなく、長い時を経た今でも色あせることのない、極めて重大な提案であったことの証しだと思います。
また会長が、指示や命令ではなく、あくまで「提案」したことに対して、後継の人々が、その意思をくんで実現し、実践しているところに、同センターの限りない未来性が表れているのではないでしょうか。
どの地球課題も、若い世代が受け継ぎ、長期的に取り組むことが、解決策を得る唯一の方法だからです。
――具体的には、どのような取り組みをされているのですか。
主に「世界市民教育」と「核軍縮」を焦点にしています。
まず、「世界市民教育」では、池田会長が提言で言及した「世界市民教育の教科書」の作成を推進しています。今はその前段階として、幼児期から高校レベルまでの教育機関で活用できるカリキュラムの作成を進め、この取り組みに関心がある教育者の相互交流も促進しています。
また、「核軍縮」については、SUA同窓生の代表による、核廃絶のためのワーキンググループを結成し、学術界の専門家や研究者、市民社会、宗教団体等とのネットワークを広げます。学生や若手専門家を集めた多国間のワークショップも実施する予定です。本年6月には、SUAで、核軍縮教育の夏季セミナーを開催し、九つの大学・大学院から16人の学生らが集い、核なき世界に向けた課題などを学び合いました。

本年6月、「地球的問題群研究センター」の主催で開催された核軍縮教育の夏季セミナー(アメリカ創価大学で)
本年6月、「地球的問題群研究センター」の主催で開催された核軍縮教育の夏季セミナー(アメリカ創価大学で)
――ウクライナ情勢に伴い、核戦争の脅威が高まっているこの時代に、若い世代を巻き込んで核軍縮について学ぶことは意義深いですね。
核の脅威は、全ての人類の運命に関係する大きな課題の一つです。
核兵器を“必要なもの”とする考え方の根底には、「他者への恐れ」があります。他の誰かが核兵器を使うかもしれないという恐怖心から、より多くの核兵器で身を守るべきだという発想が生まれ、その結果、際限のない核開発競争に陥った人類は、地球上のあらゆる人々を死に至らしめるだけの大量の核兵器を生み出しました。
しかし、忘れてはいけないのは、“恐れている他者”もまた、同じ人間であるという紛れもない事実です。
本年5月に広島で行われたG7サミット(先進7カ国首脳会議)では、史上初めて、各国の首脳がそろって被爆地の広島平和記念資料館(原爆資料館)等を訪れましたが、大切なことは、核兵器は広島と長崎の人々の上に落とされたのではなく、私たち「人類」の上に落とされたのだと認識することではないでしょうか。
民族や国家というアイデンティティーを超え、「人類」としてのアイデンティティーを持った人々、すなわち「世界市民」を育て、世界中にネットワークを広げることが、核廃絶、そして平和構築への重要な一歩であると考えています。
――“世界市民の要件”として、池田先生は、ニューヨークのコロンビア大学ティーチャーズ・カレッジで行った講演「『世界市民』教育への一考察」(1996年6月)の中で、①生命の相関性を深く認識しゆく「智慧の人」②人種や民族や文化の“差異”を恐れず、尊重し、理解し、成長の糧としゆく「勇気の人」③身近に限らず、遠いところで苦しんでいる人々にも同苦し、連帯しゆく「慈悲の人」の3点を挙げました。
まさしく地球的問題群解決への条件としても置き換えられる、重要な要件だと思います。
私は、コロンビア大学での池田会長の講演を直接拝聴しました。非常に印象的だったのは、会長が一つ一つの言葉に信念を込めて話をされていたことでした。単に、考えを共有するだけではなく、本気で何かを変えようという強い意志を感じる講演でした。
イタリア生まれでカトリック信徒の私は、1992年に35歳でニューヨークに渡り、すぐに研究者としてコロンビア大学で働き始めました。
講演に参加した当時、私は“一人の若き移民”だったのです。
会長の講演を聴きながら、私は胸を熱くしました。多くの課題が集まるニューヨークという場所で、イタリア移民のカトリック信徒である私が、日本の仏教者である池田会長と出会い、心から共感し合えている。そのこと自体が、平和という一つの目的に向かう時、人類は差異を超えて、「人間」として一つになれるということを象徴するような出来事だと思ったからです。
この講演は、私のような移民にも、大きな可能性があることを心から実感できた、かけがえのない体験となりました。
――ウクライナ情勢に伴い、核戦争の脅威が高まっているこの時代に、若い世代を巻き込んで核軍縮について学ぶことは意義深いですね。
核の脅威は、全ての人類の運命に関係する大きな課題の一つです。
核兵器を“必要なもの”とする考え方の根底には、「他者への恐れ」があります。他の誰かが核兵器を使うかもしれないという恐怖心から、より多くの核兵器で身を守るべきだという発想が生まれ、その結果、際限のない核開発競争に陥った人類は、地球上のあらゆる人々を死に至らしめるだけの大量の核兵器を生み出しました。
しかし、忘れてはいけないのは、“恐れている他者”もまた、同じ人間であるという紛れもない事実です。
本年5月に広島で行われたG7サミット(先進7カ国首脳会議)では、史上初めて、各国の首脳がそろって被爆地の広島平和記念資料館(原爆資料館)等を訪れましたが、大切なことは、核兵器は広島と長崎の人々の上に落とされたのではなく、私たち「人類」の上に落とされたのだと認識することではないでしょうか。
民族や国家というアイデンティティーを超え、「人類」としてのアイデンティティーを持った人々、すなわち「世界市民」を育て、世界中にネットワークを広げることが、核廃絶、そして平和構築への重要な一歩であると考えています。
――“世界市民の要件”として、池田先生は、ニューヨークのコロンビア大学ティーチャーズ・カレッジで行った講演「『世界市民』教育への一考察」(1996年6月)の中で、①生命の相関性を深く認識しゆく「智慧の人」②人種や民族や文化の“差異”を恐れず、尊重し、理解し、成長の糧としゆく「勇気の人」③身近に限らず、遠いところで苦しんでいる人々にも同苦し、連帯しゆく「慈悲の人」の3点を挙げました。
まさしく地球的問題群解決への条件としても置き換えられる、重要な要件だと思います。
私は、コロンビア大学での池田会長の講演を直接拝聴しました。非常に印象的だったのは、会長が一つ一つの言葉に信念を込めて話をされていたことでした。単に、考えを共有するだけではなく、本気で何かを変えようという強い意志を感じる講演でした。
イタリア生まれでカトリック信徒の私は、1992年に35歳でニューヨークに渡り、すぐに研究者としてコロンビア大学で働き始めました。
講演に参加した当時、私は“一人の若き移民”だったのです。
会長の講演を聴きながら、私は胸を熱くしました。多くの課題が集まるニューヨークという場所で、イタリア移民のカトリック信徒である私が、日本の仏教者である池田会長と出会い、心から共感し合えている。そのこと自体が、平和という一つの目的に向かう時、人類は差異を超えて、「人間」として一つになれるということを象徴するような出来事だと思ったからです。
この講演は、私のような移民にも、大きな可能性があることを心から実感できた、かけがえのない体験となりました。

SUAの至る所で見られる麗しい友情の語らい
SUAの至る所で見られる麗しい友情の語らい
――この「智慧・勇気・慈悲」を兼ね備えた世界市民の育成を教育理念に掲げるSUAに対する期待と、「地球的問題群研究センター」のこれからの展望をお聞かせください。
すでに、はっきりと道は示されています。
SUAの同窓生が模範となって、世界中の人々に「世界市民」というアイデンティティーを持ってもらえるよう努めていくことです。
池田会長がそうであるように、模範となる生き方を通して、人間のあるべき姿を示し、異文化の人々と相互理解を広げていく挑戦を貫いてもらいたいと思います。
人類が一つになることを願っている人々は、世界中にたくさんいます。その一人一人と手を取り合い、ネットワークを広げていっていただきたいのです。諦めず、幻滅せず、偏見を持たず、粘り強くチャレンジしていくことが重要です。
「地球的問題群研究センター」は、その世界市民のネットワークを構築するための、アンカー(錨)の役割を果たし得る機関です。
それは、平和という課題について、いかなる変化にも対応できる、柔軟で強靱な安定性と安心感を生み出す存在だということです。
現代において、最も困難な地球規模の問題に対する現実的な解決策を模索しながら、平和の構築へ、世界市民のネットワークを大きく広げゆくことこそ、同センターとSUAの使命であると信じています。
――この「智慧・勇気・慈悲」を兼ね備えた世界市民の育成を教育理念に掲げるSUAに対する期待と、「地球的問題群研究センター」のこれからの展望をお聞かせください。
すでに、はっきりと道は示されています。
SUAの同窓生が模範となって、世界中の人々に「世界市民」というアイデンティティーを持ってもらえるよう努めていくことです。
池田会長がそうであるように、模範となる生き方を通して、人間のあるべき姿を示し、異文化の人々と相互理解を広げていく挑戦を貫いてもらいたいと思います。
人類が一つになることを願っている人々は、世界中にたくさんいます。その一人一人と手を取り合い、ネットワークを広げていっていただきたいのです。諦めず、幻滅せず、偏見を持たず、粘り強くチャレンジしていくことが重要です。
「地球的問題群研究センター」は、その世界市民のネットワークを構築するための、アンカー(錨)の役割を果たし得る機関です。
それは、平和という課題について、いかなる変化にも対応できる、柔軟で強靱な安定性と安心感を生み出す存在だということです。
現代において、最も困難な地球規模の問題に対する現実的な解決策を模索しながら、平和の構築へ、世界市民のネットワークを大きく広げゆくことこそ、同センターとSUAの使命であると信じています。
〈プロフィル〉
Andrea Bartoli
イタリア生まれ。ミラノ大学で公衆衛生学の博士号を取得。アメリカに移住し、コロンビア大学で国際紛争解決センターを設立するなど、平和教育に貢献。ジョージ・メイソン大学の紛争分析・解決学部の学部長、シートンホール大学外交・国際関係学部の学部長などを歴任。現在「平和と対話のための聖エジディオ財団」で会長を務める。
〈プロフィル〉
Andrea Bartoli
イタリア生まれ。ミラノ大学で公衆衛生学の博士号を取得。アメリカに移住し、コロンビア大学で国際紛争解決センターを設立するなど、平和教育に貢献。ジョージ・メイソン大学の紛争分析・解決学部の学部長、シートンホール大学外交・国際関係学部の学部長などを歴任。現在「平和と対話のための聖エジディオ財団」で会長を務める。
◆SUAが24期生を募集中!
◆SUAが24期生を募集中!
SUAでは現在、2024年度に入学する学士課程24期生を募集しています。
出願資格者は、高等学校卒業もしくは同等の資格を持つ者。定員は130人程度。
選考では、高校の成績、TOEFLまたはDuolingoのスコア、推薦書、エッセー、課外活動などが総合的に考慮されます。
出願は、明年1月15日まで(必着)。
早期合格発表の希望者は、本年11月1日までに出願する必要があります。
入試情報の詳細はSUAのホームページへ。
SUAでは現在、2024年度に入学する学士課程24期生を募集しています。
出願資格者は、高等学校卒業もしくは同等の資格を持つ者。定員は130人程度。
選考では、高校の成績、TOEFLまたはDuolingoのスコア、推薦書、エッセー、課外活動などが総合的に考慮されます。
出願は、明年1月15日まで(必着)。
早期合格発表の希望者は、本年11月1日までに出願する必要があります。
入試情報の詳細はSUAのホームページへ。
◆動画「アメリカ創価大学キャンパスツアー2023」
◆動画「アメリカ創価大学キャンパスツアー2023」
現役学生の河合裕美さん(3年生)を案内役に、動画による「アメリカ創価大学キャンパスツアー2023」を開催!
SUAの魅力あふれるスペシャル動画はこちらから。
現役学生の河合裕美さん(3年生)を案内役に、動画による「アメリカ創価大学キャンパスツアー2023」を開催!
SUAの魅力あふれるスペシャル動画はこちらから。
※SUAリポートのバックナンバーが無料で読めます!
※SUAリポートのバックナンバーが無料で読めます!
※ご感想をお寄せください。
kansou@seikyo-np.jp
※ご感想をお寄せください。
kansou@seikyo-np.jp