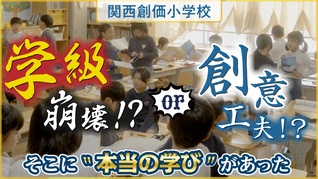9C319D6AF2A62E9EB64BE5C3FC3DB96F
あす池田先生の環境提言発表20周年
あす池田先生の環境提言発表20周年
2022年8月25日
あす26日は池田先生が環境提言「地球革命への挑戦――持続可能な未来のための教育」を発表して20周年。同提言で示された理念に基づき、創価学会およびSGIは、持続可能な社会の建設へ運動を進めてきた。東京都市大学大学院の佐藤真久教授へのインタビューと併せて特集する。
あす26日は池田先生が環境提言「地球革命への挑戦――持続可能な未来のための教育」を発表して20周年。同提言で示された理念に基づき、創価学会およびSGIは、持続可能な社会の建設へ運動を進めてきた。東京都市大学大学院の佐藤真久教授へのインタビューと併せて特集する。
持続可能な未来を私たち一人一人の手で
持続可能な未来を私たち一人一人の手で
1960年代から70年代にかけて、経済発展が物質的な豊かさをもたらす一方で、地球環境は悪化が進んだ。先進国では公害が社会問題化し、途上国では貧困が深刻な課題となっていた。
そうした中で72年、世界的シンクタンクであるローマクラブが『成長の限界』を発表。地球資源は有限であることが指摘され、「かけがえのない地球」をテーマにした同年の国連人間環境会議(ストックホルム会議)では、環境に配慮した経済・社会の開発が呼び掛けられた。その後87年に「持続可能な開発」の概念が提唱され、環境と開発を共存させる形として、「将来世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」が示された。
環境問題への関心が高まる中で開かれた92年の国連環境開発会議(地球サミット)では、持続可能な開発は人類が安全に繁栄する道であることが確認され、今後の行動計画などが定められた。同会議ではさらに、持続可能な開発を実現する上での教育の重要性が強調された。
こうした国際社会の取り組みを後押しするべく、池田先生は2002年8月26日、「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(ヨハネスブルクサミット)に寄せて環境提言を発表。目指すべき教育の方向性などについて提案を行った。
提言で先生は、地球環境問題の解決には法制度の整備といった“上からの改革”とともに、それを支え、後押しする民衆レベルの連帯を築く“下からの改革”が不可欠と指摘。一人一人が環境問題をわが事として捉え、共通の未来のために力を合わせていく原動力は教育であるとし、①地球環境問題の現状を知り、学ぶこと②持続可能な未来を目指し、生き方を見直すこと③問題解決のために、ともに立ち上がり、具体的な行動に踏み出すためのエンパワーメント、という三つの段階に基づく教育の在り方を提案した。
また、10年後の2012年には、国連持続可能な開発会議(リオ+20)に寄せて、さらに議論を深めた提言「持続可能な地球社会への大道」を発表している。
1960年代から70年代にかけて、経済発展が物質的な豊かさをもたらす一方で、地球環境は悪化が進んだ。先進国では公害が社会問題化し、途上国では貧困が深刻な課題となっていた。
そうした中で72年、世界的シンクタンクであるローマクラブが『成長の限界』を発表。地球資源は有限であることが指摘され、「かけがえのない地球」をテーマにした同年の国連人間環境会議(ストックホルム会議)では、環境に配慮した経済・社会の開発が呼び掛けられた。その後87年に「持続可能な開発」の概念が提唱され、環境と開発を共存させる形として、「将来世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」が示された。
環境問題への関心が高まる中で開かれた92年の国連環境開発会議(地球サミット)では、持続可能な開発は人類が安全に繁栄する道であることが確認され、今後の行動計画などが定められた。同会議ではさらに、持続可能な開発を実現する上での教育の重要性が強調された。
こうした国際社会の取り組みを後押しするべく、池田先生は2002年8月26日、「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(ヨハネスブルクサミット)に寄せて環境提言を発表。目指すべき教育の方向性などについて提案を行った。
提言で先生は、地球環境問題の解決には法制度の整備といった“上からの改革”とともに、それを支え、後押しする民衆レベルの連帯を築く“下からの改革”が不可欠と指摘。一人一人が環境問題をわが事として捉え、共通の未来のために力を合わせていく原動力は教育であるとし、①地球環境問題の現状を知り、学ぶこと②持続可能な未来を目指し、生き方を見直すこと③問題解決のために、ともに立ち上がり、具体的な行動に踏み出すためのエンパワーメント、という三つの段階に基づく教育の在り方を提案した。
また、10年後の2012年には、国連持続可能な開発会議(リオ+20)に寄せて、さらに議論を深めた提言「持続可能な地球社会への大道」を発表している。
●提言を元に推進 “変革の主体者”の意識育む活動
●提言を元に推進 “変革の主体者”の意識育む活動

ブラジルのマナウス市郊外にある、アマゾン創価研究所が実施するフィールドワーク(2019年)。同研究所は植樹活動や貴重な種子の採取・保存などを通して熱帯雨林の再生に尽力。環境教育啓発プロジェクトには市内の公立学校の児童・生徒2万5000人以上が参加してきた
ブラジルのマナウス市郊外にある、アマゾン創価研究所が実施するフィールドワーク(2019年)。同研究所は植樹活動や貴重な種子の採取・保存などを通して熱帯雨林の再生に尽力。環境教育啓発プロジェクトには市内の公立学校の児童・生徒2万5000人以上が参加してきた

SGIが制作支援した映画「静かなる革命」を用いた韓国・ソウル保健大学(当時)の授業(2003年)。「一人の人間が世界を変えていく」をテーマにした同映画は、地球評議会が制作し、国連環境計画、国連開発計画が協力したもので、大学の授業等でも活用された
SGIが制作支援した映画「静かなる革命」を用いた韓国・ソウル保健大学(当時)の授業(2003年)。「一人の人間が世界を変えていく」をテーマにした同映画は、地球評議会が制作し、国連環境計画、国連開発計画が協力したもので、大学の授業等でも活用された

沖縄・北谷町での「わたしと地球の環境展」(2014年)。同展は国連の取り組みを後押しする草の根の活動として、学会が「21世紀環境展」に続いて制作。SGIでは地球憲章インタナショナルと共に「希望と行動の種子」展など環境展示を制作し、世界各地を巡回してきた
沖縄・北谷町での「わたしと地球の環境展」(2014年)。同展は国連の取り組みを後押しする草の根の活動として、学会が「21世紀環境展」に続いて制作。SGIでは地球憲章インタナショナルと共に「希望と行動の種子」展など環境展示を制作し、世界各地を巡回してきた

楽しくSDGsを学んで実践し、その様子を共有できるスマートフォンアプリ「マプティング」
楽しくSDGsを学んで実践し、その様子を共有できるスマートフォンアプリ「マプティング」

「マプティング」は日本語など5言語に対応し、SDGsの各目標に関連する地球憲章の理念も学ぶ機能等が反響を呼んでいる(2017年、アメリカ・ニューヨーク)
「マプティング」は日本語など5言語に対応し、SDGsの各目標に関連する地球憲章の理念も学ぶ機能等が反響を呼んでいる(2017年、アメリカ・ニューヨーク)
〈インタビュー〉 東京都市大学大学院 佐藤真久教授
〈インタビュー〉 東京都市大学大学院 佐藤真久教授
ESD(持続可能な開発のための教育)の特徴の一つは、社会と個人の変化の連動を強く意識する点にあります。従来、教育の議論は、それを受ける「人の変化」に重きが置かれがちでした。一方、社会の在り方を見直す議論では、私たちそのものの変革と結び付けて考える発想が往々にして弱かった。
ESDの視点は社会を変えるために学び、社会に関わる中で自らの在り方を変えていくところにあります。社会を「変える」と自分が「変わる」の連動の中で変革を起こすという点に、本質があるのです。
そうした考えから、近年ESDの議論において、社会や世界の課題を踏まえて「自分はどうあるべきか」「どうありたいか」と内省するプロセスの重要性が強調されています。その点、池田SGI会長が提言で指摘された「生き方を見直す」との視座は、今日的な知見とも非常に響き合っています。
また、SDGs(持続可能な開発目標)における重要なメッセージの一つは、「先進国が変わる」ということです。つまり、もし世界を変えたいのなら、技術支援や資金協力を通して“途上国を変えればよい”ということではなく、先進国自身も変わる努力が不可欠になってくる。「変わる」と「変える」の連動という視点は、ローカルなレベルでもグローバルなレベルでも重要なのです。そうした意味で私は、貴会が進められている「人間革命」――すなわち、社会や世界の変革を自分の変革とつなげて考えるという実践は非常に本質的だと思います。
とりわけ2000年代以降、世界が「VUCA」と呼ばれる不確実で予測不可能な時代に突入してくる中で、さまざまな面で社会から余裕が失われてきたという印象を強くしています。そうした状況では、人々が自らの考えや基準を押し付け、自分さえよければいいとする傾向が強まりがちです。その結果“正しさ”の衝突が起きてくる。実際、コロナ禍への対応や気候変動問題などでも、そうした事態が見られます。
ゆえに求められるのは、“相手も正しいかもしれない”と考えてみること。まさに「内省」のプロセスです。と同時に、相手と向き合い、対話する中で自分も変わっていこうという姿勢です。社会が不確実で予測不能だからこそ、生涯を通して学び、他の人たちとコミュニケーションし続け、自分の考え方を検証し、時々の最適解を更新し続ける――そうした姿勢が、これからの時代は一段と必要だろうと思います。
こうした中で、私は仏法の「依正不二」という理念に注目しています。私たちは自分と他者、内部と外部といった区切りを設けがちですが、グローバル化によって、現代はさまざまなものがつながる“外部のない時代”を迎えています。だからこそ、人と環境・国土は分かちがたく結び付いているとする「依正不二」のような視点を、SDGs、ESDの文脈でも再認識させる必要があります。こうしたつながりの認識は、自分さえよければいいという姿勢を抑え、他者や自然に対する配慮を生むことにつながるでしょう。
昨年、ユネスコが発刊した書籍で、社会の不確実性や予測不可能性は今後も深まっていくとの予測が示されました。こうした状況下で大切なことは、変化の中を共に生きていく仲間の存在です。多元的、多層的なものの捉え方を持った人たちが対話を続けながら、共に互いの“解”を更新していける関係性を築くことができたなら、変化や不確実性はストレスにならないし、分断や衝突を乗り越え、持続可能な社会を推進していく大きな力となるでしょう。
貴会には世界各地に会員がおられます。会員という点では同じでも、それぞれ個性があり多様ですから、互いに学び合いながら人間革命の捉え方、依正不二というメッセージを足元から広げていくことができれば、貴会そのものがESDを推進する重要な場になるのではないでしょうか。(聞き手=南秀一)
ESD(持続可能な開発のための教育)の特徴の一つは、社会と個人の変化の連動を強く意識する点にあります。従来、教育の議論は、それを受ける「人の変化」に重きが置かれがちでした。一方、社会の在り方を見直す議論では、私たちそのものの変革と結び付けて考える発想が往々にして弱かった。
ESDの視点は社会を変えるために学び、社会に関わる中で自らの在り方を変えていくところにあります。社会を「変える」と自分が「変わる」の連動の中で変革を起こすという点に、本質があるのです。
そうした考えから、近年ESDの議論において、社会や世界の課題を踏まえて「自分はどうあるべきか」「どうありたいか」と内省するプロセスの重要性が強調されています。その点、池田SGI会長が提言で指摘された「生き方を見直す」との視座は、今日的な知見とも非常に響き合っています。
また、SDGs(持続可能な開発目標)における重要なメッセージの一つは、「先進国が変わる」ということです。つまり、もし世界を変えたいのなら、技術支援や資金協力を通して“途上国を変えればよい”ということではなく、先進国自身も変わる努力が不可欠になってくる。「変わる」と「変える」の連動という視点は、ローカルなレベルでもグローバルなレベルでも重要なのです。そうした意味で私は、貴会が進められている「人間革命」――すなわち、社会や世界の変革を自分の変革とつなげて考えるという実践は非常に本質的だと思います。
とりわけ2000年代以降、世界が「VUCA」と呼ばれる不確実で予測不可能な時代に突入してくる中で、さまざまな面で社会から余裕が失われてきたという印象を強くしています。そうした状況では、人々が自らの考えや基準を押し付け、自分さえよければいいとする傾向が強まりがちです。その結果“正しさ”の衝突が起きてくる。実際、コロナ禍への対応や気候変動問題などでも、そうした事態が見られます。
ゆえに求められるのは、“相手も正しいかもしれない”と考えてみること。まさに「内省」のプロセスです。と同時に、相手と向き合い、対話する中で自分も変わっていこうという姿勢です。社会が不確実で予測不能だからこそ、生涯を通して学び、他の人たちとコミュニケーションし続け、自分の考え方を検証し、時々の最適解を更新し続ける――そうした姿勢が、これからの時代は一段と必要だろうと思います。
こうした中で、私は仏法の「依正不二」という理念に注目しています。私たちは自分と他者、内部と外部といった区切りを設けがちですが、グローバル化によって、現代はさまざまなものがつながる“外部のない時代”を迎えています。だからこそ、人と環境・国土は分かちがたく結び付いているとする「依正不二」のような視点を、SDGs、ESDの文脈でも再認識させる必要があります。こうしたつながりの認識は、自分さえよければいいという姿勢を抑え、他者や自然に対する配慮を生むことにつながるでしょう。
昨年、ユネスコが発刊した書籍で、社会の不確実性や予測不可能性は今後も深まっていくとの予測が示されました。こうした状況下で大切なことは、変化の中を共に生きていく仲間の存在です。多元的、多層的なものの捉え方を持った人たちが対話を続けながら、共に互いの“解”を更新していける関係性を築くことができたなら、変化や不確実性はストレスにならないし、分断や衝突を乗り越え、持続可能な社会を推進していく大きな力となるでしょう。
貴会には世界各地に会員がおられます。会員という点では同じでも、それぞれ個性があり多様ですから、互いに学び合いながら人間革命の捉え方、依正不二というメッセージを足元から広げていくことができれば、貴会そのものがESDを推進する重要な場になるのではないでしょうか。(聞き手=南秀一)