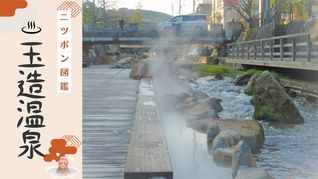〈Seikyo Gift〉 ワールドトゥデイ 世界の今――世界一自由な都市アムステルダム
〈Seikyo Gift〉 ワールドトゥデイ 世界の今――世界一自由な都市アムステルダム
2025年10月25日
オランダの首都アムステルダムは世界一自由な都市と呼ばれる。昔も今も、世界中から人々が移り住む同市の学会員を取材した。(3月6日付)
オランダの首都アムステルダムは世界一自由な都市と呼ばれる。昔も今も、世界中から人々が移り住む同市の学会員を取材した。(3月6日付)

世界遺産に登録されているアムステルダムの運河地区。運河と歴史的建造物が織りなす美しい景観は、世界経済の「要」であった17世紀当時の面影をそのまま残す
世界遺産に登録されているアムステルダムの運河地区。運河と歴史的建造物が織りなす美しい景観は、世界経済の「要」であった17世紀当時の面影をそのまま残す
「世界は神がつくったが、オランダはオランダ人がつくった」との言葉がある。オランダは現在でも国土の4分の1が海面より低い。その多くが、13世紀以降の干拓事業によって、「自力で造り出した」土地だ。
アムステルダムも高潮の被害を防ぐために、アムステル川の河口に“ダム”を築いたのが歴史の始まり。本年で誕生から750年を迎える。
運河と歴史的建造物が織りなす美しいアムステルダムの景観が形成されたのは、17世紀。商業都市として機能させるべく、中心街の外側に何本も運河を扇状に掘り、沼地を街へと変えた。
当時のオランダは世界経済の「要」であり、アムステルダムは世界最古とされる証券取引所がつくられるなど、商業と金融の中心地として栄えた。出自や思想で取引相手を選別することは、ビジネスに何の意味も持たない。
アムステルダムは、多様な民族、宗教を持った人々が多数流入する「移民都市」となり、さまざまなよそ者、民族、宗教の異端者をも積極的に包摂していく政策が取られていった。
「世界は神がつくったが、オランダはオランダ人がつくった」との言葉がある。オランダは現在でも国土の4分の1が海面より低い。その多くが、13世紀以降の干拓事業によって、「自力で造り出した」土地だ。
アムステルダムも高潮の被害を防ぐために、アムステル川の河口に“ダム”を築いたのが歴史の始まり。本年で誕生から750年を迎える。
運河と歴史的建造物が織りなす美しいアムステルダムの景観が形成されたのは、17世紀。商業都市として機能させるべく、中心街の外側に何本も運河を扇状に掘り、沼地を街へと変えた。
当時のオランダは世界経済の「要」であり、アムステルダムは世界最古とされる証券取引所がつくられるなど、商業と金融の中心地として栄えた。出自や思想で取引相手を選別することは、ビジネスに何の意味も持たない。
アムステルダムは、多様な民族、宗教を持った人々が多数流入する「移民都市」となり、さまざまなよそ者、民族、宗教の異端者をも積極的に包摂していく政策が取られていった。

建物には、自然光を取り入れるたくさんの窓がある
建物には、自然光を取り入れるたくさんの窓がある
アムステルダムを池田大作先生は4回訪れている。
3度目の訪問となった1973年(昭和48年)5月。パリからの帰国の経由地として、スキポール空港に約1時間滞在する予定だったが、機材トラブルで出発が4時間ほど遅れた。
先生は長旅の疲労で、数日前から微熱が続いていた。しかし、出迎えたメンバーに「皆さんの題目に引き寄せられたんだね」と語り、「公園かどこかで、座談会を行いましょう」と提案した。
空港から車で30分ほどのアムステル公園で「青空座談会」を。先生は一人一人に近況を尋ね、仕事や病気の悩みなどの質問に答えた。「皆さんは、世界広布の尊い使命を担って、今、このオランダに集った地涌の菩薩です。皆さんこそ、人びとの苦悩の闇を晴らす、希望の太陽なんです」
アムステルダムを池田大作先生は4回訪れている。
3度目の訪問となった1973年(昭和48年)5月。パリからの帰国の経由地として、スキポール空港に約1時間滞在する予定だったが、機材トラブルで出発が4時間ほど遅れた。
先生は長旅の疲労で、数日前から微熱が続いていた。しかし、出迎えたメンバーに「皆さんの題目に引き寄せられたんだね」と語り、「公園かどこかで、座談会を行いましょう」と提案した。
空港から車で30分ほどのアムステル公園で「青空座談会」を。先生は一人一人に近況を尋ね、仕事や病気の悩みなどの質問に答えた。「皆さんは、世界広布の尊い使命を担って、今、このオランダに集った地涌の菩薩です。皆さんこそ、人びとの苦悩の闇を晴らす、希望の太陽なんです」

市の人口は約90万人。180を超える国籍の人々が暮らす
市の人口は約90万人。180を超える国籍の人々が暮らす
座談会はオープンダイアローグ(開かれた対話)の場
座談会はオープンダイアローグ(開かれた対話)の場
あの日から半世紀――今、アムステルダムでは毎月、約40会場で座談会が開かれる。1月21日夜、郊外のバウテンフェルデルト地区の座談会を取材した。
19時30分から、アルゼンチン出身のメリッサー・スタウツ地区女子部長の導師で勤行・唱題を。20時からはインド出身の女子部チャルー・バンサルさんの司会で、それぞれが自己紹介。
オランダ人はもちろん、イタリア、ポルトガル、韓国、アルゼンチン、インドと国籍は多様。友人も2人参加していた。会話は全員、母国語ではない英語で。オランダ語しか話せない高齢者がいる時などは、誰かが通訳するという。
オランダSGIでは毎月、座談会で研鑽するテーマを決めている。1月は「人間革命」。同SGIの機関誌「インディゴ」に掲載された池田先生の指導を皆で読み、その後、「人間革命はあなたにとって何を意味する?」などの定められた質問に、各人が答える形で会合は進む。
あの日から半世紀――今、アムステルダムでは毎月、約40会場で座談会が開かれる。1月21日夜、郊外のバウテンフェルデルト地区の座談会を取材した。
19時30分から、アルゼンチン出身のメリッサー・スタウツ地区女子部長の導師で勤行・唱題を。20時からはインド出身の女子部チャルー・バンサルさんの司会で、それぞれが自己紹介。
オランダ人はもちろん、イタリア、ポルトガル、韓国、アルゼンチン、インドと国籍は多様。友人も2人参加していた。会話は全員、母国語ではない英語で。オランダ語しか話せない高齢者がいる時などは、誰かが通訳するという。
オランダSGIでは毎月、座談会で研鑽するテーマを決めている。1月は「人間革命」。同SGIの機関誌「インディゴ」に掲載された池田先生の指導を皆で読み、その後、「人間革命はあなたにとって何を意味する?」などの定められた質問に、各人が答える形で会合は進む。

世界中から赴任した駐在員が多く住む、市郊外のバウテンフェルデルト地区の座談会
世界中から赴任した駐在員が多く住む、市郊外のバウテンフェルデルト地区の座談会
途中、友人の一人が質問した。「革命とは、大きな変化を起こすことなのか?」
イタリア人のギドー・ピアンタニダ地区部長が「不幸を幸福へと転じていくことかな」と答えると、他のメンバーも「人生の問題から価値を創造していく内面の変革だね」「その変化はそれで終わりではなく、どんどん好転させていく感じだよ」とそれぞれ意見を述べていく。ディスカッションは1時間ほど続き、座談会は終了した。
400年にわたって、「移民都市」の歴史を刻んできたアムステルダムでは、「自由と寛容」が何よりも重んじられる。17世紀の哲学者スピノザはユダヤ人の移民2世としてアムステルダムに生まれ、迫害に屈することなく、「意志とは何か」「自由とは何か」を世に問い続けた。
同じ時代を生きた哲学者ジョン・ロックも、イングランドの内戦からアムステルダムに亡命し、『寛容についての手紙』を執筆した。個人の意思を尊重する精神は現代のオランダにも受け継がれ、同性婚や安楽死も世界に先駆けて法制化されている。
ピアンタニダ地区部長は語る。「オランダでは意見を押し付けてはいけない。どこまでも心を開いた対話が大事なんだ。座談会はオープンダイアローグ(開かれた対話)の場。オランダの象徴だよ」
途中、友人の一人が質問した。「革命とは、大きな変化を起こすことなのか?」
イタリア人のギドー・ピアンタニダ地区部長が「不幸を幸福へと転じていくことかな」と答えると、他のメンバーも「人生の問題から価値を創造していく内面の変革だね」「その変化はそれで終わりではなく、どんどん好転させていく感じだよ」とそれぞれ意見を述べていく。ディスカッションは1時間ほど続き、座談会は終了した。
400年にわたって、「移民都市」の歴史を刻んできたアムステルダムでは、「自由と寛容」が何よりも重んじられる。17世紀の哲学者スピノザはユダヤ人の移民2世としてアムステルダムに生まれ、迫害に屈することなく、「意志とは何か」「自由とは何か」を世に問い続けた。
同じ時代を生きた哲学者ジョン・ロックも、イングランドの内戦からアムステルダムに亡命し、『寛容についての手紙』を執筆した。個人の意思を尊重する精神は現代のオランダにも受け継がれ、同性婚や安楽死も世界に先駆けて法制化されている。
ピアンタニダ地区部長は語る。「オランダでは意見を押し付けてはいけない。どこまでも心を開いた対話が大事なんだ。座談会はオープンダイアローグ(開かれた対話)の場。オランダの象徴だよ」

市内中心部を走るトラム(路面電車)
市内中心部を走るトラム(路面電車)
近年、精神医療でも注目される「オープンダイアローグ」。フィンランドで生まれたケアの手法で、困難を抱えた人と家族や医療者など、複数の人がその場で一緒に対話する。評価したり断定したりせず、その人をそのまま理解しようと努めることで、心の回復を目指していく。
バウテンフェルデルト地区の座談会はまさに、その実践の場のようだった。“こうした方がいいのに”と自分の考えを押し付ける人など誰もいない。“私はこう思うけど、あなたの考えはどう?”との問いかけに徹していた。
近年、精神医療でも注目される「オープンダイアローグ」。フィンランドで生まれたケアの手法で、困難を抱えた人と家族や医療者など、複数の人がその場で一緒に対話する。評価したり断定したりせず、その人をそのまま理解しようと努めることで、心の回復を目指していく。
バウテンフェルデルト地区の座談会はまさに、その実践の場のようだった。“こうした方がいいのに”と自分の考えを押し付ける人など誰もいない。“私はこう思うけど、あなたの考えはどう?”との問いかけに徹していた。
一人立つ精神――Stand-Alone Spirit
一人立つ精神――Stand-Alone Spirit
1月22日、アムステルダムの中心街・ゴッホ美術館近くの会場で開かれた青年座談会も同じような光景が広がっていた。
オランダ、イタリア、インド、フィリピン、日本、台湾。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーたちが、それぞれに思いを語っていく。
1月22日、アムステルダムの中心街・ゴッホ美術館近くの会場で開かれた青年座談会も同じような光景が広がっていた。
オランダ、イタリア、インド、フィリピン、日本、台湾。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーたちが、それぞれに思いを語っていく。

オランダ、イタリア、インド、フィリピン、日本、台湾――国や地域を超え、信頼の絆でつながる青年部メンバー
オランダ、イタリア、インド、フィリピン、日本、台湾――国や地域を超え、信頼の絆でつながる青年部メンバー
男子部のマサト・セザワさんは一昨年、ジャーナリストとして日本からアムステルダムに渡ってきた。当初は、日照時間が短く曇りばかりの冬の天気に気がめいり、食事も合わず、心晴れない日が続いた。
そんな時に参加した青年部の研修会。「オランダの人は自分の状況を事細かには語りません。しかし、皆それぞれ何かを抱えながら頑張っていることが分かって。そんな彼らの自立した信心に勇気づけられました」
“自分は一人ではない。けれども、一人立って戦おう”。そう祈り、仕事に向かう中、昨年制作したドキュメンタリー映画が高い評価を受けた。
家電や服、自転車など、あらゆるものを地域のボランティアが無料で修理してくれる、オランダ発祥の「リペアカフェ」を取り上げた作品だ。カフェには、コーヒーを飲みたいだけの人、ただおしゃべりを楽しみたい人なども集まる。
「座談会のような語り合える居場所の大切さを伝えたかった」とセザワさん。
男子部のマサト・セザワさんは一昨年、ジャーナリストとして日本からアムステルダムに渡ってきた。当初は、日照時間が短く曇りばかりの冬の天気に気がめいり、食事も合わず、心晴れない日が続いた。
そんな時に参加した青年部の研修会。「オランダの人は自分の状況を事細かには語りません。しかし、皆それぞれ何かを抱えながら頑張っていることが分かって。そんな彼らの自立した信心に勇気づけられました」
“自分は一人ではない。けれども、一人立って戦おう”。そう祈り、仕事に向かう中、昨年制作したドキュメンタリー映画が高い評価を受けた。
家電や服、自転車など、あらゆるものを地域のボランティアが無料で修理してくれる、オランダ発祥の「リペアカフェ」を取り上げた作品だ。カフェには、コーヒーを飲みたいだけの人、ただおしゃべりを楽しみたい人なども集まる。
「座談会のような語り合える居場所の大切さを伝えたかった」とセザワさん。

市民の最大の足は今も昔も自転車
市民の最大の足は今も昔も自転車
インド出身の女子部プリア・クラーナさんは、家族で一人、信心を貫く。「家庭でも仕事でも実証を大切にしてきました。ようやく義理の両親も学会に理解を示してくれるようになりました」
イタリア出身の女子部セレーナ・ジャジャニーさんも「オランダは自由だからこそ、一人一人が強くなければいけないよね」と。
クリエーターとして働く彼女は「学会活動からインスピレーションを得ている」と言う。小説『人間革命』『新・人間革命』を学ぶと、「池田先生に“一人立つ精神”を教えてもらっている気がする」と語る。
「自由と寛容」の天地に一人立ち、信仰の実証を示していく――青年の飛翔が新たなオランダ広布を開いている。
インド出身の女子部プリア・クラーナさんは、家族で一人、信心を貫く。「家庭でも仕事でも実証を大切にしてきました。ようやく義理の両親も学会に理解を示してくれるようになりました」
イタリア出身の女子部セレーナ・ジャジャニーさんも「オランダは自由だからこそ、一人一人が強くなければいけないよね」と。
クリエーターとして働く彼女は「学会活動からインスピレーションを得ている」と言う。小説『人間革命』『新・人間革命』を学ぶと、「池田先生に“一人立つ精神”を教えてもらっている気がする」と語る。
「自由と寛容」の天地に一人立ち、信仰の実証を示していく――青年の飛翔が新たなオランダ広布を開いている。
〈取材に協力してくださった方々〉アキコ・コテラさん、アイノ・トンダーさん
〈取材に協力してくださった方々〉アキコ・コテラさん、アイノ・トンダーさん
【参考文献】水島治郎著『隠れ家と広場――移民都市アムステルダムのユダヤ人』『反転する福祉国家 オランダモデルの光と影』、森川すいめい著『感じるオープンダイアローグ』
【参考文献】水島治郎著『隠れ家と広場――移民都市アムステルダムのユダヤ人』『反転する福祉国家 オランダモデルの光と影』、森川すいめい著『感じるオープンダイアローグ』
音声読み上げ