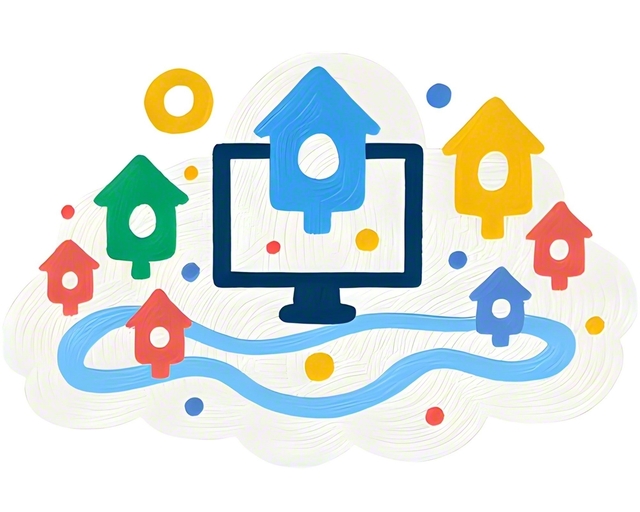〈AIと未来〉 駒崎弘樹さん×サイボウズ社長・青野慶久さん 「AI for Good」への挑戦(後編)
〈AIと未来〉 駒崎弘樹さん×サイボウズ社長・青野慶久さん 「AI for Good」への挑戦(後編)
2025年10月20日
連載「駒崎弘樹のAIと未来」では、「AIで人の孤独を減らせるのか?」というテーマに挑戦しながら、自治体や学校と一緒に実験を重ねている、「つながりAI」社長の駒崎弘樹さんがホストを務め、毎回さまざまな分野の人と、AIがもたらす未来をテーマに語り合います。
今回は、サイボウズ社長の青野慶久さんとの対談〈後編〉です。青野さんは、「『人にしかできないこと』を探す発想自体は、AI時代においては少し古いのではないか」と指摘します。その真意とは? 「AIの可能性」について語ってもらいました。
〈前編〉はこちらから読めます。
連載「駒崎弘樹のAIと未来」では、「AIで人の孤独を減らせるのか?」というテーマに挑戦しながら、自治体や学校と一緒に実験を重ねている、「つながりAI」社長の駒崎弘樹さんがホストを務め、毎回さまざまな分野の人と、AIがもたらす未来をテーマに語り合います。
今回は、サイボウズ社長の青野慶久さんとの対談〈後編〉です。青野さんは、「『人にしかできないこと』を探す発想自体は、AI時代においては少し古いのではないか」と指摘します。その真意とは? 「AIの可能性」について語ってもらいました。
〈前編〉はこちらから読めます。
■デジタル赤字とGAFA依存
■デジタル赤字とGAFA依存
――前編では、AIが企業や働き方をどう変えていくのかを中心に伺いました。ここからは、日本社会全体の課題についてお聞きします。最近は「デジタル赤字」という言葉を耳にしますが、これはどういう状況なのでしょうか。
青野 簡単に言えば、日本は「デジタル製品を作らず、ただ買っている国」になってしまった、ということです。
ニュースではインバウンド(外国人が日本に観光しにくること)で景気が良さそうに見えても、今や検索エンジンもSNSもクラウドサービスも、ほとんどが海外製なので、裏側では、グーグルやアップルなどGAFAと呼ばれる米巨大IT企業に巨額の資金が流出しています。
駒崎 たしかにSNSやクラウドといったサービスが外国企業のものだと、サービス利用や広告で生まれた「お金」や「データの価値」が外資の企業に流れていきます。
多くの人が「Youtube楽しい!」と動画を見ているその裏で、日本のお金が海外に流れていくわけですね。
青野 EUは、こうした巨大IT企業に対して、きちんとルールを設けています。
――調べてみると、EUはIT大手に厳しいルールを設けていますね。
①人のデータを勝手に集めたり、売らせたりしない(消去・開示の権利を保障)。
②一社だけが有利になる仕組みをやめさせ、乗り換えもしやすくする。
③危険な投稿や広告に素早く対処し、理由も説明させる。
青野 EUは、利用者の安全と、公正な競争への意識が強いんです。それこそ、違反すれば、EU以外の企業であっても、巨額の罰金が科されます。
一方で日本はこうした仕組みが弱く、無防備な状態が続いてきました。だからこそ“やられ放題”になってしまっているのです。
――なるほど……。日本は安全面、公正面の対処で出遅れ、経済面でいえば、デジタルの「貿易赤字」のような状態になっているんですね。
青野 日本全体にとって大きな課題です。
――前編では、AIが企業や働き方をどう変えていくのかを中心に伺いました。ここからは、日本社会全体の課題についてお聞きします。最近は「デジタル赤字」という言葉を耳にしますが、これはどういう状況なのでしょうか。
青野 簡単に言えば、日本は「デジタル製品を作らず、ただ買っている国」になってしまった、ということです。
ニュースではインバウンド(外国人が日本に観光しにくること)で景気が良さそうに見えても、今や検索エンジンもSNSもクラウドサービスも、ほとんどが海外製なので、裏側では、グーグルやアップルなどGAFAと呼ばれる米巨大IT企業に巨額の資金が流出しています。
駒崎 たしかにSNSやクラウドといったサービスが外国企業のものだと、サービス利用や広告で生まれた「お金」や「データの価値」が外資の企業に流れていきます。
多くの人が「Youtube楽しい!」と動画を見ているその裏で、日本のお金が海外に流れていくわけですね。
青野 EUは、こうした巨大IT企業に対して、きちんとルールを設けています。
――調べてみると、EUはIT大手に厳しいルールを設けていますね。
①人のデータを勝手に集めたり、売らせたりしない(消去・開示の権利を保障)。
②一社だけが有利になる仕組みをやめさせ、乗り換えもしやすくする。
③危険な投稿や広告に素早く対処し、理由も説明させる。
青野 EUは、利用者の安全と、公正な競争への意識が強いんです。それこそ、違反すれば、EU以外の企業であっても、巨額の罰金が科されます。
一方で日本はこうした仕組みが弱く、無防備な状態が続いてきました。だからこそ“やられ放題”になってしまっているのです。
――なるほど……。日本は安全面、公正面の対処で出遅れ、経済面でいえば、デジタルの「貿易赤字」のような状態になっているんですね。
青野 日本全体にとって大きな課題です。
■国産技術を育てる戦略
■国産技術を育てる戦略
――では、デジタル赤字から抜け出すために、日本はどうすればいいのでしょうか。
青野 単にAIを“使う”だけではなく、自分たちで基盤やプラットフォームを作る側に回らなければ、いつまでも同じ構図が続いていきます。ですから「使うだけでなく作る側」に回る必要があると思います。「国産の技術」を育てながら、“使う”と“作る”の両輪を回していくことが不可欠です。
駒崎 たしかに日本は人口が減少していますが、その中でも、日本独自のプラットフォームやミドルウエア(OS=オペレーティングシステムとアプリケーションの間に入って、両者の役割を補佐するソフトウエア)を育てれば、国内市場だけでなく海外展開も可能です。
とはいえ、検索エンジンやOSを今から国産で作るのは難しそうですが……。
青野 そうですね。ただ、自治体や企業向けの業務基盤なら十分に勝負できます。例えば「日本語のニュアンスを理解する業務アプリ」とか、「自治体業務に特化したAI基盤」とか。こうした分野であれば海外製品よりも日本が強みを出せるはずです。
駒崎 地味だけど、大事なところを押さえる、と。サッカーでいえば、華麗なドリブルよりも、泥臭い守備でチームの勝利に貢献するといったイメージですかね。
青野 そうかもしれない(笑)。何にせよ、勝つためには必要な戦略です。
――では、デジタル赤字から抜け出すために、日本はどうすればいいのでしょうか。
青野 単にAIを“使う”だけではなく、自分たちで基盤やプラットフォームを作る側に回らなければ、いつまでも同じ構図が続いていきます。ですから「使うだけでなく作る側」に回る必要があると思います。「国産の技術」を育てながら、“使う”と“作る”の両輪を回していくことが不可欠です。
駒崎 たしかに日本は人口が減少していますが、その中でも、日本独自のプラットフォームやミドルウエア(OS=オペレーティングシステムとアプリケーションの間に入って、両者の役割を補佐するソフトウエア)を育てれば、国内市場だけでなく海外展開も可能です。
とはいえ、検索エンジンやOSを今から国産で作るのは難しそうですが……。
青野 そうですね。ただ、自治体や企業向けの業務基盤なら十分に勝負できます。例えば「日本語のニュアンスを理解する業務アプリ」とか、「自治体業務に特化したAI基盤」とか。こうした分野であれば海外製品よりも日本が強みを出せるはずです。
駒崎 地味だけど、大事なところを押さえる、と。サッカーでいえば、華麗なドリブルよりも、泥臭い守備でチームの勝利に貢献するといったイメージですかね。
青野 そうかもしれない(笑)。何にせよ、勝つためには必要な戦略です。
■地方から始まるDXの新しい形
■地方から始まるDXの新しい形
駒崎 地方の課題についても考えてみたいと思います。個人的には今後、自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)が本当に重要になると思います。
職員の人手不足が深刻な中、AIが相談業務や情報整理を担い、人間は「人にしかできない対応」に集中する。そうすれば限られたリソースで機能を維持できます。
その点では、小さな自治体ほどフットワークが軽いですし、人口が少ないからこそ、全員参加型の仕組みができやすいのかもしれませんね。
青野 おっしゃる通りです。テクノロジーを駆使すれば、自治体だけでなく、病院や学校、福祉機関を横串でつなぎ、情報を共有しながらの連携も可能になります。
駒崎 それは面白いですね。
青野 実は、サイボウズは2025年9月に、愛媛県松山市と包括連携協定(自治体と民間企業が協力し、地域の課題解決を目指す連携)を結びました。
現在、愛媛県内のプロバスケットチーム「愛媛オレンジバイキングス」の運営に参画しています。
自社製品(kintone)を活用して、業務を効率化し、契約書や勤怠の管理をするなど、デジタル化に取り組んでいます。将来的には、チームに所属する選手のコンディション管理などにも生かしたいと考えています。
駒崎 バスケチーム運営については、うわさでは聞いていましたが、サイボウズさんが何で取り組むのだろうと少し不思議には思っていたんです。
青野 地域に根ざしたスポーツチームは、「住民・行政・企業を巻き込むハブ」になりやすく、関係者をつなぐ力があります。
ですから、DXによって、プロバスケチームの競争力が強化されれば、スポンサー企業をはじめ、さまざまな関係者にDXの必要性を認識してもらえると思うんです。
駒崎 なるほど。まち全体でDXが進めば、住民・行政・企業が同じ情報をリアルタイムで共有し、防災や交通、福祉などの課題をすぐに把握・連携できます。
そうなれば、高齢者の見守り情報や、地域の医療機関の空き状況を共有できるので、緊急時の支援や搬送が迅速に行えるようになる。
企業にとっても、地域の需要データや観光動向を分析できれば、新商品の開発やサービス改善に役立ち、売り上げ拡大や新規顧客の獲得につながりそう。他にもいろんな可能性が生まれそうですね。
駒崎 地方の課題についても考えてみたいと思います。個人的には今後、自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)が本当に重要になると思います。
職員の人手不足が深刻な中、AIが相談業務や情報整理を担い、人間は「人にしかできない対応」に集中する。そうすれば限られたリソースで機能を維持できます。
その点では、小さな自治体ほどフットワークが軽いですし、人口が少ないからこそ、全員参加型の仕組みができやすいのかもしれませんね。
青野 おっしゃる通りです。テクノロジーを駆使すれば、自治体だけでなく、病院や学校、福祉機関を横串でつなぎ、情報を共有しながらの連携も可能になります。
駒崎 それは面白いですね。
青野 実は、サイボウズは2025年9月に、愛媛県松山市と包括連携協定(自治体と民間企業が協力し、地域の課題解決を目指す連携)を結びました。
現在、愛媛県内のプロバスケットチーム「愛媛オレンジバイキングス」の運営に参画しています。
自社製品(kintone)を活用して、業務を効率化し、契約書や勤怠の管理をするなど、デジタル化に取り組んでいます。将来的には、チームに所属する選手のコンディション管理などにも生かしたいと考えています。
駒崎 バスケチーム運営については、うわさでは聞いていましたが、サイボウズさんが何で取り組むのだろうと少し不思議には思っていたんです。
青野 地域に根ざしたスポーツチームは、「住民・行政・企業を巻き込むハブ」になりやすく、関係者をつなぐ力があります。
ですから、DXによって、プロバスケチームの競争力が強化されれば、スポンサー企業をはじめ、さまざまな関係者にDXの必要性を認識してもらえると思うんです。
駒崎 なるほど。まち全体でDXが進めば、住民・行政・企業が同じ情報をリアルタイムで共有し、防災や交通、福祉などの課題をすぐに把握・連携できます。
そうなれば、高齢者の見守り情報や、地域の医療機関の空き状況を共有できるので、緊急時の支援や搬送が迅速に行えるようになる。
企業にとっても、地域の需要データや観光動向を分析できれば、新商品の開発やサービス改善に役立ち、売り上げ拡大や新規顧客の獲得につながりそう。他にもいろんな可能性が生まれそうですね。
■“Can”ではなく“Want”
■“Can”ではなく“Want”
――AI時代において、人間にしかできないことは何だと思いますか?
青野 私は「人にしかできないこと」を探す発想自体は、少し古いのではないかと思っています。
それよりも大事なことは「自分がやりたいことをやる」という視点ではないでしょうか。
例えば、ワインのテイスティング。AIに任せれば成分分析をして、「この味はこうです」と的確に説明してくれるでしょう。でも、人間は「うん、おいしいね」と言い合う、その体験を楽しんでいて、そこに価値を感じるわけですから、そこはAIに任せずに自分でやりたいところです。
駒崎 なるほど。“Can(できること)”ではなく“Want(やりたいこと)”こそ人間の領域だというわけですね。
青野 やりたいことまでAIに任せてしまうと、人間は幸せを失いますから。
だから日頃から、「自分は人生で何をしたいのか」「どんなことに喜びを感じるのか」を自問自答していくことが、AI時代には、より大事になってくるでしょう。
――AI時代において、人間にしかできないことは何だと思いますか?
青野 私は「人にしかできないこと」を探す発想自体は、少し古いのではないかと思っています。
それよりも大事なことは「自分がやりたいことをやる」という視点ではないでしょうか。
例えば、ワインのテイスティング。AIに任せれば成分分析をして、「この味はこうです」と的確に説明してくれるでしょう。でも、人間は「うん、おいしいね」と言い合う、その体験を楽しんでいて、そこに価値を感じるわけですから、そこはAIに任せずに自分でやりたいところです。
駒崎 なるほど。“Can(できること)”ではなく“Want(やりたいこと)”こそ人間の領域だというわけですね。
青野 やりたいことまでAIに任せてしまうと、人間は幸せを失いますから。
だから日頃から、「自分は人生で何をしたいのか」「どんなことに喜びを感じるのか」を自問自答していくことが、AI時代には、より大事になってくるでしょう。
■分断を超えるAIの可能性
■分断を超えるAIの可能性
――最後に、AIと社会の関係についてお聞きします。今、社会は分断の様相が強まっているように感じます。そのような社会にあって、AIは人と人を分断する道具になってしまうのか、それともつなぐ道具になり得るのか。
駒崎 両方の可能性があると思います。認知戦のようなAIの悪用によって分断は深まります。
でも、例えば教育の観点などからは、逆に格差を埋める力にもなり得ると思っています。
うちの子どもはChatGPTを「チャッピー」と呼んで、宿題を一緒にやっています(笑)。親や学校の先生に聞きづらいことでも気軽に質問できるので、これまで「できないまま」だったことがAIのおかげで補うことができるんです。
青野 いいですね、「チャッピー先生」(笑)。
私はここからがAIと社会の「第2ラウンド」だと思っています。第1ラウンドでは分断や対立を助長する使われ方もありました。
でも、これからは「良き使い方」で社会を豊かにする「第2ラウンド」の段階に入ります。
駒崎 「AI for Good」――AIを良き方向で活用していこうとする人間の意思は、どうすれば強くしていけるのか。各人、各組織のありようが問われています。
僕も自身のフィールドで、AIを活用しながら、孤立を防ぎ、人と人とがつながっていく世界をつくっていきたいと思います。
――最後に、AIと社会の関係についてお聞きします。今、社会は分断の様相が強まっているように感じます。そのような社会にあって、AIは人と人を分断する道具になってしまうのか、それともつなぐ道具になり得るのか。
駒崎 両方の可能性があると思います。認知戦のようなAIの悪用によって分断は深まります。
でも、例えば教育の観点などからは、逆に格差を埋める力にもなり得ると思っています。
うちの子どもはChatGPTを「チャッピー」と呼んで、宿題を一緒にやっています(笑)。親や学校の先生に聞きづらいことでも気軽に質問できるので、これまで「できないまま」だったことがAIのおかげで補うことができるんです。
青野 いいですね、「チャッピー先生」(笑)。
私はここからがAIと社会の「第2ラウンド」だと思っています。第1ラウンドでは分断や対立を助長する使われ方もありました。
でも、これからは「良き使い方」で社会を豊かにする「第2ラウンド」の段階に入ります。
駒崎 「AI for Good」――AIを良き方向で活用していこうとする人間の意思は、どうすれば強くしていけるのか。各人、各組織のありようが問われています。
僕も自身のフィールドで、AIを活用しながら、孤立を防ぎ、人と人とがつながっていく世界をつくっていきたいと思います。
【プロフィル】
あおの・よしひさ サイボウズ株式会社代表取締役社長。1971年、愛媛県生まれ。社内のワークスタイル変革を推進し、離職率を大幅に低減するとともに、3児の父として3度の育児休暇を取得。総務省、厚労省、経産省、内閣府、内閣官房の働き方変革プロジェクトの外部アドバイザーを歴任し、SAJ(一般社団法人ソフトウェア協会)筆頭副会長を務める。近年は「kintone AIラボ」を立ち上げ、クラウドとAIを融合した業務改善の研究開発を推進。人の創造性を支える存在としてAIを生かし、地域活性化をはじめとする社会課題の解決や、多様な働き方の実現に向けた未来像を打ち出している。
こまざき・ひろき つながりAI株式会社代表取締役社長。1979年、東京都生まれ。認定NPO法人フローレンスを創設し、病児保育やひとり親支援を先導してきた。2025年に「孤立をなくす」をミッションに掲げ、つながりAI株式会社を設立し、AIを活用した社会インフラづくりに挑む。自治体の窓口で相談を受ける「相談AI」、中学生など若者の声を匿名で受け止める「友達AI」、職場での孤立を和らげる「同僚AI」などを展開。さらに物資支援と相談AIを組み合わせた伴走モデルを実証し、AIと人の協働による新しい福祉モデルを模索する社会起業家。
※本コンテンツ内のイラストには、AI生成によるビジュアルが含まれます。
●最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご感想はこちらにお寄せください。
【プロフィル】
あおの・よしひさ サイボウズ株式会社代表取締役社長。1971年、愛媛県生まれ。社内のワークスタイル変革を推進し、離職率を大幅に低減するとともに、3児の父として3度の育児休暇を取得。総務省、厚労省、経産省、内閣府、内閣官房の働き方変革プロジェクトの外部アドバイザーを歴任し、SAJ(一般社団法人ソフトウェア協会)筆頭副会長を務める。近年は「kintone AIラボ」を立ち上げ、クラウドとAIを融合した業務改善の研究開発を推進。人の創造性を支える存在としてAIを生かし、地域活性化をはじめとする社会課題の解決や、多様な働き方の実現に向けた未来像を打ち出している。
こまざき・ひろき つながりAI株式会社代表取締役社長。1979年、東京都生まれ。認定NPO法人フローレンスを創設し、病児保育やひとり親支援を先導してきた。2025年に「孤立をなくす」をミッションに掲げ、つながりAI株式会社を設立し、AIを活用した社会インフラづくりに挑む。自治体の窓口で相談を受ける「相談AI」、中学生など若者の声を匿名で受け止める「友達AI」、職場での孤立を和らげる「同僚AI」などを展開。さらに物資支援と相談AIを組み合わせた伴走モデルを実証し、AIと人の協働による新しい福祉モデルを模索する社会起業家。
※本コンテンツ内のイラストには、AI生成によるビジュアルが含まれます。
●最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご感想はこちらにお寄せください。