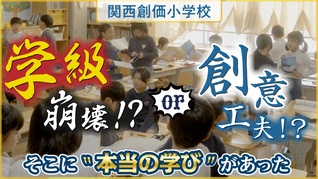自分も相手も生きたいように生きられる社会を築くには?――インタビュー㊤ 熊本大学大学院 苫野一徳准教授
自分も相手も生きたいように生きられる社会を築くには?――インタビュー㊤ 熊本大学大学院 苫野一徳准教授
2025年4月18日
- 〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉
- 〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉
価値観が多様化する現代社会。SNSの普及によって、誰もが意見を「自由」に発信できるようになりました。しかし、その中で過激な「対立」が生まれ、「分断」にまで至っているケースも見られます。一方で日常生活の人間関係においては、意見の「対立」を恐れるあまり、同じような意見を持つ人・気の合う人とばかり接したり、本音を話せるつながりが築けなかったりする人も、少なくないようです。多様で互いに異質な存在である私たちが、自分の自由も、相手の価値観も押しつぶされることなく、幸せに生きていくには、どうすればいいのでしょうか。哲学者・教育学者である苫野一徳・熊本大学大学院准教授は、その問いに答える営みを「公教育」から始めることを提唱し、学校や自治体の関係者との対話を通して協働してきました。上下2回にわたって、インタビューを掲載します。(聞き手=大宮将之、村上進)
価値観が多様化する現代社会。SNSの普及によって、誰もが意見を「自由」に発信できるようになりました。しかし、その中で過激な「対立」が生まれ、「分断」にまで至っているケースも見られます。一方で日常生活の人間関係においては、意見の「対立」を恐れるあまり、同じような意見を持つ人・気の合う人とばかり接したり、本音を話せるつながりが築けなかったりする人も、少なくないようです。多様で互いに異質な存在である私たちが、自分の自由も、相手の価値観も押しつぶされることなく、幸せに生きていくには、どうすればいいのでしょうか。哲学者・教育学者である苫野一徳・熊本大学大学院准教授は、その問いに答える営みを「公教育」から始めることを提唱し、学校や自治体の関係者との対話を通して協働してきました。上下2回にわたって、インタビューを掲載します。(聞き手=大宮将之、村上進)
■哲学者として
■哲学者として
――数多くある苫野さんのご著作を読みますと、繰り返し出てくるキーワードがあります。それが「自由」です。そして、そもそも「教育の目的」も、この「自由」を誰もが得られるようにするためにあると、おっしゃっていますね。
哲学者の仕事は、「そもそも◯◯って何だろう?」「そもそも◯◯って何のためだっけ?」と考え抜き、「本質」を明らかにしようとするものなんです。「めんどくさいな」と感じる人も、いるかもしれませんが(苦笑)。
「絶対に正しい答え」がないとされる問題について、「なるほど! ここまでなら確かに、誰もが深く納得できる!」という本質的な考えにたどり着くこと、たどり続けることに、哲学の命があります。
「自由」とは何か。教育の目的が、なぜ「自由に生きるため」なのか。まずは、ここから一緒に考えましょう。最後に「社会を変えるには『教育の力』と『“何のため”を問う対話』が大事」という点について、分かち合えたらうれしいです。
――数多くある苫野さんのご著作を読みますと、繰り返し出てくるキーワードがあります。それが「自由」です。そして、そもそも「教育の目的」も、この「自由」を誰もが得られるようにするためにあると、おっしゃっていますね。
哲学者の仕事は、「そもそも◯◯って何だろう?」「そもそも◯◯って何のためだっけ?」と考え抜き、「本質」を明らかにしようとするものなんです。「めんどくさいな」と感じる人も、いるかもしれませんが(苦笑)。
「絶対に正しい答え」がないとされる問題について、「なるほど! ここまでなら確かに、誰もが深く納得できる!」という本質的な考えにたどり着くこと、たどり続けることに、哲学の命があります。
「自由」とは何か。教育の目的が、なぜ「自由に生きるため」なのか。まずは、ここから一緒に考えましょう。最後に「社会を変えるには『教育の力』と『“何のため”を問う対話』が大事」という点について、分かち合えたらうれしいです。
■1万年の争い
■1万年の争い
――では、そもそも「自由」とは?
一言で言えば「生きたいように生きられること」。これは、動物にはおそらくあまり自覚的にはない、「人間的な欲望」と言えます。「生きたいように生きられていない」と感じる時、苦しみや「不幸だ」という感覚を覚えませんか? なぜなら、人間が本質的に「自由」を欲しているからです。
ただし「生きたいように生きる」といっても、「わがまま放題」に生きることではありません。わがまま放題をして、人の自由を奪うことになったら、相手はこちらにも害を加えてくるかもしれません。そうなったら、自分が「自由」に生きることはできませんよね?
人類は約1万年にわたって、そんな「争いの歴史」を経験してきました。土地や富を巡って戦争に次ぐ戦争が起き、凄惨な命の奪い合いが繰り返され、支配する者と支配される者が生まれたわけです。
――では、そもそも「自由」とは?
一言で言えば「生きたいように生きられること」。これは、動物にはおそらくあまり自覚的にはない、「人間的な欲望」と言えます。「生きたいように生きられていない」と感じる時、苦しみや「不幸だ」という感覚を覚えませんか? なぜなら、人間が本質的に「自由」を欲しているからです。
ただし「生きたいように生きる」といっても、「わがまま放題」に生きることではありません。わがまま放題をして、人の自由を奪うことになったら、相手はこちらにも害を加えてくるかもしれません。そうなったら、自分が「自由」に生きることはできませんよね?
人類は約1万年にわたって、そんな「争いの歴史」を経験してきました。土地や富を巡って戦争に次ぐ戦争が起き、凄惨な命の奪い合いが繰り返され、支配する者と支配される者が生まれたわけです。
どうすれば、そんな殺し合いを終わらせられるのか。大多数の人が不自由を強制される社会に、終止符を打てるのか。こうした問いに答える根本原理を示したのが、フランスのルソーやドイツのヘーゲルといった、哲学者たちでした。今から約250年前のことですから、人類の長い歴史から見れば“最近”ですね。
たどり着いた根本原理とは何か。それは「自由の相互承認」と呼ばれるものです。自分が社会の中で「自由」に、つまり「生きたいように生きる」ことを望むなら、他者の自由を侵害しないようにしながら、お互いが対等に「自由な存在」であること、お互いが自由に生きることを、認め合う以外にありません。
こうして、それぞれの「自由」と、「自由の相互承認」を保障するための「法(ルール)」がつくられ、「民主主義」社会の土台が築かれていったわけです。
どうすれば、そんな殺し合いを終わらせられるのか。大多数の人が不自由を強制される社会に、終止符を打てるのか。こうした問いに答える根本原理を示したのが、フランスのルソーやドイツのヘーゲルといった、哲学者たちでした。今から約250年前のことですから、人類の長い歴史から見れば“最近”ですね。
たどり着いた根本原理とは何か。それは「自由の相互承認」と呼ばれるものです。自分が社会の中で「自由」に、つまり「生きたいように生きる」ことを望むなら、他者の自由を侵害しないようにしながら、お互いが対等に「自由な存在」であること、お互いが自由に生きることを、認め合う以外にありません。
こうして、それぞれの「自由」と、「自由の相互承認」を保障するための「法(ルール)」がつくられ、「民主主義」社会の土台が築かれていったわけです。
■羅針盤を手に
■羅針盤を手に
――「自由の相互承認」と「教育の目的」が、どう関係するのでしょうか?
ルールによって「自由」と「自由の相互承認」が保障されても、それだけでは「絵に描いた餅」です。私たちが本当に「自由」に生きるためには、実際に「自由」に生きるための“力”が必要であり、それと同時に全ての人が「自由の相互承認」の感度(価値観・感受性)を持っていなければなりません。
ここで「公教育」が登場します。公立学校だけでなく、私立も含めた、幼児教育から高等教育までの教育一般のことですね。
結論を言えば、教育の目的とは、全ての子どもに「自由の相互承認」の感度を育むことを土台として、「自由」に生きるための力を育むためにあります。これによって、「自由の相互承認」を原理とした民主主義社会が成熟していくんです。
――「自由の相互承認」と「教育の目的」が、どう関係するのでしょうか?
ルールによって「自由」と「自由の相互承認」が保障されても、それだけでは「絵に描いた餅」です。私たちが本当に「自由」に生きるためには、実際に「自由」に生きるための“力”が必要であり、それと同時に全ての人が「自由の相互承認」の感度(価値観・感受性)を持っていなければなりません。
ここで「公教育」が登場します。公立学校だけでなく、私立も含めた、幼児教育から高等教育までの教育一般のことですね。
結論を言えば、教育の目的とは、全ての子どもに「自由の相互承認」の感度を育むことを土台として、「自由」に生きるための力を育むためにあります。これによって、「自由の相互承認」を原理とした民主主義社会が成熟していくんです。
「教育は何のためにあるのか」という本質が明らかになって初めて、私たちは「よい教育とは何か」と考える時の、ぶれない“羅針盤”を手に入れることができます。この羅針盤がないと、「よい教育」を巡る議論がトンチンカンな方向に行ったり、流行に左右されたり、個々の教育論者の信念が激しく対立してしまうんですね。「ゆとり」か「詰め込み」か、とか、「平等」か「競争」か、とか……。
私たちが繰り返し問うべきは、「教育を通して、どうすれば『自由』とその『相互承認』を実現できるのか」ということ。そして「現在の学校は、その教育の目的に向かっているのか」ということです。
ところが、日本の公教育のシステムは明治5年(1872年)の「学制」発布以来、約150年間、ほぼ変わらずに来てしまいました。それは、「みんなで同じことを、同じペースで、同質性の高い学級の中で、教科ごとの出来合いの答えを、子どもたちに一斉に勉強させる」――というものです。
「教育は何のためにあるのか」という本質が明らかになって初めて、私たちは「よい教育とは何か」と考える時の、ぶれない“羅針盤”を手に入れることができます。この羅針盤がないと、「よい教育」を巡る議論がトンチンカンな方向に行ったり、流行に左右されたり、個々の教育論者の信念が激しく対立してしまうんですね。「ゆとり」か「詰め込み」か、とか、「平等」か「競争」か、とか……。
私たちが繰り返し問うべきは、「教育を通して、どうすれば『自由』とその『相互承認』を実現できるのか」ということ。そして「現在の学校は、その教育の目的に向かっているのか」ということです。
ところが、日本の公教育のシステムは明治5年(1872年)の「学制」発布以来、約150年間、ほぼ変わらずに来てしまいました。それは、「みんなで同じことを、同じペースで、同質性の高い学級の中で、教科ごとの出来合いの答えを、子どもたちに一斉に勉強させる」――というものです。

苫野さんの研究室に置かれている著作。「ポップ」と呼ばれる手書き広告は、苫野さんのゼミに所属している学生たちが自ら考えて作成してくれたものという
苫野さんの研究室に置かれている著作。「ポップ」と呼ばれる手書き広告は、苫野さんのゼミに所属している学生たちが自ら考えて作成してくれたものという
■古いシステム
■古いシステム
――そのシステムが構築されたもともとの目的は、富国強兵や殖産興業にありました。
ええ。大量の子どもたちに一気に教育を与えるためには、子どもたちを同質化・均質化して、みんなに同じことを同じように教えていくほうが、効率的だったわけですね。功罪は別にして、それまで教育を受ける機会のなかった子どもたちに、学校への門戸を開いたという点では、一定の役割があったのですが……。
しかし、その学校システムはもう限界を迎えています。現在の教育現場が直面している「不登校」「いじめ」「過度の管理・統率」「理不尽な校則」「過度に空気を読み合う人間関係」等の問題の根底には、旧態依然とした学校システムがあると私は考えています。
――そうしたシステムに疑問を呈したのが、教育者であった創価学会初代会長の牧口常三郎先生でした。昭和5年(1930年)に発刊した『創価教育学体系』の中で、“何のための教育か”と問い、学習の主体者である子どもの幸福のためにあると結論。「価値創造の力」を引き出すため、一方的に知識を与えるのではなく、皆で協働しつつ「自分の力で知識する方法を会得させること」「発見・発明の過程を踏ませること」を重視したのです。また民衆一人一人が自分の頭で考えて自由に議論し合う民主主義的な社会を理想とし、学校も「立憲政治の一部」だと明言しました。
――そのシステムが構築されたもともとの目的は、富国強兵や殖産興業にありました。
ええ。大量の子どもたちに一気に教育を与えるためには、子どもたちを同質化・均質化して、みんなに同じことを同じように教えていくほうが、効率的だったわけですね。功罪は別にして、それまで教育を受ける機会のなかった子どもたちに、学校への門戸を開いたという点では、一定の役割があったのですが……。
しかし、その学校システムはもう限界を迎えています。現在の教育現場が直面している「不登校」「いじめ」「過度の管理・統率」「理不尽な校則」「過度に空気を読み合う人間関係」等の問題の根底には、旧態依然とした学校システムがあると私は考えています。
――そうしたシステムに疑問を呈したのが、教育者であった創価学会初代会長の牧口常三郎先生でした。昭和5年(1930年)に発刊した『創価教育学体系』の中で、“何のための教育か”と問い、学習の主体者である子どもの幸福のためにあると結論。「価値創造の力」を引き出すため、一方的に知識を与えるのではなく、皆で協働しつつ「自分の力で知識する方法を会得させること」「発見・発明の過程を踏ませること」を重視したのです。また民衆一人一人が自分の頭で考えて自由に議論し合う民主主義的な社会を理想とし、学校も「立憲政治の一部」だと明言しました。

1930年11月18日に発刊された『創価教育学体系』
1930年11月18日に発刊された『創価教育学体系』
牧口氏の本を読んだことがなかったのですが、戦前にそういったことを言われていたのですね。
日本の教育史を振り返ると、これまでに「学習者主体の教育」へと転換しようとした大きな教育改革が3度、ありました。
1回目が、100年前の大正自由教育の流れ。これは、軍国主義によって弾圧されました。2回目が、80年前の戦後教育。これも高度経済成長・工業化の流れによって失速しています。3度目は1998年の学習指導要領の改訂、いわゆる「ゆとり教育」ですね。これも結局、学力低下を懸念する声に押され、挫折しました。もっとも、学力が本当に低下したのか、そもそも学力は何をもって測定されるのかという点は、検討されなければいけない問題ですが……。
牧口氏の本を読んだことがなかったのですが、戦前にそういったことを言われていたのですね。
日本の教育史を振り返ると、これまでに「学習者主体の教育」へと転換しようとした大きな教育改革が3度、ありました。
1回目が、100年前の大正自由教育の流れ。これは、軍国主義によって弾圧されました。2回目が、80年前の戦後教育。これも高度経済成長・工業化の流れによって失速しています。3度目は1998年の学習指導要領の改訂、いわゆる「ゆとり教育」ですね。これも結局、学力低下を懸念する声に押され、挫折しました。もっとも、学力が本当に低下したのか、そもそも学力は何をもって測定されるのかという点は、検討されなければいけない問題ですが……。
■4度目の正直
■4度目の正直
――3度の改革が失敗してしまった理由は、何だと思われますか?
大きく二つあります。一つが、「そもそも教育は何のためか」という本質的な原理が共有されていなかったこと。もう一つが、トップダウンの改革に終始し、現場レベルの「対話の文化や仕組み」を十分につくれなかった点です。
私自身、「4度目の正直」との思いで、ゆるやかに、けれど着実に「公教育の構造転換」を実現しようと、全国の学校や自治体の関係者と対話を重ね、協働してきました。かれこれ、10年以上になるでしょうか。
うまくいっている所に共通しているのは、教師も子どもも、保護者も地域の人たちも、みんなが一緒になって「この授業って、子どもが自由に生きるための力を育むことになっているかな」「このルールって、自由の相互承認の感度を育むことに、つながっているかな」との本質的な問いに何度も立ち返りながら、対話して練り上げている点ですね。これは、ほぼ例外がありません。
――3度の改革が失敗してしまった理由は、何だと思われますか?
大きく二つあります。一つが、「そもそも教育は何のためか」という本質的な原理が共有されていなかったこと。もう一つが、トップダウンの改革に終始し、現場レベルの「対話の文化や仕組み」を十分につくれなかった点です。
私自身、「4度目の正直」との思いで、ゆるやかに、けれど着実に「公教育の構造転換」を実現しようと、全国の学校や自治体の関係者と対話を重ね、協働してきました。かれこれ、10年以上になるでしょうか。
うまくいっている所に共通しているのは、教師も子どもも、保護者も地域の人たちも、みんなが一緒になって「この授業って、子どもが自由に生きるための力を育むことになっているかな」「このルールって、自由の相互承認の感度を育むことに、つながっているかな」との本質的な問いに何度も立ち返りながら、対話して練り上げている点ですね。これは、ほぼ例外がありません。
「自由」と「自由の相互承認」の実現へ
「何のための教育か」を問い続けよう
「自由」と「自由の相互承認」の実現へ
「何のための教育か」を問い続けよう

「何のため?」と本質を問う対話を、大人も、子どもたちも(PIXTA)
「何のため?」と本質を問う対話を、大人も、子どもたちも(PIXTA)
反対に「対話の文化」がないと、教育観(学校観・子ども観・授業観)がバラバラになってむやみに対立が起こったり、“声の大きな人”の意見ばかりが通ったりしてしまいます。
過度に空気を読み合って忖度したり、「うちの学校のこの規則、おかしいよな」と思っていても、「どうせ言っても聞き入れてもらえないだろう」といった自縄自縛の悪循環に陥ったりもします。結果的に、本来はやらなくてもいいような、意味のよく分からない仕事も、どんどん増えてしまうわけです。
反対に「対話の文化」がないと、教育観(学校観・子ども観・授業観)がバラバラになってむやみに対立が起こったり、“声の大きな人”の意見ばかりが通ったりしてしまいます。
過度に空気を読み合って忖度したり、「うちの学校のこの規則、おかしいよな」と思っていても、「どうせ言っても聞き入れてもらえないだろう」といった自縄自縛の悪循環に陥ったりもします。結果的に、本来はやらなくてもいいような、意味のよく分からない仕事も、どんどん増えてしまうわけです。
■信頼して支え
■信頼して支え
――その意味でも、みんなが安心して、対等な立場で対話ができる環境づくりが大切ですね。
その通りです。学校であれば、校長をはじめとした管理職の理解が鍵となるでしょう。現場の先生方を、そして子どもたちを「信頼して、任せて、待って、支える」勇気を持っていただくことが、第一歩になると思います。これが、子どもたちや若い人たちが伸びていくための「教育の“基本”であり“秘訣”」だからです。
同じように、保護者や世間の人たちにも、学校の先生方、特に若い人たちを、どうか信頼していただきたいと願っています。教師や学校への風当たりが強い時代です。教師の不祥事がニュースで報じられると、ますます不信の目が向けられます。
けれど、人は信頼されてこそ、その力を発揮できるものでしょう。「だからお前たちはダメなんだ」とか「勝手なことをするな」と言われてばかりいたら、萎縮してしまい、伸びるものも伸びません。子どもたちを、若い人たちを「信頼して、任せて、みんなで支える」――そんな温かい社会にしていきたいものです。
「自由の相互承認」の感度を育むといっても、私たち大人が「相互不信」の負のスパイラルに陥ってしまっていないでしょうか。これを、「相互信頼」「相互承認」のスパイラルへと、“逆回転”させなければなりません。
――その意味でも、みんなが安心して、対等な立場で対話ができる環境づくりが大切ですね。
その通りです。学校であれば、校長をはじめとした管理職の理解が鍵となるでしょう。現場の先生方を、そして子どもたちを「信頼して、任せて、待って、支える」勇気を持っていただくことが、第一歩になると思います。これが、子どもたちや若い人たちが伸びていくための「教育の“基本”であり“秘訣”」だからです。
同じように、保護者や世間の人たちにも、学校の先生方、特に若い人たちを、どうか信頼していただきたいと願っています。教師や学校への風当たりが強い時代です。教師の不祥事がニュースで報じられると、ますます不信の目が向けられます。
けれど、人は信頼されてこそ、その力を発揮できるものでしょう。「だからお前たちはダメなんだ」とか「勝手なことをするな」と言われてばかりいたら、萎縮してしまい、伸びるものも伸びません。子どもたちを、若い人たちを「信頼して、任せて、みんなで支える」――そんな温かい社会にしていきたいものです。
「自由の相互承認」の感度を育むといっても、私たち大人が「相互不信」の負のスパイラルに陥ってしまっていないでしょうか。これを、「相互信頼」「相互承認」のスパイラルへと、“逆回転”させなければなりません。
■信仰の意義とは
■信仰の意義とは
――牧口初代会長も「信の確立」こそ教育上の先決問題であるとし、自他共の「信用」を基礎とした学校と社会の構築を訴えました(『創価教育学体系梗概』)。この「信」を支え強める力として、万人に「仏性」を見いだす日蓮仏法を自ら実践したことが、創価学会の宗教運動の原点です。
私は特定の信仰を持っていませんが、哲学者として歴史を学び、また信仰を持った教育者の方々と接してきた中で、その大きな意義を実感しています。互いに認め合い、助け合うつながりをつくる土台となるもので、宗教団体は歴史的にも「自由の相互承認」の感度を育む母体になってきましたね。
ではここからは、現代において「自由」に生きるための力とは具体的に何なのか、どうすれば育めるのかといった点について、教育現場や自治体の実例も踏まえながら、お話ししたいと思います。(㊦に続く。20日付に掲載予定)
――牧口初代会長も「信の確立」こそ教育上の先決問題であるとし、自他共の「信用」を基礎とした学校と社会の構築を訴えました(『創価教育学体系梗概』)。この「信」を支え強める力として、万人に「仏性」を見いだす日蓮仏法を自ら実践したことが、創価学会の宗教運動の原点です。
私は特定の信仰を持っていませんが、哲学者として歴史を学び、また信仰を持った教育者の方々と接してきた中で、その大きな意義を実感しています。互いに認め合い、助け合うつながりをつくる土台となるもので、宗教団体は歴史的にも「自由の相互承認」の感度を育む母体になってきましたね。
ではここからは、現代において「自由」に生きるための力とは具体的に何なのか、どうすれば育めるのかといった点について、教育現場や自治体の実例も踏まえながら、お話ししたいと思います。(㊦に続く。20日付に掲載予定)

とまの・いっとく 1980年生まれ。哲学者・教育学者。熊本大学大学院教育学研究科准教授。2児の父。早稲田大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。経済産業省「産業構造審議会」委員、熊本市教育委員のほか、全国の多くの自治体・学校等のアドバイザーを歴任。著書に『親子で哲学対話』『子どもの頃から哲学者』(大和書房)、『どのような教育が「よい」教育か』(講談社選書メチエ)、『「学校」をつくり直す』(河出新書)、『「エミール」を読む』(岩波書店)など多数
とまの・いっとく 1980年生まれ。哲学者・教育学者。熊本大学大学院教育学研究科准教授。2児の父。早稲田大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。経済産業省「産業構造審議会」委員、熊本市教育委員のほか、全国の多くの自治体・学校等のアドバイザーを歴任。著書に『親子で哲学対話』『子どもの頃から哲学者』(大和書房)、『どのような教育が「よい」教育か』(講談社選書メチエ)、『「学校」をつくり直す』(河出新書)、『「エミール」を読む』(岩波書店)など多数
●ご感想をお寄せください。
kansou@seikyo-np.jp
ファクス 03-5360-9613
●こちらから、「危機の時代を生きる」識者インタビューの過去の連載の一部をご覧いただけます。
●ご感想をお寄せください。
kansou@seikyo-np.jp
ファクス 03-5360-9613
●こちらから、「危機の時代を生きる」識者インタビューの過去の連載の一部をご覧いただけます。
音声読み上げ