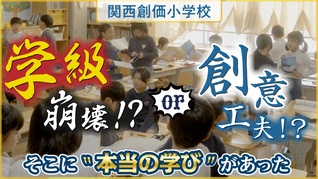株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長 小室淑恵さんに聞く
株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長 小室淑恵さんに聞く
2025年3月18日
- 〈SDGs×SEIKYO〉 働き方改革で経済成長を
- 〈SDGs×SEIKYO〉 働き方改革で経済成長を
企業の働き方改革を支援する株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長の小室淑恵さんは、「残業に頼らない働き方にこそ、日本の経済成長の鍵がある」と語ります。SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」をテーマに、働き方で変わる日本の未来の姿や、皆が働きがいを持てるための方途について、小室さんに聞きました。(取材=玉川直美、樹下智)
企業の働き方改革を支援する株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長の小室淑恵さんは、「残業に頼らない働き方にこそ、日本の経済成長の鍵がある」と語ります。SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」をテーマに、働き方で変わる日本の未来の姿や、皆が働きがいを持てるための方途について、小室さんに聞きました。(取材=玉川直美、樹下智)
――小室さんは2006年、働き方のコンサルティングを提供する「ワーク・ライフバランス社」を創業されました。起業のきっかけを教えてください。
大学生の時から、女性がもっと活躍できる社会になってほしい、そのために何かで役に立ちたいと思っていました。
大手化粧品会社に新卒で就職し、1年目で社内のビジネスコンテストに応募しました。女性が育児休業を取得した後、職場に復帰できるよう支援するプログラムを提案したのですが、103件の応募の中から選ばれ、優勝したんです。
このプログラムは事業化され、さまざまな企業に導入していただきました。しかし、育休から復帰した女性が仕事を辞めてしまうケースも多くありました。長時間労働の企業ほど、その傾向が顕著で、「長い子育て期と仕事を両立できるよう、『働き方』自体を変えないと根本的な解決にはならない」と気付きました。
当時、男性でも、介護やメンタル疾患などで仕事を休む人が増え始めていました。さまざまな事情がある人も、皆で活躍できるようにならなければ、日本社会そのものが衰退していくのではないか――。そんな危機感から、“新しい働き方”を提案するコンサルティング会社を起業しようと決めました。
――小室さんは2006年、働き方のコンサルティングを提供する「ワーク・ライフバランス社」を創業されました。起業のきっかけを教えてください。
大学生の時から、女性がもっと活躍できる社会になってほしい、そのために何かで役に立ちたいと思っていました。
大手化粧品会社に新卒で就職し、1年目で社内のビジネスコンテストに応募しました。女性が育児休業を取得した後、職場に復帰できるよう支援するプログラムを提案したのですが、103件の応募の中から選ばれ、優勝したんです。
このプログラムは事業化され、さまざまな企業に導入していただきました。しかし、育休から復帰した女性が仕事を辞めてしまうケースも多くありました。長時間労働の企業ほど、その傾向が顕著で、「長い子育て期と仕事を両立できるよう、『働き方』自体を変えないと根本的な解決にはならない」と気付きました。
当時、男性でも、介護やメンタル疾患などで仕事を休む人が増え始めていました。さまざまな事情がある人も、皆で活躍できるようにならなければ、日本社会そのものが衰退していくのではないか――。そんな危機感から、“新しい働き方”を提案するコンサルティング会社を起業しようと決めました。

小室さんはこれまで企業、自治体、学校、中央省庁など多岐にわたる団体の働き方コンサルティングを手がけてきた ©ワーク・ライフバランス社
小室さんはこれまで企業、自治体、学校、中央省庁など多岐にわたる団体の働き方コンサルティングを手がけてきた ©ワーク・ライフバランス社
――これまで、3000社以上の企業や自治体に、働き方改革のコンサルティングをされてきました。
長時間労働の是正が企業の業績アップにつながっていくことを、“経営戦略”としてご提案してきました。方法は100社100通りですが、チームの人間関係の質を高めることや、仕事の見える化・共有化などを行っています。
例えば、新潟にある従業員150~200人の製造業の会社では、ある業務が特定の人にしかこなせない「仕事の属人化」の解消を行いました。仕事を見える化・共有化し、「誰でもまわせる職場づくり」に取り組んだのです。
2年かけて地道に改革していった結果、1人あたりの残業時間は1カ月で平均1・2時間、1日あたり3分にまで減りました。それでも業績は堅調です。
経営者にとって、月々の残業代がいくらになるかは切実な問題ですが、この会社では残業代を一定程度に抑えられるようになった結果、資金を従業員のベースアップ(基本給の底上げ)に回し、給与を1・5倍にすることができました。ベースアップを行うと、新卒の応募も増えます。
また、男性の育児休業の取得期間は平均5カ月(2022年)となり、取得率も上がりました。残業が減り、育休の取得が進んだことで、従業員の家庭で生まれる子どもの数が4・5倍に増えました。夫が育児に参画することで、妻は第1子の育児経験で懲りてしまわずに、「第2子、第3子を産んでも、この人となら子育てしていける」と信頼が生まれるのです。
コンサルティングを始めた当初は、所在地が雪深い場所なこともあってか、新卒の採用に苦心しておられました。しかし今では、企業のイメージが大幅にアップし、採用に全く困らなくなったそうです。
――これまで、3000社以上の企業や自治体に、働き方改革のコンサルティングをされてきました。
長時間労働の是正が企業の業績アップにつながっていくことを、“経営戦略”としてご提案してきました。方法は100社100通りですが、チームの人間関係の質を高めることや、仕事の見える化・共有化などを行っています。
例えば、新潟にある従業員150~200人の製造業の会社では、ある業務が特定の人にしかこなせない「仕事の属人化」の解消を行いました。仕事を見える化・共有化し、「誰でもまわせる職場づくり」に取り組んだのです。
2年かけて地道に改革していった結果、1人あたりの残業時間は1カ月で平均1・2時間、1日あたり3分にまで減りました。それでも業績は堅調です。
経営者にとって、月々の残業代がいくらになるかは切実な問題ですが、この会社では残業代を一定程度に抑えられるようになった結果、資金を従業員のベースアップ(基本給の底上げ)に回し、給与を1・5倍にすることができました。ベースアップを行うと、新卒の応募も増えます。
また、男性の育児休業の取得期間は平均5カ月(2022年)となり、取得率も上がりました。残業が減り、育休の取得が進んだことで、従業員の家庭で生まれる子どもの数が4・5倍に増えました。夫が育児に参画することで、妻は第1子の育児経験で懲りてしまわずに、「第2子、第3子を産んでも、この人となら子育てしていける」と信頼が生まれるのです。
コンサルティングを始めた当初は、所在地が雪深い場所なこともあってか、新卒の採用に苦心しておられました。しかし今では、企業のイメージが大幅にアップし、採用に全く困らなくなったそうです。

講演依頼は年間約200件に及ぶ ©ワーク・ライフバランス社
講演依頼は年間約200件に及ぶ ©ワーク・ライフバランス社
――小室さんは、14年から政府の産業競争力会議の民間議員を務めるなど、日本社会全体の働き方改革にも貢献されています。19年には「働き方改革関連法」が施行され、時間外労働(残業)の上限規制などが法律で定められました。
14年に首相官邸で行われた産業競争力会議で、「日本の経済発展のためには、労働時間の上限を定める法律が必要です。それを作らないと、これからは多様な人が労働に参画できません」と発言したら、その場が静まり返りました。
霞が関・永田町には、「長時間労働の是正なんかしたら、日本の経済が弱くなってしまう」「労働時間に比例して、経済というのは成長していくんだ」という考えが根強かったのでしょう。
しかし、当時、コンサルティングしていた企業の社長が、深夜残業を減らしたことで社内の出生率が上がった事例を、産業競争力会議で説明してくださった瞬間、議場の雰囲気が一気に変わりました。「深夜残業を86%減らしたところ、従業員の家庭で1・8倍の子どもが生まれるようになった」との結果を見て、「この国の喫緊の課題である“少子化”と長時間労働に密接な関係があること」に気付いたようで、国会議員からの質問が相次いだことをよく覚えています。
厚生労働省の調査結果で、「妻の第1子出産時に、夫の家事・育児参画時間が短い家庭ほど、第2子以降が生まれていない」(下の図参照)というデータもありましたが、企業が実例を出してくれたことが大きな後押しとなりました。
働き方改革が“少子化の解決策になる”ことが理解され始めたことで、「長時間労働の是正」に対する政策立案への優先順位が上がり、法整備が進んでいったのです。
――小室さんは、14年から政府の産業競争力会議の民間議員を務めるなど、日本社会全体の働き方改革にも貢献されています。19年には「働き方改革関連法」が施行され、時間外労働(残業)の上限規制などが法律で定められました。
14年に首相官邸で行われた産業競争力会議で、「日本の経済発展のためには、労働時間の上限を定める法律が必要です。それを作らないと、これからは多様な人が労働に参画できません」と発言したら、その場が静まり返りました。
霞が関・永田町には、「長時間労働の是正なんかしたら、日本の経済が弱くなってしまう」「労働時間に比例して、経済というのは成長していくんだ」という考えが根強かったのでしょう。
しかし、当時、コンサルティングしていた企業の社長が、深夜残業を減らしたことで社内の出生率が上がった事例を、産業競争力会議で説明してくださった瞬間、議場の雰囲気が一気に変わりました。「深夜残業を86%減らしたところ、従業員の家庭で1・8倍の子どもが生まれるようになった」との結果を見て、「この国の喫緊の課題である“少子化”と長時間労働に密接な関係があること」に気付いたようで、国会議員からの質問が相次いだことをよく覚えています。
厚生労働省の調査結果で、「妻の第1子出産時に、夫の家事・育児参画時間が短い家庭ほど、第2子以降が生まれていない」(下の図参照)というデータもありましたが、企業が実例を出してくれたことが大きな後押しとなりました。
働き方改革が“少子化の解決策になる”ことが理解され始めたことで、「長時間労働の是正」に対する政策立案への優先順位が上がり、法整備が進んでいったのです。

夫の休日の家事・育児時間別に見た、第2子以降の出生の状況
出典:厚生労働省が2015年7月15日付で発表した「第2回21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)及び第12回21世紀成年者縦断調査(平成14年成年者)の概況」
夫の休日の家事・育児時間別に見た、第2子以降の出生の状況
出典:厚生労働省が2015年7月15日付で発表した「第2回21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)及び第12回21世紀成年者縦断調査(平成14年成年者)の概況」
――働き方改革によって、「男性育休」の環境整備も進んでいます。小室さんは、厚生労働省のイクメンプロジェクトの推進委員も務め、男性育休の推進に取り組んでこられました。
厚生労働省は10年に、男性の育児・家事参画を促す目的でイクメンプロジェクトを創設し、私はその推進委員を15年以上務めてきました。当初は「父親本人たちへの意識啓発」が主な内容でした。
実際に、男性で育休取得を希望する人は増えました。しかし、どんなに本人に意識啓発をしても、約10年かけて男性の育休取得率は2%程度から約7%に増えただけでした。育休取得を阻む要因は、「職場が人手不足だから」「職場が育休を取得しづらい雰囲気だから」など、企業側にあったのです。
そこで、推進委員のメンバーで、毎回の委員会の後に別ミーティングを開き、「男性育休を義務化するプロジェクト」を始めました。ここでいう義務化とは、「企業が、育休対象者に対して『取得する権利がある』と説明する義務」です。
ワーク・ライフバランス社としても19年3月から、「自社内で男性の育児休業取得率100%を積極的に目指す」ことを宣言する「男性育休100%宣言」を各企業から募ってきました。出産した女性の10人に1人が経験するといわれる「産後うつ」の対策としても、男性育休の重要性を各所で訴えてきました。
管理職向けの研修では、「出産直後に妻と夫の愛情度の差は20%開き、夫婦が一緒に子育てできなければ、その差はその後も埋まらない」というデータを示しました。
男性管理職の皆さんは、「だから、わが家は……」と悲痛な面持ちになり、アンケートには、「部下に育休を取らせます」ではなく、「明日、妻に謝ります」といった内容のものもありました(笑)。
そして、22年4月には、企業が育休対象者に対して「育休を取得する権利がある」と周知する義務などを定めた法律が施行されました。男性の育休取得率は年々上昇し、22年度で17%、23年度は30%となっています。
――働き方改革によって、「男性育休」の環境整備も進んでいます。小室さんは、厚生労働省のイクメンプロジェクトの推進委員も務め、男性育休の推進に取り組んでこられました。
厚生労働省は10年に、男性の育児・家事参画を促す目的でイクメンプロジェクトを創設し、私はその推進委員を15年以上務めてきました。当初は「父親本人たちへの意識啓発」が主な内容でした。
実際に、男性で育休取得を希望する人は増えました。しかし、どんなに本人に意識啓発をしても、約10年かけて男性の育休取得率は2%程度から約7%に増えただけでした。育休取得を阻む要因は、「職場が人手不足だから」「職場が育休を取得しづらい雰囲気だから」など、企業側にあったのです。
そこで、推進委員のメンバーで、毎回の委員会の後に別ミーティングを開き、「男性育休を義務化するプロジェクト」を始めました。ここでいう義務化とは、「企業が、育休対象者に対して『取得する権利がある』と説明する義務」です。
ワーク・ライフバランス社としても19年3月から、「自社内で男性の育児休業取得率100%を積極的に目指す」ことを宣言する「男性育休100%宣言」を各企業から募ってきました。出産した女性の10人に1人が経験するといわれる「産後うつ」の対策としても、男性育休の重要性を各所で訴えてきました。
管理職向けの研修では、「出産直後に妻と夫の愛情度の差は20%開き、夫婦が一緒に子育てできなければ、その差はその後も埋まらない」というデータを示しました。
男性管理職の皆さんは、「だから、わが家は……」と悲痛な面持ちになり、アンケートには、「部下に育休を取らせます」ではなく、「明日、妻に謝ります」といった内容のものもありました(笑)。
そして、22年4月には、企業が育休対象者に対して「育休を取得する権利がある」と周知する義務などを定めた法律が施行されました。男性の育休取得率は年々上昇し、22年度で17%、23年度は30%となっています。

2025年4月から、一定の条件を満たせば、男性の育休手当は手取り額の実質10割となる ©folyphoto/Shutterstock.com
2025年4月から、一定の条件を満たせば、男性の育休手当は手取り額の実質10割となる ©folyphoto/Shutterstock.com
――SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」では、「働きがいのある人間らしい仕事の促進」が、「持続可能な経済成長」に欠かせないものとして位置づけられています。
私は「働きがいこそ経済成長に必須」だと思っています。
残念ながら、意欲や能力がありながらも、残業が前提となる働き方によって、仕事の第一線で働けない人たちが日本には多くいます。時間外労働ができるかどうかが人材の要件となり、「働き方の門前払い」が続けば、意思決定層は同質的になり、イノベーション(革新)も起きにくくなります。
多様な人材が“働きがい”を持って活躍できれば、日本はまだまだ経済成長できるはずです。それは、高度経済成長期のように、長時間働ける人材を集めて、業務を積み上げるような「縦方向の経済成長」ではありません。多様な働き手で仕事をまわし、イノベーションを生んでいく、「横方向の経済成長」です。
日本社会に広く目を向けてみると、約1700万人いる65~75歳のシニア世代の中には、「週5日でフルタイムは難しいが、週3日で時短勤務ならぜひ働きたい」という人もいるでしょう。また、現在は非正規社員として働いているけれど、残業や休日出勤ができないため正社員になることを諦めている女性も多くいます。
潜在的な労働力が、日本には眠っているのです。
――多様な人たちが働きがいを持てる職場づくりのために、何が必要でしょうか。
「このチームの中でなら、自分は発言できる」という安心感ではないでしょうか。専門用語で「心理的安全性」といいます。
私たちが、企業に提供しているコンサルティング手法の一つに、職場の目指したいゴール(ありたい姿)や、良いところ、もったいないところ(改善点)などを一人一人が付箋に書いて、役職に関係なく対話を行える「カエル会議」(「カエル」は仕事のやり方を「変える」、早く「帰る」、人生を「変える」の意味)があります。この取り組みを継続していくことで、社員同士が、今よりももっと良い仕事の仕方を提案して実行できる心理的安全性の高いコミュニケーションが可能になり、結果的に残業が減っていきます。
また、育児や介護をしているか否かに限らず、誰もが自分のライフ(生活や人生)を大事にできることが必要です。「子育てしている人だけが優遇されている」と一部の人が感じることで、従業員同士のいがみ合いが起きてしまう場合もあります。そうしたことを起こさないためにも、誰かが急に仕事を休んでもお互いにカバーし合える職場を日頃からつくるべきです。
たとえ時間的制約があったとしても、誰もが自分にしかない価値を生み出し、一流になっていける――。そうした“働きがい”を持ってもらえることが、多様な人材が活躍できる職場の要件ではないでしょうか。
――SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」では、「働きがいのある人間らしい仕事の促進」が、「持続可能な経済成長」に欠かせないものとして位置づけられています。
私は「働きがいこそ経済成長に必須」だと思っています。
残念ながら、意欲や能力がありながらも、残業が前提となる働き方によって、仕事の第一線で働けない人たちが日本には多くいます。時間外労働ができるかどうかが人材の要件となり、「働き方の門前払い」が続けば、意思決定層は同質的になり、イノベーション(革新)も起きにくくなります。
多様な人材が“働きがい”を持って活躍できれば、日本はまだまだ経済成長できるはずです。それは、高度経済成長期のように、長時間働ける人材を集めて、業務を積み上げるような「縦方向の経済成長」ではありません。多様な働き手で仕事をまわし、イノベーションを生んでいく、「横方向の経済成長」です。
日本社会に広く目を向けてみると、約1700万人いる65~75歳のシニア世代の中には、「週5日でフルタイムは難しいが、週3日で時短勤務ならぜひ働きたい」という人もいるでしょう。また、現在は非正規社員として働いているけれど、残業や休日出勤ができないため正社員になることを諦めている女性も多くいます。
潜在的な労働力が、日本には眠っているのです。
――多様な人たちが働きがいを持てる職場づくりのために、何が必要でしょうか。
「このチームの中でなら、自分は発言できる」という安心感ではないでしょうか。専門用語で「心理的安全性」といいます。
私たちが、企業に提供しているコンサルティング手法の一つに、職場の目指したいゴール(ありたい姿)や、良いところ、もったいないところ(改善点)などを一人一人が付箋に書いて、役職に関係なく対話を行える「カエル会議」(「カエル」は仕事のやり方を「変える」、早く「帰る」、人生を「変える」の意味)があります。この取り組みを継続していくことで、社員同士が、今よりももっと良い仕事の仕方を提案して実行できる心理的安全性の高いコミュニケーションが可能になり、結果的に残業が減っていきます。
また、育児や介護をしているか否かに限らず、誰もが自分のライフ(生活や人生)を大事にできることが必要です。「子育てしている人だけが優遇されている」と一部の人が感じることで、従業員同士のいがみ合いが起きてしまう場合もあります。そうしたことを起こさないためにも、誰かが急に仕事を休んでもお互いにカバーし合える職場を日頃からつくるべきです。
たとえ時間的制約があったとしても、誰もが自分にしかない価値を生み出し、一流になっていける――。そうした“働きがい”を持ってもらえることが、多様な人材が活躍できる職場の要件ではないでしょうか。

ワーク・ライフバランス社が提案する「カエル会議」の様子 ©ワーク・ライフバランス社
ワーク・ライフバランス社が提案する「カエル会議」の様子 ©ワーク・ライフバランス社
――仕事で自分にしか生み出せない価値を発揮する鍵は何だと思いますか。
自分の「ライフ」そのものが、本来、自分にしか生み出せない価値を創出する源泉だと考えます。
私自身、子どもの病気で3年ぐらい治療の付き添いに通っていた時期がありました。その時は1日3時間ぐらいしか働けず、社員に支えてもらいながら必死に仕事をしていました。でも、その経験があったからこそ、社員が悩みに直面した時に、「大丈夫。焦らずにいこう」と言葉をかけて寄り添い、社員が再び最前線で働ける環境を整えられていると感じます。
また、自身の生活での悩みが、お客さまの気持ちに寄り添ったアイデアを生み出すことにもつながります。一見、仕事の障害になっていると思われることが、実はそうした“強み”となっていくのではないでしょうか。
さらに、育児や介護に限らず、趣味やボランティアを通じて得た知識やつながりが、仕事で生きる場合もあります。私たちは、そのような仕事と生活の相乗効果を「ワーク・ライフ・シナジー」と呼んでいます。
一人一人が抱えている課題や気付きをオープンに共有し合い、互いの人生から学び、生かしていくことで、一人一人の生活や人生それ自体を、さらなる発展や革新の価値へと変えていける。だからこそ、多様性が重要です。
少子化対策としての「長時間労働の是正」や「男性の育休取得」は、単なる通過点でしかありません。仕事と生活を互いに生かし合う「ワーク・ライフ・シナジー」で、誰もが輝く社会を築くことが、日本がこれからも成長し続けるための鍵だと考えます。
――仕事で自分にしか生み出せない価値を発揮する鍵は何だと思いますか。
自分の「ライフ」そのものが、本来、自分にしか生み出せない価値を創出する源泉だと考えます。
私自身、子どもの病気で3年ぐらい治療の付き添いに通っていた時期がありました。その時は1日3時間ぐらいしか働けず、社員に支えてもらいながら必死に仕事をしていました。でも、その経験があったからこそ、社員が悩みに直面した時に、「大丈夫。焦らずにいこう」と言葉をかけて寄り添い、社員が再び最前線で働ける環境を整えられていると感じます。
また、自身の生活での悩みが、お客さまの気持ちに寄り添ったアイデアを生み出すことにもつながります。一見、仕事の障害になっていると思われることが、実はそうした“強み”となっていくのではないでしょうか。
さらに、育児や介護に限らず、趣味やボランティアを通じて得た知識やつながりが、仕事で生きる場合もあります。私たちは、そのような仕事と生活の相乗効果を「ワーク・ライフ・シナジー」と呼んでいます。
一人一人が抱えている課題や気付きをオープンに共有し合い、互いの人生から学び、生かしていくことで、一人一人の生活や人生それ自体を、さらなる発展や革新の価値へと変えていける。だからこそ、多様性が重要です。
少子化対策としての「長時間労働の是正」や「男性の育休取得」は、単なる通過点でしかありません。仕事と生活を互いに生かし合う「ワーク・ライフ・シナジー」で、誰もが輝く社会を築くことが、日本がこれからも成長し続けるための鍵だと考えます。
こむろ・よしえ 株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長。3000社以上の企業へのコンサルティング実績を持ち、残業を減らして業績を上げるコンサルティング手法に定評がある。著書に『働き方改革 生産性とモチベーションが上がる事例20社』『男性の育休 家族・企業・経済はこう変わる』(共著)など多数。「産業競争力会議」民間議員など複数の公務を歴任してきた。2児の母。
こむろ・よしえ 株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長。3000社以上の企業へのコンサルティング実績を持ち、残業を減らして業績を上げるコンサルティング手法に定評がある。著書に『働き方改革 生産性とモチベーションが上がる事例20社』『男性の育休 家族・企業・経済はこう変わる』(共著)など多数。「産業競争力会議」民間議員など複数の公務を歴任してきた。2児の母。
●ご感想をお寄せください。
sdgs@seikyo-np.jp
●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html
●海外識者のインタビューの英語版が「創価学会グローバルサイト」に掲載されています。
https://www.sokaglobal.org/resources/expert-perspectives.html
●ご感想をお寄せください。
sdgs@seikyo-np.jp
●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html
●海外識者のインタビューの英語版が「創価学会グローバルサイト」に掲載されています。
https://www.sokaglobal.org/resources/expert-perspectives.html
書籍「ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs」が好評発売中
書籍「ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs」が好評発売中
『ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs』(写真)が好評発売中である。
同書は本紙の企画「ちーちゃんと考える 未来のカタチ」を書籍化したもの。連載中の4こま漫画「ちーちゃん家」のキャラクターたちが、SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標や、世界が直面する諸課題について解説し、地球の未来のカタチを楽しく学ぶことができる。
SDGsに関するクイズやコラム、4こま漫画も収録。親子での学習や、座談会での企画に活用できる一書である。
潮出版社刊。1650円(税込み)。全国の書店で購入・注文可能。聖教ブックストアのウェブサイトでも受け付け中。電話=(0120)983563(午前9時~午後5時、土・日・祝日を除く)。※電話の場合、支払いは代金引換のみ。FAXでの注文はできません。コンビニ通販サイト「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」での注文、受け取りも可能です。
『ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs』(写真)が好評発売中である。
同書は本紙の企画「ちーちゃんと考える 未来のカタチ」を書籍化したもの。連載中の4こま漫画「ちーちゃん家」のキャラクターたちが、SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標や、世界が直面する諸課題について解説し、地球の未来のカタチを楽しく学ぶことができる。
SDGsに関するクイズやコラム、4こま漫画も収録。親子での学習や、座談会での企画に活用できる一書である。
潮出版社刊。1650円(税込み)。全国の書店で購入・注文可能。聖教ブックストアのウェブサイトでも受け付け中。電話=(0120)983563(午前9時~午後5時、土・日・祝日を除く)。※電話の場合、支払いは代金引換のみ。FAXでの注文はできません。コンビニ通販サイト「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」での注文、受け取りも可能です。
音声読み上げ