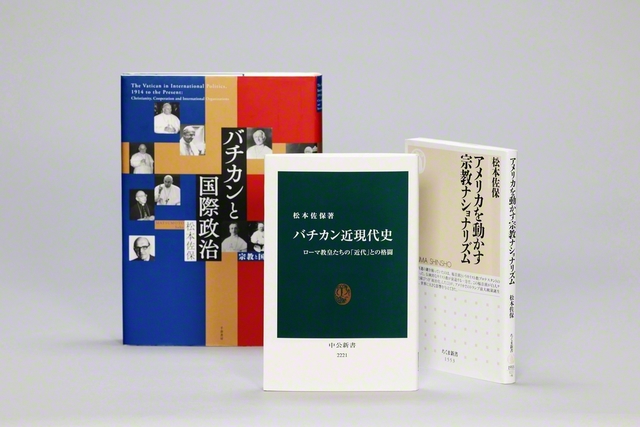難局の中で 平和構築への歩みを支える宗教的信念――インタビュー 日本大学教授・国際政治学者 松本佐保さん
難局の中で 平和構築への歩みを支える宗教的信念――インタビュー 日本大学教授・国際政治学者 松本佐保さん
2025年7月25日
- <危機の時代を生きる 希望の哲学>
- <危機の時代を生きる 希望の哲学>
世界に14億人の信者がいるローマ・カトリック教会。その最高指導者であるローマ教皇とバチカンは、国際社会で大きな影響力を持っています。紛争や対立が絶えない現代にあって、カトリックの2000年の歴史に学ぶこととは――。国際政治を専門とする、日本大学教授の松本佐保さんにインタビューしました。(聞き手=萩本秀樹)
世界に14億人の信者がいるローマ・カトリック教会。その最高指導者であるローマ教皇とバチカンは、国際社会で大きな影響力を持っています。紛争や対立が絶えない現代にあって、カトリックの2000年の歴史に学ぶこととは――。国際政治を専門とする、日本大学教授の松本佐保さんにインタビューしました。(聞き手=萩本秀樹)
新教皇が選出
新教皇が選出
――本年5月、ローマ・カトリック教会の新教皇が選出され、注目を集めました。ローマ教皇とはどのような存在でしょうか。
イタリアの首都ローマの一角に、バチカン市国があります。東京ディズニーランドよりも小さな敷地面積の、世界最小の独立国でありながら、ここがカトリック教会の総本山です。
そのバチカンの元首であり、世界のカトリック教徒の最高指導者がローマ教皇です。信者にとっては「神の代理人」と呼ばれる、神に一番近い存在ですが、信者でない人は、グローバル企業を思い浮かべるといいかもしれません。
というのも、カトリック教会には明確なヒエラルキー(位階制)が存在し、トップにはローマ教皇、そのすぐ下には約250人の枢機卿がいます。教皇はこの枢機卿の中から選出されることになっていて、先日の教皇選挙(コンクラーベ)で第267代教皇が選ばれました。さらに枢機卿の下には、約650人の大司教、約5000人の司教、約46万人の司祭、そして約14億人の一般信徒が続くといった、ピラミッドの階層をなしています。
枢機卿たちは、普段は自分の国や地域で聖職に従事していますが、一部の枢機卿は、バチカン内での国家役職にも就いています。こうした構造が、グローバル企業の組織機構と似ているのですね。
新教皇に選出されたレオ14世は、初のアメリカ出身の教皇です。南米ペルーで長年、救貧活動などを行ってきました。一方、バチカン内では、司教の選任などに影響力を持つ司教省長官を務めています。つまり、現場の“たたき上げ”でありながら、バチカン中枢からも支持を得ていた人物であるということです。
――本年5月、ローマ・カトリック教会の新教皇が選出され、注目を集めました。ローマ教皇とはどのような存在でしょうか。
イタリアの首都ローマの一角に、バチカン市国があります。東京ディズニーランドよりも小さな敷地面積の、世界最小の独立国でありながら、ここがカトリック教会の総本山です。
そのバチカンの元首であり、世界のカトリック教徒の最高指導者がローマ教皇です。信者にとっては「神の代理人」と呼ばれる、神に一番近い存在ですが、信者でない人は、グローバル企業を思い浮かべるといいかもしれません。
というのも、カトリック教会には明確なヒエラルキー(位階制)が存在し、トップにはローマ教皇、そのすぐ下には約250人の枢機卿がいます。教皇はこの枢機卿の中から選出されることになっていて、先日の教皇選挙(コンクラーベ)で第267代教皇が選ばれました。さらに枢機卿の下には、約650人の大司教、約5000人の司教、約46万人の司祭、そして約14億人の一般信徒が続くといった、ピラミッドの階層をなしています。
枢機卿たちは、普段は自分の国や地域で聖職に従事していますが、一部の枢機卿は、バチカン内での国家役職にも就いています。こうした構造が、グローバル企業の組織機構と似ているのですね。
新教皇に選出されたレオ14世は、初のアメリカ出身の教皇です。南米ペルーで長年、救貧活動などを行ってきました。一方、バチカン内では、司教の選任などに影響力を持つ司教省長官を務めています。つまり、現場の“たたき上げ”でありながら、バチカン中枢からも支持を得ていた人物であるということです。
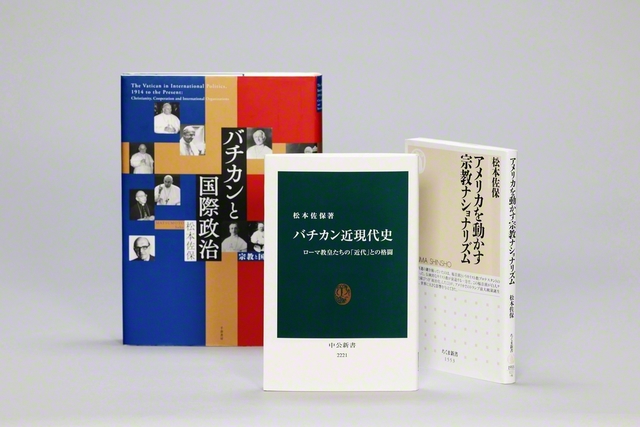
松本さんの著書の一部
松本さんの著書の一部
実社会に関わる
実社会に関わる
――レオ14世は、どのような理念を掲げているのでしょうか。
レオ14世という教皇名を選んだのは、「レオ13世を手本にします」という思いの表れです。
では、そのレオ13世は何をした人物か。一つの功績は、1891年、「レールム・ノヴァールム」という回勅(教皇が全カトリック教徒に向けて発布する書簡)で、行き過ぎた資本主義の弊害について警告し、資本家たちに搾取されていた労働者の権利と尊厳を訴えたことです。
マルクスとエンゲルスが『共産党宣言』を発表してから、40年余りたった頃のこと。同宣言の影響がヨーロッパ全土に広がる中、レオ13世は、階級闘争や暴力革命ではなく、階級間の協調で、苦しむ労働者を救う道を示しました。
例えば、労働者が権利獲得のために団結し、相互扶助をしていく必要性を説きました。これを機に、結社が禁じられていたイタリア内で、労働組合が本格的に組織化されていくことになります。後のヨーロッパ共同体(EC)に見られるような共同体論にも、影響を与えました。
この回勅は「社会回勅」とも呼ばれ、評価されています。祈るだけでよしとするのではなく、実社会と関わっていくのが教会の使命であると宣言したからです。この理念を踏襲するというのが、レオ14世の根本のビジョンです。
前教皇フランシスコも、弱い立場の人に寄り添う指導者でした。格差の拡大を深刻視し、移民や難民の問題に向き合い続けました。レオ14世もこれらの路線を継承しつつ、アメリカとの外交をはじめ、不安定な世界情勢に対してさまざまな戦略を練っているように思います。
――レオ14世は、どのような理念を掲げているのでしょうか。
レオ14世という教皇名を選んだのは、「レオ13世を手本にします」という思いの表れです。
では、そのレオ13世は何をした人物か。一つの功績は、1891年、「レールム・ノヴァールム」という回勅(教皇が全カトリック教徒に向けて発布する書簡)で、行き過ぎた資本主義の弊害について警告し、資本家たちに搾取されていた労働者の権利と尊厳を訴えたことです。
マルクスとエンゲルスが『共産党宣言』を発表してから、40年余りたった頃のこと。同宣言の影響がヨーロッパ全土に広がる中、レオ13世は、階級闘争や暴力革命ではなく、階級間の協調で、苦しむ労働者を救う道を示しました。
例えば、労働者が権利獲得のために団結し、相互扶助をしていく必要性を説きました。これを機に、結社が禁じられていたイタリア内で、労働組合が本格的に組織化されていくことになります。後のヨーロッパ共同体(EC)に見られるような共同体論にも、影響を与えました。
この回勅は「社会回勅」とも呼ばれ、評価されています。祈るだけでよしとするのではなく、実社会と関わっていくのが教会の使命であると宣言したからです。この理念を踏襲するというのが、レオ14世の根本のビジョンです。
前教皇フランシスコも、弱い立場の人に寄り添う指導者でした。格差の拡大を深刻視し、移民や難民の問題に向き合い続けました。レオ14世もこれらの路線を継承しつつ、アメリカとの外交をはじめ、不安定な世界情勢に対してさまざまな戦略を練っているように思います。

原田会長がフランシスコ前教皇と会見(昨年5月、バチカンのアポストリコ宮殿で)©Vatican Media
原田会長がフランシスコ前教皇と会見(昨年5月、バチカンのアポストリコ宮殿で)©Vatican Media
近代化の中で
近代化の中で
――著書『バチカン近現代史』(中公新書)では、バチカンの歴史を「近代化」という切り口から考察されています。
2000年の歴史の中で、バチカンあるいはカトリック教会は、幾度も危機に直面しています。それを乗り越える一つの鍵が、近代化への対応でした。
18世紀末のフランス革命では、宗教的また政治的に絶大な権力を握っていたカトリックの聖職者が、権力の座から引きずりおろされました。そしてナポレオンの帝政下、ローマ教皇が軟禁されるなどカトリック教会は弾圧の対象となります。そこからフランスでは、今日まで続く、教会と国家の完全な分離が進められていきました。
一方でフランス革命は、バチカンにとって、教会の権威を振りかざすのではなく、平和外交に重きを置いた戦略へと舵を切ることで、近代化の中で“生き残る”ための契機になったと見ることもできます。
第1次世界大戦では、教皇ベネディクト15世が戦争の平和的解決を模索し、停戦交渉に乗り出しました。戦地では、さまざまなカトリック団体を利用して、負傷兵の治療を行う医療施設の開設、戦死者の埋葬、戦争捕虜の釈放や交換などの活動を展開しています。当時、プロテスタントに起源を持つ赤十字も同様の活動を行っていたことで、両者は協力して活動しました。
かつてはカトリック対プロテスタントが争いの構図でしたが、第1次世界大戦では、同じ宗派の中に敵も味方もいました。それ故、赤十字と同様、バチカンは国際的な中立の立場を宣言します。これによって、敵か味方かを問うことなく、医療行為や救援活動などが可能になりました。
また、1962年から65年にかけて「第二バチカン公会議」(注)が行われました。この会議が現代において持つ意義は、第一に、カトリック内のエキュメニズム(一致)です。例えば従来、教会でのミサは、世界のどこでもラテン語で実施されるものと決められていましたが、公会議では、英語や日本語など各国の母語を使用していいということが、正式に認められました。
次に、他宗派とのエキュメニズムです。キリスト教は宗派によって分裂するのではなく、「普遍的(=カトリック)」な一つの教会の下に一致すべきとの思想が、公会議で打ち出されました。そして事実、後に正教会とは1000年ぶりの和解の道が開かれるなど、公会議は、他の宗派とも対話していくカトリック教会へと姿を変える転機となったのです。
また、この公会議では、軍備撤廃の義務、平和のための国際協力、貧困と不正義に立ち向かう姿勢などについても議論がなされています。その結果、バチカンは投票権を持たない中立の立場でありながら、国連の会議にオブザーバーとして参加し続けることとなり、以来、その発言による影響力は無視できないものとなっています。
国際情勢に敏感に反応しながら、紛争解決や人道活動に積極的に関与する、バチカンの今日的な姿はこうして築かれました。
――著書『バチカン近現代史』(中公新書)では、バチカンの歴史を「近代化」という切り口から考察されています。
2000年の歴史の中で、バチカンあるいはカトリック教会は、幾度も危機に直面しています。それを乗り越える一つの鍵が、近代化への対応でした。
18世紀末のフランス革命では、宗教的また政治的に絶大な権力を握っていたカトリックの聖職者が、権力の座から引きずりおろされました。そしてナポレオンの帝政下、ローマ教皇が軟禁されるなどカトリック教会は弾圧の対象となります。そこからフランスでは、今日まで続く、教会と国家の完全な分離が進められていきました。
一方でフランス革命は、バチカンにとって、教会の権威を振りかざすのではなく、平和外交に重きを置いた戦略へと舵を切ることで、近代化の中で“生き残る”ための契機になったと見ることもできます。
第1次世界大戦では、教皇ベネディクト15世が戦争の平和的解決を模索し、停戦交渉に乗り出しました。戦地では、さまざまなカトリック団体を利用して、負傷兵の治療を行う医療施設の開設、戦死者の埋葬、戦争捕虜の釈放や交換などの活動を展開しています。当時、プロテスタントに起源を持つ赤十字も同様の活動を行っていたことで、両者は協力して活動しました。
かつてはカトリック対プロテスタントが争いの構図でしたが、第1次世界大戦では、同じ宗派の中に敵も味方もいました。それ故、赤十字と同様、バチカンは国際的な中立の立場を宣言します。これによって、敵か味方かを問うことなく、医療行為や救援活動などが可能になりました。
また、1962年から65年にかけて「第二バチカン公会議」(注)が行われました。この会議が現代において持つ意義は、第一に、カトリック内のエキュメニズム(一致)です。例えば従来、教会でのミサは、世界のどこでもラテン語で実施されるものと決められていましたが、公会議では、英語や日本語など各国の母語を使用していいということが、正式に認められました。
次に、他宗派とのエキュメニズムです。キリスト教は宗派によって分裂するのではなく、「普遍的(=カトリック)」な一つの教会の下に一致すべきとの思想が、公会議で打ち出されました。そして事実、後に正教会とは1000年ぶりの和解の道が開かれるなど、公会議は、他の宗派とも対話していくカトリック教会へと姿を変える転機となったのです。
また、この公会議では、軍備撤廃の義務、平和のための国際協力、貧困と不正義に立ち向かう姿勢などについても議論がなされています。その結果、バチカンは投票権を持たない中立の立場でありながら、国連の会議にオブザーバーとして参加し続けることとなり、以来、その発言による影響力は無視できないものとなっています。
国際情勢に敏感に反応しながら、紛争解決や人道活動に積極的に関与する、バチカンの今日的な姿はこうして築かれました。
(注)公会議とは、世界中の聖職者が集まり、教義や教会規則について審議決定する会議のこと。第二バチカン公会議は、1869年以来、約100年ぶりの開催となった。
(注)公会議とは、世界中の聖職者が集まり、教義や教会規則について審議決定する会議のこと。第二バチカン公会議は、1869年以来、約100年ぶりの開催となった。
宗派を超えて
宗派を超えて
――2017年、核兵器廃絶を巡る国際会議がバチカンで開催され、創価学会も協力団体として招へいされました。以降もバチカンをはじめカトリック団体と、核廃絶や気候変動などの具体的な課題解決のため協働しています。
創価学会が活発に宗教間対話を行っていることは、存じ上げています。前ローマ教皇のフランシスコも、宗派を超えた対話の場を大切にしていました。
フランシスコは化学を専攻した背景もあり、環境問題について精力的に発信しました。2015年に出した回勅「ラウダート・シ」は、多くの科学的データを基に地球温暖化について訴え、温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」の合意も後押ししました。また、19年11月には、教皇として38年ぶりに訪日し、東京のほか広島、長崎も訪れ、核兵器のない世界への展望を語りました。
社会課題に具体的に取り組むカトリックが、その輪を広げる宗教間対話に熱心であるのは、意義深いことだと思います。近年は特にイスラム教との対話を重要視し、フランシスコもエジプト、アラブ首長国連邦、イラクといった中東国を訪れ、指導者との対話に臨んでいます。
そして今、バチカンが特に力を入れているテーマの一つはAI(人工知能)です。レオ14世は新教皇に選出された直後の演説で、レオ13世が「最初の産業革命の時代における社会問題」に取り組んだことに言及しつつ、自らが取り組むべきは、「新たな産業革命とAIの進展による、人間の尊厳、正義、そして労働を守ること」であると訴えました。バチカンは本年1月にも、AIの倫理的ガイドラインを発表しています。
今後も教皇を中心に、このテーマを巡る議論が宗教間で進んでいくことと思います。
――2017年、核兵器廃絶を巡る国際会議がバチカンで開催され、創価学会も協力団体として招へいされました。以降もバチカンをはじめカトリック団体と、核廃絶や気候変動などの具体的な課題解決のため協働しています。
創価学会が活発に宗教間対話を行っていることは、存じ上げています。前ローマ教皇のフランシスコも、宗派を超えた対話の場を大切にしていました。
フランシスコは化学を専攻した背景もあり、環境問題について精力的に発信しました。2015年に出した回勅「ラウダート・シ」は、多くの科学的データを基に地球温暖化について訴え、温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」の合意も後押ししました。また、19年11月には、教皇として38年ぶりに訪日し、東京のほか広島、長崎も訪れ、核兵器のない世界への展望を語りました。
社会課題に具体的に取り組むカトリックが、その輪を広げる宗教間対話に熱心であるのは、意義深いことだと思います。近年は特にイスラム教との対話を重要視し、フランシスコもエジプト、アラブ首長国連邦、イラクといった中東国を訪れ、指導者との対話に臨んでいます。
そして今、バチカンが特に力を入れているテーマの一つはAI(人工知能)です。レオ14世は新教皇に選出された直後の演説で、レオ13世が「最初の産業革命の時代における社会問題」に取り組んだことに言及しつつ、自らが取り組むべきは、「新たな産業革命とAIの進展による、人間の尊厳、正義、そして労働を守ること」であると訴えました。バチカンは本年1月にも、AIの倫理的ガイドラインを発表しています。
今後も教皇を中心に、このテーマを巡る議論が宗教間で進んでいくことと思います。

バチカンで開かれた核兵器のない世界を巡る国際会議にSGIの代表が参加。池田主任副会長が登壇した(2017年11月)
バチカンで開かれた核兵器のない世界を巡る国際会議にSGIの代表が参加。池田主任副会長が登壇した(2017年11月)
武力よりも対話と協調で
希望の未来を描き続ける
武力よりも対話と協調で
希望の未来を描き続ける
――軍事力を持たない国家であるバチカンの外交は、武力ではなく対話で、平和の橋を架ける「ソフトパワー」による外交です。混迷する状況でも、相手をねじ伏せるのではなく協調を模索する姿勢に、宗教的信念を見る思いです。
歴代の教皇たちが、そうしたソフトパワーによる外交を主導してきました。
冷戦期には、教会を通じたネットワークを持つバチカンが、共産主義圏である東側と直接対話できる数少ない組織の一つでした。キューバ・ミサイル危機(1962年)に際しては、教皇ヨハネ23世がアメリカ側とソ連側の両方とコンタクトを取り、核戦争を止める契機をつくりました。
また、ポーランド出身の教皇ヨハネ・パウロ2世は、共産圏であった母国を3度、訪問しています。後に同国の大統領となるワレサらを激励したことで、民主化運動は勢いづき、ポーランドでは89年6月、共産党の一党独裁政治が終わりを告げました。そしてそれは、他の東欧諸国の民主化や、「ベルリンの壁」崩壊と冷戦終結への第一歩となったのです。
国際政治はリアリズムの世界です。平和や安全保障を唱えても、それにどれほど効力があるのかと批判する人たちもいます。ウクライナ危機や中東情勢、世界を不安にするアメリカの動向など、私たちの目の前の現実を、即座に好転させられる解決策はないかもしれません。
それでも、常に長期的な視点に立ったバチカンの外交から、学べることはあります。ある日突然、起こったように見える紛争や武力行使も、長年の歴史の上に原因が蓄積された故の結果であると捉える。そして一つ一つ、歴史をさかのぼって検証すると同時に、今、これから取り組む平和のための努力が、たとえすぐには結果が出なくとも、長期的には効果を発揮するかもしれないという希望を手放さない。
過去に対しても未来に対しても、長期的な視点で世界を見つめることで、先に挙げたような歴史の扉が開かれていきました。
諦めの心に、容易に支配されてしまいそうな世の中にあって、それでもなお希望のメッセージを発信し続けていけるのが、宗教を持つ人々ではないでしょうか。バチカンの歴史が映し出すのは、人類の平和を願い、未来を信じて行動し続けていく、宗教の可能性であるようにも思います。
――軍事力を持たない国家であるバチカンの外交は、武力ではなく対話で、平和の橋を架ける「ソフトパワー」による外交です。混迷する状況でも、相手をねじ伏せるのではなく協調を模索する姿勢に、宗教的信念を見る思いです。
歴代の教皇たちが、そうしたソフトパワーによる外交を主導してきました。
冷戦期には、教会を通じたネットワークを持つバチカンが、共産主義圏である東側と直接対話できる数少ない組織の一つでした。キューバ・ミサイル危機(1962年)に際しては、教皇ヨハネ23世がアメリカ側とソ連側の両方とコンタクトを取り、核戦争を止める契機をつくりました。
また、ポーランド出身の教皇ヨハネ・パウロ2世は、共産圏であった母国を3度、訪問しています。後に同国の大統領となるワレサらを激励したことで、民主化運動は勢いづき、ポーランドでは89年6月、共産党の一党独裁政治が終わりを告げました。そしてそれは、他の東欧諸国の民主化や、「ベルリンの壁」崩壊と冷戦終結への第一歩となったのです。
国際政治はリアリズムの世界です。平和や安全保障を唱えても、それにどれほど効力があるのかと批判する人たちもいます。ウクライナ危機や中東情勢、世界を不安にするアメリカの動向など、私たちの目の前の現実を、即座に好転させられる解決策はないかもしれません。
それでも、常に長期的な視点に立ったバチカンの外交から、学べることはあります。ある日突然、起こったように見える紛争や武力行使も、長年の歴史の上に原因が蓄積された故の結果であると捉える。そして一つ一つ、歴史をさかのぼって検証すると同時に、今、これから取り組む平和のための努力が、たとえすぐには結果が出なくとも、長期的には効果を発揮するかもしれないという希望を手放さない。
過去に対しても未来に対しても、長期的な視点で世界を見つめることで、先に挙げたような歴史の扉が開かれていきました。
諦めの心に、容易に支配されてしまいそうな世の中にあって、それでもなお希望のメッセージを発信し続けていけるのが、宗教を持つ人々ではないでしょうか。バチカンの歴史が映し出すのは、人類の平和を願い、未来を信じて行動し続けていく、宗教の可能性であるようにも思います。
まつもと・さほ 神戸市生まれ。聖心女子大学卒業、慶應義塾大学大学院修士課程修了。英国ウォーリック大学大学院PhD取得。博士(国際政治史)。専門は国際政治と宗教の関係(英米日、イタリア、バチカン政治・外交・文化史)。イタリア政府給費留学生としてバチカン使徒文書(機密文書)館で調査、ローマ教皇研究を行う。名古屋市立大学大学院教授を経て現在、日本大学国際関係学部教授。著書に『バチカン近現代史――ローマ教皇たちの「近代」との格闘』(中公新書)、『バチカンと国際政治――宗教と国際機構の交錯』(千倉書房)、『アメリカを動かす宗教ナショナリズム』(ちくま新書)、『熱狂する「神の国」アメリカ――大統領とキリスト教』(文春新書)など。
まつもと・さほ 神戸市生まれ。聖心女子大学卒業、慶應義塾大学大学院修士課程修了。英国ウォーリック大学大学院PhD取得。博士(国際政治史)。専門は国際政治と宗教の関係(英米日、イタリア、バチカン政治・外交・文化史)。イタリア政府給費留学生としてバチカン使徒文書(機密文書)館で調査、ローマ教皇研究を行う。名古屋市立大学大学院教授を経て現在、日本大学国際関係学部教授。著書に『バチカン近現代史――ローマ教皇たちの「近代」との格闘』(中公新書)、『バチカンと国際政治――宗教と国際機構の交錯』(千倉書房)、『アメリカを動かす宗教ナショナリズム』(ちくま新書)、『熱狂する「神の国」アメリカ――大統領とキリスト教』(文春新書)など。
●ご感想をお寄せください。
kansou@seikyo-np.jp
ファクス 03-5360-9613
●ご感想をお寄せください。
kansou@seikyo-np.jp
ファクス 03-5360-9613
●こちらから、「危機の時代を生きる」識者インタビューの過去の連載の一部をご覧いただけます。
●こちらから、「危機の時代を生きる」識者インタビューの過去の連載の一部をご覧いただけます。