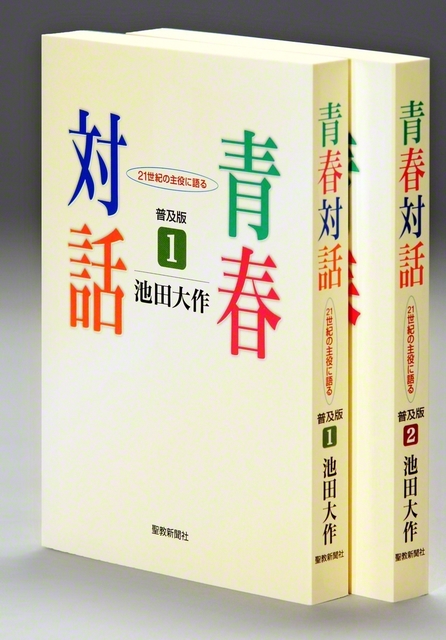作家・佐藤優さんと学園生の対話プロジェクト「明日への扉」 第1回 東京・創価高校
作家・佐藤優さんと学園生の対話プロジェクト「明日への扉」 第1回 東京・創価高校
2025年6月19日
- 池田先生の哲学を学び実践へ
- 池田先生の哲学を学び実践へ

東京・創価学園の池田講堂で行われた対話プロジェクト。より良き人生を模索する創価高校生の真剣な質問に対し、佐藤優さんの声も熱をおびた(4日)
東京・創価学園の池田講堂で行われた対話プロジェクト。より良き人生を模索する創価高校生の真剣な質問に対し、佐藤優さんの声も熱をおびた(4日)
東京・関西の創価学園生と作家・佐藤優さんとの全4回にわたる対話プロジェクトが、今月から始まりました。題名は「明日への扉――君たちだから伝えたいこと」。“現代の知の巨人”とも呼ばれる佐藤さんは、「創価学園の使命は大きい。日本や世界の発展に貢献する人たちを育み、多くの人に影響を与えてほしい」と期待しています。第1回は4日、東京・小平市の創価学園で、高校生を対象に。佐藤さんの講演に続き、生徒とのトークセッションや質疑応答も行われました。当日の模様と舞台裏に迫ります。(記事=真鍋拓馬)
東京・関西の創価学園生と作家・佐藤優さんとの全4回にわたる対話プロジェクトが、今月から始まりました。題名は「明日への扉――君たちだから伝えたいこと」。“現代の知の巨人”とも呼ばれる佐藤さんは、「創価学園の使命は大きい。日本や世界の発展に貢献する人たちを育み、多くの人に影響を与えてほしい」と期待しています。第1回は4日、東京・小平市の創価学園で、高校生を対象に。佐藤さんの講演に続き、生徒とのトークセッションや質疑応答も行われました。当日の模様と舞台裏に迫ります。(記事=真鍋拓馬)

さとう・まさる 1960年、東京都生まれ。同志社大学大学院神学研究科修了後、専門職員として外務省に入省。在イギリス大使館、在ロシア大使館での勤務を経て、外務省国際情報局で主任分析官として活躍。『国家の罠』(毎日出版文化賞特別賞)、『自壊する帝国』(新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞)、『池田大作研究 世界宗教への道を追う』など著書多数。
さとう・まさる 1960年、東京都生まれ。同志社大学大学院神学研究科修了後、専門職員として外務省に入省。在イギリス大使館、在ロシア大使館での勤務を経て、外務省国際情報局で主任分析官として活躍。『国家の罠』(毎日出版文化賞特別賞)、『自壊する帝国』(新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞)、『池田大作研究 世界宗教への道を追う』など著書多数。
教材は『青春対話』
教材は『青春対話』
創立者・池田先生の膨大な著作を読み解いてきた佐藤さんに、ぜひ講演してほしい――創価学園側からの依頼でプロジェクトは始まりました。快諾した佐藤さんと相談の末、教材は『青春対話』に決まります。青春時代の悩みについて、池田先生がアドバイスと励ましを送った書籍です。
事前に学園生に読んでもらい、印象に残った箇所と、その理由を書いてもらうことになりました。創価高校では、自由にディスカッションする機会も設けられ、さまざまな声が集まってきました。
例えば「高校の成績で一生が決まるものではない。努力で決まる。正しく歩んでいるかどうかで決まる」との箇所に触れた生徒は、「どうすれば悩める人、苦しんでいる人、不幸な人の味方になれるかを考えるようになりました」と。また、「青春時代は『学びの時代』『鍛えの時代』と思って、何にでも挑戦してみることだ」との一節に、「自分にしかできない使命を、自分にしかできない努力で見つけたい」と心の変化を述べる生徒もいました。
そうした学園生のリポートを全て読んだ佐藤さんは、学園生から“生きることへの真摯な姿勢”を感じ取ったといいます。「皆さんが池田先生と創価学園から学んでいるものを引き出すことこそ、私の役目です」
創立者・池田先生の膨大な著作を読み解いてきた佐藤さんに、ぜひ講演してほしい――創価学園側からの依頼でプロジェクトは始まりました。快諾した佐藤さんと相談の末、教材は『青春対話』に決まります。青春時代の悩みについて、池田先生がアドバイスと励ましを送った書籍です。
事前に学園生に読んでもらい、印象に残った箇所と、その理由を書いてもらうことになりました。創価高校では、自由にディスカッションする機会も設けられ、さまざまな声が集まってきました。
例えば「高校の成績で一生が決まるものではない。努力で決まる。正しく歩んでいるかどうかで決まる」との箇所に触れた生徒は、「どうすれば悩める人、苦しんでいる人、不幸な人の味方になれるかを考えるようになりました」と。また、「青春時代は『学びの時代』『鍛えの時代』と思って、何にでも挑戦してみることだ」との一節に、「自分にしかできない使命を、自分にしかできない努力で見つけたい」と心の変化を述べる生徒もいました。
そうした学園生のリポートを全て読んだ佐藤さんは、学園生から“生きることへの真摯な姿勢”を感じ取ったといいます。「皆さんが池田先生と創価学園から学んでいるものを引き出すことこそ、私の役目です」
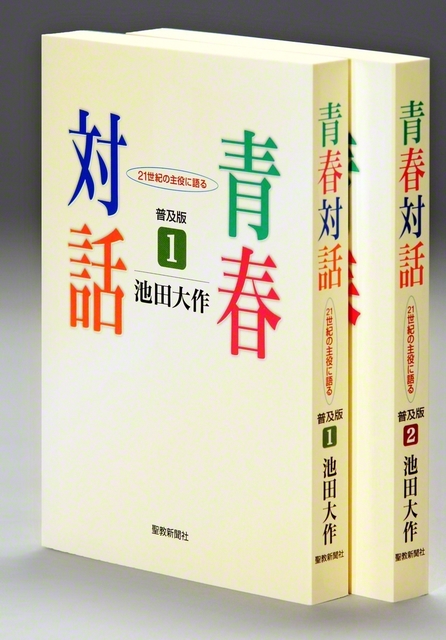
対話プロジェクトの教材となった、学園創立者・池田先生の著作『青春対話』
対話プロジェクトの教材となった、学園創立者・池田先生の著作『青春対話』
信仰の力とは?
信仰の力とは?
迎えた当日、満員の池田講堂で佐藤さんがまず話し始めたのは、自身の信仰のことでした。「プロテスタントである佐藤さんが、どうして仏教徒である創立者を敬愛してやまないのか」という、学園生が抱いている素朴な疑問に答えるように――。
佐藤さんの母親は沖縄・久米島生まれ。14歳で沖縄戦を経験します。米兵に見つかった際に、手榴弾で自決しようとして、多くの人を巻き込む寸前のところで引き止められました。また故郷の久米島では、味方であるはずの日本兵が、島民にスパイ容疑をかけ、殺害する光景も目の当たりにしたといいます。母が抱いた罪の意識と正義への疑念による“精神の空白”を埋めてくれたのがキリスト教でした。「母は最悪の状況から救われたからこそ、戦争体験を話すことができた。それが信仰の力だと思う」と語ります。
佐藤さんの話は、恩納村にある創価学会の沖縄研修道場を本年5月に訪れた時のことにも及びました。日本兵や米兵による残虐な行為を戦争体験者が描いた、常設の「沖縄戦の絵」展を見て、“ここにも信仰で救われた方々がいる”と感じたといいます。
信仰で憎しみを乗り越え、平和の心を継承する――希望と使命を与える力が宗教にはあることを、未来を担う学園生に訴えました。
迎えた当日、満員の池田講堂で佐藤さんがまず話し始めたのは、自身の信仰のことでした。「プロテスタントである佐藤さんが、どうして仏教徒である創立者を敬愛してやまないのか」という、学園生が抱いている素朴な疑問に答えるように――。
佐藤さんの母親は沖縄・久米島生まれ。14歳で沖縄戦を経験します。米兵に見つかった際に、手榴弾で自決しようとして、多くの人を巻き込む寸前のところで引き止められました。また故郷の久米島では、味方であるはずの日本兵が、島民にスパイ容疑をかけ、殺害する光景も目の当たりにしたといいます。母が抱いた罪の意識と正義への疑念による“精神の空白”を埋めてくれたのがキリスト教でした。「母は最悪の状況から救われたからこそ、戦争体験を話すことができた。それが信仰の力だと思う」と語ります。
佐藤さんの話は、恩納村にある創価学会の沖縄研修道場を本年5月に訪れた時のことにも及びました。日本兵や米兵による残虐な行為を戦争体験者が描いた、常設の「沖縄戦の絵」展を見て、“ここにも信仰で救われた方々がいる”と感じたといいます。
信仰で憎しみを乗り越え、平和の心を継承する――希望と使命を与える力が宗教にはあることを、未来を担う学園生に訴えました。
勉強や友情を巡り
勉強や友情を巡り
続いて、『青春対話』を読み、多くの学園生が“心に残った”とつづったテーマを取り上げ、エールを送ります。
恋愛についての章では、「『青春時代』『社会に出る時代』『結婚する時代』等と、人生には時代がある。その時代を、一歩一歩進んでいくのが道理です」「勉強の炎を消してはいけない。無軌道になってはいけない。軌道の人生を生きなさい」を引用しました。高校時代は勉強が主であることを確認した上で、もう一つ大事な観点を話します。「受けるよりは与えるほうが幸いである」(新約聖書)というが、今は最大限に受け取って、将来、与えられるような人になればいい――と。今は決して焦らなくていい。「自分は人に与えるものが何もない」などと卑下する必要もない。君たちは創価学園から与えられるものを思う存分、受け取って、未来に向かって力を付ければいいということでしょう。
また、長続きする友情とは何かを巡り、「友情とは、彼が苦しんでいる時に同じように苦しみ、励ます。自分が苦しんでいる時に彼が同じように苦しみ、励ましてくれる。そういう、清らかな川の流れのような姿です」との一節を引きます。佐藤さんは実体験から「自身が信じていることを尊重してくれる人」との友情は、長続きするのだと語りました。
学園生の世代が頻繁に目にするSNSでは、価値観の異なる他者に対し、差別的な意見をぶつける投稿も散見され、対立も目立ちます。そうした事実を踏まえつつ、佐藤さんは、一対一の対話を通して友情を広げてきた池田先生の言葉を通し、現代の課題に向き合うヒントを示しました。
続いて、『青春対話』を読み、多くの学園生が“心に残った”とつづったテーマを取り上げ、エールを送ります。
恋愛についての章では、「『青春時代』『社会に出る時代』『結婚する時代』等と、人生には時代がある。その時代を、一歩一歩進んでいくのが道理です」「勉強の炎を消してはいけない。無軌道になってはいけない。軌道の人生を生きなさい」を引用しました。高校時代は勉強が主であることを確認した上で、もう一つ大事な観点を話します。「受けるよりは与えるほうが幸いである」(新約聖書)というが、今は最大限に受け取って、将来、与えられるような人になればいい――と。今は決して焦らなくていい。「自分は人に与えるものが何もない」などと卑下する必要もない。君たちは創価学園から与えられるものを思う存分、受け取って、未来に向かって力を付ければいいということでしょう。
また、長続きする友情とは何かを巡り、「友情とは、彼が苦しんでいる時に同じように苦しみ、励ます。自分が苦しんでいる時に彼が同じように苦しみ、励ましてくれる。そういう、清らかな川の流れのような姿です」との一節を引きます。佐藤さんは実体験から「自身が信じていることを尊重してくれる人」との友情は、長続きするのだと語りました。
学園生の世代が頻繁に目にするSNSでは、価値観の異なる他者に対し、差別的な意見をぶつける投稿も散見され、対立も目立ちます。そうした事実を踏まえつつ、佐藤さんは、一対一の対話を通して友情を広げてきた池田先生の言葉を通し、現代の課題に向き合うヒントを示しました。

佐藤さんの当意即妙のやりとりに創価学園生の緊張もほぐれる
佐藤さんの当意即妙のやりとりに創価学園生の緊張もほぐれる
活発な質疑応答
活発な質疑応答
佐藤さんの講演の後には、学園生の代表6人も壇上に上がって、トークセッションが始まりました。気になることを自由に質問していくスタイルです。事前に打ち合わせはありましたが、シナリオはつくらず、全くのアドリブです。
中学・高校で文化系クラブに所属してきた、ある高校3年の女子生徒は、『青春対話』にある「芸術との語らい」の章を引きました。その章では、“他者と交流しよう”“皆を喜ばせたい”等の心をつくるのが本当の芸術・文化であり、上手・下手といったことよりも、“心こそ大切”であることが述べられています。
彼女は、この章を読んで、文化活動を楽しむ大切さを実感した半面、コンクールで結果を出すには技術が必要であり、両者をどう成り立たせていくかに悩んでいるようでした。結果を追い求めたゆえに、プレッシャーに苦しむ部員が出てくることもあるからです。
佐藤さんは、同じ章にある「一流を見ていれば、二流・三流は、すぐわかる。鑑識眼ができてくる。だから、最初から、最高のものに触れるべきです」「よい芸術と接することが、自分の心を養っていくのです」との一節に触れ、こう答えました。
「上を目指そうと思えば、いくらでも上の目標がある。まずは池田先生の言うように、一流に触れて自身を高めることを大事にしてほしい。そうすれば、おのずと結果はついてくると思います」
佐藤さんの講演の後には、学園生の代表6人も壇上に上がって、トークセッションが始まりました。気になることを自由に質問していくスタイルです。事前に打ち合わせはありましたが、シナリオはつくらず、全くのアドリブです。
中学・高校で文化系クラブに所属してきた、ある高校3年の女子生徒は、『青春対話』にある「芸術との語らい」の章を引きました。その章では、“他者と交流しよう”“皆を喜ばせたい”等の心をつくるのが本当の芸術・文化であり、上手・下手といったことよりも、“心こそ大切”であることが述べられています。
彼女は、この章を読んで、文化活動を楽しむ大切さを実感した半面、コンクールで結果を出すには技術が必要であり、両者をどう成り立たせていくかに悩んでいるようでした。結果を追い求めたゆえに、プレッシャーに苦しむ部員が出てくることもあるからです。
佐藤さんは、同じ章にある「一流を見ていれば、二流・三流は、すぐわかる。鑑識眼ができてくる。だから、最初から、最高のものに触れるべきです」「よい芸術と接することが、自分の心を養っていくのです」との一節に触れ、こう答えました。
「上を目指そうと思えば、いくらでも上の目標がある。まずは池田先生の言うように、一流に触れて自身を高めることを大事にしてほしい。そうすれば、おのずと結果はついてくると思います」
未来を皆で考える
未来を皆で考える
代表6人以外の生徒が質問する時間では、会場にいる参加者から多くの手が挙がりました。
質問に立った生徒が言いました。「創立者が亡くなった今、その心を継いで、学園生がこれからの時代を生き抜くために必要なことは?」
佐藤さんの目が鋭く光ります。そして答えました。「どうやって学園を盛り上げていくべきか」「どうすれば創立者の思いにかなう学園になるか」について、皆が教員と一緒になって考えてほしい。それこそが池田先生への報恩になると思います――と。
思えば創立者・池田先生自身も、先師・牧口先生と恩師・戸田先生が掲げた「創価教育の学びやをつくろう」との遺志を若き日に継ぎ、弟子である自分の手で必ず実現しようと、誓いを立てました。
「明日への扉」を開く鍵は「師弟」にある。池田先生の著作を読めば、胸中で師弟の語らいができる。それこそ「学園生の君たちに伝えたいこと」なんだ――佐藤さんが繰り返し強調した点も、ここにありました。
代表6人以外の生徒が質問する時間では、会場にいる参加者から多くの手が挙がりました。
質問に立った生徒が言いました。「創立者が亡くなった今、その心を継いで、学園生がこれからの時代を生き抜くために必要なことは?」
佐藤さんの目が鋭く光ります。そして答えました。「どうやって学園を盛り上げていくべきか」「どうすれば創立者の思いにかなう学園になるか」について、皆が教員と一緒になって考えてほしい。それこそが池田先生への報恩になると思います――と。
思えば創立者・池田先生自身も、先師・牧口先生と恩師・戸田先生が掲げた「創価教育の学びやをつくろう」との遺志を若き日に継ぎ、弟子である自分の手で必ず実現しようと、誓いを立てました。
「明日への扉」を開く鍵は「師弟」にある。池田先生の著作を読めば、胸中で師弟の語らいができる。それこそ「学園生の君たちに伝えたいこと」なんだ――佐藤さんが繰り返し強調した点も、ここにありました。

心に残った言葉や自身の感想を忘れないようにとメモをとる姿も
心に残った言葉や自身の感想を忘れないようにとメモをとる姿も
生徒の驚きと決意
生徒の驚きと決意
参加した学園生にアンケートを取りました。
「真面目な話ばかりかと思っていたら、ユーモアも交えた話で楽しめた」「私も質問したかった」など、佐藤さんの語り口に引き込まれた生徒の言葉が目立ちました。
特に多かったのは、プロテスタントである佐藤さんが、仏教徒である創立者・池田先生を深く理解していることへの驚きでした。
この日、佐藤さんは、先生に対して尊敬と感謝の念を抱くようになった出来事の一つに、外交官として旧ソ連の日本大使館に勤務していた時の思い出を挙げていました。
今から35年前の1990年7月、池田先生がソ連のゴルバチョフ大統領と初会見した折のこと。当時、国民の関心は“ソ連の国家元首として初の来日が実現するかどうか”に集まっていました。先生は平和を願う宗教者として、何より同じ人間として心を開き、ゴルバチョフ大統領と率直に語り合いました。大統領は会見の席上、「初訪日」の意向を表明し、翌年に実現したのです――。
佐藤さんの視点に感化された生徒たちは「池田先生が残してくださった、たくさんの本から学びたい」「開かれた人格があるのは、宗教の違いを超えて、『人間』という根本の視点に立たれてきたからだと感じました」等の声を寄せています。
また、「私たちが次の時代をつくっていく」との決意が、数多く寄せられたことも印象的でした。
「佐藤さんの言っていた通り、自分たちが考えていかなければならない。『何のため』を追求する学園の意義が分かりました」「佐藤さんは、考えるヒントを与えてくれたと思います」等の意見も。
対話プロジェクトは、まだ始まったばかり。次の舞台は関西です。
参加した学園生にアンケートを取りました。
「真面目な話ばかりかと思っていたら、ユーモアも交えた話で楽しめた」「私も質問したかった」など、佐藤さんの語り口に引き込まれた生徒の言葉が目立ちました。
特に多かったのは、プロテスタントである佐藤さんが、仏教徒である創立者・池田先生を深く理解していることへの驚きでした。
この日、佐藤さんは、先生に対して尊敬と感謝の念を抱くようになった出来事の一つに、外交官として旧ソ連の日本大使館に勤務していた時の思い出を挙げていました。
今から35年前の1990年7月、池田先生がソ連のゴルバチョフ大統領と初会見した折のこと。当時、国民の関心は“ソ連の国家元首として初の来日が実現するかどうか”に集まっていました。先生は平和を願う宗教者として、何より同じ人間として心を開き、ゴルバチョフ大統領と率直に語り合いました。大統領は会見の席上、「初訪日」の意向を表明し、翌年に実現したのです――。
佐藤さんの視点に感化された生徒たちは「池田先生が残してくださった、たくさんの本から学びたい」「開かれた人格があるのは、宗教の違いを超えて、『人間』という根本の視点に立たれてきたからだと感じました」等の声を寄せています。
また、「私たちが次の時代をつくっていく」との決意が、数多く寄せられたことも印象的でした。
「佐藤さんの言っていた通り、自分たちが考えていかなければならない。『何のため』を追求する学園の意義が分かりました」「佐藤さんは、考えるヒントを与えてくれたと思います」等の意見も。
対話プロジェクトは、まだ始まったばかり。次の舞台は関西です。
※ご感想をお寄せください
【メール】 kansou@seikyo-np.jp
【ファクス】 03―5360―9613
※ご感想をお寄せください
【メール】 kansou@seikyo-np.jp
【ファクス】 03―5360―9613
音声読み上げ