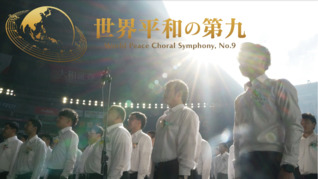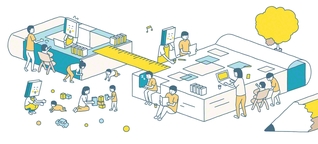多様な人々を結び合い合意つむぐ民主主義を――インタビュー 東京大学大学院教授 境家史郎さん
多様な人々を結び合い合意つむぐ民主主義を――インタビュー 東京大学大学院教授 境家史郎さん
2024年12月19日
- 〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉
- 〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉
世代も価値観も“多様”な社会における民主主義とは――。東京大学大学院の境家史郎教授は「今は、多くの人々が一緒に合意を形成する政治を試すチャンス」と語ります。政治参加の意義などを巡り、インタビューしました。(聞き手=掛川俊明、村上進)
世代も価値観も“多様”な社会における民主主義とは――。東京大学大学院の境家史郎教授は「今は、多くの人々が一緒に合意を形成する政治を試すチャンス」と語ります。政治参加の意義などを巡り、インタビューしました。(聞き手=掛川俊明、村上進)
■現役世代のニーズは何か――「バッファー・プレイヤー」の投票行動
■現役世代のニーズは何か――「バッファー・プレイヤー」の投票行動
――本年10月の衆議院議員選挙は、政権与党が議席を減らす結果になりました。一方で、無党派層が大きく動いて政権が交代した2009年の衆院選とは、また違った状況のように感じます。日本政治や政治参加を専門とする境家教授は、現在の政治状況を、どう捉えていますか。
今回の衆院選の結果は、政権与党に“お灸をすえる”意味合いの強いものだったと思います。
09年の政権交代の際は、当時の民主党に「政権を担当する能力がある」と考え、投票行動を起こした有権者がいました。しかし、今回はそれとは異なります。多くの有権者は、特定の野党に政権担当能力があるとまでは、考えていないのではないでしょうか。
政治不信が強まり、政治と金の問題なども取りざたされ、政権与党に対して「しっかりしなさい」という批判的な投票行動が現れたのだと思います。
政治学者の蒲島郁夫氏は、こうした投票行動を取る有権者を「バッファー・プレイヤー(牽制的投票者)」と呼びました。政権交代までは望まないが、政局は与野党が伯仲しているほうが良いと考える有権者のことです。
――本年10月の衆議院議員選挙は、政権与党が議席を減らす結果になりました。一方で、無党派層が大きく動いて政権が交代した2009年の衆院選とは、また違った状況のように感じます。日本政治や政治参加を専門とする境家教授は、現在の政治状況を、どう捉えていますか。
今回の衆院選の結果は、政権与党に“お灸をすえる”意味合いの強いものだったと思います。
09年の政権交代の際は、当時の民主党に「政権を担当する能力がある」と考え、投票行動を起こした有権者がいました。しかし、今回はそれとは異なります。多くの有権者は、特定の野党に政権担当能力があるとまでは、考えていないのではないでしょうか。
政治不信が強まり、政治と金の問題なども取りざたされ、政権与党に対して「しっかりしなさい」という批判的な投票行動が現れたのだと思います。
政治学者の蒲島郁夫氏は、こうした投票行動を取る有権者を「バッファー・プレイヤー(牽制的投票者)」と呼びました。政権交代までは望まないが、政局は与野党が伯仲しているほうが良いと考える有権者のことです。
同時に、今回の選挙結果には、若い世代の与党離れも影響していると思います。
主に20代から50代までの「現役世代」は、政治に何を求めているのでしょうか。各種の世論調査からは、現役世代は、自分の所得がどうなるかということに非常に敏感であり、経済の問題を争点として捉えていることが分かります。
今回の選挙では、現役世代のニーズを理解し、そうした経済政策に特化して、分かりやすいメッセージを発信した政党が議席を伸ばした印象があります。分かりやすさは、一方ではポピュリズム(大衆迎合主義)と紙一重ではありますが、今回の選挙結果は、私は一つの国民の見識であると思います。
同時に、今回の選挙結果には、若い世代の与党離れも影響していると思います。
主に20代から50代までの「現役世代」は、政治に何を求めているのでしょうか。各種の世論調査からは、現役世代は、自分の所得がどうなるかということに非常に敏感であり、経済の問題を争点として捉えていることが分かります。
今回の選挙では、現役世代のニーズを理解し、そうした経済政策に特化して、分かりやすいメッセージを発信した政党が議席を伸ばした印象があります。分かりやすさは、一方ではポピュリズム(大衆迎合主義)と紙一重ではありますが、今回の選挙結果は、私は一つの国民の見識であると思います。
■「ネオ55年体制」――現代の日本政治のあり方
■「ネオ55年体制」――現代の日本政治のあり方
――境家教授は、著書『戦後日本政治史』の中で、近年の日本の政治システムを「ネオ55年体制」と名付けられました。その体制の中で、中道政党である公明党には、現代の日本政治のあり方を決定づける役割があると指摘されています。
「ネオ55年体制」について説明する前に、元々の「55年体制」について確認します。
1955年に自民党が結党されて以来、93年に一時的に政権を失うまでの日本政治が、「55年体制」です。政治システムの側面から見て、その特徴は、①保守政党が優位政党である、②与野党第一党がイデオロギー的に分極的な立場を取っている、という2点です。
具体的に言えば、①長らく自民党が他党を圧して政権を取り続け、②自民党と社会党の政策的な立場が左右に大きく離れていたことを指します。
こうした55年体制の特徴は、近年の日本政治にも見られることから、私は「ネオ55年体制」と呼んできました。2012年に発足した第2次安倍政権が継続する中で、①自民党一党優位が続き、その後、②防衛政策などにおいて、立憲民主党が自民党と対極的な立場を取っていたからです。
――境家教授は、著書『戦後日本政治史』の中で、近年の日本の政治システムを「ネオ55年体制」と名付けられました。その体制の中で、中道政党である公明党には、現代の日本政治のあり方を決定づける役割があると指摘されています。
「ネオ55年体制」について説明する前に、元々の「55年体制」について確認します。
1955年に自民党が結党されて以来、93年に一時的に政権を失うまでの日本政治が、「55年体制」です。政治システムの側面から見て、その特徴は、①保守政党が優位政党である、②与野党第一党がイデオロギー的に分極的な立場を取っている、という2点です。
具体的に言えば、①長らく自民党が他党を圧して政権を取り続け、②自民党と社会党の政策的な立場が左右に大きく離れていたことを指します。
こうした55年体制の特徴は、近年の日本政治にも見られることから、私は「ネオ55年体制」と呼んできました。2012年に発足した第2次安倍政権が継続する中で、①自民党一党優位が続き、その後、②防衛政策などにおいて、立憲民主党が自民党と対極的な立場を取っていたからです。
新旧の55年体制を比べると、共通点は政権交代の可能性が低いことです。一方、異なる点は、ネオ55年体制において、首相への権力集中度が高まったことです。さらに、もう一つの相違点として、公明党の立場が野党から与党になっていることが挙げられます。
ネオ55年体制において、公明党は、自民党が本来持っている強い右派志向をある程度、中和するブレーキ役として機能してきました。極端な右傾化を抑え、中道化する役割を果たしてきたのです。
「一強」状態ともいわれた当時の安倍政権においても、自民党は公明党の意向を可能な限りくみ取ろうとしていました。中道的な立場を取り、固い支持層を持つ公明党は、日本政治のあり方を決定づける存在であったと考えています。
一方で、10月の衆院選を経て、ネオ55年体制の二つの条件は、揺らいできています。自民党は、比較第一党ではあるものの、一党優位とまではいえない状況になり、各政党の主張を見てもイデオロギー的な対立は少なく、中道寄りになってきています。
新旧の55年体制を比べると、共通点は政権交代の可能性が低いことです。一方、異なる点は、ネオ55年体制において、首相への権力集中度が高まったことです。さらに、もう一つの相違点として、公明党の立場が野党から与党になっていることが挙げられます。
ネオ55年体制において、公明党は、自民党が本来持っている強い右派志向をある程度、中和するブレーキ役として機能してきました。極端な右傾化を抑え、中道化する役割を果たしてきたのです。
「一強」状態ともいわれた当時の安倍政権においても、自民党は公明党の意向を可能な限りくみ取ろうとしていました。中道的な立場を取り、固い支持層を持つ公明党は、日本政治のあり方を決定づける存在であったと考えています。
一方で、10月の衆院選を経て、ネオ55年体制の二つの条件は、揺らいできています。自民党は、比較第一党ではあるものの、一党優位とまではいえない状況になり、各政党の主張を見てもイデオロギー的な対立は少なく、中道寄りになってきています。
■多様な人と合意をつむぐ「コンセンサス型民主主義」
■多様な人と合意をつむぐ「コンセンサス型民主主義」
――これからの日本の政治について、境家教授は、どのようなあり方が望まれると考えていますか。
前提として、民主主義には、いくつかの類型があります。例えば、政治学者アレンド・レイプハルトによれば、民主主義国家には「多数決型」と「コンセンサス型」の二つのタイプがあるといいます。
「多数決型民主主義」の典型はイギリスです。二大政党制の下で、定期的に政権交代を行う体制であり、政権を取った多数派に権力を集中させる制度です。
一方、「コンセンサス型民主主義」は、スイスやオランダなどで見られます。多くの政党が連立政権に参加したり、政策決定に参加したりしながら、コンセンサス(合意)を形成していく体制です。この体制では、多くの人々が統治に参画し、多数の政党に権力が分散されます。
レイプハルトは、ヨーロッパを中心に36カ国のデータを集め、二つのタイプの民主主義を実証的に比較しました。その結果、多様性のある社会においては、コンセンサス型民主主義のほうが、全般的にパフォーマンスに優れていることが分かりました。特に、福祉政策や女性の権利などの点で平等性が重視され、より寛容で、より人に優しい政策が実現しやすいことが示唆されました。
1990年代以降の日本の政治改革運動は、小選挙区制を導入するなど、二大政党を中心とした多数決型の民主主義を目指しました。しかし、日本は今でも二大政党制にはなっておらず、さらに現在は少数与党でもあります。つまり、好むと好まざるとにかかわらず、幅広い党派によるコンセンサス型になるしかありません。多様な人が政策決定に参加し、一緒に合意を形作っていく。今は、そうした政治体制を試すチャンスかもしれません。
――これからの日本の政治について、境家教授は、どのようなあり方が望まれると考えていますか。
前提として、民主主義には、いくつかの類型があります。例えば、政治学者アレンド・レイプハルトによれば、民主主義国家には「多数決型」と「コンセンサス型」の二つのタイプがあるといいます。
「多数決型民主主義」の典型はイギリスです。二大政党制の下で、定期的に政権交代を行う体制であり、政権を取った多数派に権力を集中させる制度です。
一方、「コンセンサス型民主主義」は、スイスやオランダなどで見られます。多くの政党が連立政権に参加したり、政策決定に参加したりしながら、コンセンサス(合意)を形成していく体制です。この体制では、多くの人々が統治に参画し、多数の政党に権力が分散されます。
レイプハルトは、ヨーロッパを中心に36カ国のデータを集め、二つのタイプの民主主義を実証的に比較しました。その結果、多様性のある社会においては、コンセンサス型民主主義のほうが、全般的にパフォーマンスに優れていることが分かりました。特に、福祉政策や女性の権利などの点で平等性が重視され、より寛容で、より人に優しい政策が実現しやすいことが示唆されました。
1990年代以降の日本の政治改革運動は、小選挙区制を導入するなど、二大政党を中心とした多数決型の民主主義を目指しました。しかし、日本は今でも二大政党制にはなっておらず、さらに現在は少数与党でもあります。つまり、好むと好まざるとにかかわらず、幅広い党派によるコンセンサス型になるしかありません。多様な人が政策決定に参加し、一緒に合意を形作っていく。今は、そうした政治体制を試すチャンスかもしれません。

境家さんの主な著書
境家さんの主な著書
――多くの人が政策決定に関わる上では、合意をつむぐために努力を重ね、多様な人々をつなぐ存在が必要だと感じます。その意味でも、これからは「中道」の価値観が大切になるのではないでしょうか。
そもそも有権者のボリュームを考えても、中道が最も多くなります。政治学においても、中道政党が存在感を増すことは、基本的には良いことだとされています。左右両極のポピュリズムに対する、ある種の防波堤のような存在になるからです。
今の日本の政治状況でいえば、自民党が過半数を占めるような一党優位ではなくなったことで、中道政党が役割を果たす条件が整ったと考えています。先ほども述べた通り、自民党はコンセンサス型の政策決定を模索せざるを得ないため、中道的な有権者の求める政策が実現されていくことも想定されます。その意味では、一貫して中道のスタンスを重視してきた公明党の役割は、ますます大きくなるのではないでしょうか。
――90年代以降、日本でも格差社会化が進んでいるといわれます。先ほどは、現役世代が政治に求める経済政策についても話していただきました。世代や主張の違いなどで分断を助長するのではなく、中道の理念に基づいた政治が求められていると思います。これからの政治が目指すべき社会像は、どのようなものだとお考えですか。
国際的な世論調査などで明らかになっている通り、日本では政府や政治への不信が根強く、政治の世界は、ほとんど悪いことをやっているかのように感じられています。そうした社会においては、政府や政治の役割をなるべく小さくすることを望みたくなるのかもしれません。
一方で、それとは異なる考え方もあります。例えば、経済学者の井手英策氏は、「ベーシックサービス」を提案しています。これは、医療や介護、教育、障がい者福祉などのサービスを、所得制限を設けずに、全ての人に無償で提供するという考え方です。
井手氏によれば、日本社会は「自助意識」が非常に強く、さまざまなことを自己責任で何とかしなければならないという考えが根強いといいます。そうした中でベーシックサービスのような、普遍主義的な社会扶助の制度ができたら、それは良いことだと思います。
今の日本にとって、本当に必要なことは何か。そうしたことを超党派で考え、多様な政党が関わりながら合意を生み出していく。そんな政策決定の方式があってもよいのではないでしょうか。
――多くの人が政策決定に関わる上では、合意をつむぐために努力を重ね、多様な人々をつなぐ存在が必要だと感じます。その意味でも、これからは「中道」の価値観が大切になるのではないでしょうか。
そもそも有権者のボリュームを考えても、中道が最も多くなります。政治学においても、中道政党が存在感を増すことは、基本的には良いことだとされています。左右両極のポピュリズムに対する、ある種の防波堤のような存在になるからです。
今の日本の政治状況でいえば、自民党が過半数を占めるような一党優位ではなくなったことで、中道政党が役割を果たす条件が整ったと考えています。先ほども述べた通り、自民党はコンセンサス型の政策決定を模索せざるを得ないため、中道的な有権者の求める政策が実現されていくことも想定されます。その意味では、一貫して中道のスタンスを重視してきた公明党の役割は、ますます大きくなるのではないでしょうか。
――90年代以降、日本でも格差社会化が進んでいるといわれます。先ほどは、現役世代が政治に求める経済政策についても話していただきました。世代や主張の違いなどで分断を助長するのではなく、中道の理念に基づいた政治が求められていると思います。これからの政治が目指すべき社会像は、どのようなものだとお考えですか。
国際的な世論調査などで明らかになっている通り、日本では政府や政治への不信が根強く、政治の世界は、ほとんど悪いことをやっているかのように感じられています。そうした社会においては、政府や政治の役割をなるべく小さくすることを望みたくなるのかもしれません。
一方で、それとは異なる考え方もあります。例えば、経済学者の井手英策氏は、「ベーシックサービス」を提案しています。これは、医療や介護、教育、障がい者福祉などのサービスを、所得制限を設けずに、全ての人に無償で提供するという考え方です。
井手氏によれば、日本社会は「自助意識」が非常に強く、さまざまなことを自己責任で何とかしなければならないという考えが根強いといいます。そうした中でベーシックサービスのような、普遍主義的な社会扶助の制度ができたら、それは良いことだと思います。
今の日本にとって、本当に必要なことは何か。そうしたことを超党派で考え、多様な政党が関わりながら合意を生み出していく。そんな政策決定の方式があってもよいのではないでしょうか。
■宗教が持つ役割——創価学会は人々を穏やかに社会に包摂
■宗教が持つ役割——創価学会は人々を穏やかに社会に包摂
――境家教授の著書『政治参加論』では、1950~60年代の高度成長期における、創価学会の政治参加の社会的な意義についても指摘されています。
政治学の専門書の中で、特定の宗教団体について触れるのは、珍しいことかもしれません。
しかし、創価学会が戦後の日本社会において、非常に大きな規模の現象であることは確かであり、政治学の視点からも、創価学会の活動には大きな意味があったと考えています。
高度成長期において、創価学会が果たした社会的な役割について、二つの視点から説明します。
まずマクロな視点では、創価学会の存在が、戦後日本の政治・社会全体の安定化につながったことが挙げられます。
第2次世界大戦後、多くの国々では、低所得層ほど政治参加がしづらく、政治的・経済的な不平等が起きました。しかし、日本は例外的に、戦後の発展過程において、低所得層の政治参加率が高まり、国民の経済的平等と政治的安定の二つを同時に実現しました。
社会学者の玉野和志氏によれば、創価学会は当時、集団就職で都市にやって来た多くの人を包摂し、活発な政治参加を促しました。
実際に、日本では67年に労働者層の投票率が大きく上向いており、その一因として、同年からの公明党の衆院選への進出がありました。こうした創価学会の活発な政治参加によって、政府の経済政策が、より平等志向を強めるようになったという側面があります。
このように、創価学会を通して、中道政党である公明党を支援する人が増えたことは、経済格差を小さくし、社会の安定化に寄与したと思います。
次に、ミクロな視点からいえば、創価学会が多くの人々に政治参加を促したことで、参加した市民への教育効果があったと推測されます。
政治学には「参加民主主義」という理論があります。政治に参加することで、より優れた民主的な市民に育つことができ、ひいては政治システムも安定するという、教育効果に注目する理論です。政治に関わると、公共的な精神が養われ、自分だけでなく社会全体のことを考えるようになるとされるのです。
――境家教授の著書『政治参加論』では、1950~60年代の高度成長期における、創価学会の政治参加の社会的な意義についても指摘されています。
政治学の専門書の中で、特定の宗教団体について触れるのは、珍しいことかもしれません。
しかし、創価学会が戦後の日本社会において、非常に大きな規模の現象であることは確かであり、政治学の視点からも、創価学会の活動には大きな意味があったと考えています。
高度成長期において、創価学会が果たした社会的な役割について、二つの視点から説明します。
まずマクロな視点では、創価学会の存在が、戦後日本の政治・社会全体の安定化につながったことが挙げられます。
第2次世界大戦後、多くの国々では、低所得層ほど政治参加がしづらく、政治的・経済的な不平等が起きました。しかし、日本は例外的に、戦後の発展過程において、低所得層の政治参加率が高まり、国民の経済的平等と政治的安定の二つを同時に実現しました。
社会学者の玉野和志氏によれば、創価学会は当時、集団就職で都市にやって来た多くの人を包摂し、活発な政治参加を促しました。
実際に、日本では67年に労働者層の投票率が大きく上向いており、その一因として、同年からの公明党の衆院選への進出がありました。こうした創価学会の活発な政治参加によって、政府の経済政策が、より平等志向を強めるようになったという側面があります。
このように、創価学会を通して、中道政党である公明党を支援する人が増えたことは、経済格差を小さくし、社会の安定化に寄与したと思います。
次に、ミクロな視点からいえば、創価学会が多くの人々に政治参加を促したことで、参加した市民への教育効果があったと推測されます。
政治学には「参加民主主義」という理論があります。政治に参加することで、より優れた民主的な市民に育つことができ、ひいては政治システムも安定するという、教育効果に注目する理論です。政治に関わると、公共的な精神が養われ、自分だけでなく社会全体のことを考えるようになるとされるのです。
――近年、「多様性」という言葉をよく見聞きします。今、日本には、属性や価値観の多様さもあれば、長寿化・高齢化によって異なる世代の人々が共存する世代の多様さもあります。現代社会において、境家教授は、創価学会にどのような役割を期待されますか。
高度成長期において、創価学会は、さもなければ社会的・政治的に孤立していたであろう人々を、穏やかな形で社会に包摂する役割を果たしたと思います。
これから宗教団体に期待されるのは、まずは、社会との接点を常識的に保つことでしょう。排外的ではない、社会と協調的な共同体であることが求められると思います。
そして、そこでの活動に参加することで、公共的精神を養ったり、政治参加への意欲を高めたりすることができれば、それは社会にとってポジティブな効果を発揮します。創価学会は、まさにそうした宗教団体であると思います。
政治学の研究者として伝えたいのは、政治を「自分ごと」として捉える意識が必要だということです。多くの人々が、主体的に政治に参加する意識を持つことが大切です。それがなければ、政治は、ますます私たちの現実生活から離れたものになっていってしまうからです。
孤立しがちな多様な人々を結び、政治を含めた社会全体の中に、穏やかに包摂していく。宗教には、そうした重要な役割があると思います。
――近年、「多様性」という言葉をよく見聞きします。今、日本には、属性や価値観の多様さもあれば、長寿化・高齢化によって異なる世代の人々が共存する世代の多様さもあります。現代社会において、境家教授は、創価学会にどのような役割を期待されますか。
高度成長期において、創価学会は、さもなければ社会的・政治的に孤立していたであろう人々を、穏やかな形で社会に包摂する役割を果たしたと思います。
これから宗教団体に期待されるのは、まずは、社会との接点を常識的に保つことでしょう。排外的ではない、社会と協調的な共同体であることが求められると思います。
そして、そこでの活動に参加することで、公共的精神を養ったり、政治参加への意欲を高めたりすることができれば、それは社会にとってポジティブな効果を発揮します。創価学会は、まさにそうした宗教団体であると思います。
政治学の研究者として伝えたいのは、政治を「自分ごと」として捉える意識が必要だということです。多くの人々が、主体的に政治に参加する意識を持つことが大切です。それがなければ、政治は、ますます私たちの現実生活から離れたものになっていってしまうからです。
孤立しがちな多様な人々を結び、政治を含めた社会全体の中に、穏やかに包摂していく。宗教には、そうした重要な役割があると思います。
さかいや・しろう 1978年、大阪府生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科教授。東京大学法学部卒業。博士(法学)。専攻は日本政治論、政治過程論。東京大学社会科学研究所准教授、首都大学東京法学部教授などを経て、現職。著書に『戦後日本政治史』(中公新書)、蒲島郁夫氏との共著に『政治参加論』(東京大学出版会)など。
さかいや・しろう 1978年、大阪府生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科教授。東京大学法学部卒業。博士(法学)。専攻は日本政治論、政治過程論。東京大学社会科学研究所准教授、首都大学東京法学部教授などを経て、現職。著書に『戦後日本政治史』(中公新書)、蒲島郁夫氏との共著に『政治参加論』(東京大学出版会)など。
●ご感想をお寄せください。
kansou@seikyo-np.jp
ファクス 03-5360-9613
●こちらから、「危機の時代を生きる」識者インタビューの過去の連載の一部をご覧いただけます。
●ご感想をお寄せください。
kansou@seikyo-np.jp
ファクス 03-5360-9613
●こちらから、「危機の時代を生きる」識者インタビューの過去の連載の一部をご覧いただけます。
音声読み上げ