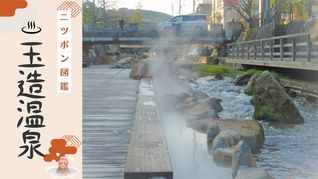191B6583CC2DB1A12388450A5D62FA56
電子版連載〈Chronicle〉 池田先生の若き日を学ぶ
電子版連載〈Chronicle〉 池田先生の若き日を学ぶ
2025年4月21日
- 第13回 5・3 第三代会長就任
- 第13回 5・3 第三代会長就任
1950年代後半から60年代初頭、日本は戦後の混乱を抜け出し、「政治の季節」を経て「経済の季節」へと移ります。時を同じくして、池田先生は創価学会の第3代会長に就任。連載「クロニクル」(年代記)の第13回は、恩師・戸田先生に託された使命を胸に、日本中を駆け、世界広布へと踏み出す、池田先生の戦いに迫ります。
1950年代後半から60年代初頭、日本は戦後の混乱を抜け出し、「政治の季節」を経て「経済の季節」へと移ります。時を同じくして、池田先生は創価学会の第3代会長に就任。連載「クロニクル」(年代記)の第13回は、恩師・戸田先生に託された使命を胸に、日本中を駆け、世界広布へと踏み出す、池田先生の戦いに迫ります。
“60年安保闘争”
“60年安保闘争”

連日、国会前で大規模なデモが行われた(1960年6月)
連日、国会前で大規模なデモが行われた(1960年6月)
1958年、首相となった岸信介は、日米安全保障条約の改定を目指した。しかしこの動きは、“再び日本が戦争の道に進みかねない”という危機感を呼び、知識人をはじめとする人々に、徐々に反発が強まった。
60年5月20日、岸内閣は衆議院で安保条約の改定を強行採決。国会前では連日、数万人規模の抗議デモが行われ、全国の労働者約560万人がストライキを実施するなど、学生から女性まで反対運動が広がった。
6月15日、デモを行っていた全学連(全日本学生自治会総連合)の一部が、国会構内になだれ込み、警官隊と激しく衝突。学生・警官双方に多数の重軽傷者を出し、女子学生の樺美智子さんが亡くなった。
安保条約は数日後に自然成立し、一連の混乱の責任を取る形で岸内閣は退陣したが、国民には虚脱感が残る。以降、広範な市民が参加する政治運動は下火となっていく。
1958年、首相となった岸信介は、日米安全保障条約の改定を目指した。しかしこの動きは、“再び日本が戦争の道に進みかねない”という危機感を呼び、知識人をはじめとする人々に、徐々に反発が強まった。
60年5月20日、岸内閣は衆議院で安保条約の改定を強行採決。国会前では連日、数万人規模の抗議デモが行われ、全国の労働者約560万人がストライキを実施するなど、学生から女性まで反対運動が広がった。
6月15日、デモを行っていた全学連(全日本学生自治会総連合)の一部が、国会構内になだれ込み、警官隊と激しく衝突。学生・警官双方に多数の重軽傷者を出し、女子学生の樺美智子さんが亡くなった。
安保条約は数日後に自然成立し、一連の混乱の責任を取る形で岸内閣は退陣したが、国民には虚脱感が残る。以降、広範な市民が参加する政治運動は下火となっていく。
「所得倍増計画」の発表
「所得倍増計画」の発表

組閣された池田勇人内閣(1960年7月)
組閣された池田勇人内閣(1960年7月)
岸内閣に代わって、池田勇人内閣が新たに誕生した。冷戦によって、世界が資本主義と社会主義の両陣営に二分される中、池田首相は「経済」を前面に掲げる。
10年以内に実質国民総生産を2倍にすることを目指す、「国民所得倍増計画」を発表。豊かな暮らしの実現によって、敗戦国・日本の国民の自信を取り戻し、資本主義のメリットを証明することを狙った。
高度経済成長に突入していた日本は、わずか4年余りで倍増の目標を達成する。この時期を境に、日本社会は「政治の季節」から、「経済の季節」へと移っていった。
岸内閣に代わって、池田勇人内閣が新たに誕生した。冷戦によって、世界が資本主義と社会主義の両陣営に二分される中、池田首相は「経済」を前面に掲げる。
10年以内に実質国民総生産を2倍にすることを目指す、「国民所得倍増計画」を発表。豊かな暮らしの実現によって、敗戦国・日本の国民の自信を取り戻し、資本主義のメリットを証明することを狙った。
高度経済成長に突入していた日本は、わずか4年余りで倍増の目標を達成する。この時期を境に、日本社会は「政治の季節」から、「経済の季節」へと移っていった。
全盛期を迎える映画
全盛期を迎える映画

映画館が立ち並ぶ浅草六区の歓楽街に人があふれる(1956年11月)
映画館が立ち並ぶ浅草六区の歓楽街に人があふれる(1956年11月)
この時期、庶民に最も親しまれた娯楽が、映画だった。1951年にサンフランシスコ講和条約が締結されたことで、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による検閲が廃止。自由な映画制作が可能になったことで、時代劇や第二次世界大戦を描いたフィルムが続々と制作される。黒澤明監督や溝口健二監督の作品をはじめ、日本映画が国際映画祭で次々と受賞し、世界的な注目を集めることになった。
国内の映画業界では、東宝・新東宝・松竹・大映・東映・日活の大手6社がプログラム・ピクチャー(二本立て映画)を量産する体制を確立。1958年には、日本の年間映画館入場者数は、前代未聞の11億2700万人に達した。
この時期、経済成長とそれに伴う「集団就職」で、多くの若者が地方から都市部へ出てきた。そんな青年たちにとっても映画は、孤独な生活の中で楽しさを感じられる、数少ない“希望”の一つであったと言える。
この時期、庶民に最も親しまれた娯楽が、映画だった。1951年にサンフランシスコ講和条約が締結されたことで、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による検閲が廃止。自由な映画制作が可能になったことで、時代劇や第二次世界大戦を描いたフィルムが続々と制作される。黒澤明監督や溝口健二監督の作品をはじめ、日本映画が国際映画祭で次々と受賞し、世界的な注目を集めることになった。
国内の映画業界では、東宝・新東宝・松竹・大映・東映・日活の大手6社がプログラム・ピクチャー(二本立て映画)を量産する体制を確立。1958年には、日本の年間映画館入場者数は、前代未聞の11億2700万人に達した。
この時期、経済成長とそれに伴う「集団就職」で、多くの若者が地方から都市部へ出てきた。そんな青年たちにとっても映画は、孤独な生活の中で楽しさを感じられる、数少ない“希望”の一つであったと言える。
全責任を担って立つ
全責任を担って立つ

第3代会長就任式に臨む池田先生。恩師の遺影が見守る中、世界広布への大前進を開始した(1960年5月3日)〈モノクロ写真を、デジタル技術を使ってカラー化した〉
第3代会長就任式に臨む池田先生。恩師の遺影が見守る中、世界広布への大前進を開始した(1960年5月3日)〈モノクロ写真を、デジタル技術を使ってカラー化した〉
1958年4月2日の戸田先生の逝去後、当時のマスコミや評論家は“指導者を失った創価学会は空中分解する”と書き立てた。学会員が、偉大な師匠を失った悲しみに暮れる中、池田先生は一人立ち上がった。
5月3日の春季総会で池田先生は「七つの鐘」の指標を発表。学会が1930年の創立以来、7年を節として大きな飛躍を遂げてきた歴史に触れるとともに、“第七の鐘が鳴り終わる79年を目指して、広宣流布の永遠の基盤をつくり上げる”と述べ、同志に希望を示した。
6月30日には、青年部の室長を兼任したまま、新設された「総務」に就任する。実質的に学会の全責任を担い立つ戦いが始まった。同年10月、学会は100万世帯を突破。池田先生は全国各地を飛び回り、励ましを送り、同志と絆を結んでいく。その姿に触れた青年たちを中心に、60年になると“池田先生を第3代会長に”との声が、澎湃と湧き起こった。
先生は、「病弱な自分が、会長として指揮を執れば、かえって同志に迷惑をかけかねない」と憂慮し、「大阪事件」による裁判も継続中であったことから、会長就任を固辞し続けた。しかし、理事室から度重なる要請があり、60年4月14日、ついに受諾。その心境を、こうつづっている。
「戸田先生に、直弟子として育てられた私だ。訓練に訓練されてきた私だ。何を恐れるものがあろう。先生のご恩に報いる時が、遂に来たのだ」(小説『人間革命』第12巻「新・黎明」の章)
1960年5月3日、東京・墨田区の日大講堂で、32歳の青年会長が誕生した。池田先生は就任のあいさつで、「若輩ではございますが、本日より、戸田門下生を代表して、化儀の広宣流布を目指し、一歩前進への指揮を執らせていただきます!」と宣言した。
5カ月後の10月2日、池田先生は初の海外指導へ。アメリカ、カナダ、ブラジルの9都市を24日間で歴訪し、世界広布の扉が開かれた。その間の同年7月には、戦後もアメリカの統治下にあった沖縄を訪問。「三日間で三年分は働く」との決意で、全力で沖縄の同志に励ましを送った。先生のまなざしは、常に最も苦しんでいる人々に向けられていた。
翌61年11月には、第10回男子部総会、第9回女子部総会が開催される。戸田先生の「国士訓」の精神を胸に、それぞれ10万人と8万5000人の青年が一堂に会した。「青年よ、一人立て!」――戸田先生の師子吼に応えようと、その先頭を走ったのが、青年会長となった池田先生であった。
青年部員の多くは、日本が高度経済成長に突入したといっても、いまだ貧しい生活の中にあった。その青年たちが、社会の安寧のために立ち上がったのである。
1958年4月2日の戸田先生の逝去後、当時のマスコミや評論家は“指導者を失った創価学会は空中分解する”と書き立てた。学会員が、偉大な師匠を失った悲しみに暮れる中、池田先生は一人立ち上がった。
5月3日の春季総会で池田先生は「七つの鐘」の指標を発表。学会が1930年の創立以来、7年を節として大きな飛躍を遂げてきた歴史に触れるとともに、“第七の鐘が鳴り終わる79年を目指して、広宣流布の永遠の基盤をつくり上げる”と述べ、同志に希望を示した。
6月30日には、青年部の室長を兼任したまま、新設された「総務」に就任する。実質的に学会の全責任を担い立つ戦いが始まった。同年10月、学会は100万世帯を突破。池田先生は全国各地を飛び回り、励ましを送り、同志と絆を結んでいく。その姿に触れた青年たちを中心に、60年になると“池田先生を第3代会長に”との声が、澎湃と湧き起こった。
先生は、「病弱な自分が、会長として指揮を執れば、かえって同志に迷惑をかけかねない」と憂慮し、「大阪事件」による裁判も継続中であったことから、会長就任を固辞し続けた。しかし、理事室から度重なる要請があり、60年4月14日、ついに受諾。その心境を、こうつづっている。
「戸田先生に、直弟子として育てられた私だ。訓練に訓練されてきた私だ。何を恐れるものがあろう。先生のご恩に報いる時が、遂に来たのだ」(小説『人間革命』第12巻「新・黎明」の章)
1960年5月3日、東京・墨田区の日大講堂で、32歳の青年会長が誕生した。池田先生は就任のあいさつで、「若輩ではございますが、本日より、戸田門下生を代表して、化儀の広宣流布を目指し、一歩前進への指揮を執らせていただきます!」と宣言した。
5カ月後の10月2日、池田先生は初の海外指導へ。アメリカ、カナダ、ブラジルの9都市を24日間で歴訪し、世界広布の扉が開かれた。その間の同年7月には、戦後もアメリカの統治下にあった沖縄を訪問。「三日間で三年分は働く」との決意で、全力で沖縄の同志に励ましを送った。先生のまなざしは、常に最も苦しんでいる人々に向けられていた。
翌61年11月には、第10回男子部総会、第9回女子部総会が開催される。戸田先生の「国士訓」の精神を胸に、それぞれ10万人と8万5000人の青年が一堂に会した。「青年よ、一人立て!」――戸田先生の師子吼に応えようと、その先頭を走ったのが、青年会長となった池田先生であった。
青年部員の多くは、日本が高度経済成長に突入したといっても、いまだ貧しい生活の中にあった。その青年たちが、社会の安寧のために立ち上がったのである。
音声読み上げ