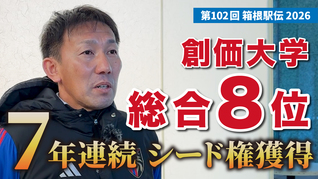オランダの水上居住区の発案者に聞く
オランダの水上居住区の発案者に聞く
2025年2月25日
- 〈SDGs×SEIKYO〉 理想のコミュニティーを目指して
- 〈SDGs×SEIKYO〉 理想のコミュニティーを目指して
運河が縦横に流れ、“水の都”として知られるオランダの首都アムステルダム。その北部ヨハン・ファン・ハッセルト運河には、数十軒の家々が浮かぶ水上居住区「スホーンスヒップ」があり、気候変動による海面上昇への対応策として注目されています。SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」をテーマに、同居住区の発案者であるマリアン・デ・ブロックさんに聞きました。(取材=田川さくら、樹下智)
運河が縦横に流れ、“水の都”として知られるオランダの首都アムステルダム。その北部ヨハン・ファン・ハッセルト運河には、数十軒の家々が浮かぶ水上居住区「スホーンスヒップ」があり、気候変動による海面上昇への対応策として注目されています。SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」をテーマに、同居住区の発案者であるマリアン・デ・ブロックさんに聞きました。(取材=田川さくら、樹下智)
――水の上に住んでいるそうですね! 水上居住区「スホーンスヒップ」について教えてください。
スホーンスヒップは、持続可能な資材で造られた家々が運河に浮かぶ水上居住区です。オランダ語で「きれいな船」という意味があります。現在、46世帯155人が住んでおり、私はパートナーと7歳になる双子の子どもと暮らしています。
家は水に浮くコンクリートの台の上に立っていて、備え付けのリングに杭を通すことで、漂流を防いでいます。水位が上がれば家も上がり、水位が下がれば家も下がる仕組みです。玄関は桟橋につながっています。
――生活の中で、揺れは感じないのですか。
風が吹くと、とても揺れます。スホーンスヒップに引っ越した当初は、いつも船酔いしたような感覚でした。ですが、そうした揺れにも、すぐに慣れます。今では、全く気付きません(笑)。
――水の上に住んでいるそうですね! 水上居住区「スホーンスヒップ」について教えてください。
スホーンスヒップは、持続可能な資材で造られた家々が運河に浮かぶ水上居住区です。オランダ語で「きれいな船」という意味があります。現在、46世帯155人が住んでおり、私はパートナーと7歳になる双子の子どもと暮らしています。
家は水に浮くコンクリートの台の上に立っていて、備え付けのリングに杭を通すことで、漂流を防いでいます。水位が上がれば家も上がり、水位が下がれば家も下がる仕組みです。玄関は桟橋につながっています。
――生活の中で、揺れは感じないのですか。
風が吹くと、とても揺れます。スホーンスヒップに引っ越した当初は、いつも船酔いしたような感覚でした。ですが、そうした揺れにも、すぐに慣れます。今では、全く気付きません(笑)。

オランダのヨハン・ファン・ハッセルト運河に浮かぶ水上居住区「スホーンスヒップ」(写真は全て本人提供)
オランダのヨハン・ファン・ハッセルト運河に浮かぶ水上居住区「スホーンスヒップ」(写真は全て本人提供)
――スホーンスヒップは水上での自給自足の生活に憧れたブロックさんと、それに賛同した人たちの手で造られました。水上での生活に興味を持ったきっかけを教えてください。
アムステルダムの住宅街に住んでいた頃、いつも心に“モヤモヤ”を感じていました。というのも、何かの形で社会の変革に貢献したいと努力していたのですが、それがあまり意味のないものに感じられたからです。
持続可能な生活の実現を意識し、ベジタリアンの食事やカーシェアリングなどを実践しました。しかし、周りを見渡すと、自分が起こした行動は、どこか“大きな世界”にのみ込まれていくような気がしました。
転機が訪れたのは、2008年です。テレビディレクターである私は、その年、あるドキュメンタリー番組を制作することになりました。そこで取材したのが、環境に配慮したハウスボートです。ハウスボートとは、居住用に改造された船のことで、この取材が私の人生を大きく変えました。
中に入ると、“これだ!”と直感しました。水の上での生活は自然との共生であり、何にも縛られていない。環境への負荷も少ないのではと思ったのです。それからは、子どもがおもちゃを欲しがるように、水の上で暮らしたくて、たまらなくなりました(笑)。
ですが、私はその道の専門家ではありません。大の大人がこんなことを考えていると知ったら、周りはどう思うだろうと、恥ずかしくもなりました。
――スホーンスヒップは水上での自給自足の生活に憧れたブロックさんと、それに賛同した人たちの手で造られました。水上での生活に興味を持ったきっかけを教えてください。
アムステルダムの住宅街に住んでいた頃、いつも心に“モヤモヤ”を感じていました。というのも、何かの形で社会の変革に貢献したいと努力していたのですが、それがあまり意味のないものに感じられたからです。
持続可能な生活の実現を意識し、ベジタリアンの食事やカーシェアリングなどを実践しました。しかし、周りを見渡すと、自分が起こした行動は、どこか“大きな世界”にのみ込まれていくような気がしました。
転機が訪れたのは、2008年です。テレビディレクターである私は、その年、あるドキュメンタリー番組を制作することになりました。そこで取材したのが、環境に配慮したハウスボートです。ハウスボートとは、居住用に改造された船のことで、この取材が私の人生を大きく変えました。
中に入ると、“これだ!”と直感しました。水の上での生活は自然との共生であり、何にも縛られていない。環境への負荷も少ないのではと思ったのです。それからは、子どもがおもちゃを欲しがるように、水の上で暮らしたくて、たまらなくなりました(笑)。
ですが、私はその道の専門家ではありません。大の大人がこんなことを考えていると知ったら、周りはどう思うだろうと、恥ずかしくもなりました。
“奇跡”の話し合い
“奇跡”の話し合い
――そこから、どのように行動を起こしたのですか。
一番の障壁は、自分自身の弱い心でした。何から始めれば良いのかも分かりません。“きっとできない”“恥ずかしい”――そんな気持ちとの戦いでした。
しかし、やりたいことに正直になり、友人たちに話してみると、皆の反応は思っていたものと違いました。「面白そうだね!」「私も計画に参加していい?」と興味を持ってくれたのです。その輪は広がり、面識のない人からも“計画に加わりたい”と電話をもらうまでになりました。
そうして開いた初回の顔合わせでは、計画に賛同した15人が集まりました。誰も、必要な専門知識は持っていません。しかし、皆が“何か変革を起こしたい”との気概にあふれていました。そして、それぞれの理想を語り合う中、持続可能な水上居住区を、自分たちの手で一から造ることになったのです。
――そこから、どのように行動を起こしたのですか。
一番の障壁は、自分自身の弱い心でした。何から始めれば良いのかも分かりません。“きっとできない”“恥ずかしい”――そんな気持ちとの戦いでした。
しかし、やりたいことに正直になり、友人たちに話してみると、皆の反応は思っていたものと違いました。「面白そうだね!」「私も計画に参加していい?」と興味を持ってくれたのです。その輪は広がり、面識のない人からも“計画に加わりたい”と電話をもらうまでになりました。
そうして開いた初回の顔合わせでは、計画に賛同した15人が集まりました。誰も、必要な専門知識は持っていません。しかし、皆が“何か変革を起こしたい”との気概にあふれていました。そして、それぞれの理想を語り合う中、持続可能な水上居住区を、自分たちの手で一から造ることになったのです。

話し合いの一こま。現在も、より持続可能な水上居住区を目指して、建設的な話し合いを重ねる
話し合いの一こま。現在も、より持続可能な水上居住区を目指して、建設的な話し合いを重ねる
――話し合いは10年以上にもおよび、2020年にスホーンスヒップが完成します。専門知識を持つ人がいない中、どのように理想を実現させたのですか。
私たちは独学で持続可能な暮らしについて学び、また、それを専門とする企業の力も借りながら、理想を一つずつ形にしていきました。
苦労したことの一つは、持続可能性と費用のバランスを取ることです。環境に優しいものほど、費用がかかります。しかし、計画に参加する人たち全員に、経済的な余裕があるわけではありません。また、裕福な人のみに開かれた居住区にはしたくありませんでした。そこで私たちは常に、「持続可能性」「手頃さ」「オープンさ」の三つの指標を軸に、意思決定を行いました。
例えば、住宅資材を選ぶ際は、どこに何を用いれば「持続可能性」と「手頃さ」を最も実現できるかを話し合い、答えを探していきました。そこではいつも皆の“納得”を大事にし、「オープンさ」を心がけました。
そうして完成したスホーンスヒップには、至る所で、環境への配慮が見られます。電気は各家に備え付けられた太陽光パネルで作り出され、シャワーの水はフィルターを通して循環させ、再利用しています。また、トイレは最小限の水で汚物を流せる真空式で、ゴミなどは堆肥化しています。生態系も守れるように、水上庭園も造りました。アヒルや白鳥なども、よく遊びに来ています。
――話し合いは10年以上にもおよび、2020年にスホーンスヒップが完成します。専門知識を持つ人がいない中、どのように理想を実現させたのですか。
私たちは独学で持続可能な暮らしについて学び、また、それを専門とする企業の力も借りながら、理想を一つずつ形にしていきました。
苦労したことの一つは、持続可能性と費用のバランスを取ることです。環境に優しいものほど、費用がかかります。しかし、計画に参加する人たち全員に、経済的な余裕があるわけではありません。また、裕福な人のみに開かれた居住区にはしたくありませんでした。そこで私たちは常に、「持続可能性」「手頃さ」「オープンさ」の三つの指標を軸に、意思決定を行いました。
例えば、住宅資材を選ぶ際は、どこに何を用いれば「持続可能性」と「手頃さ」を最も実現できるかを話し合い、答えを探していきました。そこではいつも皆の“納得”を大事にし、「オープンさ」を心がけました。
そうして完成したスホーンスヒップには、至る所で、環境への配慮が見られます。電気は各家に備え付けられた太陽光パネルで作り出され、シャワーの水はフィルターを通して循環させ、再利用しています。また、トイレは最小限の水で汚物を流せる真空式で、ゴミなどは堆肥化しています。生態系も守れるように、水上庭園も造りました。アヒルや白鳥なども、よく遊びに来ています。

水に浮かぶ住宅の建設現場
水に浮かぶ住宅の建設現場

完成した住宅は、ボートで所定の場所へ
完成した住宅は、ボートで所定の場所へ
――多くの人で一から一つのものをつくり上げるには、時に意見の衝突もあったかと思います。話し合いに長い年月を要しても、人が離れていかなかったのはなぜですか。
もちろん意見が衝突したこともありました。しかし、費やした時間や話し合いに参加した人数を考えると、こんなにもうまく進んだのは奇跡に近いと思います。きっと皆が、同じ目標、同じ志を持っていたからですね。一人一人が柔軟でした。
実は、1度だけ、法律の面で、計画の実行が難航していた時期があります。約2年間、目に見える進展がなく、グループの結束を維持することが難しいと感じました。しかし、皆で夕食を共にしたり、運河でボートに乗ったり、人としてのつながりを大切にする中で、皆の心が離れていくことはありませんでした。
――多くの人で一から一つのものをつくり上げるには、時に意見の衝突もあったかと思います。話し合いに長い年月を要しても、人が離れていかなかったのはなぜですか。
もちろん意見が衝突したこともありました。しかし、費やした時間や話し合いに参加した人数を考えると、こんなにもうまく進んだのは奇跡に近いと思います。きっと皆が、同じ目標、同じ志を持っていたからですね。一人一人が柔軟でした。
実は、1度だけ、法律の面で、計画の実行が難航していた時期があります。約2年間、目に見える進展がなく、グループの結束を維持することが難しいと感じました。しかし、皆で夕食を共にしたり、運河でボートに乗ったり、人としてのつながりを大切にする中で、皆の心が離れていくことはありませんでした。

住民同士で仲良く川下り
住民同士で仲良く川下り
155人の大家族
155人の大家族
――スホーンスヒップでは、住民同士の交流を大切にし、さまざまなイベントを開いているそうですね。
毎年1月1日には、家の周りで水泳大会を開いています。子どもたちは大はしゃぎです。また、年に1度、桟橋に大きなテーブルを並べて、夕食会も開いています。スープやパスタ、サラダを持ち寄り、皆で楽しく食事をするんです。まるで155人の大家族のようで、“スホーンスヒップに来て、人生が楽しくなった”と言ってくれる人も多くいます。
こうした地域のつながりは、実は私がずっと求めていたものでした。以前、住んでいた所では、近隣の人の顔も分からず、孤独を感じていました。血のつながりを超え、皆で一緒に料理し、子育てができたら、どれほど素敵だろうと夢見ていました。今、スホーンスヒップで見る光景は、まさに私が思い描いていたものです。
仕事から帰宅し、桟橋を歩いていると、皆が“おかえり”と声をかけてくれます。長期間、寝込んでいる人がいれば、皆で看病します。忙しそうにしているお母さんがいると、私がその子どもを学校に連れていくこともあります。思いやりにあふれた場所です。
私は、人とのつながり以上に大事なものはないと思っています。誰かが自分を知ってくれている、自分は一人じゃないと思えるだけで、心が元気になる。“ここが私の居場所だ”と思えると、その場所を大切にしたいと願うはずです。その思いが、やがて地球を守ることにつながります。人とのつながりは一見、小さなことのように見えますが、とても大事なことではないでしょうか。
――スホーンスヒップでは、住民同士の交流を大切にし、さまざまなイベントを開いているそうですね。
毎年1月1日には、家の周りで水泳大会を開いています。子どもたちは大はしゃぎです。また、年に1度、桟橋に大きなテーブルを並べて、夕食会も開いています。スープやパスタ、サラダを持ち寄り、皆で楽しく食事をするんです。まるで155人の大家族のようで、“スホーンスヒップに来て、人生が楽しくなった”と言ってくれる人も多くいます。
こうした地域のつながりは、実は私がずっと求めていたものでした。以前、住んでいた所では、近隣の人の顔も分からず、孤独を感じていました。血のつながりを超え、皆で一緒に料理し、子育てができたら、どれほど素敵だろうと夢見ていました。今、スホーンスヒップで見る光景は、まさに私が思い描いていたものです。
仕事から帰宅し、桟橋を歩いていると、皆が“おかえり”と声をかけてくれます。長期間、寝込んでいる人がいれば、皆で看病します。忙しそうにしているお母さんがいると、私がその子どもを学校に連れていくこともあります。思いやりにあふれた場所です。
私は、人とのつながり以上に大事なものはないと思っています。誰かが自分を知ってくれている、自分は一人じゃないと思えるだけで、心が元気になる。“ここが私の居場所だ”と思えると、その場所を大切にしたいと願うはずです。その思いが、やがて地球を守ることにつながります。人とのつながりは一見、小さなことのように見えますが、とても大事なことではないでしょうか。

155人が暮らすスホーンスヒップ。コミュニティー内には規則がほとんどなく、住民はのびのびと暮らす
155人が暮らすスホーンスヒップ。コミュニティー内には規則がほとんどなく、住民はのびのびと暮らす
――私たち創価学会も人とのつながりを大切にし、目の前の一人に励ましを送っています。その行動の根底にあるのは“誰しもが唯一無二の尊い存在であり、一人一人に世界を変革する力がある”との哲学です。
一人の行動が、世界に与える影響は計り知れません。実際、私が一歩を踏み出したことで、今、155人がスホーンスヒップで持続可能な生活を送っています。また、私たちのコミュニティーは世界からも注目を集め、一つのロールモデルともなっています。
玄関を出て、桟橋を歩くと、計画が始まった頃はまだ生まれていなかった子どもたちが、庭や運河で仲良く遊ぶ姿を目にします。その子どもたちにとっては、自家発電や水の再利用、近隣同士の交流は当たり前です。きっと、大人になったら、この当たり前を自分たちの子どもに伝えていくのだろうと思うと、未来に希望を感じます。
――私たち大人の行動が子どもたちの未来をつくるんですね。
現実のさまざまな課題に目を向けると、今から行動を起こしても遅いのではないかと思う瞬間もあります。自分一人が何かしたところで意味はあるのかと、無力感に襲われる時もあります。“モヤモヤ”を感じていた、あの頃の私のようにです。
しかし、私は気付きました。行動を起こす上で、遅いか否かは問題ではない。今、自分が最善だと思うことをするほかにないのだ、と。
――最後に、今後の展望を教えてください。
スホーンスヒップがロールモデルとなり、同じようなコミュニティーが各地で誕生することを願っています。環境に配慮した生活、人のつながりが強い社会がいかに素晴らしいかを、ぜひ皆さんにも体験してほしいのです。そして、その持続可能性を当たり前とする生き方が未来へ伝わってほしい。
私には、まだスホーンスヒップで実現したい持続可能性のためのアイデアがたくさんあります。
アイデアが浮かぶのを待つのではない。創造こそ、全ての始まりです。私から、世界へ、未来へ、変革の波を起こしていきたいと思っています。
――私たち創価学会も人とのつながりを大切にし、目の前の一人に励ましを送っています。その行動の根底にあるのは“誰しもが唯一無二の尊い存在であり、一人一人に世界を変革する力がある”との哲学です。
一人の行動が、世界に与える影響は計り知れません。実際、私が一歩を踏み出したことで、今、155人がスホーンスヒップで持続可能な生活を送っています。また、私たちのコミュニティーは世界からも注目を集め、一つのロールモデルともなっています。
玄関を出て、桟橋を歩くと、計画が始まった頃はまだ生まれていなかった子どもたちが、庭や運河で仲良く遊ぶ姿を目にします。その子どもたちにとっては、自家発電や水の再利用、近隣同士の交流は当たり前です。きっと、大人になったら、この当たり前を自分たちの子どもに伝えていくのだろうと思うと、未来に希望を感じます。
――私たち大人の行動が子どもたちの未来をつくるんですね。
現実のさまざまな課題に目を向けると、今から行動を起こしても遅いのではないかと思う瞬間もあります。自分一人が何かしたところで意味はあるのかと、無力感に襲われる時もあります。“モヤモヤ”を感じていた、あの頃の私のようにです。
しかし、私は気付きました。行動を起こす上で、遅いか否かは問題ではない。今、自分が最善だと思うことをするほかにないのだ、と。
――最後に、今後の展望を教えてください。
スホーンスヒップがロールモデルとなり、同じようなコミュニティーが各地で誕生することを願っています。環境に配慮した生活、人のつながりが強い社会がいかに素晴らしいかを、ぜひ皆さんにも体験してほしいのです。そして、その持続可能性を当たり前とする生き方が未来へ伝わってほしい。
私には、まだスホーンスヒップで実現したい持続可能性のためのアイデアがたくさんあります。
アイデアが浮かぶのを待つのではない。創造こそ、全ての始まりです。私から、世界へ、未来へ、変革の波を起こしていきたいと思っています。
Marjan de Blok オランダ出身のテレビディレクター。2008年、番組制作のためにハウスボートを取材し、水上での自給自足の生活に興味を持つ。その後、賛同者と構想を練り、20年に持続可能な水上居住区「スホーンスヒップ」を完成させた。イベント等で、スホーンスヒップについての講演も行う。7歳の双子の母親。
Marjan de Blok オランダ出身のテレビディレクター。2008年、番組制作のためにハウスボートを取材し、水上での自給自足の生活に興味を持つ。その後、賛同者と構想を練り、20年に持続可能な水上居住区「スホーンスヒップ」を完成させた。イベント等で、スホーンスヒップについての講演も行う。7歳の双子の母親。
●ご感想をお寄せください。
sdgs@seikyo-np.jp
●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html
●海外識者のインタビューの英語版が「創価学会グローバルサイト」に掲載されています。
https://www.sokaglobal.org/resources/expert-perspectives.html
●ご感想をお寄せください。
sdgs@seikyo-np.jp
●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html
●海外識者のインタビューの英語版が「創価学会グローバルサイト」に掲載されています。
https://www.sokaglobal.org/resources/expert-perspectives.html
音声読み上げ