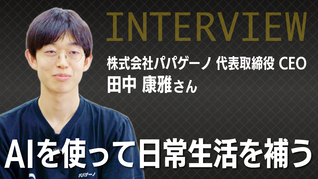〈未来対談〉 ルポ・哲学対話をやってみた
〈未来対談〉 ルポ・哲学対話をやってみた
2025年11月11日
- 創価学会青年世代×苫野一徳さん(熊本大学大学院准教授)
- 創価学会青年世代×苫野一徳さん(熊本大学大学院准教授)
連載「未来対談――これからの社会を語り合おう」では、創価学会の青年世代が、哲学者の苫野一徳さん(熊本大学大学院准教授)と行った勉強会の模様を、3回にわたって掲載してきました。
勉強会では、対話の具体的な方法として「本質観取」が話題になりました。これは、ある物事や概念をテーマに、みんなで対話しながら、その本質を考え合い、一緒に言葉を紡いでいくスタイルの対話です。本年9月、「私たちも実際にやってみよう」と、苫野さんと一緒に本質観取を実践しました。
テーマは「幸せって何?」。私たちは日々、幸せになるために信仰に励んでいます。学会活動の中でも、日常生活においても、幸せという言葉自体は、よく使われるものです。では、そもそも「幸せって何?」と聞かれたら、皆さんはどう答えますか――。
今回は、幸せについての本質観取の様子と、勉強会を終えた西方青年部長の所感を掲載します。
連載「未来対談――これからの社会を語り合おう」では、創価学会の青年世代が、哲学者の苫野一徳さん(熊本大学大学院准教授)と行った勉強会の模様を、3回にわたって掲載してきました。
勉強会では、対話の具体的な方法として「本質観取」が話題になりました。これは、ある物事や概念をテーマに、みんなで対話しながら、その本質を考え合い、一緒に言葉を紡いでいくスタイルの対話です。本年9月、「私たちも実際にやってみよう」と、苫野さんと一緒に本質観取を実践しました。
テーマは「幸せって何?」。私たちは日々、幸せになるために信仰に励んでいます。学会活動の中でも、日常生活においても、幸せという言葉自体は、よく使われるものです。では、そもそも「幸せって何?」と聞かれたら、皆さんはどう答えますか――。
今回は、幸せについての本質観取の様子と、勉強会を終えた西方青年部長の所感を掲載します。
■皆が納得できる本質を紡ぎ合う
■皆が納得できる本質を紡ぎ合う
哲学対話の一つに「本質観取」があります。熊本大学大学院の苫野一徳准教授は、本質観取とは「物事の本質を言葉にして編み上げていく哲学の思考法」だと言います。
自分や他者の体験を振り返って、「そもそも○○とは何か」と本質を考えると、参加者一人一人の「それは△△だと思う」という“確信”が見えてきます。本質観取は、それぞれの確信を持ち寄り、皆が納得できる“共通了解”を見つける対話です。
今、私たちの身の回りには、インターネット上の攻撃的な言葉の応酬をはじめ、多くの“対立”があります。考えや価値観、利害がぶつかると、対話なんてできないと思ってしまうことも……。そうした複雑な現実の中で、違いはあるけれど、それでも“ここだけはお互いに納得できる”という共通点を見つけ出す――本質観取の対話は、さまざまな対立が深まる今こそ必要です。
今回、まず私たちは、そもそも信仰は何のためにするのかを考えました。池田大作先生は「自分も幸福になり、人をも幸福にするためです」(『青春対話1』普及版)と語っています。そこで、信仰が目指す「幸福」について、その本質を掘り下げようと、本質観取のテーマを「幸せって何?」に決めました。さっそく苫野さんとウェブ会議をつないで、本質観取のスタートです。
哲学対話の一つに「本質観取」があります。熊本大学大学院の苫野一徳准教授は、本質観取とは「物事の本質を言葉にして編み上げていく哲学の思考法」だと言います。
自分や他者の体験を振り返って、「そもそも○○とは何か」と本質を考えると、参加者一人一人の「それは△△だと思う」という“確信”が見えてきます。本質観取は、それぞれの確信を持ち寄り、皆が納得できる“共通了解”を見つける対話です。
今、私たちの身の回りには、インターネット上の攻撃的な言葉の応酬をはじめ、多くの“対立”があります。考えや価値観、利害がぶつかると、対話なんてできないと思ってしまうことも……。そうした複雑な現実の中で、違いはあるけれど、それでも“ここだけはお互いに納得できる”という共通点を見つけ出す――本質観取の対話は、さまざまな対立が深まる今こそ必要です。
今回、まず私たちは、そもそも信仰は何のためにするのかを考えました。池田大作先生は「自分も幸福になり、人をも幸福にするためです」(『青春対話1』普及版)と語っています。そこで、信仰が目指す「幸福」について、その本質を掘り下げようと、本質観取のテーマを「幸せって何?」に決めました。さっそく苫野さんとウェブ会議をつないで、本質観取のスタートです。

ウェブ会議を使って、創価学会の青年世代と哲学者の苫野一徳さんが、哲学対話の「本質観取」を実践した(本年9月)
ウェブ会議を使って、創価学会の青年世代と哲学者の苫野一徳さんが、哲学対話の「本質観取」を実践した(本年9月)
①問題意識を挙げる
①問題意識を挙げる
最初に、幸せについて本質観取をすることには、どんな意味があるのかを話し合います。参加者からは、次のような意見が出ました。
「私たちが目指すものが明確になる」「学会活動がより豊かなものになると思う」「もう一歩深い対話ができるようになるかも」
幸せの本質を言葉にできたら、暮らしや信仰活動、ひいては生き方の軸を見つめることにつながります。
最初に、幸せについて本質観取をすることには、どんな意味があるのかを話し合います。参加者からは、次のような意見が出ました。
「私たちが目指すものが明確になる」「学会活動がより豊かなものになると思う」「もう一歩深い対話ができるようになるかも」
幸せの本質を言葉にできたら、暮らしや信仰活動、ひいては生き方の軸を見つめることにつながります。
②体験例・具体例を出し合う
②体験例・具体例を出し合う
次に、どんな時に幸せを感じるかを考えました。お風呂やサウナに入った時、スポーツや大自然を満喫した時、料理をおいしく作れた時。さらに、娘が欲しがった人形をクレーンゲームで取れた時といったエピソードも。
苫野さんから「違う角度の例も挙げてみましょう」と促されると、だんだん対話が深まっていきます。
ある人が口を開きました。「自分が関わった人から『ありがとう』と言われた時に深い幸せを感じた」
別の人も続きます。「自分の幸せを心から願ってくれている人がいることを実感した時が幸せだった」
次に、どんな時に幸せを感じるかを考えました。お風呂やサウナに入った時、スポーツや大自然を満喫した時、料理をおいしく作れた時。さらに、娘が欲しがった人形をクレーンゲームで取れた時といったエピソードも。
苫野さんから「違う角度の例も挙げてみましょう」と促されると、だんだん対話が深まっていきます。
ある人が口を開きました。「自分が関わった人から『ありがとう』と言われた時に深い幸せを感じた」
別の人も続きます。「自分の幸せを心から願ってくれている人がいることを実感した時が幸せだった」
③共通するキーワードを見つける
③共通するキーワードを見つける
みんなが挙げた具体例に共通することを探します。今回は「自らつかんでいく主体性」「感謝」「他者との関わり」などが挙がりました。
そこから「相対的幸福」と「絶対的幸福」が話題になりました。相対的幸福は、欲しい物が手に入るなど、物質的な充足や、欲望が満たされた状態で感じるもの。一方、絶対的幸福は、どこにいても、何があっても、生きていること自体が楽しくてしようがないという境涯です。
どちらの幸福も大切にしたい。その上で、他者から感謝されたり、誰かに支えてもらったりする関係性の中で、より深い幸せの実感があると話し合いました。
苫野さんが口を開きます。「何だか皆さんとの対話自体が、とても幸せな時間だと感じています。皆さんの話から、何を大切にするかによって、幸せの深みが変わってくるのだと気付かされました。幸せの本質観取は、これまで何度もやってきましたが、これは大きな発見です」
みんなが挙げた具体例に共通することを探します。今回は「自らつかんでいく主体性」「感謝」「他者との関わり」などが挙がりました。
そこから「相対的幸福」と「絶対的幸福」が話題になりました。相対的幸福は、欲しい物が手に入るなど、物質的な充足や、欲望が満たされた状態で感じるもの。一方、絶対的幸福は、どこにいても、何があっても、生きていること自体が楽しくてしようがないという境涯です。
どちらの幸福も大切にしたい。その上で、他者から感謝されたり、誰かに支えてもらったりする関係性の中で、より深い幸せの実感があると話し合いました。
苫野さんが口を開きます。「何だか皆さんとの対話自体が、とても幸せな時間だと感じています。皆さんの話から、何を大切にするかによって、幸せの深みが変わってくるのだと気付かされました。幸せの本質観取は、これまで何度もやってきましたが、これは大きな発見です」
④本質を言葉にする
④本質を言葉にする
挙がったキーワードをもとに、みんなで本質を言葉にしていきます。
自らつかむもの、他者との関わりの中で実感すること、心からの満足感……いろいろな言葉を挙げていく中で「自分が大切にしているもの」という言葉に共感が集まりました。
さらに、法華経が説く「衆生所遊楽」の話も出ました。私たちは、この世に楽しむために生まれてきたということです。もちろん人生には、悩みや苦しいことも、たくさんあります。けれど、強い生命力を発揮すれば、苦労や困難も“お汁粉に入れるひとつまみの塩”のように、人生の喜びを増してくれるものになっていく、と。
苦しい時も楽しい時も、人生の起伏を楽しみ、味わいながら生きていくこと。それができたら幸せではないか。同時にそれは、私たちが普段から使っている「境涯」や「人間革命」という言葉にも通じているはずです。そう話し合って、今回は幸せの本質を次の言葉にまとめました。
「自分が大切にしているものとの関わりを自ら味わうこと」
挙がったキーワードをもとに、みんなで本質を言葉にしていきます。
自らつかむもの、他者との関わりの中で実感すること、心からの満足感……いろいろな言葉を挙げていく中で「自分が大切にしているもの」という言葉に共感が集まりました。
さらに、法華経が説く「衆生所遊楽」の話も出ました。私たちは、この世に楽しむために生まれてきたということです。もちろん人生には、悩みや苦しいことも、たくさんあります。けれど、強い生命力を発揮すれば、苦労や困難も“お汁粉に入れるひとつまみの塩”のように、人生の喜びを増してくれるものになっていく、と。
苦しい時も楽しい時も、人生の起伏を楽しみ、味わいながら生きていくこと。それができたら幸せではないか。同時にそれは、私たちが普段から使っている「境涯」や「人間革命」という言葉にも通じているはずです。そう話し合って、今回は幸せの本質を次の言葉にまとめました。
「自分が大切にしているものとの関わりを自ら味わうこと」
⑤最初の問題意識や疑問点に答える。新たな発見を共有する
⑤最初の問題意識や疑問点に答える。新たな発見を共有する
普段から慣れ親しんだ言葉であるほど、ともすると深く意味を考えず、自動的に使いがちです。「幸せ」も、その一つだったのかもしれませんが、改めて幸せの本質を考えて話し合ったことで、自分たちなりの納得できる言葉を紡ぐことができました。
本質をつかみ、新たな言葉を生み出す――これは、池田先生が実践し続けたことでもあります。先生は、日蓮仏法が説く希望の哲学を、現代に生きる言葉にして語ることで、一人一人を励まし、世界に平和をつくる生き方を貫きました。
これからは、弟子である私たちが本質を考え、話し合い、新しい言葉を紡いでいく時です。
もちろん、今回の対話でまとめた言葉が、唯一の正解ではありません。異なる参加者で本質観取をすれば、また違った言葉が紡がれるはずです。幸せ以外にも、身近なさまざまな物事について本質観取をすれば、そのたびに言葉が生まれます。
苫野さんは勉強会で、こう語っていました。「どこかにユートピア(理想郷)を求めても、厳しい現実に直面すると、しんどくなってしまいます。ユートピアは存在しない。だからこそ、自分たちで一緒につくっていく。そういう姿勢が大事だと思うのです」
新しい時代の、新しい学会の在り方も、私たちみんなで一緒につくっていくものです。お互いの話を聞き合い、学びや発見を得ながら、みんなが納得できる言葉を紡いでいく。こうした対話が各地に広がったら、身近なところから、人も地域も、より良く変わっていくはず――そこにこそ、希望があると感じます。
普段から慣れ親しんだ言葉であるほど、ともすると深く意味を考えず、自動的に使いがちです。「幸せ」も、その一つだったのかもしれませんが、改めて幸せの本質を考えて話し合ったことで、自分たちなりの納得できる言葉を紡ぐことができました。
本質をつかみ、新たな言葉を生み出す――これは、池田先生が実践し続けたことでもあります。先生は、日蓮仏法が説く希望の哲学を、現代に生きる言葉にして語ることで、一人一人を励まし、世界に平和をつくる生き方を貫きました。
これからは、弟子である私たちが本質を考え、話し合い、新しい言葉を紡いでいく時です。
もちろん、今回の対話でまとめた言葉が、唯一の正解ではありません。異なる参加者で本質観取をすれば、また違った言葉が紡がれるはずです。幸せ以外にも、身近なさまざまな物事について本質観取をすれば、そのたびに言葉が生まれます。
苫野さんは勉強会で、こう語っていました。「どこかにユートピア(理想郷)を求めても、厳しい現実に直面すると、しんどくなってしまいます。ユートピアは存在しない。だからこそ、自分たちで一緒につくっていく。そういう姿勢が大事だと思うのです」
新しい時代の、新しい学会の在り方も、私たちみんなで一緒につくっていくものです。お互いの話を聞き合い、学びや発見を得ながら、みんなが納得できる言葉を紡いでいく。こうした対話が各地に広がったら、身近なところから、人も地域も、より良く変わっていくはず――そこにこそ、希望があると感じます。
■「本質観取」のやり方
■「本質観取」のやり方
●流れ
①問題意識を挙げる
②体験例・具体例を出し合う
③共通するキーワードを見つける
④本質を言葉にする
⑤最初の問題意識や疑問点に答える。新たな発見を共有する
●基本のルール
①対等な対話者として認め合う
②聞き合う、表現を尽くす
③共通了解を見いだす
④沈黙も大切な時間
●意義
①自分と他者のそれぞれが考えていることへの理解が深まり、より良いチームや組織づくりにも寄与する。
②話し合いの中で伝えたいことを的確に言語化できるようになり、言語力、思考力、対話力が高まる。
③多様な人々が、暴力ではなく、対話を通して合意形成ができるようになり、民主主義の成熟につながる。
●流れ
①問題意識を挙げる
②体験例・具体例を出し合う
③共通するキーワードを見つける
④本質を言葉にする
⑤最初の問題意識や疑問点に答える。新たな発見を共有する
●基本のルール
①対等な対話者として認め合う
②聞き合う、表現を尽くす
③共通了解を見いだす
④沈黙も大切な時間
●意義
①自分と他者のそれぞれが考えていることへの理解が深まり、より良いチームや組織づくりにも寄与する。
②話し合いの中で伝えたいことを的確に言語化できるようになり、言語力、思考力、対話力が高まる。
③多様な人々が、暴力ではなく、対話を通して合意形成ができるようになり、民主主義の成熟につながる。

西方青年部長㊧と苫野准教授(本年8月、世界聖教会館で)
西方青年部長㊧と苫野准教授(本年8月、世界聖教会館で)
■勉強会を振り返って 西方光雄青年部長
■勉強会を振り返って 西方光雄青年部長
「何のために」を問い直す
「何のために」を問い直す
私たちは今、見通しがきかない時代を生きています。
多くの人が正解を探しながらも、それが見つからない、もどかしさを抱えているのではないでしょうか。その象徴のように、SNSでは、わずかな意見の違いから非難や中傷が飛び交い、人々がリアルタイムでぶつかり合っています。
そんな今だからこそ、安易に感情に流されるのではなく、社会を冷静に見つめる視点が求められています。
今回、私たちは哲学者・苫野一徳さんと共に、「この時代をどう生きるか」について語り合いました。
対話を重ねる中で見えてきたのは、現代に広がる対立や差別の根底には、人が「自由に生きたい」と願う心が関係しているということでした。
お互いの自由がぶつかり合うとき、どうすれば私たちは共に生きることができるのか。
哲学者たちは、その問いに対して「自由の相互承認」という原理にたどり着きました。
お互いを“自由な存在”として認め合うこと――。そうした関係を築くためには、たとえ裏切られることがあっても、相手を信じるという「信頼」が欠かせません。
私たちが創価学会の活動を通して実践していることも、自分を信じ、他者を信じるという生き方そのものです。
情報があふれ、何が正しいのか見えにくい時代において、私たちは「何のために」という問いを見失ってはなりません。情報を拒むのでも、盲目的に受け入れるのでもなく、人と語り、考えを磨き合うこと。そうした地道な対話の積み重ねこそが、社会をより良くしていく力になると感じます。
池田先生は、宗教者が立ち返るべきは、あらゆる差異を超えた「人間」「生命」という原点である、と。一見すると遠回りに思えても、この普遍の共通項を基盤とする対話こそが、私たちを相互不信から相互理解へ、分断から結合へと導く道なのだと思います。
対話を通して目指すのは、ただ一つの“正解”を見つけることではありません。互いに「なるほど」と、うなずくことができる“納得解”を見いだすことです。その過程で、人と人とが結ばれ、新しい言葉や発想が生まれていきます。
混迷の時代にあっても「何のために」という問いを胸に、対話を重ねながら、自分と他者、そして社会を結び直していきたい。そこにこそ、未来をひらく希望があると信じています。
私たちは今、見通しがきかない時代を生きています。
多くの人が正解を探しながらも、それが見つからない、もどかしさを抱えているのではないでしょうか。その象徴のように、SNSでは、わずかな意見の違いから非難や中傷が飛び交い、人々がリアルタイムでぶつかり合っています。
そんな今だからこそ、安易に感情に流されるのではなく、社会を冷静に見つめる視点が求められています。
今回、私たちは哲学者・苫野一徳さんと共に、「この時代をどう生きるか」について語り合いました。
対話を重ねる中で見えてきたのは、現代に広がる対立や差別の根底には、人が「自由に生きたい」と願う心が関係しているということでした。
お互いの自由がぶつかり合うとき、どうすれば私たちは共に生きることができるのか。
哲学者たちは、その問いに対して「自由の相互承認」という原理にたどり着きました。
お互いを“自由な存在”として認め合うこと――。そうした関係を築くためには、たとえ裏切られることがあっても、相手を信じるという「信頼」が欠かせません。
私たちが創価学会の活動を通して実践していることも、自分を信じ、他者を信じるという生き方そのものです。
情報があふれ、何が正しいのか見えにくい時代において、私たちは「何のために」という問いを見失ってはなりません。情報を拒むのでも、盲目的に受け入れるのでもなく、人と語り、考えを磨き合うこと。そうした地道な対話の積み重ねこそが、社会をより良くしていく力になると感じます。
池田先生は、宗教者が立ち返るべきは、あらゆる差異を超えた「人間」「生命」という原点である、と。一見すると遠回りに思えても、この普遍の共通項を基盤とする対話こそが、私たちを相互不信から相互理解へ、分断から結合へと導く道なのだと思います。
対話を通して目指すのは、ただ一つの“正解”を見つけることではありません。互いに「なるほど」と、うなずくことができる“納得解”を見いだすことです。その過程で、人と人とが結ばれ、新しい言葉や発想が生まれていきます。
混迷の時代にあっても「何のために」という問いを胸に、対話を重ねながら、自分と他者、そして社会を結び直していきたい。そこにこそ、未来をひらく希望があると信じています。
●ご感想・ご意見は、こちらからお寄せください。
●過去の記事は、こちらからご覧いただけます。
●ご感想・ご意見は、こちらからお寄せください。
●過去の記事は、こちらからご覧いただけます。
音声読み上げ