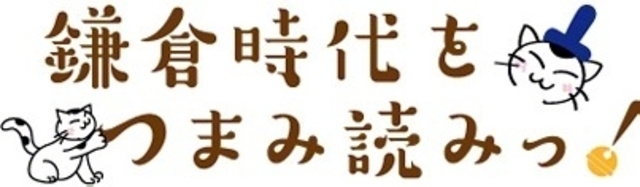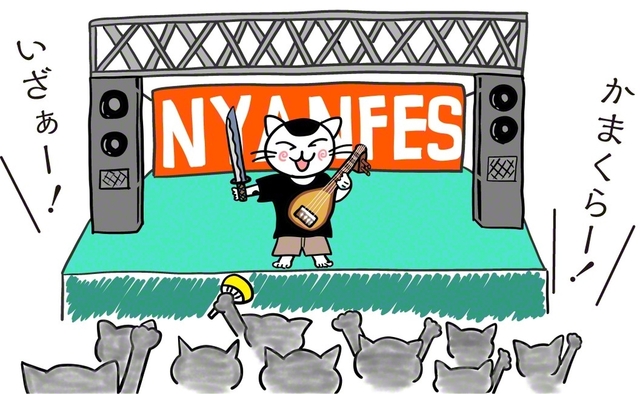〈鎌倉時代をつまみ読みっ!〉第17回 武器と楽器の“二刀流”?
〈鎌倉時代をつまみ読みっ!〉第17回 武器と楽器の“二刀流”?
2025年9月26日
今も昔も、人々は音楽が大好き。もちろん鎌倉時代も同じです。幕府のある鎌倉でも、農村でも、どこからともなくにぎやかな音楽が響いていたようですよ。それでは早速、かいつまんでいきましょう。いざ、鎌倉時代!
今も昔も、人々は音楽が大好き。もちろん鎌倉時代も同じです。幕府のある鎌倉でも、農村でも、どこからともなくにぎやかな音楽が響いていたようですよ。それでは早速、かいつまんでいきましょう。いざ、鎌倉時代!
おっと、音が出ていません! 武士が音楽のレッスンを?
おっと、音が出ていません! 武士が音楽のレッスンを?
ようやく秋の足音が聞こえてきそうな、きょうこの頃。
どんなに季節が移り変わろうとも、ネコたま殿が鎌倉武士をリスペクトする気持ちは変わりません。仲間と鍛錬の日々を送っています。
きょうは遠くから、その道の達人がやってきてレッスンを受けているようです。
きっと、刀や弓矢などの腕を磨くのでしょう。いつになく真剣な表情です。
部屋にこもったネコたま殿。聞こえてくるのは、威勢のいい掛け声ではなく、音楽の演奏……。
どうやら、琴や鼓の稽古に励んでいるようです。
実は、鎌倉武士は、武器だけではなく楽器の鍛錬にも余念がありませんでした。
それにしてもなぜ、武士が楽器を?
◆
楽器の音色は笛・篳篥がよい。常に聞きたいのは琵琶や和琴である――〈注1〉。
これは、鎌倉時代の随筆『徒然草』の一節です。
多様な楽器が演奏されて、人によって好みもあったことが伝わってきますね。
京都で隆盛した雅楽〈注2〉は、鎌倉にも広がっていきました。
初代将軍である源頼朝が、武家社会にも上流階級の洗練された文化を根付かせようと、雅楽のミュージシャンである楽人を京都から鎌倉に招き、演奏させていたのです。
さらに、武士に対する楽器のレッスンも行われるようになりました。
「おっと、音が出ていません!」なんて、注意される場面があったかもしれません。
歴史書『吾妻鏡』には、頼朝の前で有力な武士が鼓や銅拍子(シンバルに似た楽器)を演奏するシーンが描かれています。まさに、武器と楽器の“二刀流”です。
鎌倉では、コンサートのようなイベントも行われていたようです。音楽フェスティバルを催すなんて、粋な将軍ですね。
さらに、「船楽」〈注3〉という行事も行われていました。これは、船での音楽パーティーのようなもの。
「戦場に行く前に、船上で楽しもう」なんて、士気を高めていたのかもしれません。
戦いを担う集団というだけでなく、音楽を通じて文化的な教養も身につけていた鎌倉武士。強さと優雅さを併せ持つ生き方に、憧れてしまいますね。
ようやく秋の足音が聞こえてきそうな、きょうこの頃。
どんなに季節が移り変わろうとも、ネコたま殿が鎌倉武士をリスペクトする気持ちは変わりません。仲間と鍛錬の日々を送っています。
きょうは遠くから、その道の達人がやってきてレッスンを受けているようです。
きっと、刀や弓矢などの腕を磨くのでしょう。いつになく真剣な表情です。
部屋にこもったネコたま殿。聞こえてくるのは、威勢のいい掛け声ではなく、音楽の演奏……。
どうやら、琴や鼓の稽古に励んでいるようです。
実は、鎌倉武士は、武器だけではなく楽器の鍛錬にも余念がありませんでした。
それにしてもなぜ、武士が楽器を?
◆
楽器の音色は笛・篳篥がよい。常に聞きたいのは琵琶や和琴である――〈注1〉。
これは、鎌倉時代の随筆『徒然草』の一節です。
多様な楽器が演奏されて、人によって好みもあったことが伝わってきますね。
京都で隆盛した雅楽〈注2〉は、鎌倉にも広がっていきました。
初代将軍である源頼朝が、武家社会にも上流階級の洗練された文化を根付かせようと、雅楽のミュージシャンである楽人を京都から鎌倉に招き、演奏させていたのです。
さらに、武士に対する楽器のレッスンも行われるようになりました。
「おっと、音が出ていません!」なんて、注意される場面があったかもしれません。
歴史書『吾妻鏡』には、頼朝の前で有力な武士が鼓や銅拍子(シンバルに似た楽器)を演奏するシーンが描かれています。まさに、武器と楽器の“二刀流”です。
鎌倉では、コンサートのようなイベントも行われていたようです。音楽フェスティバルを催すなんて、粋な将軍ですね。
さらに、「船楽」〈注3〉という行事も行われていました。これは、船での音楽パーティーのようなもの。
「戦場に行く前に、船上で楽しもう」なんて、士気を高めていたのかもしれません。
戦いを担う集団というだけでなく、音楽を通じて文化的な教養も身につけていた鎌倉武士。強さと優雅さを併せ持つ生き方に、憧れてしまいますね。

雅楽に用いる管楽器の笙(しょう)。鎌倉時代の音楽書『教訓抄』、随筆『徒然草』にも、その名が見られる。長短の竹管を並べ、和音による演奏ができる©MIN-ON
雅楽に用いる管楽器の笙(しょう)。鎌倉時代の音楽書『教訓抄』、随筆『徒然草』にも、その名が見られる。長短の竹管を並べ、和音による演奏ができる©MIN-ON
稲を植えるのも楽しいね! 田んぼでダンス!
稲を植えるのも楽しいね! 田んぼでダンス!
武士や貴族だけではありません。庶民も音楽を楽しんでいました。
中でも人気だったのが、平曲です。これは、弦楽器の琵琶の演奏に合わせ、「平家物語」〈注4〉を歌い語るもの。
当時の絵巻物には、人々でにぎわう市に琵琶の演奏家の姿が描かれています。現代でいう、路上での弾き語りのようなイメージでしょうか。
「ヘイ! ヘイ! 平曲の時間だよ!」なんて、呼びかけていたかもしれません。
当時は、テレビもインターネットもありません。琵琶の伴奏で物語が歌い語られることで、音楽と共に源平合戦や平家の衰亡など、歴史や時事が伝わっていったのです。
さらに庶民は、鑑賞するだけでなく、祭礼や農作業の時期に自ら歌い、踊って音楽を楽しみました。
田植えの時に笛や鼓の伴奏でダンスする、田楽もブームに。平安時代から鎌倉時代にかけて、職業的な芸人集団が登場するほど発展しました。
「音楽があれば、稲を植えるのも、楽しいね!」
そんな声が聞こえてきそうです。
また、ユーモラスな囃子を交えた猿楽も、庶民に親しまれました。
時代が下り、室町時代になると田楽や猿楽は、能楽や狂言のような洗練された芸術に発展していきました。
貴族の文化が武士や庶民に伝わり、庶民の自由で活発な芸能が、上流階級に触発を与える――。
こうして、新たな日本の文化が、にぎやかに形成されていったんですね。
武士や貴族だけではありません。庶民も音楽を楽しんでいました。
中でも人気だったのが、平曲です。これは、弦楽器の琵琶の演奏に合わせ、「平家物語」〈注4〉を歌い語るもの。
当時の絵巻物には、人々でにぎわう市に琵琶の演奏家の姿が描かれています。現代でいう、路上での弾き語りのようなイメージでしょうか。
「ヘイ! ヘイ! 平曲の時間だよ!」なんて、呼びかけていたかもしれません。
当時は、テレビもインターネットもありません。琵琶の伴奏で物語が歌い語られることで、音楽と共に源平合戦や平家の衰亡など、歴史や時事が伝わっていったのです。
さらに庶民は、鑑賞するだけでなく、祭礼や農作業の時期に自ら歌い、踊って音楽を楽しみました。
田植えの時に笛や鼓の伴奏でダンスする、田楽もブームに。平安時代から鎌倉時代にかけて、職業的な芸人集団が登場するほど発展しました。
「音楽があれば、稲を植えるのも、楽しいね!」
そんな声が聞こえてきそうです。
また、ユーモラスな囃子を交えた猿楽も、庶民に親しまれました。
時代が下り、室町時代になると田楽や猿楽は、能楽や狂言のような洗練された芸術に発展していきました。
貴族の文化が武士や庶民に伝わり、庶民の自由で活発な芸能が、上流階級に触発を与える――。
こうして、新たな日本の文化が、にぎやかに形成されていったんですね。
〈注1〉『徒然草』第16段を参照。篳篥は雅楽で用いられた管楽器。
〈注2〉貴族社会と結びつき発展してきた日本固有の芸能。琵琶や龍笛、鼓などが古くから用いられていた。
〈注3〉京都の貴族は池に船を浮かべて行っていたが、鎌倉では由比ケ浜などの海上でも行われていた。
〈注4〉鎌倉時代に成立したとされる軍記物語。平家の興亡が叙事詩的に描かれている。
【参考文献】荻美津夫著『古代中世音楽史の研究』(吉川弘文館)。遠藤徹他著『図説 雅楽入門事典』(柏書房)。吉川英史著『日本音楽の歴史』(創元社)。田辺尚雄著『日本の音楽』(全音楽譜出版社)。林幸光著『器楽と声楽のはなし』(音楽之友社)。兵藤裕己著『琵琶法師』(岩波新書)。釣谷真弓著『歴史からでも楽しい! おもしろ日本音楽』(東京堂出版)。
〈注1〉『徒然草』第16段を参照。篳篥は雅楽で用いられた管楽器。
〈注2〉貴族社会と結びつき発展してきた日本固有の芸能。琵琶や龍笛、鼓などが古くから用いられていた。
〈注3〉京都の貴族は池に船を浮かべて行っていたが、鎌倉では由比ケ浜などの海上でも行われていた。
〈注4〉鎌倉時代に成立したとされる軍記物語。平家の興亡が叙事詩的に描かれている。
【参考文献】荻美津夫著『古代中世音楽史の研究』(吉川弘文館)。遠藤徹他著『図説 雅楽入門事典』(柏書房)。吉川英史著『日本音楽の歴史』(創元社)。田辺尚雄著『日本の音楽』(全音楽譜出版社)。林幸光著『器楽と声楽のはなし』(音楽之友社)。兵藤裕己著『琵琶法師』(岩波新書)。釣谷真弓著『歴史からでも楽しい! おもしろ日本音楽』(東京堂出版)。
その時、日蓮大聖人は――
その時、日蓮大聖人は――
鎌倉時代の人々は楽器に親しみがあり、その音色も含めてイメージしやすかったのでしょうか。日蓮大聖人も、門下へのお手紙の中で、しばしば楽器を譬えに用いられています。
はるかかなたの地まで瞬時に音が伝わったとされる、中国の「雷門の鼓」を譬えに、遠く離れている門下に対して、「お顔を見たからといってなんになるでしょう。心こそ大切です」〈※1〉とつづられました。“あなたの心は、確かに私に届いていますよ”との真心が伝わってきます。
さらに大聖人は、弦楽器の「琴」を譬えに、妙法の偉大さを説かれています。
「師子の筋を琴の絃にして、これを弾けば、他の一切の獣の筋の絃は皆、切ってもいないのに切れてしまう。仏の説法を師子吼という」〈※2〉
百獣の王の筋を絃として奏でる音色が、他を圧倒するように、法華経こそが「師子吼」であることを強調されました。
大聖人の真心と大確信が、門下の心に深く響きわたったに違いありません。
鎌倉時代の人々は楽器に親しみがあり、その音色も含めてイメージしやすかったのでしょうか。日蓮大聖人も、門下へのお手紙の中で、しばしば楽器を譬えに用いられています。
はるかかなたの地まで瞬時に音が伝わったとされる、中国の「雷門の鼓」を譬えに、遠く離れている門下に対して、「お顔を見たからといってなんになるでしょう。心こそ大切です」〈※1〉とつづられました。“あなたの心は、確かに私に届いていますよ”との真心が伝わってきます。
さらに大聖人は、弦楽器の「琴」を譬えに、妙法の偉大さを説かれています。
「師子の筋を琴の絃にして、これを弾けば、他の一切の獣の筋の絃は皆、切ってもいないのに切れてしまう。仏の説法を師子吼という」〈※2〉
百獣の王の筋を絃として奏でる音色が、他を圧倒するように、法華経こそが「師子吼」であることを強調されました。
大聖人の真心と大確信が、門下の心に深く響きわたったに違いありません。
〈※1〉御書新版1746ページ・御書全集1316ページ、趣意
〈※2〉御書新版1528ページ・御書全集1122ページ、趣意
〈※1〉御書新版1746ページ・御書全集1316ページ、趣意
〈※2〉御書新版1528ページ・御書全集1122ページ、趣意