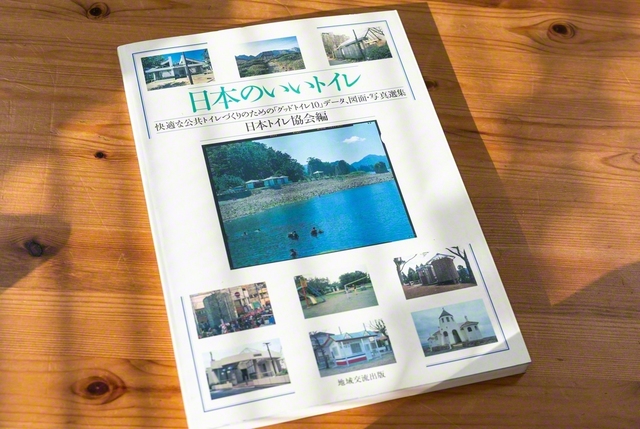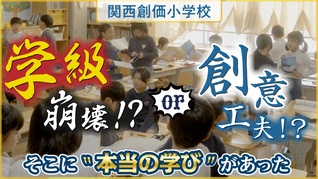トイレ研究40年! 日本トイレ協会会長に聞く
トイレ研究40年! 日本トイレ協会会長に聞く
2025年4月15日
- 〈SDGs×SEIKYO〉 “矜持”が生んだ、世界の“憧れ”
- 〈SDGs×SEIKYO〉 “矜持”が生んだ、世界の“憧れ”
言葉からあふれる、トイレ愛。聞けば聞くほど、白く丸みを帯びたトイレが愛おしく思えてくる……。日本トイレ協会の山本耕平会長は、トイレ研究を続けて40年。その情熱で、日本のトイレ環境に変革の波を起こしてきました。今、改めて注目される災害時のトイレ問題や、SDGsの目標6「安全な水とトイレを世界中に」を巡って、山本会長にインタビューしました。(取材=田川さくら、樹下智)
言葉からあふれる、トイレ愛。聞けば聞くほど、白く丸みを帯びたトイレが愛おしく思えてくる……。日本トイレ協会の山本耕平会長は、トイレ研究を続けて40年。その情熱で、日本のトイレ環境に変革の波を起こしてきました。今、改めて注目される災害時のトイレ問題や、SDGsの目標6「安全な水とトイレを世界中に」を巡って、山本会長にインタビューしました。(取材=田川さくら、樹下智)
――なぜ、トイレに興味を持ったのですか。
僕は大学時代、政治学科で自治体のごみ対策について研究しました。卒業後は市役所勤務を経て、都市政策のシンクタンクで空き缶のポイ捨て対策に取り組んでいたのですが、観光地で調査を続けると、空き缶よりも気になることがあったんです。それが、トイレです。
数少ない公衆トイレはどれも汚く、“関係者以外、使用禁止”と書いてある。「これは一体、どういうことだ!」と公衆トイレに問題意識を持つようになりました。
当時、東京・西新橋のビルの地下に、サラリーマンのたまり場となっている店がありました。うまい酒と料理を味わいながら、面白いネタで語り合う。テーマごとに会ができ、いろんな事業の誕生の場ともなっていました。
そこで僕が立ち上げたのが「トイレットピアの会」です。トイレを切り口に、いろんな社会課題を語り合う。医師や社長など、多くの人が「面白い」と参加してくれていましたね(笑)。風変わりだからか、テレビや新聞の取材も来るようになりました。
実は、それまでのメディアは、トイレに関するニュース報道をはばかっていました。だけど、僕たちの特集を機に、トイレにまつわる話題が一気に増えた。この勢いのままいけば、日本のトイレを変革できるかもしれない――そんな思いで1985年に日本トイレ協会を設立しました。
――なぜ、トイレに興味を持ったのですか。
僕は大学時代、政治学科で自治体のごみ対策について研究しました。卒業後は市役所勤務を経て、都市政策のシンクタンクで空き缶のポイ捨て対策に取り組んでいたのですが、観光地で調査を続けると、空き缶よりも気になることがあったんです。それが、トイレです。
数少ない公衆トイレはどれも汚く、“関係者以外、使用禁止”と書いてある。「これは一体、どういうことだ!」と公衆トイレに問題意識を持つようになりました。
当時、東京・西新橋のビルの地下に、サラリーマンのたまり場となっている店がありました。うまい酒と料理を味わいながら、面白いネタで語り合う。テーマごとに会ができ、いろんな事業の誕生の場ともなっていました。
そこで僕が立ち上げたのが「トイレットピアの会」です。トイレを切り口に、いろんな社会課題を語り合う。医師や社長など、多くの人が「面白い」と参加してくれていましたね(笑)。風変わりだからか、テレビや新聞の取材も来るようになりました。
実は、それまでのメディアは、トイレに関するニュース報道をはばかっていました。だけど、僕たちの特集を機に、トイレにまつわる話題が一気に増えた。この勢いのままいけば、日本のトイレを変革できるかもしれない――そんな思いで1985年に日本トイレ協会を設立しました。
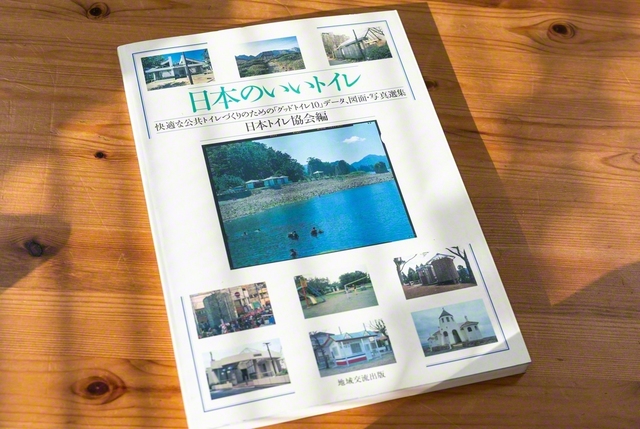
きれいなトイレがずらり!――日本トイレ協会が編集した『日本のいいトイレ』
きれいなトイレがずらり!――日本トイレ協会が編集した『日本のいいトイレ』
――今や、外出先のトイレでよく見かける設備ができたのも、日本トイレ協会のおかげだとか……。
僕たちは、設立時から毎年、トイレシンポジウムを開催し、トイレに関するさまざまな問題を議論してきました。
まだ和式が主流だった頃です。子育て中のお母さんから“赤ちゃんを抱いていると用が足せない”と聞き、シンポジウムで取り上げたことがあります。これがきっかけで、後にベビーキープと呼ばれる乳児専用チェアが開発されました。
また、協会の活動として、一部の公衆トイレにおむつ交換用のベビーベッドを設置したことがあります。そのことをシンポジウムで話したところ、参加していたある会社が、おむつ交換台を作ってくれました。
ほかにも、協会では、長年にわたり、きれいなトイレを顕彰するコンテストを開いています。実はこれが、日本のトイレを変革する起爆剤となったんです。
コンテストで入賞すると、地元紙が報じますよね。すると、周辺の市町村が「我々も!」と対抗心を燃やして、トイレの改善に力を入れる。徐々に、きれいなトイレが増えていきました。
――そうした反応は、国内にとどまらなかったそうですね。
僕たちのうわさはあっという間に海を越え、イギリスのBBCやフランスの公共放送などからも取材を受けるようになりました。
面白かったのは、フランスのテレビ局から取材を受けた時のことです。トイレをテーマに、両国の交流を提案してみたところ、フランス側は意外にも乗り気な反応で。なんと、ベルサイユ宮殿の離宮で「日仏トイレフォーラム」を行うことになったんです(笑)。これを機に、フランスでは「フランストイレ協会」が発足しました。
今では多くの国で、僕たちと同じような団体ができ、各地のトイレ環境改善のために活動していますよ。
――今や、外出先のトイレでよく見かける設備ができたのも、日本トイレ協会のおかげだとか……。
僕たちは、設立時から毎年、トイレシンポジウムを開催し、トイレに関するさまざまな問題を議論してきました。
まだ和式が主流だった頃です。子育て中のお母さんから“赤ちゃんを抱いていると用が足せない”と聞き、シンポジウムで取り上げたことがあります。これがきっかけで、後にベビーキープと呼ばれる乳児専用チェアが開発されました。
また、協会の活動として、一部の公衆トイレにおむつ交換用のベビーベッドを設置したことがあります。そのことをシンポジウムで話したところ、参加していたある会社が、おむつ交換台を作ってくれました。
ほかにも、協会では、長年にわたり、きれいなトイレを顕彰するコンテストを開いています。実はこれが、日本のトイレを変革する起爆剤となったんです。
コンテストで入賞すると、地元紙が報じますよね。すると、周辺の市町村が「我々も!」と対抗心を燃やして、トイレの改善に力を入れる。徐々に、きれいなトイレが増えていきました。
――そうした反応は、国内にとどまらなかったそうですね。
僕たちのうわさはあっという間に海を越え、イギリスのBBCやフランスの公共放送などからも取材を受けるようになりました。
面白かったのは、フランスのテレビ局から取材を受けた時のことです。トイレをテーマに、両国の交流を提案してみたところ、フランス側は意外にも乗り気な反応で。なんと、ベルサイユ宮殿の離宮で「日仏トイレフォーラム」を行うことになったんです(笑)。これを機に、フランスでは「フランストイレ協会」が発足しました。
今では多くの国で、僕たちと同じような団体ができ、各地のトイレ環境改善のために活動していますよ。

1989年、ベルサイユ宮殿の離宮で行われた「日仏トイレフォーラム」(本人提供)
1989年、ベルサイユ宮殿の離宮で行われた「日仏トイレフォーラム」(本人提供)
「使えない!」
「使えない!」
――排せつは、人が生きる上で避けられない大切な行為です。トイレは私たちの生活環境を陰で守ってくれていますが、そのことが浮き彫りになるのが災害時ですね。
ええ。阪神・淡路大震災が起こった時、僕は、トイレ掃除のボランティアをするため、被災地へ向かいました。目に飛び込んできたのは、筆舌に尽くしがたい光景――。多くの被災者がトイレに困っていました。
実は、被害が大きかった神戸市では、大半のトイレが水洗トイレでした。
水洗トイレは、上下水道管の破損はいうまでもなく、停電によって、建物へ配水するポンプが作動しないことで機能しない場合もあります。地震により、ほぼ全てのライフラインが損壊した神戸市では、多くの水洗トイレが使用不能になっていました。
当時、災害時のトイレ対策は不十分で、救援物資として届けられた仮設トイレも計画的に配置されませんでした。仮設トイレ1基当たりの利用者数はすさまじく、くみ取り式のトイレには排せつ物があふれる始末。ひどすぎる汚れに、仮設トイレもかなりの数が封鎖されていました。
だけど、掃除に必要なデッキブラシやゴム手袋などの道具も足りない。トイレに困り、地面に穴を掘って用を足した痕跡も、至る所で見られました。
――排せつは、人が生きる上で避けられない大切な行為です。トイレは私たちの生活環境を陰で守ってくれていますが、そのことが浮き彫りになるのが災害時ですね。
ええ。阪神・淡路大震災が起こった時、僕は、トイレ掃除のボランティアをするため、被災地へ向かいました。目に飛び込んできたのは、筆舌に尽くしがたい光景――。多くの被災者がトイレに困っていました。
実は、被害が大きかった神戸市では、大半のトイレが水洗トイレでした。
水洗トイレは、上下水道管の破損はいうまでもなく、停電によって、建物へ配水するポンプが作動しないことで機能しない場合もあります。地震により、ほぼ全てのライフラインが損壊した神戸市では、多くの水洗トイレが使用不能になっていました。
当時、災害時のトイレ対策は不十分で、救援物資として届けられた仮設トイレも計画的に配置されませんでした。仮設トイレ1基当たりの利用者数はすさまじく、くみ取り式のトイレには排せつ物があふれる始末。ひどすぎる汚れに、仮設トイレもかなりの数が封鎖されていました。
だけど、掃除に必要なデッキブラシやゴム手袋などの道具も足りない。トイレに困り、地面に穴を掘って用を足した痕跡も、至る所で見られました。

阪神・淡路大震災の発生後、トイレ掃除をはじめ被災地支援のために集まった山本会長(左から5人目)らボランティアのスタッフ(同)
阪神・淡路大震災の発生後、トイレ掃除をはじめ被災地支援のために集まった山本会長(左から5人目)らボランティアのスタッフ(同)
――排せつ物の処理を適切に行わなければ、生活環境はすぐに劣悪化してしまいます。
衛生状態の悪化は、僕たちの健康にも被害を及ぼします。実際、過去には、水洗トイレが機能しないことや、仮設トイレの掃除が適切に行えないことから、ノロウイルスなどのトイレを起因とする感染症がまん延した避難所もありました。
一方、不潔なトイレを避けようと、飲食を控えるのも非常に危険です。十分な水分を取らなければ、脱水状態になります。その上、避難所などで長時間、同じ姿勢でいると「エコノミークラス症候群」になる危険性が高まります。これは、血液中にできた血栓が肺動脈に詰まる病気で、最悪の場合、死に至ります。
――そうした教訓も踏まえ、政府や各自治体も今、災害時のトイレ対策に力を入れています。
今や、大規模な災害が起こると、政府は「プッシュ型支援」として、被災地の要請を待たずして、携帯トイレを現地に緊急輸送しています。また自治体に対し、避難所となる学校などにマンホールトイレを整備するよう働きかけています。
マンホールトイレとは、マンホールの上に簡易の便器を設置し、汚物を直接、下水に流せるようにしたもので、阪神・淡路大震災の教訓から生まれました。熊本地震では、整備したばかりのマンホールトイレが活躍したと聞いています。
しかし、いくらトイレが進化を遂げようと、災害時におけるトイレの問題は、まだまだ山積みです。昨年の能登半島地震では、道路の寸断や土砂崩れなどにより、仮設トイレをはじめとする救援物資がなかなか届かない地域がありました。届けたい物は、そろっているにもかかわらずです。
そこで、僕が強く訴えたいのは、災害時のトイレは、必ず「自助(自分で自分を守る)」が必要だということです。「共助(地域住民の助け合い)」や「公助(行政による防災)」だけでどうにかなるものではありません。
僕たちが1日にトイレに行く回数は、平均して5~7回。政府が迅速に救援物資を送っても、トイレに行きたくなったタイミングで、トイレが届いているとは限りません。もしかすると、在宅避難を余儀なくされることもあるかもしれない。使えなくなったトイレを無理に使うと、汚物が逆流して、大変なことになります。
「首都直下地震」や「南海トラフ地震」など、大規模地震が発生する確率は、30年以内に70%といわれています。わが身、そして大切な人を守り抜くためにも、必ず、携帯トイレを自宅に備蓄していただきたい。理想は1週間分、1人当たり35袋(5回×7日=35袋)です。携帯トイレは、ホームセンターなどの小売店やネット通販で購入することができます。
――排せつ物の処理を適切に行わなければ、生活環境はすぐに劣悪化してしまいます。
衛生状態の悪化は、僕たちの健康にも被害を及ぼします。実際、過去には、水洗トイレが機能しないことや、仮設トイレの掃除が適切に行えないことから、ノロウイルスなどのトイレを起因とする感染症がまん延した避難所もありました。
一方、不潔なトイレを避けようと、飲食を控えるのも非常に危険です。十分な水分を取らなければ、脱水状態になります。その上、避難所などで長時間、同じ姿勢でいると「エコノミークラス症候群」になる危険性が高まります。これは、血液中にできた血栓が肺動脈に詰まる病気で、最悪の場合、死に至ります。
――そうした教訓も踏まえ、政府や各自治体も今、災害時のトイレ対策に力を入れています。
今や、大規模な災害が起こると、政府は「プッシュ型支援」として、被災地の要請を待たずして、携帯トイレを現地に緊急輸送しています。また自治体に対し、避難所となる学校などにマンホールトイレを整備するよう働きかけています。
マンホールトイレとは、マンホールの上に簡易の便器を設置し、汚物を直接、下水に流せるようにしたもので、阪神・淡路大震災の教訓から生まれました。熊本地震では、整備したばかりのマンホールトイレが活躍したと聞いています。
しかし、いくらトイレが進化を遂げようと、災害時におけるトイレの問題は、まだまだ山積みです。昨年の能登半島地震では、道路の寸断や土砂崩れなどにより、仮設トイレをはじめとする救援物資がなかなか届かない地域がありました。届けたい物は、そろっているにもかかわらずです。
そこで、僕が強く訴えたいのは、災害時のトイレは、必ず「自助(自分で自分を守る)」が必要だということです。「共助(地域住民の助け合い)」や「公助(行政による防災)」だけでどうにかなるものではありません。
僕たちが1日にトイレに行く回数は、平均して5~7回。政府が迅速に救援物資を送っても、トイレに行きたくなったタイミングで、トイレが届いているとは限りません。もしかすると、在宅避難を余儀なくされることもあるかもしれない。使えなくなったトイレを無理に使うと、汚物が逆流して、大変なことになります。
「首都直下地震」や「南海トラフ地震」など、大規模地震が発生する確率は、30年以内に70%といわれています。わが身、そして大切な人を守り抜くためにも、必ず、携帯トイレを自宅に備蓄していただきたい。理想は1週間分、1人当たり35袋(5回×7日=35袋)です。携帯トイレは、ホームセンターなどの小売店やネット通販で購入することができます。
誇るべき文化
誇るべき文化
――そんな命を守るトイレですが、私たちの生活と密着しているからこそ、トイレを切り口にすると、さまざまな社会課題が見えてきますね。
国連は、SDGsの目標6に「安全な水とトイレを世界中に」を掲げ、トイレの普及やトイレ環境の改善などを呼びかけています。一見、トイレの問題は独立しているように見えますが、実は、他のSDGsの目標ともつながっています。
例えば、建設現場で女性が使いやすいトイレはあるか、性的少数者の人権に配慮したトイレはあるかなど、トイレ環境の改善は、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」を推進する上で、重要な要素となります。
また、目標11「住み続けられるまちづくりを」には、誰もが使いやすい公共スペースの充実が掲げられていますが、トイレを見ると、女性や子ども、障がい者、家族連れなどに、どれくらい配慮されているかを推し量れます。トイレはさまざまな指標となり、“社会の鏡”ともいえるのです。
――そんな命を守るトイレですが、私たちの生活と密着しているからこそ、トイレを切り口にすると、さまざまな社会課題が見えてきますね。
国連は、SDGsの目標6に「安全な水とトイレを世界中に」を掲げ、トイレの普及やトイレ環境の改善などを呼びかけています。一見、トイレの問題は独立しているように見えますが、実は、他のSDGsの目標ともつながっています。
例えば、建設現場で女性が使いやすいトイレはあるか、性的少数者の人権に配慮したトイレはあるかなど、トイレ環境の改善は、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」を推進する上で、重要な要素となります。
また、目標11「住み続けられるまちづくりを」には、誰もが使いやすい公共スペースの充実が掲げられていますが、トイレを見ると、女性や子ども、障がい者、家族連れなどに、どれくらい配慮されているかを推し量れます。トイレはさまざまな指標となり、“社会の鏡”ともいえるのです。

昨年度、日本トイレ協会主催のトイレコンテストで選ばれた長崎市の公衆トイレ。出入り口には死角がないため、不審者が隠れることはできない。男女共用トイレなども設置されている(同)
昨年度、日本トイレ協会主催のトイレコンテストで選ばれた長崎市の公衆トイレ。出入り口には死角がないため、不審者が隠れることはできない。男女共用トイレなども設置されている(同)
――日本のトイレは世界で、どう評価されているのでしょうか。
まだまだ改善すべき点はあるものの、世界では“きれい”と評判です。
僕は海外の方を迎えて、日本のトイレを案内することがありますが、皆さん、いつも「美しい!」と感動しています。先日も、台湾からの視察団が高速道路のトイレを見学したのですが、興奮気味に僕に聞いてきましたね。「この美しさの秘訣は何ですか?」と。
その答えには、もちろん設備の良さが挙げられるかもしれません。だけど僕は、トイレ清掃員の「プロ意識」、他者を敬う「おもてなしの心」があってこそだと思っています。
たとえ設備が古い所でも、掃除が行き届き、1輪の花なんかが飾ってある。場合によっては、トイレ掃除をしている人から「ご利用ありがとうございました」とお礼まで言われる。そんな国は、どこにもありません。
日本も昔は、トイレが汚かった。それでも、日の当たらない所で、黙々とトイレを掃除し続けた人がいた。“私も、この街を盛り上げる一人なんだ”と、誇りを胸に、矜持を胸に、便器を磨き続けた人がいた。
今、トイレ清掃員はエッセンシャルワーカーと呼ばれ、社会でなくてはならない存在です。そうした人たちがいて、世界が憧れる日本のトイレの今がある。
トイレは、日本が誇るべき文化の結晶――僕はそう思いますね。
――日本のトイレは世界で、どう評価されているのでしょうか。
まだまだ改善すべき点はあるものの、世界では“きれい”と評判です。
僕は海外の方を迎えて、日本のトイレを案内することがありますが、皆さん、いつも「美しい!」と感動しています。先日も、台湾からの視察団が高速道路のトイレを見学したのですが、興奮気味に僕に聞いてきましたね。「この美しさの秘訣は何ですか?」と。
その答えには、もちろん設備の良さが挙げられるかもしれません。だけど僕は、トイレ清掃員の「プロ意識」、他者を敬う「おもてなしの心」があってこそだと思っています。
たとえ設備が古い所でも、掃除が行き届き、1輪の花なんかが飾ってある。場合によっては、トイレ掃除をしている人から「ご利用ありがとうございました」とお礼まで言われる。そんな国は、どこにもありません。
日本も昔は、トイレが汚かった。それでも、日の当たらない所で、黙々とトイレを掃除し続けた人がいた。“私も、この街を盛り上げる一人なんだ”と、誇りを胸に、矜持を胸に、便器を磨き続けた人がいた。
今、トイレ清掃員はエッセンシャルワーカーと呼ばれ、社会でなくてはならない存在です。そうした人たちがいて、世界が憧れる日本のトイレの今がある。
トイレは、日本が誇るべき文化の結晶――僕はそう思いますね。

昨年、開催された第40回「全国トイレシンポジウム」。テーマは「能登半島地震の経験から考えるインクルーシブ防災と災害トイレ」(同)
昨年、開催された第40回「全国トイレシンポジウム」。テーマは「能登半島地震の経験から考えるインクルーシブ防災と災害トイレ」(同)
やまもと・こうへい 兵庫県出身。早稲田大学政治経済学部を卒業後、神戸市役所に勤務。1984年にダイナックス都市環境研究所を設立し、代表取締役に就任した。日本トイレ協会会長のほか、NPO法人「雨水市民の会」の理事長も務める。
やまもと・こうへい 兵庫県出身。早稲田大学政治経済学部を卒業後、神戸市役所に勤務。1984年にダイナックス都市環境研究所を設立し、代表取締役に就任した。日本トイレ協会会長のほか、NPO法人「雨水市民の会」の理事長も務める。
●ご感想をお寄せください。
sdgs@seikyo-np.jp
●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html
●海外識者のインタビューの英語版が「創価学会グローバルサイト」に掲載されています。
https://www.sokaglobal.org/resources/expert-perspectives.html
●ご感想をお寄せください。
sdgs@seikyo-np.jp
●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html
●海外識者のインタビューの英語版が「創価学会グローバルサイト」に掲載されています。
https://www.sokaglobal.org/resources/expert-perspectives.html
書籍「ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs」が好評発売中
書籍「ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs」が好評発売中
『ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs』(写真)が好評発売中である。
同書は本紙の企画「ちーちゃんと考える 未来のカタチ」を書籍化したもの。連載中の4こま漫画「ちーちゃん家」のキャラクターたちが、SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標や、世界が直面する諸課題について解説し、地球の未来のカタチを楽しく学ぶことができる。
SDGsに関するクイズやコラム、4こま漫画も収録。親子での学習や、座談会での企画に活用できる一書である。
潮出版社刊。1650円(税込み)。全国の書店で購入・注文可能。聖教ブックストアのウェブサイトでも受け付け中。電話=(0120)983563(午前9時~午後5時、土・日・祝日を除く)。※電話の場合、支払いは代金引換のみ。FAXでの注文はできません。コンビニ通販サイト「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」での注文、受け取りも可能です。
『ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs』(写真)が好評発売中である。
同書は本紙の企画「ちーちゃんと考える 未来のカタチ」を書籍化したもの。連載中の4こま漫画「ちーちゃん家」のキャラクターたちが、SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標や、世界が直面する諸課題について解説し、地球の未来のカタチを楽しく学ぶことができる。
SDGsに関するクイズやコラム、4こま漫画も収録。親子での学習や、座談会での企画に活用できる一書である。
潮出版社刊。1650円(税込み)。全国の書店で購入・注文可能。聖教ブックストアのウェブサイトでも受け付け中。電話=(0120)983563(午前9時~午後5時、土・日・祝日を除く)。※電話の場合、支払いは代金引換のみ。FAXでの注文はできません。コンビニ通販サイト「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」での注文、受け取りも可能です。
音声読み上げ