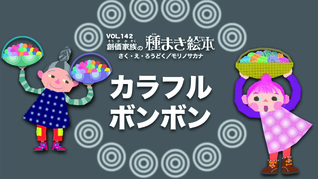〈未来対談〉 テーマ②「平等」って何?
〈未来対談〉 テーマ②「平等」って何?
2025年5月1日
- 創価学会青年世代×慶應義塾大学 井手英策教授
- 創価学会青年世代×慶應義塾大学 井手英策教授
連載「未来対談」――2回目のテーマは「『平等』って何?」です。初回(4月11日付)に続き、慶應義塾大学経済学部の井手英策教授と共に、池田大作先生と松下幸之助氏の対談集『人生問答』(『池田大作全集』第8巻所収)を学びました(勉強会を本年2、3、4月に実施)。「不平等」を感じることの多い競争社会にあって、「平等」とは何かを、読者のみなさんと一緒に考えたいと思います。
連載「未来対談」――2回目のテーマは「『平等』って何?」です。初回(4月11日付)に続き、慶應義塾大学経済学部の井手英策教授と共に、池田大作先生と松下幸之助氏の対談集『人生問答』(『池田大作全集』第8巻所収)を学びました(勉強会を本年2、3、4月に実施)。「不平等」を感じることの多い競争社会にあって、「平等」とは何かを、読者のみなさんと一緒に考えたいと思います。

学会の青年世代と慶應義塾大学の井手教授が活発に意見交換(4月25日、世界聖教会館で)
学会の青年世代と慶應義塾大学の井手教授が活発に意見交換(4月25日、世界聖教会館で)
〈井手教授〉
日本は「不平等社会」になりました。夢を見る自由すら若者からうばう。これほど残酷なことはありません。私は、とてもまずしい母子家庭で育ちました。それでも、母と叔母が借金まみれになって学費をはらってくれ、学者になれました。一方、私と同じ境遇の子どもたちが、勉強や進学の機会を与えられず、未来をあきらめようとしています。「まずしい家に生まれた」というだけで絶望を押しつけられる。こんな「不平等」を許していいのでしょうか。
〈青年世代〉
私たちも全く同じ思いです。私も弟が不登校になり、苦しんでいる姿を見た時は、本当に悔しかった。大好きな家族が「学校に行けない」というだけで、どうして絶望するまで追い込まれなくちゃいけないのか。胸が張り裂けそうでした。家族にも相談できず、悩んでいた時、寄り添ってくれたのは周りの学会員のみなさんでした。私の様子が少し変だと気付いて、「大丈夫?」「どうしたの?」と声をかけてくれたんです。みなさんの優しさに、どれほど救われたか分かりません。
〈井手教授〉
日本は「不平等社会」になりました。夢を見る自由すら若者からうばう。これほど残酷なことはありません。私は、とてもまずしい母子家庭で育ちました。それでも、母と叔母が借金まみれになって学費をはらってくれ、学者になれました。一方、私と同じ境遇の子どもたちが、勉強や進学の機会を与えられず、未来をあきらめようとしています。「まずしい家に生まれた」というだけで絶望を押しつけられる。こんな「不平等」を許していいのでしょうか。
〈青年世代〉
私たちも全く同じ思いです。私も弟が不登校になり、苦しんでいる姿を見た時は、本当に悔しかった。大好きな家族が「学校に行けない」というだけで、どうして絶望するまで追い込まれなくちゃいけないのか。胸が張り裂けそうでした。家族にも相談できず、悩んでいた時、寄り添ってくれたのは周りの学会員のみなさんでした。私の様子が少し変だと気付いて、「大丈夫?」「どうしたの?」と声をかけてくれたんです。みなさんの優しさに、どれほど救われたか分かりません。
現役世代を元気に
現役世代を元気に
〈井手教授〉
悲しい記憶を話してくれてありがとう。「目の前の一人」を大事にする。理屈を重んじる学者には、なかなかできないことです。「不平等」だらけの社会にあって、みなさんの宗教活動は希望の曙光です。でもね、私には、もう一つの「不平等」が見える気がするのです。みなさんと出会えた人は幸せです。どんな不遇にあっても勇気をもらえるのだから。でも、みなさんと出会えない人たちは、おびえながら生きるしかない。これは「不平等」ではないのでしょうか。そもそも、みなさんの優しさに頼りきった社会は、健全なのでしょうか。今の日本は「不平等」に苦しんでいる人がいても見て見ぬふりをする、不遇や苦境を「自己責任」と切り捨てる、そんな社会です。
〈青年世代〉
こういう現実から目を背けず、社会を変えたいと思っています。日本では「不平等」に悩んでいる人が多いのに、支え合うどころか互いを批判してしまっています。最近よく耳にする「世代間の分断」という言葉も、その一例だと思います。『人生問答』第9章(現代文明への反省)の中でも、池田先生と松下氏が、このことについて語り合っています。発刊当時(1975年)の日本では「世代の断絶」「親子の断絶」といったフレーズが流行し、社会現象になっていました。「断絶」という言葉を安易に使い、人々の心をあおるような社会の風潮に、松下氏は強い危機感を示しています。
〈井手教授〉
悲しい記憶を話してくれてありがとう。「目の前の一人」を大事にする。理屈を重んじる学者には、なかなかできないことです。「不平等」だらけの社会にあって、みなさんの宗教活動は希望の曙光です。でもね、私には、もう一つの「不平等」が見える気がするのです。みなさんと出会えた人は幸せです。どんな不遇にあっても勇気をもらえるのだから。でも、みなさんと出会えない人たちは、おびえながら生きるしかない。これは「不平等」ではないのでしょうか。そもそも、みなさんの優しさに頼りきった社会は、健全なのでしょうか。今の日本は「不平等」に苦しんでいる人がいても見て見ぬふりをする、不遇や苦境を「自己責任」と切り捨てる、そんな社会です。
〈青年世代〉
こういう現実から目を背けず、社会を変えたいと思っています。日本では「不平等」に悩んでいる人が多いのに、支え合うどころか互いを批判してしまっています。最近よく耳にする「世代間の分断」という言葉も、その一例だと思います。『人生問答』第9章(現代文明への反省)の中でも、池田先生と松下氏が、このことについて語り合っています。発刊当時(1975年)の日本では「世代の断絶」「親子の断絶」といったフレーズが流行し、社会現象になっていました。「断絶」という言葉を安易に使い、人々の心をあおるような社会の風潮に、松下氏は強い危機感を示しています。
〈井手教授〉
状況は、50年たった今も変わっていません。いや、「世代間の分断」を強調し、対立をあおるような心ない人々は、増えてさえいる気がします。
〈青年世代〉
世代の分断をあおっても、私たちの生活は一ミリも良くなりません。高齢化が進んでいる日本では、多くの若者が“財政負担を一方的に背負わされている”と反感を示しています。SNSでは、高齢者を「逃げ切り世代」と呼び、批判する投稿が後をたちません。たしかに、私たちの世代には生活苦で悩んでいる人が大勢います。でも高齢者の中にも、同じように経済的に苦しんでいる人たちがいるのも現実です。現役世代をはじめ、今、希望を失っている人たちが、生き生きと働けるようになっていけば、税収が増え、社会保障の担い手も増えます。そうすれば、全世代が元気になるはずです。「高齢者か若者か」という二者択一論で対立をあおるのではなく、全ての世代が、より良く生きられるような社会を目指さねばならないと思います。
〈井手教授〉
みなさんらしい視点です。「だれか」ではなく、「みんな」の幸せ。第1回の「自他共の幸福」を思い出します。他者の命や価値を大事にする社会は、他者が「私」の命や価値を認めてくれる平等な社会。池田会長も、各世代、それぞれの持ち味を「調和」させることの大切さを説かれました。これは本当に大事な点です。「共にある」という連帯感を広げなければ、「自分の力で何とかしなさい」という冷血な自己責任論におしつぶされる。「断絶」を「協調」に変えるには、まず、みなが「平等」に生きられる社会をつくらねばなりませんが、「平等」には、いろんな形があります。
〈青年世代〉
池田先生は『人生問答』の中で、差別があってはならない“絶対的な平等”として、“機会の平等”を挙げられています。私たちは学会の中で、全ての人に「仏の生命」が備わっていると教わっています。だからこそ、全ての人の生命には「尊厳性」がある――と。一人一人が自己の能力を発揮するためには、だれもが挑戦できる機会の平等を実現することが大切だと考えます。
〈井手教授〉
状況は、50年たった今も変わっていません。いや、「世代間の分断」を強調し、対立をあおるような心ない人々は、増えてさえいる気がします。
〈青年世代〉
世代の分断をあおっても、私たちの生活は一ミリも良くなりません。高齢化が進んでいる日本では、多くの若者が“財政負担を一方的に背負わされている”と反感を示しています。SNSでは、高齢者を「逃げ切り世代」と呼び、批判する投稿が後をたちません。たしかに、私たちの世代には生活苦で悩んでいる人が大勢います。でも高齢者の中にも、同じように経済的に苦しんでいる人たちがいるのも現実です。現役世代をはじめ、今、希望を失っている人たちが、生き生きと働けるようになっていけば、税収が増え、社会保障の担い手も増えます。そうすれば、全世代が元気になるはずです。「高齢者か若者か」という二者択一論で対立をあおるのではなく、全ての世代が、より良く生きられるような社会を目指さねばならないと思います。
〈井手教授〉
みなさんらしい視点です。「だれか」ではなく、「みんな」の幸せ。第1回の「自他共の幸福」を思い出します。他者の命や価値を大事にする社会は、他者が「私」の命や価値を認めてくれる平等な社会。池田会長も、各世代、それぞれの持ち味を「調和」させることの大切さを説かれました。これは本当に大事な点です。「共にある」という連帯感を広げなければ、「自分の力で何とかしなさい」という冷血な自己責任論におしつぶされる。「断絶」を「協調」に変えるには、まず、みなが「平等」に生きられる社会をつくらねばなりませんが、「平等」には、いろんな形があります。
〈青年世代〉
池田先生は『人生問答』の中で、差別があってはならない“絶対的な平等”として、“機会の平等”を挙げられています。私たちは学会の中で、全ての人に「仏の生命」が備わっていると教わっています。だからこそ、全ての人の生命には「尊厳性」がある――と。一人一人が自己の能力を発揮するためには、だれもが挑戦できる機会の平等を実現することが大切だと考えます。
〈井手教授〉
生命の尊厳。これほど大事な言葉はありません。私も、生命の尊厳に上下はないと思うからこそ、教育や医療、介護、子育て、障がい者福祉など、命と暮らしを守るためのサービスを「ベーシックサービス」と名づけ、それらを“だれもが無料で使える”社会を提案してきました。お金持ちも、まずしい人も、みなが平等にサービスを使う、所得で人間を区別しない社会です。池田会長は『人生問答』で、「人間生命」は「共通基盤にささえられ、そのうえで、個々の才能なり、天分を発揮できる」と言われました。だれもが能力を発揮するには、暮らしの安心という共通基盤が必要です。それは、まずしい人を支えるだけでなく、みなが安心できる社会をつくるということです。
〈青年世代〉
「弱者が出たら助ける社会」ではなく「弱者を生まない社会」を実現する、ということですね。そのためには、制度化し、人の意識や環境を変えていくことが欠かせません。ですが、井手先生にお聞きしたいことがあります。日本では、国から助けてもらう、だれかに守ってもらう、という感覚に陥りがちで、“生命の主体性”が発揮されにくい状況があるように感じます。
〈井手教授〉
池田会長は、『政治と宗教』(潮出版社)の中で、「大衆の福祉」の本質は「相互扶助」だと言われました。相互扶助とは、喜びと同時に、苦しみも分かち合うこと。ベーシックサービスの無償化にはお金がかかります。税金が必要です。あなたが税をはらうことで、ある人が支えられます。でもその人もまた、どんなにまずしくても、どんなにわずかでも税金をはらって、あなたの暮らしを支えています。「生命の主体性」がなくなるのではない。「主体的に生命を支え合う」決意を示すのです。
残念なことに、日本は「税」に対する意識がとても低い。恥ずかしげもなく、「令和の税負担は江戸時代の『五公五民』並み」などと言う人がいる。江戸時代の年貢は取られっぱなしでした。私たちの税金は、使い道を私たちの代表が決め、道路や学校をつくり、医療や介護を充実させる財源です。私たちは「負担者」であると同時に「受益者」でもあるのです。
〈青年世代〉
確かに、日本では“税金は国から搾取されるもの”といった偏見が強いと感じます。私たちはもっと「税」や「財政」について考え、自分たちが納めた税の使い道をどうするかについて、議論する場を増やしていく必要があります。
〈井手教授〉
生命の尊厳。これほど大事な言葉はありません。私も、生命の尊厳に上下はないと思うからこそ、教育や医療、介護、子育て、障がい者福祉など、命と暮らしを守るためのサービスを「ベーシックサービス」と名づけ、それらを“だれもが無料で使える”社会を提案してきました。お金持ちも、まずしい人も、みなが平等にサービスを使う、所得で人間を区別しない社会です。池田会長は『人生問答』で、「人間生命」は「共通基盤にささえられ、そのうえで、個々の才能なり、天分を発揮できる」と言われました。だれもが能力を発揮するには、暮らしの安心という共通基盤が必要です。それは、まずしい人を支えるだけでなく、みなが安心できる社会をつくるということです。
〈青年世代〉
「弱者が出たら助ける社会」ではなく「弱者を生まない社会」を実現する、ということですね。そのためには、制度化し、人の意識や環境を変えていくことが欠かせません。ですが、井手先生にお聞きしたいことがあります。日本では、国から助けてもらう、だれかに守ってもらう、という感覚に陥りがちで、“生命の主体性”が発揮されにくい状況があるように感じます。
〈井手教授〉
池田会長は、『政治と宗教』(潮出版社)の中で、「大衆の福祉」の本質は「相互扶助」だと言われました。相互扶助とは、喜びと同時に、苦しみも分かち合うこと。ベーシックサービスの無償化にはお金がかかります。税金が必要です。あなたが税をはらうことで、ある人が支えられます。でもその人もまた、どんなにまずしくても、どんなにわずかでも税金をはらって、あなたの暮らしを支えています。「生命の主体性」がなくなるのではない。「主体的に生命を支え合う」決意を示すのです。
残念なことに、日本は「税」に対する意識がとても低い。恥ずかしげもなく、「令和の税負担は江戸時代の『五公五民』並み」などと言う人がいる。江戸時代の年貢は取られっぱなしでした。私たちの税金は、使い道を私たちの代表が決め、道路や学校をつくり、医療や介護を充実させる財源です。私たちは「負担者」であると同時に「受益者」でもあるのです。
〈青年世代〉
確かに、日本では“税金は国から搾取されるもの”といった偏見が強いと感じます。私たちはもっと「税」や「財政」について考え、自分たちが納めた税の使い道をどうするかについて、議論する場を増やしていく必要があります。
水面の波紋のよう
水面の波紋のよう
〈井手教授〉
尊厳ある生命を等しくあつかう財政。この考えに共感していただけるのなら、僕もひとつみなさんに聞きたい。池田会長は、みんなに一律に「物質的な平等」を押しつけること――つまり、頑張った人もそうでない人も平等な結果になることはおかしい。かえって不平等になり、ひいては人間としての尊厳を無視した結果になると警告されています。
その一方で、「仏の慈悲は平等大慧であるが、苦悩、懊悩の人こそ、まず救済するのだ」とも語っています。僕が『人生問答』で一番分からなかったのは、ここです。なぜ池田会長は、“苦悩、懊悩の人をまず救うんだ”と言われたのでしょうか。なぜ、みんなを幸せにしよう、と言わなかったのでしょうか。
〈青年世代〉
池田先生は『人生問答』の中で、「内なる世界の充実のうえに、外的幸福の要素が築かれていくべき」と語っています。つまり、苦しんでいる人への「物質的な充足」の前に「心の充実」をもたらすことが大事なのだ、それが「救う」ことの意味なのだ、と。現代社会に即していえば、“物心両面”の繁栄を視野に入れているといえるのではないでしょうか。
ここで池田先生が紹介されている「苦悩、懊悩の人こそ、まず救済」という話は、仏典に説かれた釈尊と阿闍世王のエピソード(注)がもとになっていると思います。池田先生は、どこまでも「目の前の一人」を大切にし、渾身の激励をされました。それは同時に、その人の周りにいる人たち――家族や友人をはじめ、同じ境遇で悩んでいる人たち――にも勇気や生きる力を与えてきました。水面に小石を投げると波紋が広がるように、先生の励ましは、目の前の一人にとどまらず、普遍的な広がりがありました。だから、最後はみんなが幸せになれるのです。
〈井手教授〉
なるほど、そういうことか! 水面の波紋のように。じつに面白い。「目の前の一人」を救済しているように見えるけれど、じつは遠くのだれかにも届いている、と。話をうかがって、「いじめ」についての池田会長の言葉を思い出しました。学者は理由を考えます。「いじめられている子どもはかわいそうだけど、いじめられることにも理由がある」というように。ところが、池田会長は、理由はどうあれ「“いじめ”は、いじめている側が100%悪い」と断言されました。「たとえ諸君が、自分なんかダメだと思っても、私はそう思わない。私は信じている」と。その子の感じた愛は、また別の子へ、そして未来へと続くのですね。
〈青年世代〉
池田先生は『人生問答』でも「一人を手本として一切衆生平等」(新714・全564)との日蓮大聖人の言葉を紹介されていますが、まさに「苦悩・懊悩する一人」への励ましが、一切衆生すなわち「万人」を勇気づけることにつながるのではないでしょうか。「弱者を生まない」ように制度を整える。それでも、制度は万能ではありません。いくら医療が無償になっても、「病に勝とうとする生命力」がなければ、制度を生かすことができない。「弱者を生まない社会」を実現するには、制度を使う「人間の心」を強く、賢く、豊かにしていくことが肝心であると思います。
〈井手教授〉
尊厳ある生命を等しくあつかう財政。この考えに共感していただけるのなら、僕もひとつみなさんに聞きたい。池田会長は、みんなに一律に「物質的な平等」を押しつけること――つまり、頑張った人もそうでない人も平等な結果になることはおかしい。かえって不平等になり、ひいては人間としての尊厳を無視した結果になると警告されています。
その一方で、「仏の慈悲は平等大慧であるが、苦悩、懊悩の人こそ、まず救済するのだ」とも語っています。僕が『人生問答』で一番分からなかったのは、ここです。なぜ池田会長は、“苦悩、懊悩の人をまず救うんだ”と言われたのでしょうか。なぜ、みんなを幸せにしよう、と言わなかったのでしょうか。
〈青年世代〉
池田先生は『人生問答』の中で、「内なる世界の充実のうえに、外的幸福の要素が築かれていくべき」と語っています。つまり、苦しんでいる人への「物質的な充足」の前に「心の充実」をもたらすことが大事なのだ、それが「救う」ことの意味なのだ、と。現代社会に即していえば、“物心両面”の繁栄を視野に入れているといえるのではないでしょうか。
ここで池田先生が紹介されている「苦悩、懊悩の人こそ、まず救済」という話は、仏典に説かれた釈尊と阿闍世王のエピソード(注)がもとになっていると思います。池田先生は、どこまでも「目の前の一人」を大切にし、渾身の激励をされました。それは同時に、その人の周りにいる人たち――家族や友人をはじめ、同じ境遇で悩んでいる人たち――にも勇気や生きる力を与えてきました。水面に小石を投げると波紋が広がるように、先生の励ましは、目の前の一人にとどまらず、普遍的な広がりがありました。だから、最後はみんなが幸せになれるのです。
〈井手教授〉
なるほど、そういうことか! 水面の波紋のように。じつに面白い。「目の前の一人」を救済しているように見えるけれど、じつは遠くのだれかにも届いている、と。話をうかがって、「いじめ」についての池田会長の言葉を思い出しました。学者は理由を考えます。「いじめられている子どもはかわいそうだけど、いじめられることにも理由がある」というように。ところが、池田会長は、理由はどうあれ「“いじめ”は、いじめている側が100%悪い」と断言されました。「たとえ諸君が、自分なんかダメだと思っても、私はそう思わない。私は信じている」と。その子の感じた愛は、また別の子へ、そして未来へと続くのですね。
〈青年世代〉
池田先生は『人生問答』でも「一人を手本として一切衆生平等」(新714・全564)との日蓮大聖人の言葉を紹介されていますが、まさに「苦悩・懊悩する一人」への励ましが、一切衆生すなわち「万人」を勇気づけることにつながるのではないでしょうか。「弱者を生まない」ように制度を整える。それでも、制度は万能ではありません。いくら医療が無償になっても、「病に勝とうとする生命力」がなければ、制度を生かすことができない。「弱者を生まない社会」を実現するには、制度を使う「人間の心」を強く、賢く、豊かにしていくことが肝心であると思います。
〈井手教授〉
現代は「生命に内在する力」を自覚しないから、「生命そのものの主体性がなくなっている」と池田会長が嘆かれた意味がよく分かりました。政治や制度による変革と、目の前の一人から広がる激励の波紋――この両軸が大切なのですね。でもあえて言わせてください。みなさんは、草の根の活動で感じた人々の苦悩を、自分たちだけでかかえこんでいないでしょうか。それは、とてもしんどいことです。みなさんが日常の対話で聞いた「苦悩」「悲哀」「怒り」、世代を超えた人々の声なき声を、安心社会をつくる「制度」や「政策」にできるよう、積極的に発信してほしい。
〈青年世代〉
今、私たちの周りには政治への不信感や絶望感が漂っていると感じています。公明党には、もう一度、結党の原点に立ち返り、政治への信頼を取り戻すべく、生まれ変わった決意で頑張ってほしい。私たちもまた、社会を変える主体者として、だれもが安心して生きられる社会をつくれるよう、あらゆる方々の声に耳を傾けながら、政治に届けていきたいと思っています。
〈井手教授〉
現代は「生命に内在する力」を自覚しないから、「生命そのものの主体性がなくなっている」と池田会長が嘆かれた意味がよく分かりました。政治や制度による変革と、目の前の一人から広がる激励の波紋――この両軸が大切なのですね。でもあえて言わせてください。みなさんは、草の根の活動で感じた人々の苦悩を、自分たちだけでかかえこんでいないでしょうか。それは、とてもしんどいことです。みなさんが日常の対話で聞いた「苦悩」「悲哀」「怒り」、世代を超えた人々の声なき声を、安心社会をつくる「制度」や「政策」にできるよう、積極的に発信してほしい。
〈青年世代〉
今、私たちの周りには政治への不信感や絶望感が漂っていると感じています。公明党には、もう一度、結党の原点に立ち返り、政治への信頼を取り戻すべく、生まれ変わった決意で頑張ってほしい。私たちもまた、社会を変える主体者として、だれもが安心して生きられる社会をつくれるよう、あらゆる方々の声に耳を傾けながら、政治に届けていきたいと思っています。
注=阿闍世王は、釈尊在世から滅後にかけてのインドのマガダ国の王。提婆達多にそそのかされ、父を幽閉して死亡させて自らが王位につき、釈尊に敵対した。後に父を殺した罪に悩み、全身に悪いできものができた際、勧めによって釈尊のもとに赴き、その説法を信受して癒えたという。池田先生はつづっている。「釈尊は、入滅する時に阿闍世王のことを大変に心配していた。もちろん、仏が一切衆生を思う気持ちは平等であり、差別があるわけではない。しかし、例えて言えば、親の愛情も、すべての子どもたちに平等に注がれていても、とりわけ病気の子をいっそう心配するものです。同じように、仏もまた、悪道に堕ちようとしている衆生が心配で仕方がない、ということが示されています」(『希望の経典「御書」に学ぶ』第2巻 妙一尼御前御消息から)
注=阿闍世王は、釈尊在世から滅後にかけてのインドのマガダ国の王。提婆達多にそそのかされ、父を幽閉して死亡させて自らが王位につき、釈尊に敵対した。後に父を殺した罪に悩み、全身に悪いできものができた際、勧めによって釈尊のもとに赴き、その説法を信受して癒えたという。池田先生はつづっている。「釈尊は、入滅する時に阿闍世王のことを大変に心配していた。もちろん、仏が一切衆生を思う気持ちは平等であり、差別があるわけではない。しかし、例えて言えば、親の愛情も、すべての子どもたちに平等に注がれていても、とりわけ病気の子をいっそう心配するものです。同じように、仏もまた、悪道に堕ちようとしている衆生が心配で仕方がない、ということが示されています」(『希望の経典「御書」に学ぶ』第2巻 妙一尼御前御消息から)
感想・ご意見はこちらから
テーマ①の記事はこちらから
感想・ご意見はこちらから
テーマ①の記事はこちらから