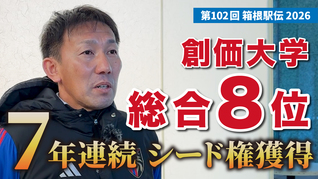〈インタビュー〉 「まち」全体で家族になる「希望のまち」をつくる 認定NPO法人抱樸理事長 奥田知志さん(「第三文明」11月号から)
〈インタビュー〉 「まち」全体で家族になる「希望のまち」をつくる 認定NPO法人抱樸理事長 奥田知志さん(「第三文明」11月号から)
2025年11月10日

おくだ・ともし 1963年、滋賀県生まれ。14歳でキリスト教徒に。関西学院大学神学部に入学後、ホームレスや困窮者の支援に携わるようになる。西南学院大学神学部専攻科卒業。九州大学大学院博士後期課程単位取得退学。90年、日本バプテスト連盟東八幡キリスト教会牧師として赴任。ホームレス支援全国ネットワーク理事長。共生地域創造財団代表理事。全国居住支援法人協議会共同代表。著書に『わたしがいる あなたがいる なんとかなる「希望のまち」のつくりかた』(西日本新聞社)など多数
おくだ・ともし 1963年、滋賀県生まれ。14歳でキリスト教徒に。関西学院大学神学部に入学後、ホームレスや困窮者の支援に携わるようになる。西南学院大学神学部専攻科卒業。九州大学大学院博士後期課程単位取得退学。90年、日本バプテスト連盟東八幡キリスト教会牧師として赴任。ホームレス支援全国ネットワーク理事長。共生地域創造財団代表理事。全国居住支援法人協議会共同代表。著書に『わたしがいる あなたがいる なんとかなる「希望のまち」のつくりかた』(西日本新聞社)など多数
37年間ホームレス支援に当たってきた奥田知志さんが、北九州市に「希望のまち」をつくる。その未来像を聞いた。
37年間ホームレス支援に当たってきた奥田知志さんが、北九州市に「希望のまち」をつくる。その未来像を聞いた。
変わりゆく家族のかたち
変わりゆく家族のかたち
戦後の日本社会では、家族が福祉や経済を支える基礎単位として機能してきました。ゆえに、困窮や育児・介護など生活に問題が生じ、本来なら共助・公助が求められる場面でも、「それは家族でなんとかすべき」と、解決を家族に委ねてきたのです。
ところが近年、家族のかたちが変容しています。祖父母・両親・子どもという「3世代同居」から、夫婦と子どもの「核家族」が主流となってきましたが、昨今はその核家族すら減少し、「一人暮らし」世帯が急増しています。
2020年の国勢調査によれば、単身世帯が全世帯の38・1%に達し、夫婦と子の世帯は25・1%、3世代等の世帯は7・7%に減少しました。これが2050年には単身世帯が全世帯の44・3%に達し、特に65歳以上の男性単身者の約6割が生涯未婚で高齢期を迎えると予測されています。つまり、多くの人が身内の支えを持たずに、老後を迎えざるを得ない時代が目前に迫っているのです。
戦後の日本社会では、家族が福祉や経済を支える基礎単位として機能してきました。ゆえに、困窮や育児・介護など生活に問題が生じ、本来なら共助・公助が求められる場面でも、「それは家族でなんとかすべき」と、解決を家族に委ねてきたのです。
ところが近年、家族のかたちが変容しています。祖父母・両親・子どもという「3世代同居」から、夫婦と子どもの「核家族」が主流となってきましたが、昨今はその核家族すら減少し、「一人暮らし」世帯が急増しています。
2020年の国勢調査によれば、単身世帯が全世帯の38・1%に達し、夫婦と子の世帯は25・1%、3世代等の世帯は7・7%に減少しました。これが2050年には単身世帯が全世帯の44・3%に達し、特に65歳以上の男性単身者の約6割が生涯未婚で高齢期を迎えると予測されています。つまり、多くの人が身内の支えを持たずに、老後を迎えざるを得ない時代が目前に迫っているのです。
社会の側から「家族機能」を補う
社会の側から「家族機能」を補う
私は1988年に北九州市でホームレスを訪ねて夜の町を歩き始めて以来、ホームレスの自立支援や生活困窮者の伴走型支援に取り組んできました。その過程で家族がいない人や、家族はいるものの支えが得られない人など、しんどい状況にある人々の現実に向き合い、社会の側から「家族機能」を補うことができないか模索してきました。
改めて「家族とは何か」を問い直してみると、例えば「子どもに弁当を作る」のが親の役割なら、親の代わりに弁当を作ってくれる人は、その子にとって「親代わり」と言えるのではないでしょうか。同様に「お葬式を出す」のが家族の務めだというなら、葬儀を執り行う人は、社会的な「家族」と呼べるはずです。
そこで私たち「抱樸」は、家族だけに任されすぎていた役割を、社会全体で分かち合う仕組みづくりを進めてきました。例えば、月額500円で誰でも入会可能な「地域互助会」の取り組みでは、バス旅行や誕生日会といった行事やカラオケ・卓球などのサロン、スタッフによる見守り活動などを行っています。最大の特色は希望者への「互助会葬」の実施で、互助会の仲間たちで葬儀や偲ぶ会を行います。この互助会葬には副次的な効果があり、不動産オーナーが高齢単身者の孤独死を恐れて、入居を拒否することがなくなりました。
私は1988年に北九州市でホームレスを訪ねて夜の町を歩き始めて以来、ホームレスの自立支援や生活困窮者の伴走型支援に取り組んできました。その過程で家族がいない人や、家族はいるものの支えが得られない人など、しんどい状況にある人々の現実に向き合い、社会の側から「家族機能」を補うことができないか模索してきました。
改めて「家族とは何か」を問い直してみると、例えば「子どもに弁当を作る」のが親の役割なら、親の代わりに弁当を作ってくれる人は、その子にとって「親代わり」と言えるのではないでしょうか。同様に「お葬式を出す」のが家族の務めだというなら、葬儀を執り行う人は、社会的な「家族」と呼べるはずです。
そこで私たち「抱樸」は、家族だけに任されすぎていた役割を、社会全体で分かち合う仕組みづくりを進めてきました。例えば、月額500円で誰でも入会可能な「地域互助会」の取り組みでは、バス旅行や誕生日会といった行事やカラオケ・卓球などのサロン、スタッフによる見守り活動などを行っています。最大の特色は希望者への「互助会葬」の実施で、互助会の仲間たちで葬儀や偲ぶ会を行います。この互助会葬には副次的な効果があり、不動産オーナーが高齢単身者の孤独死を恐れて、入居を拒否することがなくなりました。
その上で私たちが家族の機能として大切にしているのは、「気づき」と「つなぎ」です。活動を通して家族のような信頼関係を築くことで、小さな日常の変化にも気づき、事態が深刻化する前に行政や福祉機関につなぐことができる。今後も、この「気づき」と「つなぎ」を大切に、地域社会の活性化に率先していきます。
そして、私たちの活動の集大成ともいうべき「希望のまち」(北九州市小倉北区)が来年完成予定です。「希望のまち」は、従来の福祉施設と地域社会の垣根を取り払うべく、1階は地域に開かれた公共空間、2階・3階は全室個室の救護施設として生活困窮者が入居します。例えば、地域の方々が1階のレストランで購入した料理を2階の中庭へ持っていき、入居者らと共に食事をしたり、大浴場を開放して近隣の単身高齢者や子育て世帯も利用したりできるようにする予定です。こうすることで地域に暮らす多様な人々が、世代や環境を超えて日常的に交流できるようにしたいと考えています。
この「希望のまち」には、先述した抱樸が目指す「家族機能の社会化」の他に、2つの目的があります。1つは「助けてと言える」です。現在、子どもたちの自殺が大きな社会課題になっていますが、私は子どもたちが「助けて」と言えなくなった理由の1つに、大人たちが過剰な「自己責任」の風潮にさらされ、「助けてと言わない(言えない)」ことがあると考えています。
その上で私たちが家族の機能として大切にしているのは、「気づき」と「つなぎ」です。活動を通して家族のような信頼関係を築くことで、小さな日常の変化にも気づき、事態が深刻化する前に行政や福祉機関につなぐことができる。今後も、この「気づき」と「つなぎ」を大切に、地域社会の活性化に率先していきます。
そして、私たちの活動の集大成ともいうべき「希望のまち」(北九州市小倉北区)が来年完成予定です。「希望のまち」は、従来の福祉施設と地域社会の垣根を取り払うべく、1階は地域に開かれた公共空間、2階・3階は全室個室の救護施設として生活困窮者が入居します。例えば、地域の方々が1階のレストランで購入した料理を2階の中庭へ持っていき、入居者らと共に食事をしたり、大浴場を開放して近隣の単身高齢者や子育て世帯も利用したりできるようにする予定です。こうすることで地域に暮らす多様な人々が、世代や環境を超えて日常的に交流できるようにしたいと考えています。
この「希望のまち」には、先述した抱樸が目指す「家族機能の社会化」の他に、2つの目的があります。1つは「助けてと言える」です。現在、子どもたちの自殺が大きな社会課題になっていますが、私は子どもたちが「助けて」と言えなくなった理由の1つに、大人たちが過剰な「自己責任」の風潮にさらされ、「助けてと言わない(言えない)」ことがあると考えています。
そのため「希望のまち」では、「助けて!」をまちのキーワードに設定しました。自然に助けてと言い合えることで、他人に助けてと言える安心感、自分が助けてと言われる自己有用感を高めたいと考えています。
もう1つの目的が、「まち」が子どもを育てるという「相続の社会化」です。現在、日本の子どもの相対的貧困率は11・5%(9人に1人)といわれています。そうした中で抱樸では、学校にも行けない、子ども食堂にも来ない子どもの自宅を訪問し、学習支援などを行う「子ども・家族まるごと支援」を推進してきました。
その中で分かったのは、こうした家庭の親御さん自身も、似たような環境で育っていたという事実です。勉強を教えてもらった、お弁当を作ってもらった、どこかに連れて行ってもらった――こうした経験をした人は、次の世代にも引き継げる。これを「社会的相続」といいますが、その相続を当たり前に受けられていない親もいるのです。果たしてこれを「自己責任」の一言で切り捨ててよいのでしょうか。「希望のまち」では、この「社会的相続」をまち全体で担っていきたいと考えています。
そのため「希望のまち」では、「助けて!」をまちのキーワードに設定しました。自然に助けてと言い合えることで、他人に助けてと言える安心感、自分が助けてと言われる自己有用感を高めたいと考えています。
もう1つの目的が、「まち」が子どもを育てるという「相続の社会化」です。現在、日本の子どもの相対的貧困率は11・5%(9人に1人)といわれています。そうした中で抱樸では、学校にも行けない、子ども食堂にも来ない子どもの自宅を訪問し、学習支援などを行う「子ども・家族まるごと支援」を推進してきました。
その中で分かったのは、こうした家庭の親御さん自身も、似たような環境で育っていたという事実です。勉強を教えてもらった、お弁当を作ってもらった、どこかに連れて行ってもらった――こうした経験をした人は、次の世代にも引き継げる。これを「社会的相続」といいますが、その相続を当たり前に受けられていない親もいるのです。果たしてこれを「自己責任」の一言で切り捨ててよいのでしょうか。「希望のまち」では、この「社会的相続」をまち全体で担っていきたいと考えています。
生きること自体に意味がある
生きること自体に意味がある
改めて日本の社会情勢を俯瞰する時、外国人を敵視する排外主義的言説が社会の中で力を持ち始めていることに懸念を抱かざるを得ません。歴史を振り返れば、排外主義は容易に“排内主義”へと転じ、やがてその矛先は障害者や高齢者などに向けられる危険を常にはらんでいます。
しかし、このような主張をする人々を「差別主義者だ」と糾弾するだけでは根本的な解決になりません。主張の背後には、「自分は大切にされていない」「将来どうなるのか」との怒りにも似た不満や不安が積み重なっており、政治がそうした声と真摯に向き合い、未来への希望を提示することが肝要です。ゆえに与野党には互いの立場を乗り越え、戦後からの制度や政策を徹底的に検証し、社会構造のゆがみにメスを入れていく強い覚悟を求めたいと思います。
改めて日本の社会情勢を俯瞰する時、外国人を敵視する排外主義的言説が社会の中で力を持ち始めていることに懸念を抱かざるを得ません。歴史を振り返れば、排外主義は容易に“排内主義”へと転じ、やがてその矛先は障害者や高齢者などに向けられる危険を常にはらんでいます。
しかし、このような主張をする人々を「差別主義者だ」と糾弾するだけでは根本的な解決になりません。主張の背後には、「自分は大切にされていない」「将来どうなるのか」との怒りにも似た不満や不安が積み重なっており、政治がそうした声と真摯に向き合い、未来への希望を提示することが肝要です。ゆえに与野党には互いの立場を乗り越え、戦後からの制度や政策を徹底的に検証し、社会構造のゆがみにメスを入れていく強い覚悟を求めたいと思います。
私は今夏、『わたしがいる あなたがいる なんとかなる 「希望のまち」のつくりかた』(西日本新聞社)を出版しました。このタイトルには、「私がいて、あなたがいれば必ず希望は生まれる」との私の信念が反映されています。「生きる意味を問う」ことも必要ですが、現代にあってより重要なのは、「生きること自体に意味がある」との価値観を社会に取り戻すこと。まさに、80年前の戦争で痛感した「命」や「人権」の重要性を再確認することが、共生社会の大前提であると私は考えます。
私は今夏、『わたしがいる あなたがいる なんとかなる 「希望のまち」のつくりかた』(西日本新聞社)を出版しました。このタイトルには、「私がいて、あなたがいれば必ず希望は生まれる」との私の信念が反映されています。「生きる意味を問う」ことも必要ですが、現代にあってより重要なのは、「生きること自体に意味がある」との価値観を社会に取り戻すこと。まさに、80年前の戦争で痛感した「命」や「人権」の重要性を再確認することが、共生社会の大前提であると私は考えます。