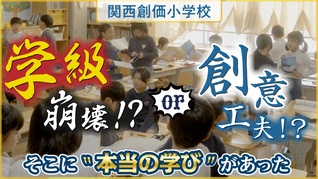〈SDGs×SEIKYO〉 事例編 徳島県・上勝町 ごみのリサイクル率80%を達成
〈SDGs×SEIKYO〉 事例編 徳島県・上勝町 ごみのリサイクル率80%を達成
2025年4月1日
「SDGs×SEIKYO」の新企画「ちーちゃんと訪ねる ミライの現場」では、各地の先駆的なSDGsの取り組みを紹介していきます。第1回は徳島県の上勝町です。同町は、総務省の「ふるさとづくり大賞」(2021年度)で最優秀賞(内閣総理大臣賞)を受賞。内閣府が選定する「SDGs未来都市」にも選出されています。
「SDGs×SEIKYO」の新企画「ちーちゃんと訪ねる ミライの現場」では、各地の先駆的なSDGsの取り組みを紹介していきます。第1回は徳島県の上勝町です。同町は、総務省の「ふるさとづくり大賞」(2021年度)で最優秀賞(内閣総理大臣賞)を受賞。内閣府が選定する「SDGs未来都市」にも選出されています。
母さんから聞いたんだけど、ごみをゼロにしようとしている町があるって本当なの?
母さんから聞いたんだけど、ごみをゼロにしようとしている町があるって本当なの?
本当じゃ。徳島県の上勝町では、町民や企業などが協力してリサイクル率80%を達成し、国内外から注目を浴びているんじゃよ。
本当じゃ。徳島県の上勝町では、町民や企業などが協力してリサイクル率80%を達成し、国内外から注目を浴びているんじゃよ。
すごい! どうしてそんなにリサイクルが進んでいるの?
すごい! どうしてそんなにリサイクルが進んでいるの?
町や住民らが協力して、次代のために、おいしい水やきれいな空気、豊かな大地を残そうと努力しているからじゃ。それでは、一緒に上勝町の取り組みを見ていこう!
町や住民らが協力して、次代のために、おいしい水やきれいな空気、豊かな大地を残そうと努力しているからじゃ。それでは、一緒に上勝町の取り組みを見ていこう!
分別への道のり
分別への道のり
上勝町には、ごみ収集車が1台も走っていない。
町民が自ら、自家用車で町内唯一の「ゴミステーション」にごみを持ち込むのだ(車の運転が困難な人は、運搬支援の登録を行えば、無料で回収してくれる)。
ステーション内にある分別エリア。ここで町民は指定された分別に従って、ごみを仕分ける。
たとえば、金属類はスチール缶、スプレー缶、アルミ缶、雑金属の4種類に細かく分けられている。どこに仕分ければよいのか分からない物は、ステーションのスタッフに聞けば案内してくれる。
上勝町には、ごみ収集車が1台も走っていない。
町民が自ら、自家用車で町内唯一の「ゴミステーション」にごみを持ち込むのだ(車の運転が困難な人は、運搬支援の登録を行えば、無料で回収してくれる)。
ステーション内にある分別エリア。ここで町民は指定された分別に従って、ごみを仕分ける。
たとえば、金属類はスチール缶、スプレー缶、アルミ缶、雑金属の4種類に細かく分けられている。どこに仕分ければよいのか分からない物は、ステーションのスタッフに聞けば案内してくれる。

徳島県上勝町のゴミステーション。町民は、持ち込んだごみを自分で分別する ©上勝町
徳島県上勝町のゴミステーション。町民は、持ち込んだごみを自分で分別する ©上勝町
「自分は使わないが、まだ使える“もったいない物”」は、ゴミステーションに併設されている「くるくるショップ」に持ち込むと、ショップ内に展示され、誰でも無料で持ち帰ることができる。
そして生ごみは自家処理。各家庭に設置されたコンポストや電動生ごみ処理機(町の補助がある)で、たい肥化し、自然に返す。
同町での分別は、全部で計13種類43分別に及ぶ。
「自分は使わないが、まだ使える“もったいない物”」は、ゴミステーションに併設されている「くるくるショップ」に持ち込むと、ショップ内に展示され、誰でも無料で持ち帰ることができる。
そして生ごみは自家処理。各家庭に設置されたコンポストや電動生ごみ処理機(町の補助がある)で、たい肥化し、自然に返す。
同町での分別は、全部で計13種類43分別に及ぶ。

不要だが、まだ使える物を持ち込める「くるくるショップ」。欲しい物があれば、誰でも無料で持ち帰ることができる
不要だが、まだ使える物を持ち込める「くるくるショップ」。欲しい物があれば、誰でも無料で持ち帰ることができる
上勝町は、人口約1370人。日本の棚田百選に選ばれた「樫原の棚田」など、“日本の原風景”とうたわれる美観が広がる。
町ではかつて「野焼き」が行われ、車のタイヤなど、何でも燃やしたため、悪臭がひどく、黒い煙が一日中、立ち上っていたという。
やがて法規制などによって、野焼きの継続が困難に。1994年にごみの減量を目指す「リサイクルタウン計画」を策定し、3年後にはゴミステーションを開設。9分別の資源回収を開始した。
町は2基の小型焼却炉を導入したが、そのうち1基が環境基準を満たせなくなり、もう1基は使用できたが、当時の町長は、可燃ごみを減らし、分別をさらに増やすことを決断。2000年12月、焼却炉は閉鎖され、01年4月からは35種類の分別が始まった。
上勝町は、人口約1370人。日本の棚田百選に選ばれた「樫原の棚田」など、“日本の原風景”とうたわれる美観が広がる。
町ではかつて「野焼き」が行われ、車のタイヤなど、何でも燃やしたため、悪臭がひどく、黒い煙が一日中、立ち上っていたという。
やがて法規制などによって、野焼きの継続が困難に。1994年にごみの減量を目指す「リサイクルタウン計画」を策定し、3年後にはゴミステーションを開設。9分別の資源回収を開始した。
町は2基の小型焼却炉を導入したが、そのうち1基が環境基準を満たせなくなり、もう1基は使用できたが、当時の町長は、可燃ごみを減らし、分別をさらに増やすことを決断。2000年12月、焼却炉は閉鎖され、01年4月からは35種類の分別が始まった。

上勝町内を流れる清流・勝浦川
上勝町内を流れる清流・勝浦川
無駄をなくす取り組み
無駄をなくす取り組み
03年、同町が多分別を推進していることを聞き、アメリカの化学者で、世界の「ゼロ・ウェイスト(ごみゼロ)」運動に尽力してきたポール・コネット博士が来訪した。博士は講演で「無駄や浪費を限りなくゼロにする」という「ゼロ・ウェイスト」の理念を町民に紹介し、大きな反響を呼ぶ。
博士の勧めを受けた上勝町議会は同年9月、日本の自治体として初となる「ゼロ・ウェイスト」宣言を、満場一致で可決した。同宣言では、ごみの再利用・再資源化を進め、2020年までに焼却・埋め立て処分をなくす最善の努力をすることが記された。
本格的にごみゼロを進めるに当たって、町民の理解と協力は不可欠である。
03年、同町が多分別を推進していることを聞き、アメリカの化学者で、世界の「ゼロ・ウェイスト(ごみゼロ)」運動に尽力してきたポール・コネット博士が来訪した。博士は講演で「無駄や浪費を限りなくゼロにする」という「ゼロ・ウェイスト」の理念を町民に紹介し、大きな反響を呼ぶ。
博士の勧めを受けた上勝町議会は同年9月、日本の自治体として初となる「ゼロ・ウェイスト」宣言を、満場一致で可決した。同宣言では、ごみの再利用・再資源化を進め、2020年までに焼却・埋め立て処分をなくす最善の努力をすることが記された。
本格的にごみゼロを進めるに当たって、町民の理解と協力は不可欠である。

上勝町内の家庭で、町民がゴミを分別する。自宅では大別しておき、ゴミステーションで細かく分別する
上勝町内の家庭で、町民がゴミを分別する。自宅では大別しておき、ゴミステーションで細かく分別する
同町の山田稔さん宅を訪ねると、納屋にはごみを10種類ほどに分別するための箱や袋が設置されており、畑の横にコンポストが置かれていた。
山田さんは「面倒くさいことも、もちろんありますが、慣れれば苦になりません。何より、無駄な買い物がなくなり、捨てる物が減りました。ごみゼロの手助けになっていればうれしい」と。
同町の山田稔さん宅を訪ねると、納屋にはごみを10種類ほどに分別するための箱や袋が設置されており、畑の横にコンポストが置かれていた。
山田さんは「面倒くさいことも、もちろんありますが、慣れれば苦になりません。何より、無駄な買い物がなくなり、捨てる物が減りました。ごみゼロの手助けになっていればうれしい」と。

上勝町ゼロ・ウェイストセンター。「?」の形状には、“なぜそれを買うのか”など、自分の暮らしを見つめ直してほしいとの意味が込められている ©上勝町
上勝町ゼロ・ウェイストセンター。「?」の形状には、“なぜそれを買うのか”など、自分の暮らしを見つめ直してほしいとの意味が込められている ©上勝町
「ゼロ・ウェイスト」を推進する上勝町企画環境課の菅翠さんは、次のように語る。
「ゴミステーションで実際に作業をする現場のスタッフと、住民との良好な関係が、何より大切だと思っています。その上で、ただ単に協力してもらうだけでなく、負担感を軽減し、楽しみながら推進してもらえるよう、ポイントサービスを導入しています」
同町で実施している「ちりつもポイントサービス」は、資源として売却できる紙パックなどの分別に協力した住民に、ポイントを付与。ポイントが貯まると、環境に配慮した商品等と交換できる。これらの商品は、町民が分別した資源の売上金で賄われている。
「ゼロ・ウェイスト」を推進する上勝町企画環境課の菅翠さんは、次のように語る。
「ゴミステーションで実際に作業をする現場のスタッフと、住民との良好な関係が、何より大切だと思っています。その上で、ただ単に協力してもらうだけでなく、負担感を軽減し、楽しみながら推進してもらえるよう、ポイントサービスを導入しています」
同町で実施している「ちりつもポイントサービス」は、資源として売却できる紙パックなどの分別に協力した住民に、ポイントを付与。ポイントが貯まると、環境に配慮した商品等と交換できる。これらの商品は、町民が分別した資源の売上金で賄われている。

「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」は、地産地消と廃品活用をテーマに建設され、町内のスギやヒノキが使用されている。
「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」は、地産地消と廃品活用をテーマに建設され、町内のスギやヒノキが使用されている。
住民や町の職員らの協力と努力によって、リサイクル率の全国平均が約20%の中、同町では16年に初めて80%を達成することができた。
当初の目標だった20年には、「ゼロ・ウェイスト」の理念を国内外に発信する拠点「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」が完成。ゴミステーションとともに、町の分別を体験できる宿泊施設や、シェアオフィスなども併設され、学びと交流の場となっている。
住民や町の職員らの協力と努力によって、リサイクル率の全国平均が約20%の中、同町では16年に初めて80%を達成することができた。
当初の目標だった20年には、「ゼロ・ウェイスト」の理念を国内外に発信する拠点「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」が完成。ゴミステーションとともに、町の分別を体験できる宿泊施設や、シェアオフィスなども併設され、学びと交流の場となっている。

「ゼロ・ウェイスト」を体験できる宿泊施設
「ゼロ・ウェイスト」を体験できる宿泊施設
持続可能な地域社会を
持続可能な地域社会を
「上勝町地域創生総合戦略」では、町のブランドとして確立された「ゼロ・ウェイスト」を、持続可能で暮らしやすい地域社会の実現を目指すための三つの戦略の一つと位置付けている。
町は今、少子高齢化、人口減少により、さまざまな基盤の維持が困難になってきている。その中で「ゼロ・ウェイスト」のブランドを高め、その魅力を発信することで、交流人口の増加など、地域活性化に結びつけることも期待されている。
「上勝町地域創生総合戦略」では、町のブランドとして確立された「ゼロ・ウェイスト」を、持続可能で暮らしやすい地域社会の実現を目指すための三つの戦略の一つと位置付けている。
町は今、少子高齢化、人口減少により、さまざまな基盤の維持が困難になってきている。その中で「ゼロ・ウェイスト」のブランドを高め、その魅力を発信することで、交流人口の増加など、地域活性化に結びつけることも期待されている。

不要になった布や綿をリメークして販売する「くるくる工房」
不要になった布や綿をリメークして販売する「くるくる工房」
次なる目標は2030年。20年に発表した“新ゼロ・ウェイスト宣言”では、環境教育や人材育成を重点目標として、未来を担う子どもたちを育むことなどが盛り込まれている。
次なる目標は2030年。20年に発表した“新ゼロ・ウェイスト宣言”では、環境教育や人材育成を重点目標として、未来を担う子どもたちを育むことなどが盛り込まれている。

「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」の窓には、町民から寄せられた建具が使用されている
「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」の窓には、町民から寄せられた建具が使用されている
花本靖町長は、「現在、『ゼロ・ウェイスト』の取り組みに共感し、協力を申し出てくれる企業が増加しています。東京の大手不動産開発企業では、施設から出る生ごみを液肥化し、その液肥で育てた農作物を社員食堂で提供する取り組みが進んでいます。仲間が増える分だけ、ごみを減らす取り組みも広がります。21世紀を、絶対に“環境の世紀”にしていかなければなりません」と強調する。
「小さな町の大きな挑戦」は、これからも国内外に、大きなインパクトを与えながら、持続可能な地域社会のモデルケースであり続けるにちがいない。
花本靖町長は、「現在、『ゼロ・ウェイスト』の取り組みに共感し、協力を申し出てくれる企業が増加しています。東京の大手不動産開発企業では、施設から出る生ごみを液肥化し、その液肥で育てた農作物を社員食堂で提供する取り組みが進んでいます。仲間が増える分だけ、ごみを減らす取り組みも広がります。21世紀を、絶対に“環境の世紀”にしていかなければなりません」と強調する。
「小さな町の大きな挑戦」は、これからも国内外に、大きなインパクトを与えながら、持続可能な地域社会のモデルケースであり続けるにちがいない。
この取り組みに関わるSDGsの主な目標
この取り組みに関わるSDGsの主な目標
ご感想をお寄せください
sdgs@seikyo-np.jp
ご感想をお寄せください
sdgs@seikyo-np.jp
聖教電子版の「SDGs」特集ページが閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html
聖教電子版の「SDGs」特集ページが閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html