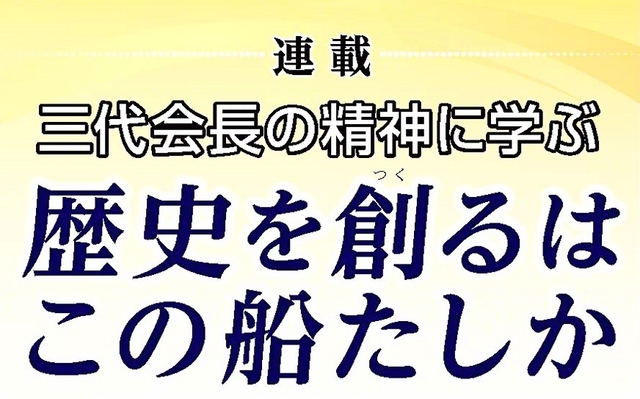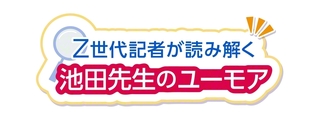D2E348C106B0310D02723ACF3E5FAC83
〈連載 三代会長の精神に学ぶ〉第41回 池田先生「第1回SGI世界青年部総会」でのスピーチ㊤
〈連載 三代会長の精神に学ぶ〉第41回 池田先生「第1回SGI世界青年部総会」でのスピーチ㊤
2025年9月1日
- 《歴史を創るは この船たしか》
- 東京オリンピックの最中に東欧を初訪問
- 仏法は人類全体の幸福のために存在
- 《歴史を創るは この船たしか》
- 東京オリンピックの最中に東欧を初訪問
- 仏法は人類全体の幸福のために存在
池田先生 「第1回SGI世界青年部総会」でのスピーチ (1992年9月)
仏とは、最高の「人間」である。決して「人間」以上の存在なのではない。(中略)
大聖人は、弘安元年(一二七八年)、身延の山で、「今年は異常に寒い」とおっしゃり、土地の古老たちにたずねてみたら、八十、九十、百歳になる老人も「昔から、これほど寒かったことはありません」と言っていたと書かれている。
山の中の庶民と、何のへだてもなく「寒いね」「こんなことは、いまだかつてありません」と、和やかに語らっておられる。これが御本仏の世界なのである。(中略)
釈尊も、旅から旅への布教の人生の最後に、ある村(ベールヴァ村)で病気になり、侍者の阿難に、私の体は、もうボロボロなんだよ、と告げている。ありのままの人間の姿であり、行動であった。
仏というと、何か特別の金ピカに光る絶対者のようなイメージが広められているが、それは後世の人が、仏の偉大さを強調するなかで、つくられていった表現であり、一つの象徴といえよう。
◇
経典では、現代では旧ソ連の一部が含まれるとも考えられる北方の地域(鬱単越。古代インドの世界観で須弥山を中心とした四大洲のうち北方の世界)は、仏法には縁がないとされていた。
しかし、私は確信していた。――大聖人の仏法は、全世界、全宇宙の大法である。大聖人の大慈悲は、全世界の民衆へ、もれなく向けられているはずだ、と。
ゆえに、私は、大聖人の弟子として初めて、ソ連に行った。(中略)
ソ連にも人間がいる。人間がいるかぎり、私は行く。民衆がいるところ、すべて私の法戦の舞台だ、と。ゆえに、まず第一歩を踏み出した。そして信義を貫いた――。
あれから十八年。今や、ロシアをはじめ旧ソ連にも、仏法への理解と共感は大きく広がった。(中略)
どうか決してあせることなく、朗らかに皆をリードし、楽しく進んでいっていただきたい。末法は万年である。悠々と進んでいきましょう!
(『池田大作全集』第81巻)
池田先生 「第1回SGI世界青年部総会」でのスピーチ (1992年9月)
仏とは、最高の「人間」である。決して「人間」以上の存在なのではない。(中略)
大聖人は、弘安元年(一二七八年)、身延の山で、「今年は異常に寒い」とおっしゃり、土地の古老たちにたずねてみたら、八十、九十、百歳になる老人も「昔から、これほど寒かったことはありません」と言っていたと書かれている。
山の中の庶民と、何のへだてもなく「寒いね」「こんなことは、いまだかつてありません」と、和やかに語らっておられる。これが御本仏の世界なのである。(中略)
釈尊も、旅から旅への布教の人生の最後に、ある村(ベールヴァ村)で病気になり、侍者の阿難に、私の体は、もうボロボロなんだよ、と告げている。ありのままの人間の姿であり、行動であった。
仏というと、何か特別の金ピカに光る絶対者のようなイメージが広められているが、それは後世の人が、仏の偉大さを強調するなかで、つくられていった表現であり、一つの象徴といえよう。
◇
経典では、現代では旧ソ連の一部が含まれるとも考えられる北方の地域(鬱単越。古代インドの世界観で須弥山を中心とした四大洲のうち北方の世界)は、仏法には縁がないとされていた。
しかし、私は確信していた。――大聖人の仏法は、全世界、全宇宙の大法である。大聖人の大慈悲は、全世界の民衆へ、もれなく向けられているはずだ、と。
ゆえに、私は、大聖人の弟子として初めて、ソ連に行った。(中略)
ソ連にも人間がいる。人間がいるかぎり、私は行く。民衆がいるところ、すべて私の法戦の舞台だ、と。ゆえに、まず第一歩を踏み出した。そして信義を貫いた――。
あれから十八年。今や、ロシアをはじめ旧ソ連にも、仏法への理解と共感は大きく広がった。(中略)
どうか決してあせることなく、朗らかに皆をリードし、楽しく進んでいっていただきたい。末法は万年である。悠々と進んでいきましょう!
(『池田大作全集』第81巻)

1992年6月8日、欧州と中東5カ国の歴訪のため、まずドイツに赴いた池田先生は、フランクフルトの空港を出て宿舎に到着するやいなや、SGIのメンバーと記念撮影を。友の労苦をねぎらうとともに、未来を担う子どもたちに声をかけた(フランクフルト市郊外で)。その4日後の6月12日、ハンガリーやチェコスロバキアなど13カ国の同志が集い、「中欧・東欧・ロシア合同会議」がフランクフルト市内で開催された
1992年6月8日、欧州と中東5カ国の歴訪のため、まずドイツに赴いた池田先生は、フランクフルトの空港を出て宿舎に到着するやいなや、SGIのメンバーと記念撮影を。友の労苦をねぎらうとともに、未来を担う子どもたちに声をかけた(フランクフルト市郊外で)。その4日後の6月12日、ハンガリーやチェコスロバキアなど13カ国の同志が集い、「中欧・東欧・ロシア合同会議」がフランクフルト市内で開催された
冷戦の終結に伴い、世界の多くの国が分断を乗り越えるための道を模索し始め、人権や民主を求める意識が高まっていた、1990年代の初頭――。
宗教においても、“世界に開かれた宗教”の要件や、“民衆のための宗教”のあり方が問われる時代に入っていた。
その中で創価学会が、日蓮大聖人の仏法を信奉する民衆信徒の団体として、1992年から開始したのが「創価ルネサンス」の運動である。
当時、大聖人の精神に違背し腐敗堕落していた日蓮正宗が、宗門の体質改善を求める学会の要望を無視するだけにとどまらず、長年にわたって宗門の外護を続けてきた学会の壊滅を画策するという「第2次宗門事件」が惹起していた。
しかし学会は微動だにせず、陰湿で非道な策謀を打ち破っていった。出家者の権威で信徒を問答無用で支配しようとする宗門と決別し、仏法の人間主義に基づく「創価ルネサンス」の運動を力強く進めていったのだ。
池田先生は1992年5月に行ったスピーチで、「創価ルネサンス」の運動に込めた思いについてこう語った。
「末法において、民衆を救い、世界に正法を弘め、広宣流布していく――その仏とは、日蓮大聖人であり、大聖人直結の『民衆』自身である。
『民衆こそ仏』なのである。大聖人の仏法を口にしながら、その本義と正反対の『民衆抑圧』を繰り返す人間には、大聖人の仏法の根本がわからない」
「一宗一派ではない。世界を視野に、全人類をつつみゆくのが、大聖人の一閻浮提の仏法である。いわば『地球仏法』『人類仏法』――その真価を発揮すべき時代である」と。
そして翌6月、池田先生は、冷戦による分断に長年苦しめられてきたヨーロッパの国々に足を運んだ。1991年の訪問に続く、14回目の渡欧である。
訪問中、仏法の歴史を画するSGIの会合が、ドイツのフランクフルトで開催された。
ロシアをはじめ、ハンガリー、チェコスロバキア(当時)、ポーランド、ブルガリアの旧東側諸国の同志と共に、ドイツ、オーストリア、イギリス、フランス、スペインなど13カ国の友が、一堂に会した「中欧・東欧・ロシア合同会議」である。
冷戦の終結に伴い、世界の多くの国が分断を乗り越えるための道を模索し始め、人権や民主を求める意識が高まっていた、1990年代の初頭――。
宗教においても、“世界に開かれた宗教”の要件や、“民衆のための宗教”のあり方が問われる時代に入っていた。
その中で創価学会が、日蓮大聖人の仏法を信奉する民衆信徒の団体として、1992年から開始したのが「創価ルネサンス」の運動である。
当時、大聖人の精神に違背し腐敗堕落していた日蓮正宗が、宗門の体質改善を求める学会の要望を無視するだけにとどまらず、長年にわたって宗門の外護を続けてきた学会の壊滅を画策するという「第2次宗門事件」が惹起していた。
しかし学会は微動だにせず、陰湿で非道な策謀を打ち破っていった。出家者の権威で信徒を問答無用で支配しようとする宗門と決別し、仏法の人間主義に基づく「創価ルネサンス」の運動を力強く進めていったのだ。
池田先生は1992年5月に行ったスピーチで、「創価ルネサンス」の運動に込めた思いについてこう語った。
「末法において、民衆を救い、世界に正法を弘め、広宣流布していく――その仏とは、日蓮大聖人であり、大聖人直結の『民衆』自身である。
『民衆こそ仏』なのである。大聖人の仏法を口にしながら、その本義と正反対の『民衆抑圧』を繰り返す人間には、大聖人の仏法の根本がわからない」
「一宗一派ではない。世界を視野に、全人類をつつみゆくのが、大聖人の一閻浮提の仏法である。いわば『地球仏法』『人類仏法』――その真価を発揮すべき時代である」と。
そして翌6月、池田先生は、冷戦による分断に長年苦しめられてきたヨーロッパの国々に足を運んだ。1991年の訪問に続く、14回目の渡欧である。
訪問中、仏法の歴史を画するSGIの会合が、ドイツのフランクフルトで開催された。
ロシアをはじめ、ハンガリー、チェコスロバキア(当時)、ポーランド、ブルガリアの旧東側諸国の同志と共に、ドイツ、オーストリア、イギリス、フランス、スペインなど13カ国の友が、一堂に会した「中欧・東欧・ロシア合同会議」である。

“同志を喜ばせてあげたい”との思いで、ドラムをたたく和服姿の戸田先生。池田先生も師に続いてリズムをとった(1956年5月、静岡の富士宮市内で)
“同志を喜ばせてあげたい”との思いで、ドラムをたたく和服姿の戸田先生。池田先生も師に続いてリズムをとった(1956年5月、静岡の富士宮市内で)
この歴史的な会合において、池田先生はしみじみと語った。
「今回の出発の日の前夜、夢を見た。戸田先生の夢であった。先生は和服を着て立っておられた。
私は、先生の体を支えながら、申し上げた。
『先生、これから先生の思想・理念を、世界に広めに行ってまいります』
戸田先生は『私は、うれしい』『本当にうれしい』と、泣いておられた」
「本日のこの会合を、いちばん喜んでくださっているのも、戸田先生であると私は信ずる。戸田先生は、当時、東欧・ロシアの民衆のことを、深く深く思いやられていたからである。
とくに、一九五六年の“ハンガリー動乱”の折には、先生は民衆の嘆きに、それはそれは心を痛めておられた」と。
戸田先生は当時、民衆の嘆きに同苦してこう述べていた。
「民族と民族が争うべきが必然のすがたであり、当然のことであると考えて、この現実のすがたを、そのまま認めるのが正しい考え方であろうか」
「こういう悲惨な社会事情に憤激を感じないとするならば、これまた、あまりにも無関心な態度ではないかと思う」
「吾人らが仏法哲学を弘めて、真実の平和、民衆の救済を叫ぶゆえんは、先哲の平和欲求の精神をどこまでも実現せんがためである」
池田先生は、この師の思いを身に帯びて、1964年10月にハンガリーを初訪問した。
時あたかも、東京オリンピックが開幕し、学会本部がある信濃町の近くの国立競技場で各国の選手が繰り広げる熱戦に、世界の目が向けられていた。
その最中にあって、池田先生は、東西冷戦による分断で交流が途絶えていた共産圏の国々に初めて足を踏み入れたのだ。
ハンガリーに行く前に訪れたチェコスロバキアで、空港からホテルに車で向かう時も、池田先生は寸暇を惜しんで、通訳を介して運転手に話しかけた。
家族のことを聞くと、和やかに会話が続いたが、暮らしのことが話題になると運転手は「苦しいね……」と言ったきり、口を閉ざしてしまったという。
首都のプラハも重々しい空気に包まれていたが、ホテルでは思わぬ交流の機会があった。
喫茶室のテレビで、オリンピックの開会式を見ていた人たちが、池田先生ら一行を見て日本人だと気付いて、次々と笑顔で握手を求めてきたのだ。
冷戦による“鉄のカーテン”で隔てられた場所であっても、心と心が通い合う瞬間は確かに生まれたのである。
(㊦に続く)
この歴史的な会合において、池田先生はしみじみと語った。
「今回の出発の日の前夜、夢を見た。戸田先生の夢であった。先生は和服を着て立っておられた。
私は、先生の体を支えながら、申し上げた。
『先生、これから先生の思想・理念を、世界に広めに行ってまいります』
戸田先生は『私は、うれしい』『本当にうれしい』と、泣いておられた」
「本日のこの会合を、いちばん喜んでくださっているのも、戸田先生であると私は信ずる。戸田先生は、当時、東欧・ロシアの民衆のことを、深く深く思いやられていたからである。
とくに、一九五六年の“ハンガリー動乱”の折には、先生は民衆の嘆きに、それはそれは心を痛めておられた」と。
戸田先生は当時、民衆の嘆きに同苦してこう述べていた。
「民族と民族が争うべきが必然のすがたであり、当然のことであると考えて、この現実のすがたを、そのまま認めるのが正しい考え方であろうか」
「こういう悲惨な社会事情に憤激を感じないとするならば、これまた、あまりにも無関心な態度ではないかと思う」
「吾人らが仏法哲学を弘めて、真実の平和、民衆の救済を叫ぶゆえんは、先哲の平和欲求の精神をどこまでも実現せんがためである」
池田先生は、この師の思いを身に帯びて、1964年10月にハンガリーを初訪問した。
時あたかも、東京オリンピックが開幕し、学会本部がある信濃町の近くの国立競技場で各国の選手が繰り広げる熱戦に、世界の目が向けられていた。
その最中にあって、池田先生は、東西冷戦による分断で交流が途絶えていた共産圏の国々に初めて足を踏み入れたのだ。
ハンガリーに行く前に訪れたチェコスロバキアで、空港からホテルに車で向かう時も、池田先生は寸暇を惜しんで、通訳を介して運転手に話しかけた。
家族のことを聞くと、和やかに会話が続いたが、暮らしのことが話題になると運転手は「苦しいね……」と言ったきり、口を閉ざしてしまったという。
首都のプラハも重々しい空気に包まれていたが、ホテルでは思わぬ交流の機会があった。
喫茶室のテレビで、オリンピックの開会式を見ていた人たちが、池田先生ら一行を見て日本人だと気付いて、次々と笑顔で握手を求めてきたのだ。
冷戦による“鉄のカーテン”で隔てられた場所であっても、心と心が通い合う瞬間は確かに生まれたのである。
(㊦に続く)
<語句解説>
第2次宗門事件 日蓮正宗の管長だった阿部日顕らによる策謀。1991年11月28日、破門通告書を送付し、創価学会の壊滅を目論んだが失敗に終わった。学会ではこの日を、「魂の独立記念日」として意義づけ、日蓮大聖人の本義に基づく活動を力強く進めてきた。
ハンガリー動乱 1956年10月、民衆デモが起こる中で発足したハンガリーの新政権が、ソ連の影響から抜け出そうとする姿勢をみせたことに対し、ソ連が軍事介入して、多数の民衆が犠牲となった。
鉄のカーテン ソ連などの東側諸国が非共産圏の国々に閉鎖的であることを、比喩を用いて表現した言葉。1946年3月、イギリスのチャーチル首相が演説で述べた。
<語句解説>
第2次宗門事件 日蓮正宗の管長だった阿部日顕らによる策謀。1991年11月28日、破門通告書を送付し、創価学会の壊滅を目論んだが失敗に終わった。学会ではこの日を、「魂の独立記念日」として意義づけ、日蓮大聖人の本義に基づく活動を力強く進めてきた。
ハンガリー動乱 1956年10月、民衆デモが起こる中で発足したハンガリーの新政権が、ソ連の影響から抜け出そうとする姿勢をみせたことに対し、ソ連が軍事介入して、多数の民衆が犠牲となった。
鉄のカーテン ソ連などの東側諸国が非共産圏の国々に閉鎖的であることを、比喩を用いて表現した言葉。1946年3月、イギリスのチャーチル首相が演説で述べた。
※次回(第42回)は9月2日に配信予定
※次回(第42回)は9月2日に配信予定
音声読み上げ