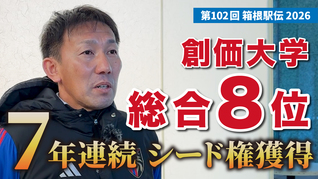あがき続ける。そのプロセスを大事にしたい――NewsPicksパブリッシング創刊編集長 井上慎平さん
あがき続ける。そのプロセスを大事にしたい――NewsPicksパブリッシング創刊編集長 井上慎平さん
2025年7月11日
- 電子版連載〈WITH あなたと〉 #メンタルヘルス
- 電子版連載〈WITH あなたと〉 #メンタルヘルス
担当編集者として、『シン・ニホン』(安宅和人著)など数々のベストセラーを生み出し、NewsPicksパブリッシングの創刊編集長を務めた井上慎平さんは、仕事に没頭する中で双極性障害を発症しました。
その経験から社会における強さと弱さについて問い直しています。(取材=久保田健一、宮本勇介)
担当編集者として、『シン・ニホン』(安宅和人著)など数々のベストセラーを生み出し、NewsPicksパブリッシングの創刊編集長を務めた井上慎平さんは、仕事に没頭する中で双極性障害を発症しました。
その経験から社会における強さと弱さについて問い直しています。(取材=久保田健一、宮本勇介)
■双極性障害と診断されて
■双極性障害と診断されて
――新著『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の弱さ考』(ダイヤモンド社)で、うつ発症時の体験や、復職後の働き方や生き方などをつづられています。若い社会人に向けて、特に伝えておきたいことは何でしょうか?
――新著『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の弱さ考』(ダイヤモンド社)で、うつ発症時の体験や、復職後の働き方や生き方などをつづられています。若い社会人に向けて、特に伝えておきたいことは何でしょうか?
体調を崩して思うのは、「長く働く」という視点を持つことの大切さです。
私は2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksの書籍レーベルを立ち上げて編集長になり、強くて優秀なリーダーであろうと、がむしゃらに働いていました。
でも、無理がたたって、ある日、突然、心身が限界を迎え、全く動けなくなってしまったんです。双極性障害と診断され、当時は人と話すことも、本を読むこともできないほど深刻な状態でした。
休職を経て復職はできたものの、もう以前と同じようには働けなくなりました。NewsPicksを辞めるまでに計4回ほどの休職を経験しました。
その中で尊敬する先輩から「どんなに優秀でも、無理をしていたら40歳までに、心が強い人は体を壊すし、体が強い人はメンタルを崩す」と言われたんですが、正直ピンとこなかったんです。
若い時は、がむしゃらにやるのも正解ですが、健康を損ねないよう意識することもまた大事なんだと、後になってから気付かされました。
体調を崩して思うのは、「長く働く」という視点を持つことの大切さです。
私は2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksの書籍レーベルを立ち上げて編集長になり、強くて優秀なリーダーであろうと、がむしゃらに働いていました。
でも、無理がたたって、ある日、突然、心身が限界を迎え、全く動けなくなってしまったんです。双極性障害と診断され、当時は人と話すことも、本を読むこともできないほど深刻な状態でした。
休職を経て復職はできたものの、もう以前と同じようには働けなくなりました。NewsPicksを辞めるまでに計4回ほどの休職を経験しました。
その中で尊敬する先輩から「どんなに優秀でも、無理をしていたら40歳までに、心が強い人は体を壊すし、体が強い人はメンタルを崩す」と言われたんですが、正直ピンとこなかったんです。
若い時は、がむしゃらにやるのも正解ですが、健康を損ねないよう意識することもまた大事なんだと、後になってから気付かされました。

井上慎平さんの新著『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の弱さ考』(ダイヤモンド社)
井上慎平さんの新著『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の弱さ考』(ダイヤモンド社)
■どんなゲームをしているのか
■どんなゲームをしているのか
――体調を崩してしまう前にブレーキを踏み、バランスを取っていくにはどうすればいいですか。
――体調を崩してしまう前にブレーキを踏み、バランスを取っていくにはどうすればいいですか。
経済の論理では、個人も、企業も成長し続け、利益を出し続けることが善とされます。そうした枠内で、変化に適応し、自分の言動をコントロールし続けられる人が“強い”人であり、それができない人が“弱い”と見なされがちです。僕はそうした「こうあるべき」という規範に忠実であろうとし過ぎた結果、「本当はこうしたい」という心の声に耳を傾けられなくなったんだと思います。
現代社会は、転職までの期間が短くなったり、業界のビジネスモデルがすぐに変わったりと、流動性がますます高まっています。変化が目まぐるしく、それに合わせて自分を変えることが困難になっており、その点からいうと「弱い人」はどんどん増えているように見えます。
ただ僕は、資本主義社会を否定しようとは思いません。市場経済と複雑な分業がなければ、今僕たちが当たり前に享受している生活は成り立っていかないので。けれども、その中で生きる私たちは、“異常なゲームをさせられている”という自覚は持っておくべきだと思います。自覚できれば、楽になるというか、多少「しらける」ことができます。
「しらける」は、サボるとは違います。あくまでも、いい仕事をしようとはするんだけど、仕事以外の家庭や地域には「また別のルールのゲームがある」ことを知っていれば、無茶はしにくくなります。もし、経済の論理だけで思考してしまったら、会社や上司の要求に対して「頑張ります」としか言えなくなってしまうでしょう。
経済の論理では、個人も、企業も成長し続け、利益を出し続けることが善とされます。そうした枠内で、変化に適応し、自分の言動をコントロールし続けられる人が“強い”人であり、それができない人が“弱い”と見なされがちです。僕はそうした「こうあるべき」という規範に忠実であろうとし過ぎた結果、「本当はこうしたい」という心の声に耳を傾けられなくなったんだと思います。
現代社会は、転職までの期間が短くなったり、業界のビジネスモデルがすぐに変わったりと、流動性がますます高まっています。変化が目まぐるしく、それに合わせて自分を変えることが困難になっており、その点からいうと「弱い人」はどんどん増えているように見えます。
ただ僕は、資本主義社会を否定しようとは思いません。市場経済と複雑な分業がなければ、今僕たちが当たり前に享受している生活は成り立っていかないので。けれども、その中で生きる私たちは、“異常なゲームをさせられている”という自覚は持っておくべきだと思います。自覚できれば、楽になるというか、多少「しらける」ことができます。
「しらける」は、サボるとは違います。あくまでも、いい仕事をしようとはするんだけど、仕事以外の家庭や地域には「また別のルールのゲームがある」ことを知っていれば、無茶はしにくくなります。もし、経済の論理だけで思考してしまったら、会社や上司の要求に対して「頑張ります」としか言えなくなってしまうでしょう。
■「はじっこ」の可能性
■「はじっこ」の可能性
――今、仕事のことで落ち込んでいたり、心身共にきつくなっていたりする人へのアドバイスはありますか?
――今、仕事のことで落ち込んでいたり、心身共にきつくなっていたりする人へのアドバイスはありますか?
能力とは何かについても知っておいてほしいです。認知科学者の鈴木宏昭さんは著書『私たちはどう学んでいるのか』の中で、“能力という仮説は無効であり、能力は虚構なのだ”と書いています。
「コミュ力」や「論理的思考力」のように、「能力」をあたかも自分の引き出しに入れて所有できるモノだと錯覚している。しかし、「個人の内側に存在するもの」と捉えるような「モノ的」能力観は、間違っている。
実際には、自分の「経験・記憶」と「状況・環境」とが相互作用を起こした結果、僕たちが「能力」と呼んでいるものがそのつど生成される。鈴木さんはそれを、「モノ」と対比して「コト」的と呼んでいます。
例えば、どれだけ会社で「コミュカ」が高いと評価される口達者な人も、老人ホームという全く異なるコミュニティーを訪問すれば、その「コミュ力」を発揮することはできないでしょう。そこで「コミュカ」が高いとされるのは、むしろ聞き上手な人です。けれど、その聞き上手な人は、会社組織では「主体性が低そうだ」と評価されていることも少なくありません。
つまり、能力は環境によって変化する。強さ・弱さといっても、場面によってコロコロと変わるんです。そう考えるようになってからは、僕は中心だけでなく、「はじっこ」を歩くことの可能性も伝えたいと思うようになりました。
能力とは何かについても知っておいてほしいです。認知科学者の鈴木宏昭さんは著書『私たちはどう学んでいるのか』の中で、“能力という仮説は無効であり、能力は虚構なのだ”と書いています。
「コミュ力」や「論理的思考力」のように、「能力」をあたかも自分の引き出しに入れて所有できるモノだと錯覚している。しかし、「個人の内側に存在するもの」と捉えるような「モノ的」能力観は、間違っている。
実際には、自分の「経験・記憶」と「状況・環境」とが相互作用を起こした結果、僕たちが「能力」と呼んでいるものがそのつど生成される。鈴木さんはそれを、「モノ」と対比して「コト」的と呼んでいます。
例えば、どれだけ会社で「コミュカ」が高いと評価される口達者な人も、老人ホームという全く異なるコミュニティーを訪問すれば、その「コミュ力」を発揮することはできないでしょう。そこで「コミュカ」が高いとされるのは、むしろ聞き上手な人です。けれど、その聞き上手な人は、会社組織では「主体性が低そうだ」と評価されていることも少なくありません。
つまり、能力は環境によって変化する。強さ・弱さといっても、場面によってコロコロと変わるんです。そう考えるようになってからは、僕は中心だけでなく、「はじっこ」を歩くことの可能性も伝えたいと思うようになりました。
――はじっこ、ですか?
――はじっこ、ですか?
「この世の中にいるかぎり、市場経済的なものから逃げられない」と僕は書いてきたし、今もそうだと思います。でも、逃げられないんだけど、中心と周縁とでは状況が異なっているのではないでしょうか。
分かりやすくいえば、就活での人気企業が市場経済の中心です。中心では「この人が有能」という評価基準が、画一的になりがちです。でも、市場経済のはじっこ、例えば都会よりも地方、大企業よりも中小企業に目を向けてみると、求められるものがまた違ってきますよね。
中心で成長していくことだけが“勝者の物語”だと思う人もいますが、それは大きな間違いで、他でももっと多彩な物語があることは強く主張しておきたいところです。
「この世の中にいるかぎり、市場経済的なものから逃げられない」と僕は書いてきたし、今もそうだと思います。でも、逃げられないんだけど、中心と周縁とでは状況が異なっているのではないでしょうか。
分かりやすくいえば、就活での人気企業が市場経済の中心です。中心では「この人が有能」という評価基準が、画一的になりがちです。でも、市場経済のはじっこ、例えば都会よりも地方、大企業よりも中小企業に目を向けてみると、求められるものがまた違ってきますよね。
中心で成長していくことだけが“勝者の物語”だと思う人もいますが、それは大きな間違いで、他でももっと多彩な物語があることは強く主張しておきたいところです。
■「受け入れる」と「引き受ける」
■「受け入れる」と「引き受ける」
――井上さんはNewsPicks退社後、東京から長野に移住し、健康に気を配りながらも新事業を立ち上げました。井上さん自身は“新たな物語”へスムーズに移行できたということですか。
――井上さんはNewsPicks退社後、東京から長野に移住し、健康に気を配りながらも新事業を立ち上げました。井上さん自身は“新たな物語”へスムーズに移行できたということですか。
いやいや、言っておいてなんですが、そんな簡単にはいかなかったです。正直、うつになったことは未だに嫌なわけです。すごく不自由だし、何をしてもしんどいし。そのくせ、まだ目立ちたがりの性分が残っているので、いろいろ諦めることもできなくって。
どうすりゃいいのと悩むことは多々ありました。そうした中で、現状は、うつの自分を受け入れてはいないけれど、「引き受ける」ようにはなり、生きやすさは増しました。
いやいや、言っておいてなんですが、そんな簡単にはいかなかったです。正直、うつになったことは未だに嫌なわけです。すごく不自由だし、何をしてもしんどいし。そのくせ、まだ目立ちたがりの性分が残っているので、いろいろ諦めることもできなくって。
どうすりゃいいのと悩むことは多々ありました。そうした中で、現状は、うつの自分を受け入れてはいないけれど、「引き受ける」ようにはなり、生きやすさは増しました。
――「受け入れる」と「引き受ける」。何が違うのでしょうか?
――「受け入れる」と「引き受ける」。何が違うのでしょうか?
個人的な見解ですが、「人生はこういうものだから、しょうがないよね」と認めるのが、受け入れるということ。一方で、引き受けるっていうのは、「障がいも僕の愛すべき一部なのです」なんて悟ったようなフリはせず、納得していない、成熟していないままの自分を引きずって歩くようなイメージです。
簡単に受け入れられるほど、人はいつでも理性的に振る舞えるわけではないし、かといって魔法のように状況を打開するような手立てが見つかるわけでもない。
じゃあ、そこで行き止まりかというと、そんなことはなくて。病や障がい、コンプレックスや欲望をなかったことにせず、あがき続ける自分を、自分だけは誇っていいんじゃないかと思うんです。
挫折したり、病を経験したりすることで感性の幅が広がりました。自分と同じように上手く身動きが取れずにいる人たちの存在が、自分とはまったく違う苦しみなはずなのに自分の心に迫ってくる。僕自身、闘病記を読んで、共感して救われたり、気付きを得たりすることがよくあります。
今回、出版させていただいた『弱さ考』は、今元気な方にとっては手に取ろうとは中々思えない本かもしれません。ですので、防災用品のように思ってもらえたらありがたいです。使われないに越したことはないんだけど、人生のどこかのステージでピンチが訪れた際に、その人の琴線に触れるような言葉が一つでも、二つでもあればと願っています。
個人的な見解ですが、「人生はこういうものだから、しょうがないよね」と認めるのが、受け入れるということ。一方で、引き受けるっていうのは、「障がいも僕の愛すべき一部なのです」なんて悟ったようなフリはせず、納得していない、成熟していないままの自分を引きずって歩くようなイメージです。
簡単に受け入れられるほど、人はいつでも理性的に振る舞えるわけではないし、かといって魔法のように状況を打開するような手立てが見つかるわけでもない。
じゃあ、そこで行き止まりかというと、そんなことはなくて。病や障がい、コンプレックスや欲望をなかったことにせず、あがき続ける自分を、自分だけは誇っていいんじゃないかと思うんです。
挫折したり、病を経験したりすることで感性の幅が広がりました。自分と同じように上手く身動きが取れずにいる人たちの存在が、自分とはまったく違う苦しみなはずなのに自分の心に迫ってくる。僕自身、闘病記を読んで、共感して救われたり、気付きを得たりすることがよくあります。
今回、出版させていただいた『弱さ考』は、今元気な方にとっては手に取ろうとは中々思えない本かもしれません。ですので、防災用品のように思ってもらえたらありがたいです。使われないに越したことはないんだけど、人生のどこかのステージでピンチが訪れた際に、その人の琴線に触れるような言葉が一つでも、二つでもあればと願っています。
――井上さんは今年、「問い読」という会社を共同創業されたそうですね。
――井上さんは今年、「問い読」という会社を共同創業されたそうですね。
これまで編集者として本を作ってきましたが、次第に「いい本を出すだけで本が読まれるようになるのだろうか?」と疑問を抱くようになりました。
本は単なる情報の束ではない。読書は、もっとおもしろい「体験」にできる。読者が問いを投げかけられ、能動的にアウトプットし合う場があれば、本の可能性をさらに引き出せるのではないかと考えました。
僕と共同創業者の岩佐文夫さんで試行錯誤し、生まれたのが「問いからはじめるアウトプット読書ゼミ」、略して「問い読」です。
どうなるかは分かりませんし、これからの人生を考えると怖いと感じる時もあります。ただ、「まだまだ、こんなもんじゃねえ」とあがく、そのプロセス自体を大事にしていきたいと思っています。
これまで編集者として本を作ってきましたが、次第に「いい本を出すだけで本が読まれるようになるのだろうか?」と疑問を抱くようになりました。
本は単なる情報の束ではない。読書は、もっとおもしろい「体験」にできる。読者が問いを投げかけられ、能動的にアウトプットし合う場があれば、本の可能性をさらに引き出せるのではないかと考えました。
僕と共同創業者の岩佐文夫さんで試行錯誤し、生まれたのが「問いからはじめるアウトプット読書ゼミ」、略して「問い読」です。
どうなるかは分かりませんし、これからの人生を考えると怖いと感じる時もあります。ただ、「まだまだ、こんなもんじゃねえ」とあがく、そのプロセス自体を大事にしていきたいと思っています。
〈プロフィル〉
いのうえ・しんぺい 1988年生まれ。京都大学総合人間学部卒業。ディスカヴァー・トゥエンティワン、ダイヤモンド社を経て、2019年、NewsPicksパブリッシングを立ち上げる。25年、株式会社問い読を共同創業。
〈プロフィル〉
いのうえ・しんぺい 1988年生まれ。京都大学総合人間学部卒業。ディスカヴァー・トゥエンティワン、ダイヤモンド社を経て、2019年、NewsPicksパブリッシングを立ち上げる。25年、株式会社問い読を共同創業。
●最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご感想をお寄せください。
メール youth@seikyo-np.jp
ファクス 03-5360-9470
●最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご感想をお寄せください。
メール youth@seikyo-np.jp
ファクス 03-5360-9470