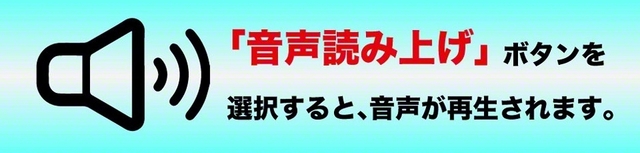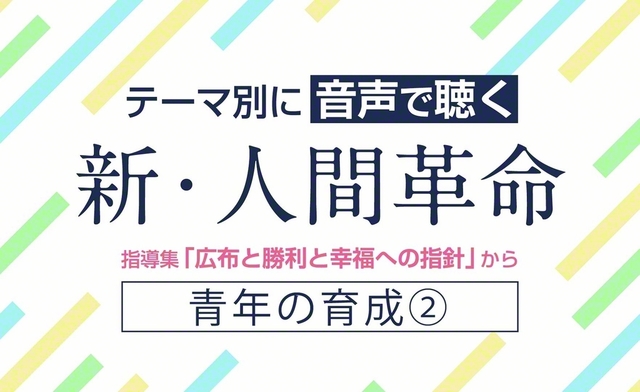AEE8151D1F1DACB13A609F800B709C38
テーマ別に音声で聴く「新・人間革命」 青年の育成②
テーマ別に音声で聴く「新・人間革命」 青年の育成②
2025年10月20日
- 指導集「広布と勝利と幸福への指針」から
- 指導集「広布と勝利と幸福への指針」から
音声の再生時間3分35秒です。
音声の再生時間3分35秒です。
第14巻「使命」の章 181ページ
第14巻「使命」の章 181ページ
次代の建設とは、「人」をつくることであり、若い世代を育むということです。それには、「心」を育てることです。人間としていかに生きるかということを教えることです。
(中略)
四十年先、五十年先を創るんです。
いつの時代でも、学会のリーダーは、後継の育成に全精魂を傾けなければならない──これは、私の遺言として語っておきたいんです。
次代の建設とは、「人」をつくることであり、若い世代を育むということです。それには、「心」を育てることです。人間としていかに生きるかということを教えることです。
(中略)
四十年先、五十年先を創るんです。
いつの時代でも、学会のリーダーは、後継の育成に全精魂を傾けなければならない──これは、私の遺言として語っておきたいんです。
第24巻「人間教育」の章 204ページ
第24巻「人間教育」の章 204ページ
学会が、どうして、ここまで発展することができたのか。その要因の一つは、常に青年を大切にし、青年を前面に押し出すことによって、育ててきたからだよ。
時代は、どんどん変わっていく。信心という根本は、決して変わってはいけないが、運営の仕方や、感覚というものは、時代とともに変わるものだ。学会は、その時代感覚を、青年から吸収し、先取りして、新しい前進の活力を得てきた。
壮年や婦人は、ともすれば、これまで自分が行ってきたやり方に固執し、それを見直そうとはしないものだ。しかし、それでは、時代の変化についていけなくなってしまう。
社会の流れや時代感覚は、青年に学んでいく以外にない。その意味からも、男子部や女子部が、壮年や婦人にも、どんどん意見を言える学会でなくてはならない。
学会が、どうして、ここまで発展することができたのか。その要因の一つは、常に青年を大切にし、青年を前面に押し出すことによって、育ててきたからだよ。
時代は、どんどん変わっていく。信心という根本は、決して変わってはいけないが、運営の仕方や、感覚というものは、時代とともに変わるものだ。学会は、その時代感覚を、青年から吸収し、先取りして、新しい前進の活力を得てきた。
壮年や婦人は、ともすれば、これまで自分が行ってきたやり方に固執し、それを見直そうとはしないものだ。しかし、それでは、時代の変化についていけなくなってしまう。
社会の流れや時代感覚は、青年に学んでいく以外にない。その意味からも、男子部や女子部が、壮年や婦人にも、どんどん意見を言える学会でなくてはならない。
第25巻「福光」の章 19~20ページ
第25巻「福光」の章 19~20ページ
私は常に、自分の方から青年たちに声をかけ、率直に対話し、励ましてきた。幹部が、つんと澄まして、知らん顔をしているようでは駄目です。胸襟を開いて飛び込んでいくんです。たとえば、座談会の終わりごろに、仕事を終えて駆けつけて来た青年がいたら、『よく来たね。ご苦労様! 大変だっただろう。頑張ったね」と、包み込むように、力の限り励ましていくんです。そうすれば、“次も頑張って参加しよう”と思うものです。
それを、“遅れて来てなんだ!”というような顔をして、声もかけなければ、“もう、来るのはよそう”と思ってしまう。「励ます」ということは、「讃える」ということでもあるんです。
(中略)
また、私は、青年を包容しながら、大きな責任を託した。実戦こそが最高の学習の場だからです。そして、失敗した時には、最後は、全部、私が責任を取った。大切なのは、その度量だよ。
私は常に、自分の方から青年たちに声をかけ、率直に対話し、励ましてきた。幹部が、つんと澄まして、知らん顔をしているようでは駄目です。胸襟を開いて飛び込んでいくんです。たとえば、座談会の終わりごろに、仕事を終えて駆けつけて来た青年がいたら、『よく来たね。ご苦労様! 大変だっただろう。頑張ったね」と、包み込むように、力の限り励ましていくんです。そうすれば、“次も頑張って参加しよう”と思うものです。
それを、“遅れて来てなんだ!”というような顔をして、声もかけなければ、“もう、来るのはよそう”と思ってしまう。「励ます」ということは、「讃える」ということでもあるんです。
(中略)
また、私は、青年を包容しながら、大きな責任を託した。実戦こそが最高の学習の場だからです。そして、失敗した時には、最後は、全部、私が責任を取った。大切なのは、その度量だよ。
音声読み上げ