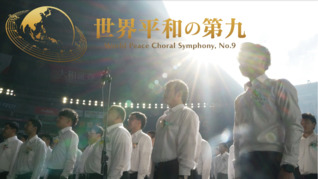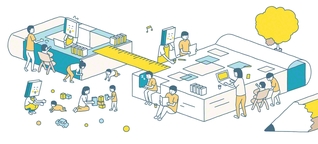AB16F073D29BB8ACFAA2249C5BBD5B3E
〈未来を想像/創造する倫理〉4 京都大学教授 児玉聡 精子や卵子をつくる技術
〈未来を想像/創造する倫理〉4 京都大学教授 児玉聡 精子や卵子をつくる技術
2025年11月25日
- 家族や生殖のあり方問うことも
- 家族や生殖のあり方問うことも
自分の皮膚から精子や卵子をつくる。空想のような話ですが、体外配偶子形成(IVG)という技術が実現に近づいています。生殖とは何か、家族とは何かという問いが改めて重要になっています。
事例 不妊治療クリニックを訪れた夫婦。医師はモニターの画像を示して説明する。
「こちらが奥さまの皮膚細胞からつくった『iPS卵子』です。減数分裂も正常で、受精の準備ができています。複数育てれば、多数の胚をつくることも可能です」
体外受精では卵子が採れず、治療が難航していた夫婦は息をのむ。医師は続ける。
「IVGで妊娠の可能性は広がりますが、安全性はまだ確立されていません。研究への参加を考えますか」
子を持ちたい気持ちと未知への不安が二人の胸中で揺れ続ける。
◇
IVGはiPS細胞等の幹細胞から配偶子(精子や卵子)を体外でつくる技術です。従来の体外受精が「すでに存在する配偶子を扱う技術」だったのに対し、IVGは「配偶子そのものをつくる」点で質的に異なります。
マウスでは2010年代以降、IVG由来の配偶子から健康な子が生まれ、23年には、オス同士から子を得た研究も報告されました。ヒトでは、精子・卵子の前段階の細胞の作製に成功しており、完全な実現にはまだ距離があるものの技術の進展は確かです。
この技術は無精子症や卵巣機能低下で妊娠が難しかった人には新たな選択肢になり、さらに閉経後の女性や同性カップルが遺伝的につながる子を持つ可能性も開かれます。
一方、IVGでは大量の卵子をつくれるため、多数の胚を比較して「望ましい特徴」を選ぶプロセスが一般化する懸念があります。また、一人の体細胞から精子と卵子の両方がつくれれば「ソロ生殖」も理論上は可能で、生殖の自由と子の福祉という古くて新しい問題が改めて浮上します。
日本では25年、不妊治療や遺伝研究に限ってIVG由来の配偶子による受精を認める方向性が示されましたが、出産への利用は今後の議論に委ねられています。
◇
IVGは生殖医療の可能性を広げると同時に、家族のかたちや遺伝的つながりの意味などの問い直しを求めるような技術です。生殖が「自然に任せるもの」から「設計しうるもの」へ変わりつつある現在、私たちは未来の生殖のあり方について議論する時期に来ているのかもしれません。
自分の皮膚から精子や卵子をつくる。空想のような話ですが、体外配偶子形成(IVG)という技術が実現に近づいています。生殖とは何か、家族とは何かという問いが改めて重要になっています。
事例 不妊治療クリニックを訪れた夫婦。医師はモニターの画像を示して説明する。
「こちらが奥さまの皮膚細胞からつくった『iPS卵子』です。減数分裂も正常で、受精の準備ができています。複数育てれば、多数の胚をつくることも可能です」
体外受精では卵子が採れず、治療が難航していた夫婦は息をのむ。医師は続ける。
「IVGで妊娠の可能性は広がりますが、安全性はまだ確立されていません。研究への参加を考えますか」
子を持ちたい気持ちと未知への不安が二人の胸中で揺れ続ける。
◇
IVGはiPS細胞等の幹細胞から配偶子(精子や卵子)を体外でつくる技術です。従来の体外受精が「すでに存在する配偶子を扱う技術」だったのに対し、IVGは「配偶子そのものをつくる」点で質的に異なります。
マウスでは2010年代以降、IVG由来の配偶子から健康な子が生まれ、23年には、オス同士から子を得た研究も報告されました。ヒトでは、精子・卵子の前段階の細胞の作製に成功しており、完全な実現にはまだ距離があるものの技術の進展は確かです。
この技術は無精子症や卵巣機能低下で妊娠が難しかった人には新たな選択肢になり、さらに閉経後の女性や同性カップルが遺伝的につながる子を持つ可能性も開かれます。
一方、IVGでは大量の卵子をつくれるため、多数の胚を比較して「望ましい特徴」を選ぶプロセスが一般化する懸念があります。また、一人の体細胞から精子と卵子の両方がつくれれば「ソロ生殖」も理論上は可能で、生殖の自由と子の福祉という古くて新しい問題が改めて浮上します。
日本では25年、不妊治療や遺伝研究に限ってIVG由来の配偶子による受精を認める方向性が示されましたが、出産への利用は今後の議論に委ねられています。
◇
IVGは生殖医療の可能性を広げると同時に、家族のかたちや遺伝的つながりの意味などの問い直しを求めるような技術です。生殖が「自然に任せるもの」から「設計しうるもの」へ変わりつつある現在、私たちは未来の生殖のあり方について議論する時期に来ているのかもしれません。

生殖医療が急速に発展するなか、家族とは何かという問いが改めて重要になっている(イメージマート)
生殖医療が急速に発展するなか、家族とは何かという問いが改めて重要になっている(イメージマート)