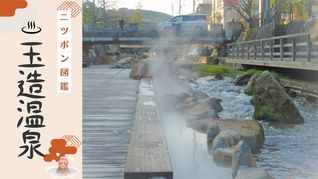〈Seikyo Gift〉 作家・宮本輝さん、初の歴史小説「潮音」――時代の水底にある動きを感じ、その音に耳を澄ませる〈文化〉
〈Seikyo Gift〉 作家・宮本輝さん、初の歴史小説「潮音」――時代の水底にある動きを感じ、その音に耳を澄ませる〈文化〉
2025年4月26日
◆激動の幕末期を新たな視点で活写(全4巻の長編を毎月連続で刊行)
◆激動の幕末期を新たな視点で活写(全4巻の長編を毎月連続で刊行)

全4巻の長編を1月から毎月1巻ずつ刊行している
全4巻の長編を1月から毎月1巻ずつ刊行している
作家・宮本輝さんが手がけた初めての歴史小説『潮音』(文藝春秋、全4巻)の刊行が続いている。富山の薬売りを主人公に、幕末から近代へと推移する激動期の日本を新たな視点から描いた長編。作品に込めた思いなどについて宮本さんに聞いた。(2月24日付)
作家・宮本輝さんが手がけた初めての歴史小説『潮音』(文藝春秋、全4巻)の刊行が続いている。富山の薬売りを主人公に、幕末から近代へと推移する激動期の日本を新たな視点から描いた長編。作品に込めた思いなどについて宮本さんに聞いた。(2月24日付)
●物語は主人公の語りで展開
●物語は主人公の語りで展開
〈近作の『潮音』は、文芸誌「文學界」2015年4月号から24年4月号まで、足かけ10年にわたって掲載された長編作品。全4巻のうち第1巻が本年1月に上梓され、4月まで毎月連続して刊行される。主人公の川上弥一は越中富山の売薬人。激動の幕末に薩摩藩を担当し、動乱を目の当たりにする。物語は、生まれ故郷の越中八尾で来し方を振り返る「わたくし」=弥一の語りで展開していく〉
主人公の「わたくし」、八尾の紙問屋・川上屋の跡取りに生まれた弥一が、なぜ、16歳の時に薬種問屋兼売薬商の高麗屋に奉公にあがったか。最初に少し思い出として語らせてプロローグを終えてから第1章に入ろう。第2章までは時々、弥一の独白が入るけれども、そのほかは三人称でずっと進めよう。そんなつもりで書き始めました。
結局、一人称で通した初めての長編になりましたが、話が安政の時代に移ったり明治に戻ったりしても、弥一の語りだと自然に成立することができた。でも、こんなに長いものを書くとは自分でも思いませんでした(笑)。
〈近作の『潮音』は、文芸誌「文學界」2015年4月号から24年4月号まで、足かけ10年にわたって掲載された長編作品。全4巻のうち第1巻が本年1月に上梓され、4月まで毎月連続して刊行される。主人公の川上弥一は越中富山の売薬人。激動の幕末に薩摩藩を担当し、動乱を目の当たりにする。物語は、生まれ故郷の越中八尾で来し方を振り返る「わたくし」=弥一の語りで展開していく〉
主人公の「わたくし」、八尾の紙問屋・川上屋の跡取りに生まれた弥一が、なぜ、16歳の時に薬種問屋兼売薬商の高麗屋に奉公にあがったか。最初に少し思い出として語らせてプロローグを終えてから第1章に入ろう。第2章までは時々、弥一の独白が入るけれども、そのほかは三人称でずっと進めよう。そんなつもりで書き始めました。
結局、一人称で通した初めての長編になりましたが、話が安政の時代に移ったり明治に戻ったりしても、弥一の語りだと自然に成立することができた。でも、こんなに長いものを書くとは自分でも思いませんでした(笑)。
●庶民の目線で時代の歩みを描く
●庶民の目線で時代の歩みを描く
〈清国産の薬種を必要とする越中富山。五百万両という借金で財政難の薩摩藩。利害が一致して手を組む両者は、蝦夷地の干し昆布を欲しがる清国との密貿易を始め、琉球も加えた一大交易圏を隠密裏に築き上げた。史実を踏まえつつ、弥一ら名もなき庶民の視点から時代の歩みを活写していくスタイルは新鮮だ〉
ペリーが浦賀沖(神奈川県)にやって来た時、幕府は慌てふためきます。うわさに聞いていた以上に大きな船に見えたのでしょう。
向こうは大砲を備えた艦隊。長身で屈強な男たちが整然と並ぶ。ところが幕府側ときたら、200年前の父祖の形見みたいなよろいを着て、やりを持ったじいさんが、足を引きずりながら集まっているわけです。
遠巻きに見る庶民が心を動かされたのは、ペリー艦隊に対する驚きというより、うろたえ、ぺこぺこする幕府の重臣たちの頼りなさだったのではないでしょうか。「幕府って弱いんや」「徳川、たいしたことないで」。これが始まりだったと思うんです。
西南戦争では西郷軍約7000人が犠牲になりましたが、その多くが青年でした。なぜ無策・無謀とも言える戦いで大勢の若者を道連れにしたのかと、疑問に感じられて仕方ありませんでした。
歴史小説について、「うっかり足を踏み入れたらえらいことになるぞ」と作家の先輩である池上義一さんに言われたことがあったんですが、その意味がよく分かりました。書いていると、一つ一つの出来事が面白くて、先に進まない。“歴史の泥沼”に足を取られて、出られへんようになってしまったんです。「でも、いつか輝ちゃんは書くことになるやろなあ。できることなら幕末はやめとけよ」とも言われてたのに(笑い)。
攘夷とか佐幕とか勤王倒幕とか、さらに外国の動きや思惑を考え過ぎると、政治的な小説になって、富山から遠ざかってしまう。そうならないよう、常に富山の薬へ、富山の薬へと戻すことを意識しました。
〈清国産の薬種を必要とする越中富山。五百万両という借金で財政難の薩摩藩。利害が一致して手を組む両者は、蝦夷地の干し昆布を欲しがる清国との密貿易を始め、琉球も加えた一大交易圏を隠密裏に築き上げた。史実を踏まえつつ、弥一ら名もなき庶民の視点から時代の歩みを活写していくスタイルは新鮮だ〉
ペリーが浦賀沖(神奈川県)にやって来た時、幕府は慌てふためきます。うわさに聞いていた以上に大きな船に見えたのでしょう。
向こうは大砲を備えた艦隊。長身で屈強な男たちが整然と並ぶ。ところが幕府側ときたら、200年前の父祖の形見みたいなよろいを着て、やりを持ったじいさんが、足を引きずりながら集まっているわけです。
遠巻きに見る庶民が心を動かされたのは、ペリー艦隊に対する驚きというより、うろたえ、ぺこぺこする幕府の重臣たちの頼りなさだったのではないでしょうか。「幕府って弱いんや」「徳川、たいしたことないで」。これが始まりだったと思うんです。
西南戦争では西郷軍約7000人が犠牲になりましたが、その多くが青年でした。なぜ無策・無謀とも言える戦いで大勢の若者を道連れにしたのかと、疑問に感じられて仕方ありませんでした。
歴史小説について、「うっかり足を踏み入れたらえらいことになるぞ」と作家の先輩である池上義一さんに言われたことがあったんですが、その意味がよく分かりました。書いていると、一つ一つの出来事が面白くて、先に進まない。“歴史の泥沼”に足を取られて、出られへんようになってしまったんです。「でも、いつか輝ちゃんは書くことになるやろなあ。できることなら幕末はやめとけよ」とも言われてたのに(笑い)。
攘夷とか佐幕とか勤王倒幕とか、さらに外国の動きや思惑を考え過ぎると、政治的な小説になって、富山から遠ざかってしまう。そうならないよう、常に富山の薬へ、富山の薬へと戻すことを意識しました。

歴史を動かす水底の力は、名もなき民衆――。宮本さんにとって、動乱の幕末期を舞台にした近著『潮音』は初めて手がけた歴史小説である
歴史を動かす水底の力は、名もなき民衆――。宮本さんにとって、動乱の幕末期を舞台にした近著『潮音』は初めて手がけた歴史小説である
●「弥一になれた」。美々津の港で
●「弥一になれた」。美々津の港で
〈越中八尾、薩摩、京都など、弥一たちの姿と併せて、風景が丁寧に描出される。風景から物語が立ち上がるように感じるのも、宮本さんの作品に共通する滋味だろう。また、主人公たち、彼らを支えつつ帰りを待つ富山の人々の描写一つにも、創作にかける間断なき飛翔の軌跡がある〉
越中富山から薩摩までは約35日。弥一たちは途中、高鍋藩領の美々津(宮崎県日向市)という港町に立ち寄ります。ここの特産品は、樫で作った櫓でした。日本中の船乗りが美々津の櫓を欲しがったそうです。
思いもよらない品物を扱って土地の人々を養った商人たち、あるいは、その品を求めた船頭や漁師たちがいた。小さな商いだけれども、広く行き渡る商売をしていたんだなと、僕も実際に美々津へ行き、そこに座って風景を見ているうちに絵として浮かんできたんです。
こっちに山。ここには廻船問屋が並ぶ通りがあって、海には船がずらっと並んで、特産品を送り出している――。そういうふうに絵として浮かんできたら、僕はうまいこといくんです(笑)。
「弥一もここに座ったかな」と思ったその時に、美々津という港町に初めて来て漁師や廻船問屋の動きを見つめる越中売薬人の川上弥一に自分がなれた気がしました。言葉ではうまく説明できないんですが、「俺、弥一になれたな」と。その時に「書ける」と思いました。最後まで一人称で書こうと思ったのも、この時でした。
〈越中八尾、薩摩、京都など、弥一たちの姿と併せて、風景が丁寧に描出される。風景から物語が立ち上がるように感じるのも、宮本さんの作品に共通する滋味だろう。また、主人公たち、彼らを支えつつ帰りを待つ富山の人々の描写一つにも、創作にかける間断なき飛翔の軌跡がある〉
越中富山から薩摩までは約35日。弥一たちは途中、高鍋藩領の美々津(宮崎県日向市)という港町に立ち寄ります。ここの特産品は、樫で作った櫓でした。日本中の船乗りが美々津の櫓を欲しがったそうです。
思いもよらない品物を扱って土地の人々を養った商人たち、あるいは、その品を求めた船頭や漁師たちがいた。小さな商いだけれども、広く行き渡る商売をしていたんだなと、僕も実際に美々津へ行き、そこに座って風景を見ているうちに絵として浮かんできたんです。
こっちに山。ここには廻船問屋が並ぶ通りがあって、海には船がずらっと並んで、特産品を送り出している――。そういうふうに絵として浮かんできたら、僕はうまいこといくんです(笑)。
「弥一もここに座ったかな」と思ったその時に、美々津という港町に初めて来て漁師や廻船問屋の動きを見つめる越中売薬人の川上弥一に自分がなれた気がしました。言葉ではうまく説明できないんですが、「俺、弥一になれたな」と。その時に「書ける」と思いました。最後まで一人称で書こうと思ったのも、この時でした。
●書かずに存在を感じさせる
●書かずに存在を感じさせる
国もとの富山では妻や子、父や母、家族が弥一たちを支え、帰りを待っています。それを文章にせず、どう感じさせるかということは常に考えていました。その人たちの存在が絶えず弥一たちの後ろにあることを、どうやって表現しようか、と。
ここ数年、小説家でありながら“書かずに表現する”ということが自分の大きなテーマになっているんですが、それが少しできるようになってきた気がします。
何も書いてないけれども、その背後に累々と重なるものをどうやって感じさせるか。
例えば、井上靖さんの小説『天平の甍』。経巻が海に沈んでいく場面で、その経巻を書き写した者の顔が浮かんできます。こういう姿かたちをしていて、これくらいの身長で、こういう姿勢で歩き、こんな冗談を言い、こういうものを食べて、というようなことが、ざーっと浮かんでくる。
では、文章のどこにあるかというと、ないんです。ただ経巻が沈んでいった、とあるだけ。けれども、そう感じさせる。これが「文芸」だと思うんです。文字通り、芸の世界であり、修練を重ねて培う“わざ”の世界なんです。
80歳近くになって、やっと自分もその世界に入れたかなと感じています。
国もとの富山では妻や子、父や母、家族が弥一たちを支え、帰りを待っています。それを文章にせず、どう感じさせるかということは常に考えていました。その人たちの存在が絶えず弥一たちの後ろにあることを、どうやって表現しようか、と。
ここ数年、小説家でありながら“書かずに表現する”ということが自分の大きなテーマになっているんですが、それが少しできるようになってきた気がします。
何も書いてないけれども、その背後に累々と重なるものをどうやって感じさせるか。
例えば、井上靖さんの小説『天平の甍』。経巻が海に沈んでいく場面で、その経巻を書き写した者の顔が浮かんできます。こういう姿かたちをしていて、これくらいの身長で、こういう姿勢で歩き、こんな冗談を言い、こういうものを食べて、というようなことが、ざーっと浮かんでくる。
では、文章のどこにあるかというと、ないんです。ただ経巻が沈んでいった、とあるだけ。けれども、そう感じさせる。これが「文芸」だと思うんです。文字通り、芸の世界であり、修練を重ねて培う“わざ”の世界なんです。
80歳近くになって、やっと自分もその世界に入れたかなと感じています。
●“一人の人間を救う”という使命
●“一人の人間を救う”という使命
〈タイトルの「潮音」とは、海の底にある潮流の音。人知れぬ水底の流れのように、時代の底でも巨大な潮が静かに動いている、と宮本さんは言う。私たちは、その響きを感じ、その音に耳を澄ませられているだろうか〉
弥一が高麗屋に奉公にあがった弘化4年(1847年)頃、富山では約2000人が売薬業に携わっていたそうです。全国の人々に健康を届けるため、富山の民を食べさせるため、何十日間もかけてお客さまを訪ね、薬を置く。再び富山に帰って優れた薬を作る工夫を重ね、また旅に出て家々を回る。弥一たちはその営みを何十年も続けました。目の前にいる一人の人間を救うことを自らの大きな使命と感じていたのだと思います。
幕末から明治へと時代は変わっていきますが、彼らの営みは何も変わりません。海に例えるなら、世の中の変化は海面から5メートル、10メートル程度の波の動き。弥一たちの営みは、深い水底の大きな潮流です。
時代の水底でも大きな潮が静かに、ゆっくりと動いている。この動きは誰も止めることができません。そして、誰もがこの流れの中で生きているのです。
弥一と一緒に時代の「潮音」を感じてみてください。
〈タイトルの「潮音」とは、海の底にある潮流の音。人知れぬ水底の流れのように、時代の底でも巨大な潮が静かに動いている、と宮本さんは言う。私たちは、その響きを感じ、その音に耳を澄ませられているだろうか〉
弥一が高麗屋に奉公にあがった弘化4年(1847年)頃、富山では約2000人が売薬業に携わっていたそうです。全国の人々に健康を届けるため、富山の民を食べさせるため、何十日間もかけてお客さまを訪ね、薬を置く。再び富山に帰って優れた薬を作る工夫を重ね、また旅に出て家々を回る。弥一たちはその営みを何十年も続けました。目の前にいる一人の人間を救うことを自らの大きな使命と感じていたのだと思います。
幕末から明治へと時代は変わっていきますが、彼らの営みは何も変わりません。海に例えるなら、世の中の変化は海面から5メートル、10メートル程度の波の動き。弥一たちの営みは、深い水底の大きな潮流です。
時代の水底でも大きな潮が静かに、ゆっくりと動いている。この動きは誰も止めることができません。そして、誰もがこの流れの中で生きているのです。
弥一と一緒に時代の「潮音」を感じてみてください。
▼プロフィル
▼プロフィル
みやもと・てる 1947年、兵庫県生まれ。広告代理店勤務などを経て77年に『泥の河』で太宰治賞、翌78年に『螢川』で芥川賞を受賞。『道頓堀川』『錦繍』『青が散る』『春の夢』『優駿』(吉川英治文学賞)、『約束の冬』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『骸骨ビルの庭』(司馬遼太郎賞)、『流転の海』(全九部、毎日芸術賞)など著書多数。兵庫県伊丹市在住。
みやもと・てる 1947年、兵庫県生まれ。広告代理店勤務などを経て77年に『泥の河』で太宰治賞、翌78年に『螢川』で芥川賞を受賞。『道頓堀川』『錦繍』『青が散る』『春の夢』『優駿』(吉川英治文学賞)、『約束の冬』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『骸骨ビルの庭』(司馬遼太郎賞)、『流転の海』(全九部、毎日芸術賞)など著書多数。兵庫県伊丹市在住。