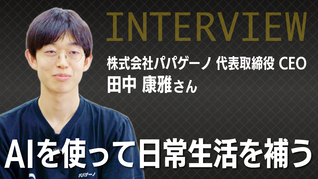〈フォーカス 平和運動〉 クローズアップ アマゾン創価研究所
〈フォーカス 平和運動〉 クローズアップ アマゾン創価研究所
2025年5月13日

大アマゾンの起点に面して立つ「創価研究所――アマゾン環境研究センター」
大アマゾンの起点に面して立つ「創価研究所――アマゾン環境研究センター」
多様な生物種が生息している「生命の宝庫」アマゾン。しかし近年、商用開発などで森林が消失し、乾燥や生物多様性の喪失が進んでいる。本年11月には、気候変動対策の国連の会議「COP30(国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議)」がアマゾン地域で初めて開催される。
アマゾン川の起点に面して立つ「創価研究所――アマゾン環境研究センター」は、“アマゾンを守ることで人類の生存を守る”との池田先生の構想のもと、1992年に「アマゾン自然環境研究センター」として発足。研究所の一帯は、ブラジル環境省の行政機関から「池田大作博士自然遺産私有保護区」として認定されている。
設立以来、主に「環境保護」「環境教育」「研究支援」を推進。野生の種子から苗木を育て、約2万本を植樹してきたほか、原生植物の再生と生産のために樹木の種子を採取・保存する“種子銀行”の取り組みも行っている。また、アマゾナス州の裁判所などと協力して、「生命の種子プロジェクト」を実施。市内の産科病院で子どもが一人生まれるたびに苗木を植えている。希少動物の保護にも努めており、保護区内の自然林は、希少動物の生息地としても重要な役割を担う。
さらに、マナウス市の公立学校や政府機関などと協力して「環境アカデミー」を毎週、開催している。
研究所のウェブサイトはこちら
多様な生物種が生息している「生命の宝庫」アマゾン。しかし近年、商用開発などで森林が消失し、乾燥や生物多様性の喪失が進んでいる。本年11月には、気候変動対策の国連の会議「COP30(国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議)」がアマゾン地域で初めて開催される。
アマゾン川の起点に面して立つ「創価研究所――アマゾン環境研究センター」は、“アマゾンを守ることで人類の生存を守る”との池田先生の構想のもと、1992年に「アマゾン自然環境研究センター」として発足。研究所の一帯は、ブラジル環境省の行政機関から「池田大作博士自然遺産私有保護区」として認定されている。
設立以来、主に「環境保護」「環境教育」「研究支援」を推進。野生の種子から苗木を育て、約2万本を植樹してきたほか、原生植物の再生と生産のために樹木の種子を採取・保存する“種子銀行”の取り組みも行っている。また、アマゾナス州の裁判所などと協力して、「生命の種子プロジェクト」を実施。市内の産科病院で子どもが一人生まれるたびに苗木を植えている。希少動物の保護にも努めており、保護区内の自然林は、希少動物の生息地としても重要な役割を担う。
さらに、マナウス市の公立学校や政府機関などと協力して「環境アカデミー」を毎週、開催している。
研究所のウェブサイトはこちら
●ルシアノ・ナシメント所長に聞く
●ルシアノ・ナシメント所長に聞く
アマゾン創価研究所の取り組みなどについて、ルシアノ・ナシメント所長に聞いた(聞き手=福島尊弘)。
アマゾン創価研究所の取り組みなどについて、ルシアノ・ナシメント所長に聞いた(聞き手=福島尊弘)。
――アマゾン創価研究所はどのような理念で活動されているのでしょうか。
研究所の創立者である池田先生は、アマゾンを非常に重視されていました。かつてマナウスで行われた国際環境会議にメッセージを寄せてくださり、「アマゾンが病むとき、地球は病み、アマゾンが泣くとき、地球は泣くのです。アマゾンが羽ばたくとき、人類は羽ばたくのです」と述べられ、“大切な地球を、後の世代に伝えゆくため、みずみずしい「生命の家」アマゾンを守り抜く”と真情をつづってくださったこともあります。
そして先生は、生命と環境は決してかけ離れたものではないことを強調され、生命の尊厳を最大限に尊重し、人間と自然の調和の取れた共存を広げることでアマゾンの生態系を守るよう訴えられました。それが研究所の基本的な理念であり、使命になっています。
こうした理念を具体化する取り組みの一つに、毎週水曜日に実施している「環境アカデミー」があります。
マナウス市の小学生や中学生を中心に、多くの若者を研究所のある自然保護区に招いており、自然と接することでアマゾンの森林と生態系の重要性についての感性を高め、人間の行動が環境に与える影響を考える機会になっています。参加した生徒からは「日常とかけ離れた体験ができて感謝している」「森林が大事であることは重々わかっているつもりだったけれど、木の前に立って初めて自然と自分の生命を結びつけることができた」などの感想がありました。
また、持続可能なコミュニティーの構築の一助となるよう、日常生活において自然の再構築に貢献できる取り組みなどを伝えています。昨年度は41の学校から2500人以上の生徒がアカデミーに参加しました。
――アマゾン創価研究所はどのような理念で活動されているのでしょうか。
研究所の創立者である池田先生は、アマゾンを非常に重視されていました。かつてマナウスで行われた国際環境会議にメッセージを寄せてくださり、「アマゾンが病むとき、地球は病み、アマゾンが泣くとき、地球は泣くのです。アマゾンが羽ばたくとき、人類は羽ばたくのです」と述べられ、“大切な地球を、後の世代に伝えゆくため、みずみずしい「生命の家」アマゾンを守り抜く”と真情をつづってくださったこともあります。
そして先生は、生命と環境は決してかけ離れたものではないことを強調され、生命の尊厳を最大限に尊重し、人間と自然の調和の取れた共存を広げることでアマゾンの生態系を守るよう訴えられました。それが研究所の基本的な理念であり、使命になっています。
こうした理念を具体化する取り組みの一つに、毎週水曜日に実施している「環境アカデミー」があります。
マナウス市の小学生や中学生を中心に、多くの若者を研究所のある自然保護区に招いており、自然と接することでアマゾンの森林と生態系の重要性についての感性を高め、人間の行動が環境に与える影響を考える機会になっています。参加した生徒からは「日常とかけ離れた体験ができて感謝している」「森林が大事であることは重々わかっているつもりだったけれど、木の前に立って初めて自然と自分の生命を結びつけることができた」などの感想がありました。
また、持続可能なコミュニティーの構築の一助となるよう、日常生活において自然の再構築に貢献できる取り組みなどを伝えています。昨年度は41の学校から2500人以上の生徒がアカデミーに参加しました。

アマゾン創価研究所で行われた環境アカデミー
アマゾン創価研究所で行われた環境アカデミー
――ブラジルは商用地の拡大や火災などによって、過去5年間で世界で最も森林の消失が進んでおり、とりわけアマゾン地域の熱帯林が急速に消失しているといわれています。
本当に悲しい事実です。国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の研究でも、気候変動と森林火災の増加傾向や被害には関連があることが分かっています。
火災が発生すると、市民の健康にも大きな影響が出ます。例えばマナウス市で火災が起きた際には、町中に黒煙が充満し、多くの市民が呼吸困難に陥りました。また、多くの動物たちが命を落とし、自然のリズムが乱れてしまいました。さらには、火災が発生すると土の乾燥や、川の水量にも影響が及びます。
森林伐採や火災の問題は大学・学術機関、非政府組織などでも広く議論されています。2023年8月から24年6月までの間においては、森林伐採量が前年比で半減するなど、改善してきてはいますが、依然としてやるべきことは多くあります。
――ブラジルは商用地の拡大や火災などによって、過去5年間で世界で最も森林の消失が進んでおり、とりわけアマゾン地域の熱帯林が急速に消失しているといわれています。
本当に悲しい事実です。国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の研究でも、気候変動と森林火災の増加傾向や被害には関連があることが分かっています。
火災が発生すると、市民の健康にも大きな影響が出ます。例えばマナウス市で火災が起きた際には、町中に黒煙が充満し、多くの市民が呼吸困難に陥りました。また、多くの動物たちが命を落とし、自然のリズムが乱れてしまいました。さらには、火災が発生すると土の乾燥や、川の水量にも影響が及びます。
森林伐採や火災の問題は大学・学術機関、非政府組織などでも広く議論されています。2023年8月から24年6月までの間においては、森林伐採量が前年比で半減するなど、改善してきてはいますが、依然としてやるべきことは多くあります。

観測史上最悪といわれる干ばつ被害でアマゾンの多くの集落が孤立(昨年10月)
観測史上最悪といわれる干ばつ被害でアマゾンの多くの集落が孤立(昨年10月)
――気候変動が影響している被害の一つに干ばつもあります。ブラジルでも近年、アマゾン川の支流の水位が観測史上最も低くなるなど、深刻な被害に見舞われています。
アマゾン地域の干ばつは、特に川沿いにある集落に壊滅的な影響を与えています。彼らは川を中心に生活しているので、干ばつにより舟が出せず多くの家庭が孤立してしまいました。農業を生業にしている家庭も多く存在しており、生活が深刻なダメージを受けています。また、安全な飲料水や食料の不足による健康被害をはじめ、子どもたちの教育の機会も奪われ、生命の尊厳を脅かしています。
干ばつの影響を受けた地域では、政府や市民団体からの支援が必要不可欠です。支援がなければ、コミュニティー自体が生き残れないという危機に直面しています。
アマゾン創価研究所では、企業や機関と協力し、干ばつ被害に遭った川沿いの集落に対して「アグアス・デ・アジュリ」という支援活動を実施しました。アジュリとは、先住民の言葉で「力を合わせる」という意味です。
これまで深刻な被害に見舞われた集落に、浄水器や食品、子どもたちが遊べるおもちゃを届けることができました。特に企業などの機関と地域コミュニティーを結ぶという点において、研究所は一定の役割を果たしてきました。
――気候変動が影響している被害の一つに干ばつもあります。ブラジルでも近年、アマゾン川の支流の水位が観測史上最も低くなるなど、深刻な被害に見舞われています。
アマゾン地域の干ばつは、特に川沿いにある集落に壊滅的な影響を与えています。彼らは川を中心に生活しているので、干ばつにより舟が出せず多くの家庭が孤立してしまいました。農業を生業にしている家庭も多く存在しており、生活が深刻なダメージを受けています。また、安全な飲料水や食料の不足による健康被害をはじめ、子どもたちの教育の機会も奪われ、生命の尊厳を脅かしています。
干ばつの影響を受けた地域では、政府や市民団体からの支援が必要不可欠です。支援がなければ、コミュニティー自体が生き残れないという危機に直面しています。
アマゾン創価研究所では、企業や機関と協力し、干ばつ被害に遭った川沿いの集落に対して「アグアス・デ・アジュリ」という支援活動を実施しました。アジュリとは、先住民の言葉で「力を合わせる」という意味です。
これまで深刻な被害に見舞われた集落に、浄水器や食品、子どもたちが遊べるおもちゃを届けることができました。特に企業などの機関と地域コミュニティーを結ぶという点において、研究所は一定の役割を果たしてきました。

干ばつ被害に遭ったイランドゥーバ市内の集落で実施された支援活動「アグアス・デ・アジュリ」(昨年10月)
干ばつ被害に遭ったイランドゥーバ市内の集落で実施された支援活動「アグアス・デ・アジュリ」(昨年10月)
――そうしたアマゾン創価研究所の活動は、社会でどのように評価されていますか?
私たちの研究所は、ブラジル北部のアマゾナス州マナウス市郊外にありますが、少しずつブラジル社会全体の信頼を得ています。多くの企業や政府機関が研究所を訪れ、環境保護のためのパートナーシップを結ぶことが増えてきました。特に、環境教育に力を入れており、人々の行動を変えることが持続可能な社会を築く鍵だと信じています。
本年11月には気候変動対策の会議「COP30」がブラジルのベレンで開催される予定となっており、研究所としても議論に貢献できるよう準備を進めています。
――気候変動問題の解決に向けて、私たちはどのように行動を起こしていくべきでしょうか。
状況打開に向けた変化は、一人一人の行動の変化から始まると思っています。もちろん個人の努力に頼るだけで問題が解決するほど気候変動は容易な課題ではありませんが、個人の行動、とりわけ若い世代の行動が、やがて多くの人を巻き込む継続的な変化につながると確信します。
「家庭や地域でゴミの分別やリサイクルをすること」「物を大切にし、長く使用すること」「再利用可能な製品を使うこと」など、できることから今いる場所で行動を起こしていくことが大事だと思います。
――そうしたアマゾン創価研究所の活動は、社会でどのように評価されていますか?
私たちの研究所は、ブラジル北部のアマゾナス州マナウス市郊外にありますが、少しずつブラジル社会全体の信頼を得ています。多くの企業や政府機関が研究所を訪れ、環境保護のためのパートナーシップを結ぶことが増えてきました。特に、環境教育に力を入れており、人々の行動を変えることが持続可能な社会を築く鍵だと信じています。
本年11月には気候変動対策の会議「COP30」がブラジルのベレンで開催される予定となっており、研究所としても議論に貢献できるよう準備を進めています。
――気候変動問題の解決に向けて、私たちはどのように行動を起こしていくべきでしょうか。
状況打開に向けた変化は、一人一人の行動の変化から始まると思っています。もちろん個人の努力に頼るだけで問題が解決するほど気候変動は容易な課題ではありませんが、個人の行動、とりわけ若い世代の行動が、やがて多くの人を巻き込む継続的な変化につながると確信します。
「家庭や地域でゴミの分別やリサイクルをすること」「物を大切にし、長く使用すること」「再利用可能な製品を使うこと」など、できることから今いる場所で行動を起こしていくことが大事だと思います。

アマゾン創価研究所が地元団体と協力して推進する植樹活動(2020年3月)
アマゾン創価研究所が地元団体と協力して推進する植樹活動(2020年3月)
音声読み上げ