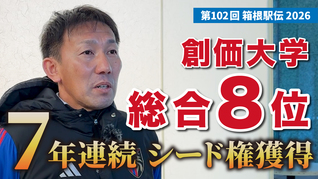〈健康PLUS〉 流行するインフルエンザや新型コロナ、マイコプラズマ肺炎を防ぐには
〈健康PLUS〉 流行するインフルエンザや新型コロナ、マイコプラズマ肺炎を防ぐには
2025年1月11日
日本感染症学会インフルエンザ委員会委員長
倉敷中央病院副院長
石田直さん
日本感染症学会インフルエンザ委員会委員長
倉敷中央病院副院長
石田直さん
今冬、インフルエンザの患者数は現行の統計開始以降、最多になっています。新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)やマイコプラズマ肺炎も流行し、三つの感染症が同時流行する「トリプルデミック」に注意が必要です。感染症対策について、日本感染症学会インフルエンザ委員会委員長で倉敷中央病院副院長の石田直さんに聞きました。
今冬、インフルエンザの患者数は現行の統計開始以降、最多になっています。新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)やマイコプラズマ肺炎も流行し、三つの感染症が同時流行する「トリプルデミック」に注意が必要です。感染症対策について、日本感染症学会インフルエンザ委員会委員長で倉敷中央病院副院長の石田直さんに聞きました。
気の緩みや集団免疫の低下
気の緩みや集団免疫の低下
空気の乾燥などから冬は感染症リスクが高まりますが、「インフルエンザ」「マイコプラズマ肺炎」「新型コロナ」の三つが同時流行するのは初めてのことです。
2023年春に新型コロナが感染症法の5類に移行して、徐々に「手洗い」や「マスクの着用」などの感染対策の意識が低下してきた“気の緩み”が影響していると考えられます。
マイコプラズマ肺炎の流行については、「集団免疫の低下」も要因の一つです。「集団免疫」とは、ある病原体に対して、免疫を持つ人が一定の割合になると、その感染症が拡がりにくくなることです。
コロナ禍の間、マイコプラズマ肺炎を含む呼吸器感染症は、おしなべて減りました。その結果、免疫を持っていない人が増えて、今回の流行につながったと思われます。
空気の乾燥などから冬は感染症リスクが高まりますが、「インフルエンザ」「マイコプラズマ肺炎」「新型コロナ」の三つが同時流行するのは初めてのことです。
2023年春に新型コロナが感染症法の5類に移行して、徐々に「手洗い」や「マスクの着用」などの感染対策の意識が低下してきた“気の緩み”が影響していると考えられます。
マイコプラズマ肺炎の流行については、「集団免疫の低下」も要因の一つです。「集団免疫」とは、ある病原体に対して、免疫を持つ人が一定の割合になると、その感染症が拡がりにくくなることです。
コロナ禍の間、マイコプラズマ肺炎を含む呼吸器感染症は、おしなべて減りました。その結果、免疫を持っていない人が増えて、今回の流行につながったと思われます。
過去最多のインフルエンザ
過去最多のインフルエンザ
現在、最も感染者が多いのはインフルエンザです。昨シーズンも流行しましたが、例年とは異なるパターンでした。今シーズンは12月から急増し過去最多となり、コロナ禍以前の流行パターンに戻ってきた印象です。
症状は、発熱や咳、鼻水などに加えて、風邪と違い、頭痛や関節痛、筋肉痛などの全身症状が強いのが特徴です。高齢者や基礎疾患がある人は、重症化リスクが高く、子どもは脳症になることもあります。
抗インフルエンザ薬は、発症後48時間以内に服用する必要があり、早期受診、早期治療が原則です。
インフルエンザには複数の種類があり、今流行しているのは初期に見られるA型です。昨シーズンは2月に日本でB型の流行が見られました。A型とB型の症状に大きな違いはないと考えて問題ありません。
ワクチンには感染と重症化の両方を防ぐ効果があります。接種してから免疫ができるまで2~3週間かかりますので、これから接種する場合は2月に流行するかもしれないB型のインフルエンザの予防に有効です。
現在、最も感染者が多いのはインフルエンザです。昨シーズンも流行しましたが、例年とは異なるパターンでした。今シーズンは12月から急増し過去最多となり、コロナ禍以前の流行パターンに戻ってきた印象です。
症状は、発熱や咳、鼻水などに加えて、風邪と違い、頭痛や関節痛、筋肉痛などの全身症状が強いのが特徴です。高齢者や基礎疾患がある人は、重症化リスクが高く、子どもは脳症になることもあります。
抗インフルエンザ薬は、発症後48時間以内に服用する必要があり、早期受診、早期治療が原則です。
インフルエンザには複数の種類があり、今流行しているのは初期に見られるA型です。昨シーズンは2月に日本でB型の流行が見られました。A型とB型の症状に大きな違いはないと考えて問題ありません。
ワクチンには感染と重症化の両方を防ぐ効果があります。接種してから免疫ができるまで2~3週間かかりますので、これから接種する場合は2月に流行するかもしれないB型のインフルエンザの予防に有効です。
若年者に多いマイコプラズマ
若年者に多いマイコプラズマ
昨年から、マイコプラズマ肺炎も過去最多レベルで流行しています。全国的にはピークは過ぎましたが、いまだ高水準であり、警戒が必要です。主な症状は、発熱や咳、頭痛、下痢、全身のけん怠感です。子どもや10~20代への感染が多く、潜伏期間が長く、解熱後も咳が長期間続くのが特徴です。
以前は、4年に1回程度の頻度で流行していたので“オリンピック肺炎”といわれていました。流行して4年ほどで集団免疫が低下し、再び流行するのを繰り返します。最後に流行したのは16年です。20年は新型コロナの影響で全く見られませんでした。この間、免疫を持たない人が増加し、過去最多の流行につながったと考えられます。
特に、コロナ禍の間は感染者が全くいなかったため、3歳までの子どもは曝露されておらず、感染するリスクが非常に高いと考えてください。逆に、高齢者は、過去に罹患した経験を持つ人が多く、ある程度の免疫ができているため、感染リスクは低いでしょう。
治療に使用される薬は、通常「マクロライド系」という抗菌薬ですが、最近、マクロライド系に耐性を持つマイコプラズマ菌(耐性菌)が増えています。薬を服用しても、効果が表れない場合は、他の抗菌薬について、かかりつけ医に相談してみてもいいでしょう。
昨年から、マイコプラズマ肺炎も過去最多レベルで流行しています。全国的にはピークは過ぎましたが、いまだ高水準であり、警戒が必要です。主な症状は、発熱や咳、頭痛、下痢、全身のけん怠感です。子どもや10~20代への感染が多く、潜伏期間が長く、解熱後も咳が長期間続くのが特徴です。
以前は、4年に1回程度の頻度で流行していたので“オリンピック肺炎”といわれていました。流行して4年ほどで集団免疫が低下し、再び流行するのを繰り返します。最後に流行したのは16年です。20年は新型コロナの影響で全く見られませんでした。この間、免疫を持たない人が増加し、過去最多の流行につながったと考えられます。
特に、コロナ禍の間は感染者が全くいなかったため、3歳までの子どもは曝露されておらず、感染するリスクが非常に高いと考えてください。逆に、高齢者は、過去に罹患した経験を持つ人が多く、ある程度の免疫ができているため、感染リスクは低いでしょう。
治療に使用される薬は、通常「マクロライド系」という抗菌薬ですが、最近、マクロライド系に耐性を持つマイコプラズマ菌(耐性菌)が増えています。薬を服用しても、効果が表れない場合は、他の抗菌薬について、かかりつけ医に相談してみてもいいでしょう。
増加傾向の新型コロナ
増加傾向の新型コロナ
新型コロナは、例年の傾向を見ると、年に2回流行しています。昨年7月に、第11波が発生しました。第12波は1~2月ごろだといわれています。実際に、5週連続で感染者数が増加しており、今後ピークを迎える可能性があります。流行初期に比べると治療薬がありますが、後遺症をもたらしたり、重症化すると命に関わったりする感染症であることを忘れないでほしいと思います。
複数の感染症が同時に流行すると、一つの感染症にかかって、体力が弱ったところに、また別の感染症にかかってしまう「感染症ドミノ」のリスクが高まります。インフルエンザの後に新型コロナにかかったり、インフルエンザA型の後にB型にかかったりする場合もあります。新型コロナとインフルエンザなどを同時に感染する人もいます。「感染症ドミノ」を防ぐには、感染症の病み上がりに無理をしないことが大切です。
新型コロナは、例年の傾向を見ると、年に2回流行しています。昨年7月に、第11波が発生しました。第12波は1~2月ごろだといわれています。実際に、5週連続で感染者数が増加しており、今後ピークを迎える可能性があります。流行初期に比べると治療薬がありますが、後遺症をもたらしたり、重症化すると命に関わったりする感染症であることを忘れないでほしいと思います。
複数の感染症が同時に流行すると、一つの感染症にかかって、体力が弱ったところに、また別の感染症にかかってしまう「感染症ドミノ」のリスクが高まります。インフルエンザの後に新型コロナにかかったり、インフルエンザA型の後にB型にかかったりする場合もあります。新型コロナとインフルエンザなどを同時に感染する人もいます。「感染症ドミノ」を防ぐには、感染症の病み上がりに無理をしないことが大切です。
基本的かつ有効な対策とは
基本的かつ有効な対策とは
いずれの感染症も、感染ルートは「接触感染」と「飛沫」であり、基本的かつ有効な対策は「手洗い」と「マスク」です。手洗いのポイントや咳エチケットを紹介しますので、参考にしてください(別掲)。
帰宅時は、手洗いとともに「うがい」をする習慣を身に付けましょう。病院や電車の中など、混雑している場所に行く時にはマスクを着けることをおすすめします。家族でタオルを共用しない、小まめに換気することも効果的です。
発熱があるなど感染が疑われる場合は、基本的には発熱外来を受診してください。特に、高齢者や基礎疾患をお持ちの方、症状が強い方は、必ず受診しましょう。子どもに症状が出た場合、子ども医療電話相談「#8000」に電話し、看護師や医師に相談することもできます。
また、ネットやSNS上には、新型コロナなどに関する玉石混交の情報があふれています。発信者は感染症対策の専門家(医師や研究者)であるか、出典は公的機関かどうか等を確認し、デマ情報には気を付けてください。
いずれの感染症も、感染ルートは「接触感染」と「飛沫」であり、基本的かつ有効な対策は「手洗い」と「マスク」です。手洗いのポイントや咳エチケットを紹介しますので、参考にしてください(別掲)。
帰宅時は、手洗いとともに「うがい」をする習慣を身に付けましょう。病院や電車の中など、混雑している場所に行く時にはマスクを着けることをおすすめします。家族でタオルを共用しない、小まめに換気することも効果的です。
発熱があるなど感染が疑われる場合は、基本的には発熱外来を受診してください。特に、高齢者や基礎疾患をお持ちの方、症状が強い方は、必ず受診しましょう。子どもに症状が出た場合、子ども医療電話相談「#8000」に電話し、看護師や医師に相談することもできます。
また、ネットやSNS上には、新型コロナなどに関する玉石混交の情報があふれています。発信者は感染症対策の専門家(医師や研究者)であるか、出典は公的機関かどうか等を確認し、デマ情報には気を付けてください。
《手洗いのポイント》
《手洗いのポイント》
●せっけんを泡立て、15~20秒以上洗う(「うさぎとかめ」を1回、または「ハッピーバースデートゥーユー」を2回歌う時間が目安)
●洗い残しやすい爪の周囲、指と指の間、手首を意識する
●タオルで十分拭いて乾燥させる(ぬれたままだと細菌が増加する)
●手洗いができない時は、消毒用アルコールを手に擦り込む
●せっけんを泡立て、15~20秒以上洗う(「うさぎとかめ」を1回、または「ハッピーバースデートゥーユー」を2回歌う時間が目安)
●洗い残しやすい爪の周囲、指と指の間、手首を意識する
●タオルで十分拭いて乾燥させる(ぬれたままだと細菌が増加する)
●手洗いができない時は、消毒用アルコールを手に擦り込む
こんな時に・・・
こんな時に・・・
・帰宅後
・食事を準備する前後
・食前
・生ごみを扱った後
・鼻をかんだ後、咳やくしゃみを手で受けた後
・用便後
・幼児のおむつ替え後や、用便の後始末後
・病気の人の世話をする前後
・傷の処置をする前後
・ペットあるいはペットの排せつ物に触れた後
・ペットの食物や用具を扱った後
・帰宅後
・食事を準備する前後
・食前
・生ごみを扱った後
・鼻をかんだ後、咳やくしゃみを手で受けた後
・用便後
・幼児のおむつ替え後や、用便の後始末後
・病気の人の世話をする前後
・傷の処置をする前後
・ペットあるいはペットの排せつ物に触れた後
・ペットの食物や用具を扱った後
《咳エチケット》
《咳エチケット》
●マスクをする。鼻と口を覆い、顔にフィットさせるのがポイント
●ティッシュペーパーで鼻や口を覆い、使用後のティッシュペーパーはごみ箱に捨てる
●ティッシュペーパーを持っていない時は、鼻や口を手ではなく服の袖で押さえる
●鼻や口の分泌物が手に付いたら、すぐに手洗いする
●マスクをする。鼻と口を覆い、顔にフィットさせるのがポイント
●ティッシュペーパーで鼻や口を覆い、使用後のティッシュペーパーはごみ箱に捨てる
●ティッシュペーパーを持っていない時は、鼻や口を手ではなく服の袖で押さえる
●鼻や口の分泌物が手に付いたら、すぐに手洗いする
いしだ・ただし 日本感染症学会インフルエンザ委員会委員長。同学会専門医・指導医。倉敷中央病院副院長。1984年、京都大学医学部卒業。同大学臨床教授。日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医。日本呼吸器学会専門医・指導医。日本アレルギー学会専門医。
いしだ・ただし 日本感染症学会インフルエンザ委員会委員長。同学会専門医・指導医。倉敷中央病院副院長。1984年、京都大学医学部卒業。同大学臨床教授。日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医。日本呼吸器学会専門医・指導医。日本アレルギー学会専門医。
※イメージ写真はPIXTA
取り上げてほしいテーマなど、ご意見・ご要望をお寄せください
↓↓
dokusha@seikyo-np.jp
※イメージ写真はPIXTA
取り上げてほしいテーマなど、ご意見・ご要望をお寄せください
↓↓
dokusha@seikyo-np.jp