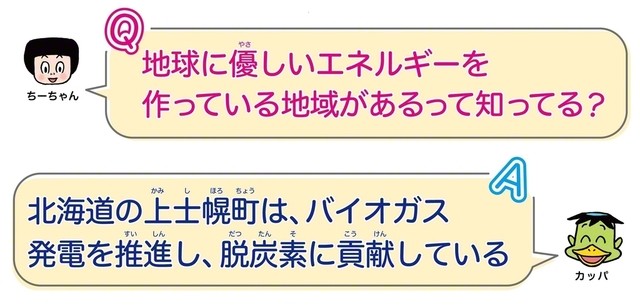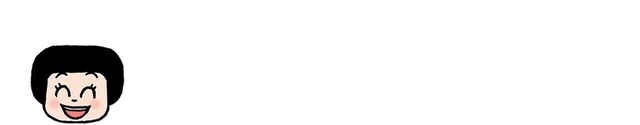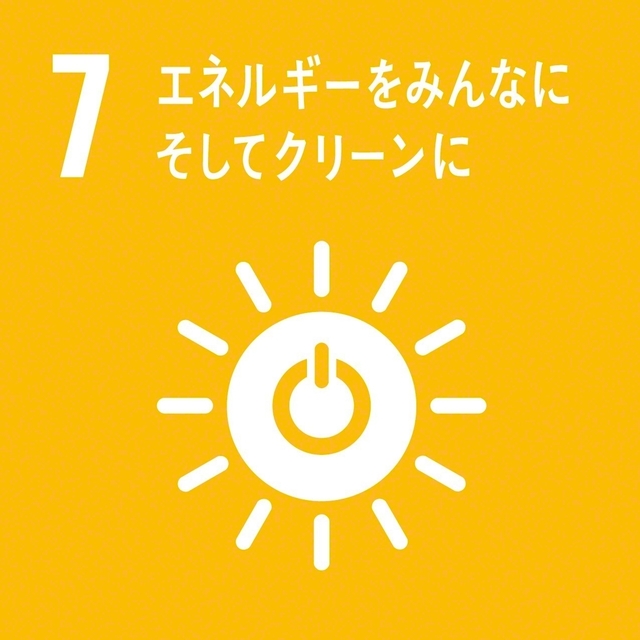〈SDGs×SEIKYO〉 事例編 北海道・上士幌町 牛のふん尿を資源に、環境に配慮した電気を創出
〈SDGs×SEIKYO〉 事例編 北海道・上士幌町 牛のふん尿を資源に、環境に配慮した電気を創出
2025年7月20日
「SDGs×SEIKYO」の事例編「ちーちゃんと訪ねる ミライの現場」。今回は北海道・上士幌町の取り組みを紹介します。同町は、第4回「ジャパンSDGsアワード」でSDGs推進副本部長賞(内閣官房長官賞)を受賞。2021年には、「SDGs未来都市」に選定されています。
「SDGs×SEIKYO」の事例編「ちーちゃんと訪ねる ミライの現場」。今回は北海道・上士幌町の取り組みを紹介します。同町は、第4回「ジャパンSDGsアワード」でSDGs推進副本部長賞(内閣官房長官賞)を受賞。2021年には、「SDGs未来都市」に選定されています。
父さんから、地球に優しいクリーンエネルギーを作っている町があるって聞いたんだ。カッパさんは知ってる?
父さんから、地球に優しいクリーンエネルギーを作っている町があるって聞いたんだ。カッパさんは知ってる?
北海道の上士幌町では、牛のふん尿を活用して、バイオガス発電を行っているよ。
北海道の上士幌町では、牛のふん尿を活用して、バイオガス発電を行っているよ。
そうなんだ! 作られた電気はどうやって使われているの?
そうなんだ! 作られた電気はどうやって使われているの?
地元の電力会社を通して、町内の一般家庭などに供給されているんだ。とても画期的な取り組みだよ。
地元の電力会社を通して、町内の一般家庭などに供給されているんだ。とても画期的な取り組みだよ。
豊かな大自然
豊かな大自然
見渡す限り続く“緑の地平線”。ここは、日本一広い公共牧場として名高い、北海道・上士幌町の「ナイタイ高原牧場」。東京ドーム358個分の面積を誇る。
見渡す限り続く“緑の地平線”。ここは、日本一広い公共牧場として名高い、北海道・上士幌町の「ナイタイ高原牧場」。東京ドーム358個分の面積を誇る。

約4700人が暮らす北海道・上士幌町。大自然の恵みを生かした酪農や農業が盛んなほか、温泉やスキー場などのレジャースポットを求めて、多くの観光客が訪れる
約4700人が暮らす北海道・上士幌町。大自然の恵みを生かした酪農や農業が盛んなほか、温泉やスキー場などのレジャースポットを求めて、多くの観光客が訪れる
ドライブルートを車で上っていくと、なだらかな斜面に牛たちの姿が。水飲み場でゆっくりと水を飲んだり、横になったりしている。
ドライブルートを車で上っていくと、なだらかな斜面に牛たちの姿が。水飲み場でゆっくりと水を飲んだり、横になったりしている。

ナイタイ高原牧場から、十勝平野を望む。頂上付近にある展望施設「ナイタイテラス」では、景色を楽しめるほか、食事や土産物も購入もできる
ナイタイ高原牧場から、十勝平野を望む。頂上付近にある展望施設「ナイタイテラス」では、景色を楽しめるほか、食事や土産物も購入もできる
北海道の十勝地方北部、日本最大級の国立公園「大雪山国立公園」の東の山麓に位置する上士幌町は、豊かな自然とともに発展してきた。じゃがいも、豆類、長芋をはじめ、豊富な種類の農作物が収穫され、食料自給率は3149%(2023年度)。さらに酪農が盛んな地域でもあり、人口約4700人に対し、牛は約3万7000頭。およそ8倍の頭数を誇る。
北海道の十勝地方北部、日本最大級の国立公園「大雪山国立公園」の東の山麓に位置する上士幌町は、豊かな自然とともに発展してきた。じゃがいも、豆類、長芋をはじめ、豊富な種類の農作物が収穫され、食料自給率は3149%(2023年度)。さらに酪農が盛んな地域でもあり、人口約4700人に対し、牛は約3万7000頭。およそ8倍の頭数を誇る。

農業が盛んな上士幌町では、あちこちに畑が広がる
農業が盛んな上士幌町では、あちこちに畑が広がる
――総面積の約76%を森林が占める上士幌町は、かつては林業で栄えていた。昭和30年代前半に、人口が約1万3600人となったが、林業の衰退と鉄道の廃止等により、減少に転じていく。人口が4884人となった2014年には、民間の有識者会議が定義する「消滅可能性自治体(今後30年間で20~39歳の女性人口が半減し、消滅する可能性がある自治体)」のリストに入った。
――総面積の約76%を森林が占める上士幌町は、かつては林業で栄えていた。昭和30年代前半に、人口が約1万3600人となったが、林業の衰退と鉄道の廃止等により、減少に転じていく。人口が4884人となった2014年には、民間の有識者会議が定義する「消滅可能性自治体(今後30年間で20~39歳の女性人口が半減し、消滅する可能性がある自治体)」のリストに入った。
住みやすい町づくり
住みやすい町づくり
翌15年、同町は人口減少対策と地方創生に向けた5カ年計画「第Ⅰ期地方創生」を開始する。取り組みには、ふるさと納税を原資として活用。「子育て・教育・文化」「交流・移住・定住促進」「医療・福祉・安心」の三つを柱に、誰もが住みやすい町づくりを推し進める。
翌15年、同町は人口減少対策と地方創生に向けた5カ年計画「第Ⅰ期地方創生」を開始する。取り組みには、ふるさと納税を原資として活用。「子育て・教育・文化」「交流・移住・定住促進」「医療・福祉・安心」の三つを柱に、誰もが住みやすい町づくりを推し進める。

複数の企業がスペースを共有する「かみしほろシェアオフィス」。テレワークやワーケーションなど、多様な働き方を推進している
複数の企業がスペースを共有する「かみしほろシェアオフィス」。テレワークやワーケーションなど、多様な働き方を推進している
同年4月には全国に先駆けて、認定こども園の保育料を無償化。中学生以下の子どもがいる家庭が新築マイホームを購入する際には、子ども1人当たり100万円を助成する「子育て住宅建設助成事業」も行った。
さらに、移住希望者向けの生活体験住宅を用意したり、ふるさと納税寄付者との交流会を東京で行ったりするなど、町の魅力を多角的に発信した。
多彩な施策を推進する中で、年を追うごとに若年層を含む移住者が増え、人口は増加に転じる。昨年4月には、「消滅可能性自治体」のリストから外れ、十勝管内の市町村の中で、「若年女性人口減少率」が、最も低い自治体となった。
同年4月には全国に先駆けて、認定こども園の保育料を無償化。中学生以下の子どもがいる家庭が新築マイホームを購入する際には、子ども1人当たり100万円を助成する「子育て住宅建設助成事業」も行った。
さらに、移住希望者向けの生活体験住宅を用意したり、ふるさと納税寄付者との交流会を東京で行ったりするなど、町の魅力を多角的に発信した。
多彩な施策を推進する中で、年を追うごとに若年層を含む移住者が増え、人口は増加に転じる。昨年4月には、「消滅可能性自治体」のリストから外れ、十勝管内の市町村の中で、「若年女性人口減少率」が、最も低い自治体となった。

地域住民参加型のまちづくりを担う「株式会社 生涯活躍のまち かみしほろ」が拠点とする「hareta(ハレタ)上士幌」。同社では、起業家育成の講座や無料職業紹介、スマートフォンの操作についての相談窓口など、住民が生涯にわたって生き生きと暮らせるまちづくりに資する事業を幅広く行っている
地域住民参加型のまちづくりを担う「株式会社 生涯活躍のまち かみしほろ」が拠点とする「hareta(ハレタ)上士幌」。同社では、起業家育成の講座や無料職業紹介、スマートフォンの操作についての相談窓口など、住民が生涯にわたって生き生きと暮らせるまちづくりに資する事業を幅広く行っている
第Ⅰ期地方創生で議論された課題の一つに、家畜ふん尿の適正処理があった。牛から毎日排出されるふん尿は、1頭当たり約60キロ。これらの処理は、酪農家の負担となり、悪臭の原因にもなっていた。
第Ⅰ期地方創生で議論された課題の一つに、家畜ふん尿の適正処理があった。牛から毎日排出されるふん尿は、1頭当たり約60キロ。これらの処理は、酪農家の負担となり、悪臭の原因にもなっていた。

日本一広い公共牧場・ナイタイ高原牧場。最上部は標高約800メートルに位置し、十勝平野などが一望できるテラスが設置されている
日本一広い公共牧場・ナイタイ高原牧場。最上部は標高約800メートルに位置し、十勝平野などが一望できるテラスが設置されている
同町は農業関係者で組織する協議会で適正処理を巡る調査研究をはじめ、17年度から、バイオガスプラントの整備に着手。資源循環型農業実現への取り組みを始めた。
まず牛などから出たふん尿を、バイオガスプラントで、ゆっくりと発酵させる。その過程で発生したメタンガスで、ガスエンジンを回して発電し、電力に変える。発酵後のふん尿の固形物は家畜の寝わらとなる。液体分は液肥となって、畑などにまかれる。その畑でできた飼料を再び牛が食べると、地域内で完結する資源循環型農業が成立する。なお、余剰ガスはハウス栽培にも使われている。
同町は農業関係者で組織する協議会で適正処理を巡る調査研究をはじめ、17年度から、バイオガスプラントの整備に着手。資源循環型農業実現への取り組みを始めた。
まず牛などから出たふん尿を、バイオガスプラントで、ゆっくりと発酵させる。その過程で発生したメタンガスで、ガスエンジンを回して発電し、電力に変える。発酵後のふん尿の固形物は家畜の寝わらとなる。液体分は液肥となって、畑などにまかれる。その畑でできた飼料を再び牛が食べると、地域内で完結する資源循環型農業が成立する。なお、余剰ガスはハウス栽培にも使われている。

上士幌町内にあるバイオガスプラント
上士幌町内にあるバイオガスプラント
現在、計7基が運用されており、発電した電力の一部は、地域商社を通して、町内に供給されている。バイオガス発電の総発電量は、町内の全ての一般家庭や主要施設をまかなえるものであり、地産地消の再生可能エネルギーとして、注目を集める。
現在、計7基が運用されており、発電した電力の一部は、地域商社を通して、町内に供給されている。バイオガス発電の総発電量は、町内の全ての一般家庭や主要施設をまかなえるものであり、地産地消の再生可能エネルギーとして、注目を集める。

上士幌町内には、牛の飼料となるデントコーンや、じゃがいもなどの畑が、あちこちに広がる
上士幌町内には、牛の飼料となるデントコーンや、じゃがいもなどの畑が、あちこちに広がる
特色光る取り組み
特色光る取り組み
第Ⅰ期の取り組みは、実質、持続可能なまちづくりそのものとなり、SDGs推進の大きな足がかりとなった。
20年度から始まった同町の「第Ⅱ期地方創生」では、取り組みの五つの柱に、SDGsを関連付けた。
第Ⅰ期の取り組みは、実質、持続可能なまちづくりそのものとなり、SDGs推進の大きな足がかりとなった。
20年度から始まった同町の「第Ⅱ期地方創生」では、取り組みの五つの柱に、SDGsを関連付けた。

2020年5月に誕生した「道の駅 かみしほろ」。天井が高く、開放的な施設内には、地元の食材を使ったレストランやベーカリーなどがあり、レンタサイクルやドッグランも併設されている
2020年5月に誕生した「道の駅 かみしほろ」。天井が高く、開放的な施設内には、地元の食材を使ったレストランやベーカリーなどがあり、レンタサイクルやドッグランも併設されている
上士幌町ゼロカーボン推進課の木川陽介さんは、次のように語る。
「町として新たにSDGsに取り組むというよりも、それぞれの施策にSDGsの視点を取り入れて深め、より価値を高めていくという方針で、まちづくりを推進してきました」
上士幌町ゼロカーボン推進課の木川陽介さんは、次のように語る。
「町として新たにSDGsに取り組むというよりも、それぞれの施策にSDGsの視点を取り入れて深め、より価値を高めていくという方針で、まちづくりを推進してきました」

上士幌町の交通ターミナル。バスの停留所のほか、実証実験中の自動運転バスの発着点等にもなっている
上士幌町の交通ターミナル。バスの停留所のほか、実証実験中の自動運転バスの発着点等にもなっている
ここにも、町独自の特色ある取り組みが光る。
その一つが、自動運転バスの実用化に向けた取り組みだ。マイカーを手放した高齢者や交通・物流事業者の不足などの課題解決に向けて、ICT(情報通信技術)を利用した未来の移動サービス「MaaS(マース)」の活用を目指している。22年12月からは、町内の市街地を周遊する自動運転バスの定期運行を無料で開始。実証実験を積み重ねている。
また、ドローンを活用した新聞の定期配送や、買い物代行の実証などが行われており、省人化と脱炭素化を同時に進めながら、物流の最適化を行っている。
ここにも、町独自の特色ある取り組みが光る。
その一つが、自動運転バスの実用化に向けた取り組みだ。マイカーを手放した高齢者や交通・物流事業者の不足などの課題解決に向けて、ICT(情報通信技術)を利用した未来の移動サービス「MaaS(マース)」の活用を目指している。22年12月からは、町内の市街地を周遊する自動運転バスの定期運行を無料で開始。実証実験を積み重ねている。
また、ドローンを活用した新聞の定期配送や、買い物代行の実証などが行われており、省人化と脱炭素化を同時に進めながら、物流の最適化を行っている。

町の市街地を走る自動運転バス
町の市街地を走る自動運転バス
こうしたまちづくりが評価され、上士幌町は「SDGs未来都市」(21年)、「脱炭素先行地域」(22年)に選定されている。
竹中貢町長は、「町の皆さんが地域特性を生かして、努力を重ねる中で、ハイレベルなSDGsの取り組みになっていったと実感しています。グローバルな取り組みをローカルな視点で推進していく。その先頭に立っていくとの思いで、これからも町を挙げてSDGsに挑戦していきます」と。
上士幌町の人々は、地域の“得意分野”を生かし、持続可能な社会の実現へ、大きく歩みを進めている。
こうしたまちづくりが評価され、上士幌町は「SDGs未来都市」(21年)、「脱炭素先行地域」(22年)に選定されている。
竹中貢町長は、「町の皆さんが地域特性を生かして、努力を重ねる中で、ハイレベルなSDGsの取り組みになっていったと実感しています。グローバルな取り組みをローカルな視点で推進していく。その先頭に立っていくとの思いで、これからも町を挙げてSDGsに挑戦していきます」と。
上士幌町の人々は、地域の“得意分野”を生かし、持続可能な社会の実現へ、大きく歩みを進めている。

気球の形状をした電灯。上士幌町では1974年から、熱気球の大会「バルーンフェスティバル」が行われ、多くの観光客が訪れる
気球の形状をした電灯。上士幌町では1974年から、熱気球の大会「バルーンフェスティバル」が行われ、多くの観光客が訪れる
この取り組みに関わるSDGsの主な目標
この取り組みに関わるSDGsの主な目標
ご感想をお寄せください
sdgs@seikyo-np.jp
聖教電子版の「SDGs」特集ページが閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html
ご感想をお寄せください
sdgs@seikyo-np.jp
聖教電子版の「SDGs」特集ページが閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html
音声読み上げ