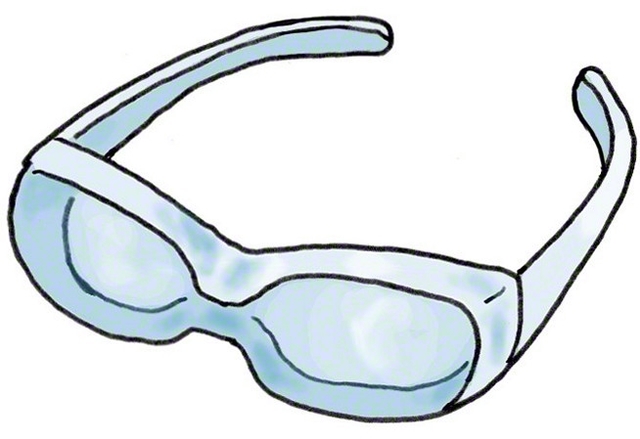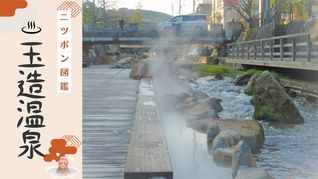〈健康PLUS〉 花粉症を軽減させるために
〈健康PLUS〉 花粉症を軽減させるために
2025年2月15日
日本医科大学大学院教授
大久保公裕さん
日本医科大学大学院教授
大久保公裕さん
くしゃみに鼻水、目のかゆみ……。つらい花粉症のシーズンになりました。今年は例年より飛散量が多いと予測されており、万全な対策が求められます。花粉症対策の第一人者である日本医科大学大学院教授の大久保公裕さんに、快適な春を過ごすためのヒントを聞きました。
くしゃみに鼻水、目のかゆみ……。つらい花粉症のシーズンになりました。今年は例年より飛散量が多いと予測されており、万全な対策が求められます。花粉症対策の第一人者である日本医科大学大学院教授の大久保公裕さんに、快適な春を過ごすためのヒントを聞きました。
春に多い理由
春に多い理由
日本ではほぼ1年を通し、何らかの植物の花粉が飛散しています。
中でも、スギ花粉の飛散量が最も多く、耳鼻咽喉科医とその家族を対象にした全国的な調査によると38・8%がスギ花粉症であることが分かっています(2019年)。
戦後、森林管理や木材資材に有用であることから、日本政府はスギを植え続けてきました。現在、全国の人工林の44%がスギ林(国土面積の12%)になっており、大量の花粉が飛散しているのです。
スギ花粉は、日本の各地で2月下旬から3月下旬にかけて飛散のピークを迎え、その後、ヒノキ花粉が4月上旬までピークを迎えます。5月上旬に、スギとヒノキ花粉の飛散は終息します。
スギ花粉症の多くの方はヒノキ花粉症ともいわれており、2月中旬から5月上旬まで花粉症に悩まされている方が多い実態があります。
日本ではほぼ1年を通し、何らかの植物の花粉が飛散しています。
中でも、スギ花粉の飛散量が最も多く、耳鼻咽喉科医とその家族を対象にした全国的な調査によると38・8%がスギ花粉症であることが分かっています(2019年)。
戦後、森林管理や木材資材に有用であることから、日本政府はスギを植え続けてきました。現在、全国の人工林の44%がスギ林(国土面積の12%)になっており、大量の花粉が飛散しているのです。
スギ花粉は、日本の各地で2月下旬から3月下旬にかけて飛散のピークを迎え、その後、ヒノキ花粉が4月上旬までピークを迎えます。5月上旬に、スギとヒノキ花粉の飛散は終息します。
スギ花粉症の多くの方はヒノキ花粉症ともいわれており、2月中旬から5月上旬まで花粉症に悩まされている方が多い実態があります。
感作と発症
感作と発症
花粉症は「季節性アレルギー性鼻炎」とも呼ばれていますが、なぜ発症するのでしょうか。そのメカニズムは大きく「感作」と「発症」の2段階に分かれます。
花粉(アレルゲン)が鼻や目、口に入ると、体の免疫システムが、花粉を「異物」と認識して抗体を作り、鼻や目、口などの粘膜にくっつきます。これを「感作」といいます。その後、再び、花粉が鼻や目、口に侵入すると、本来、人間に害を及ぼすものでないのにもかかわらず、抗体が反応してしまい、くしゃみや鼻水などで花粉を外に追い出そうとします。これが「発症」の段階です。
春はスギ、ヒノキ、夏はイネ科植物、秋はブタクサなどの花粉が飛散し、それぞれの花粉症が存在します。症状の出方や強さは個人によって違いはありますが、目のかゆみ、鼻水や鼻づまり、くしゃみなど、花粉の種類による症状に違いはありません。
そして、何らかの花粉が飛散している地域に住んでいる人であれば、誰でも花粉症になるリスクがあります。
花粉症は「季節性アレルギー性鼻炎」とも呼ばれていますが、なぜ発症するのでしょうか。そのメカニズムは大きく「感作」と「発症」の2段階に分かれます。
花粉(アレルゲン)が鼻や目、口に入ると、体の免疫システムが、花粉を「異物」と認識して抗体を作り、鼻や目、口などの粘膜にくっつきます。これを「感作」といいます。その後、再び、花粉が鼻や目、口に侵入すると、本来、人間に害を及ぼすものでないのにもかかわらず、抗体が反応してしまい、くしゃみや鼻水などで花粉を外に追い出そうとします。これが「発症」の段階です。
春はスギ、ヒノキ、夏はイネ科植物、秋はブタクサなどの花粉が飛散し、それぞれの花粉症が存在します。症状の出方や強さは個人によって違いはありますが、目のかゆみ、鼻水や鼻づまり、くしゃみなど、花粉の種類による症状に違いはありません。
そして、何らかの花粉が飛散している地域に住んでいる人であれば、誰でも花粉症になるリスクがあります。
低年齢化の実態
低年齢化の実態
患者数が年々、増加傾向にあるとともに、発症者の低年齢化も進んでいます。
ロート製薬が実施した調査では、全国の小中学生の約48%が花粉症を実感していることが明らかになっています(昨年12月調べ)。
山梨県が最も高い67・6%で、群馬県、静岡県、岐阜県、東京都、三重県でも60%以上の小中学生が花粉症を実感しているといいます。
患者が増えていたり、低年齢化が進んでいたりする理由は飛散量が増えていることの他に、食生活の偏りや運動不足などの生活習慣も影響していると見ています。
例えば、子どもが外で遊ぶ時間が減ることは、さまざまな細菌に触れる機会が減ることでもあります。すると、体内の免疫機能が低下し、全く病原体を持たない花粉に対してアレルギー反応が出てしまうことにつながります。
花粉症を防いだり、症状を緩和させたりするには、生活習慣を見直すことが一つの対策です。また当然、発症した場合は適切な治療が欠かせません。
例えば、免疫療法で、完治に近づけることもできます。
その一つに舌下免疫療法があります。舌の下から少量ずつ、アレルギーの原因となる物質を取り込むことで根本的な体質改善につなげるものです(錠剤を舌下に含むだけで自宅で行える)。
毎日3年間ほど続ける必要があります。詳しくは医師に相談してください。
最後に、つらい症状を軽減させるセルフケアを紹介します(下記)。
患者数が年々、増加傾向にあるとともに、発症者の低年齢化も進んでいます。
ロート製薬が実施した調査では、全国の小中学生の約48%が花粉症を実感していることが明らかになっています(昨年12月調べ)。
山梨県が最も高い67・6%で、群馬県、静岡県、岐阜県、東京都、三重県でも60%以上の小中学生が花粉症を実感しているといいます。
患者が増えていたり、低年齢化が進んでいたりする理由は飛散量が増えていることの他に、食生活の偏りや運動不足などの生活習慣も影響していると見ています。
例えば、子どもが外で遊ぶ時間が減ることは、さまざまな細菌に触れる機会が減ることでもあります。すると、体内の免疫機能が低下し、全く病原体を持たない花粉に対してアレルギー反応が出てしまうことにつながります。
花粉症を防いだり、症状を緩和させたりするには、生活習慣を見直すことが一つの対策です。また当然、発症した場合は適切な治療が欠かせません。
例えば、免疫療法で、完治に近づけることもできます。
その一つに舌下免疫療法があります。舌の下から少量ずつ、アレルギーの原因となる物質を取り込むことで根本的な体質改善につなげるものです(錠剤を舌下に含むだけで自宅で行える)。
毎日3年間ほど続ける必要があります。詳しくは医師に相談してください。
最後に、つらい症状を軽減させるセルフケアを紹介します(下記)。
●セルフケア●
●セルフケア●
〈外出時〉
〈外出時〉
マスク
マスク
吸い込む花粉量を約3分の1から6分の1に減らすことができます。花粉症専用のマスクだと、約84%の花粉を防ぐことができます。ガーゼなどのインナーマスクも効果的です。
吸い込む花粉量を約3分の1から6分の1に減らすことができます。花粉症専用のマスクだと、約84%の花粉を防ぐことができます。ガーゼなどのインナーマスクも効果的です。
眼鏡
眼鏡
花粉対策用の眼鏡は通常のものより、防御性能が優れていて、98%もの花粉をカットできるものもあります。
花粉対策用の眼鏡は通常のものより、防御性能が優れていて、98%もの花粉をカットできるものもあります。
衣服
衣服
ポリエステルや綿など凹凸の少ない素材の衣服を着用する(特に上着)。
ポリエステルや綿など凹凸の少ない素材の衣服を着用する(特に上着)。
ガードスプレー
ガードスプレー
肌や髪の毛など露出している部分は、市販の花粉ガードスプレー(静電気の抑制、保湿効果)が有用です。
肌や髪の毛など露出している部分は、市販の花粉ガードスプレー(静電気の抑制、保湿効果)が有用です。
〈帰宅時〉
〈帰宅時〉
花粉を持ち込まない
花粉を持ち込まない
玄関に入る前に衣服やバッグ、髪の毛などについた花粉を払い落としましょう。上から順に行うと効果的です。衣服は粘着ローラーなどを使用すると、繊維の奥に入り込んだ花粉も取り除くことができます。
玄関に入る前に衣服やバッグ、髪の毛などについた花粉を払い落としましょう。上から順に行うと効果的です。衣服は粘着ローラーなどを使用すると、繊維の奥に入り込んだ花粉も取り除くことができます。
手洗い
手洗い
せっけんを使用して指先や爪の間、指の間などを30秒以上かけて洗います。
せっけんを使用して指先や爪の間、指の間などを30秒以上かけて洗います。
うがい
うがい
「ブクブクうがい」で口内の汚れを落とします。その後、10~15秒の「ガラガラうがい」で喉奥まで洗浄します。2回ほど行うといいでしょう。抗菌作用のある緑茶などを使用するとより効果的です。
「ブクブクうがい」で口内の汚れを落とします。その後、10~15秒の「ガラガラうがい」で喉奥まで洗浄します。2回ほど行うといいでしょう。抗菌作用のある緑茶などを使用するとより効果的です。
洗顔
洗顔
特に目元や鼻回りは花粉がたまりやすく、しっかりと洗い流します。30~35度程度のぬるま湯を使用するといいでしょう。
特に目元や鼻回りは花粉がたまりやすく、しっかりと洗い流します。30~35度程度のぬるま湯を使用するといいでしょう。
〈室内〉
〈室内〉
部屋干し
部屋干し
花粉症シーズンは洗濯物を室内に干すことをおすすめします。干す際は洗濯物同士の間隔をこぶし1個分以上空け、風通しを確保します。除湿器やエアコンの除湿機能を利用すると、乾燥時間を縮めることもできます。
花粉症シーズンは洗濯物を室内に干すことをおすすめします。干す際は洗濯物同士の間隔をこぶし1個分以上空け、風通しを確保します。除湿器やエアコンの除湿機能を利用すると、乾燥時間を縮めることもできます。
換気
換気
室内の換気は、花粉の飛散量が日中に多いことから、朝と晩に行うのがいいでしょう。朝と晩といっても交通量が少ないタイミングを選んでください。ただし、風が強い日は換気を控えた方が無難です。
室内の換気は、花粉の飛散量が日中に多いことから、朝と晩に行うのがいいでしょう。朝と晩といっても交通量が少ないタイミングを選んでください。ただし、風が強い日は換気を控えた方が無難です。
おおくぼ・きみひろ 博士(医学)。日本医科大学大学院医学研究科の頭頸部感覚器科学分野教授。日本アレルギー協会理事で、日本医科大学付属病院の耳鼻咽喉科部長。1988年に同大学大学院修了。その後、アメリカ国立衛生研究所留学などを経て現職。日本における花粉症治療の第一人者として活躍する。
おおくぼ・きみひろ 博士(医学)。日本医科大学大学院医学研究科の頭頸部感覚器科学分野教授。日本アレルギー協会理事で、日本医科大学付属病院の耳鼻咽喉科部長。1988年に同大学大学院修了。その後、アメリカ国立衛生研究所留学などを経て現職。日本における花粉症治療の第一人者として活躍する。
取り上げてほしいテーマなど、ご意見・ご要望はこちらから↓↓
dokusha@seikyo-np.jp
取り上げてほしいテーマなど、ご意見・ご要望はこちらから↓↓
dokusha@seikyo-np.jp