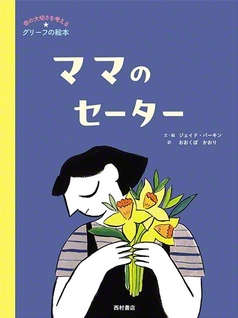小説「新・人間革命」に学ぶ 第9巻 解説編 池田主任副会長の紙上講座
小説「新・人間革命」に学ぶ 第9巻 解説編 池田主任副会長の紙上講座
2019年6月25日
今回の「世界広布の大道 小説『新・人間革命』に学ぶ」は第9巻の「解説編」。池田博正主任副会長の紙上講座とともに、同巻につづられた珠玉の名言を紹介する。
今回の「世界広布の大道 小説『新・人間革命』に学ぶ」は第9巻の「解説編」。池田博正主任副会長の紙上講座とともに、同巻につづられた珠玉の名言を紹介する。
紙上講座 池田主任副会長
紙上講座 池田主任副会長
〈ポイント〉
〈ポイント〉
①「人間革命」の執筆
①「人間革命」の執筆
②次代に信心を伝える
②次代に信心を伝える
③平和と人道の連帯
③平和と人道の連帯
第9巻では、最初の「新時代」の章で、1964年(昭和39年)4月、戸田先生の七回忌法要で、山本伸一が小説『人間革命』の執筆開始を宣言する場面が描かれ、最後の「衆望」の章で、同年12月2日、沖縄の地で執筆を開始する場面がつづられています。
「衆望」の章では、執筆を決意するにいたる、恩師との四つの思い出が記されています。
最初は伸一が入会して3カ月が過ぎたころです。「戸田城聖という、傑出した指導者を知った伸一の感動は、あまりにも大きかった」(384ページ)。この偉大な師の姿を後世に伝え抜かねばならない、との深い決意は、「師弟の尊き共戦の歴史を織り成していくなかで、不動の誓い」(同ページ)となっていきました。
二つ目は、戸田先生が妙悟空のペンネームで執筆した、小説『人間革命』の原稿を見せられた時。三つ目は、恩師の故郷である北海道の厚田村(当時)を一緒に訪問した時です。
最後は、57年(同32年)8月、戸田先生と共に長野の軽井沢でひとときを過ごしたことです。この8カ月後、戸田先生は逝去されます。
恩師との四つの思い出は、伸一が19歳から29歳の時の出来事です。この10年間は、戸田先生のもとで、彼が真の「師弟の道」を学び、歩んだ日々でした。
その間の「戸田から受けた数々の黄金不滅の指導は、むしろ、師の没後のための指標であり、規範である」(17ページ)と、伸一は捉えていました。ゆえに、『人間革命』を通して、「戸田先生から賜った指導を全部含め、先生の業績を書きつづって」(23ページ)いくと決意したのです。
伸一は『人間革命』の連載が、自分を苦しめることを覚悟していました。しかし、「偉大なる師の思想と真実を、自分が書き残していく」(393ページ)という使命感と喜びが、胸にたぎっていました。
彼の「不動の誓い」があったからこそ、私たちは今、「創価の師弟の道」を学び、歩むことができるのです。
第9巻では、最初の「新時代」の章で、1964年(昭和39年)4月、戸田先生の七回忌法要で、山本伸一が小説『人間革命』の執筆開始を宣言する場面が描かれ、最後の「衆望」の章で、同年12月2日、沖縄の地で執筆を開始する場面がつづられています。
「衆望」の章では、執筆を決意するにいたる、恩師との四つの思い出が記されています。
最初は伸一が入会して3カ月が過ぎたころです。「戸田城聖という、傑出した指導者を知った伸一の感動は、あまりにも大きかった」(384ページ)。この偉大な師の姿を後世に伝え抜かねばならない、との深い決意は、「師弟の尊き共戦の歴史を織り成していくなかで、不動の誓い」(同ページ)となっていきました。
二つ目は、戸田先生が妙悟空のペンネームで執筆した、小説『人間革命』の原稿を見せられた時。三つ目は、恩師の故郷である北海道の厚田村(当時)を一緒に訪問した時です。
最後は、57年(同32年)8月、戸田先生と共に長野の軽井沢でひとときを過ごしたことです。この8カ月後、戸田先生は逝去されます。
恩師との四つの思い出は、伸一が19歳から29歳の時の出来事です。この10年間は、戸田先生のもとで、彼が真の「師弟の道」を学び、歩んだ日々でした。
その間の「戸田から受けた数々の黄金不滅の指導は、むしろ、師の没後のための指標であり、規範である」(17ページ)と、伸一は捉えていました。ゆえに、『人間革命』を通して、「戸田先生から賜った指導を全部含め、先生の業績を書きつづって」(23ページ)いくと決意したのです。
伸一は『人間革命』の連載が、自分を苦しめることを覚悟していました。しかし、「偉大なる師の思想と真実を、自分が書き残していく」(393ページ)という使命感と喜びが、胸にたぎっていました。
彼の「不動の誓い」があったからこそ、私たちは今、「創価の師弟の道」を学び、歩むことができるのです。

イタリア・フィレンツェを訪問した池田先生が青年の輪の中へ。全精魂の励ましを注ぐ(1992年6月)
イタリア・フィレンツェを訪問した池田先生が青年の輪の中へ。全精魂の励ましを注ぐ(1992年6月)
強き一念が智慧に
強き一念が智慧に
「鳳雛」の章は、私自身の未来部時代の思い出と重なる場面が多くあります。私もそうですが、当時は学会2世の未来部員が多くなっている時でした。その中で、“いかに青年世代に信心の基本を教えていくか”は、大きな課題でした。
当時の『青少年白書』には、少年犯罪が増加の一途をたどり、犯罪の低年齢化が指摘されています。
そのような社会状況にあって、伸一は青少年育成の重要性を痛感し、「その模範を示していくことが学会の使命であり、これからの社会的な役割の一つ」(113ページ)であると考え、高等部・中等部の結成を提案したのです。
彼は、「苗を植えなければ、木は育たない。(中略)手を打つべき時を逃してはならない。そして、最も心を砕き、力を注がなくてはならないのは、苗を植えた時です」(124ページ)と、未来を担う宝の人材への激励の手を、次々に打ちます。
その一つ一つに、青年部のリーダーは驚き、「そうしたお考えは、どうすれば出てくるのでしょうか」(134ページ)と質問します。それに対して、伸一は「すべては真剣さだよ。私は、二十一世紀のことを真剣に考えている。(中略)強き祈りの一念が智慧となり、それが、さまざまな発想となる。責任感とは、その一念の強さのことだ」(136ページ)と答えます。この一節に、未来部担当者のみならず、全リーダーの根本姿勢があります。
彼は高等部員に対して、「現在は、題目をしっかり唱え、あくまでも、勉学第一で進んでいく必要がある。また、両親に迷惑をかけたり、嘆かせるようなことがあってはならない」(154ページ)と、具体的に分かりやすく語り掛けます。また、「自ら大使命に生き抜いていこうという一念、努力がなければ、結果として、使命の芽は、出ては来ない」(184ページ)と奮起を期待しています。
未来を見据え、伸一は後継の人材に触発を与え続けます。いかに時代が変わろうとも、全身全霊で励ましてこそ、青年世代に信心が伝わっていくことを、心に刻みたいと思います。
「鳳雛」の章は、私自身の未来部時代の思い出と重なる場面が多くあります。私もそうですが、当時は学会2世の未来部員が多くなっている時でした。その中で、“いかに青年世代に信心の基本を教えていくか”は、大きな課題でした。
当時の『青少年白書』には、少年犯罪が増加の一途をたどり、犯罪の低年齢化が指摘されています。
そのような社会状況にあって、伸一は青少年育成の重要性を痛感し、「その模範を示していくことが学会の使命であり、これからの社会的な役割の一つ」(113ページ)であると考え、高等部・中等部の結成を提案したのです。
彼は、「苗を植えなければ、木は育たない。(中略)手を打つべき時を逃してはならない。そして、最も心を砕き、力を注がなくてはならないのは、苗を植えた時です」(124ページ)と、未来を担う宝の人材への激励の手を、次々に打ちます。
その一つ一つに、青年部のリーダーは驚き、「そうしたお考えは、どうすれば出てくるのでしょうか」(134ページ)と質問します。それに対して、伸一は「すべては真剣さだよ。私は、二十一世紀のことを真剣に考えている。(中略)強き祈りの一念が智慧となり、それが、さまざまな発想となる。責任感とは、その一念の強さのことだ」(136ページ)と答えます。この一節に、未来部担当者のみならず、全リーダーの根本姿勢があります。
彼は高等部員に対して、「現在は、題目をしっかり唱え、あくまでも、勉学第一で進んでいく必要がある。また、両親に迷惑をかけたり、嘆かせるようなことがあってはならない」(154ページ)と、具体的に分かりやすく語り掛けます。また、「自ら大使命に生き抜いていこうという一念、努力がなければ、結果として、使命の芽は、出ては来ない」(184ページ)と奮起を期待しています。
未来を見据え、伸一は後継の人材に触発を与え続けます。いかに時代が変わろうとも、全身全霊で励ましてこそ、青年世代に信心が伝わっていくことを、心に刻みたいと思います。
「横」「縦」の広がり
「横」「縦」の広がり
「鳳雛」の章の最後に、「伸一が、『本門の時代』の出発に際し、高等部、中等部、少年部という、未来の人材の泉を掘ったことによって、創価後継の大河の流れが、一段と開かれ、二十一世紀への洋々たる水平線が見えてきたのである」(210ページ)とあります。
また、未来部育成について、伸一は最高幹部に「今やっていることの意味は、三十年後、四十年後に明確になります」(125ページ)とも語っています。
第9巻には、「本門の時代」の開幕に当たり、21世紀を展望し、未来部の結成をはじめ、新たな広宣流布の流れをつくるための、さまざまな出来事が描かれています。
この第9巻の単行本が発刊されたのは、戸田先生の生誕101周年に当たる2001年2月11日です。つまり、21世紀に入って最初の発刊でした。
当時、私たちは、「衆望」の章をはじめ、各章に記された仏法者の社会建設の使命を確認し合いながら、「平和と人道の連帯」の拡大を合言葉に、21世紀の広布の初戦にまい進しました。
さらに、この年の5月3日から、学会は新たな目標として「第2の七つの鐘」を打ち鳴らし、創立100周年の2030年を目指して、前進を開始しました。
「光彩」の章では、「広宣流布には、横と縦の二つの広がりが必要になります。友人から、また友人へ、仏法への理解の輪を広げていくのが横の広がりです。そして、縦の広がりというのは、親から子へ、子から孫へと、信心を伝え抜いていくことです」(236ページ)と記されています。
創立100周年へ向け、友人や地域への学会理解という「横の広がり」と、青年世代の信心の継承という「縦の広がり」は、ますます重要です。
また、同章には、「二十世紀は、『戦争と革命の世紀』といわれているが、同時に、人間革命の開幕の世紀となるだろう。いや、むしろ、人間革命の開幕の世紀ゆえに、二十世紀は、人類史上、最も輝かしい、生命の光彩の世紀への序曲として記録されることになる」(288ページ)とあります。
21世紀を「生命の光彩の世紀」にしていくのは、私たち一人一人です。その深き使命を担う喜びを胸に、自らの人間革命に挑み、「平和と人道の連帯」を広げていこうではありませんか。
「鳳雛」の章の最後に、「伸一が、『本門の時代』の出発に際し、高等部、中等部、少年部という、未来の人材の泉を掘ったことによって、創価後継の大河の流れが、一段と開かれ、二十一世紀への洋々たる水平線が見えてきたのである」(210ページ)とあります。
また、未来部育成について、伸一は最高幹部に「今やっていることの意味は、三十年後、四十年後に明確になります」(125ページ)とも語っています。
第9巻には、「本門の時代」の開幕に当たり、21世紀を展望し、未来部の結成をはじめ、新たな広宣流布の流れをつくるための、さまざまな出来事が描かれています。
この第9巻の単行本が発刊されたのは、戸田先生の生誕101周年に当たる2001年2月11日です。つまり、21世紀に入って最初の発刊でした。
当時、私たちは、「衆望」の章をはじめ、各章に記された仏法者の社会建設の使命を確認し合いながら、「平和と人道の連帯」の拡大を合言葉に、21世紀の広布の初戦にまい進しました。
さらに、この年の5月3日から、学会は新たな目標として「第2の七つの鐘」を打ち鳴らし、創立100周年の2030年を目指して、前進を開始しました。
「光彩」の章では、「広宣流布には、横と縦の二つの広がりが必要になります。友人から、また友人へ、仏法への理解の輪を広げていくのが横の広がりです。そして、縦の広がりというのは、親から子へ、子から孫へと、信心を伝え抜いていくことです」(236ページ)と記されています。
創立100周年へ向け、友人や地域への学会理解という「横の広がり」と、青年世代の信心の継承という「縦の広がり」は、ますます重要です。
また、同章には、「二十世紀は、『戦争と革命の世紀』といわれているが、同時に、人間革命の開幕の世紀となるだろう。いや、むしろ、人間革命の開幕の世紀ゆえに、二十世紀は、人類史上、最も輝かしい、生命の光彩の世紀への序曲として記録されることになる」(288ページ)とあります。
21世紀を「生命の光彩の世紀」にしていくのは、私たち一人一人です。その深き使命を担う喜びを胸に、自らの人間革命に挑み、「平和と人道の連帯」を広げていこうではありませんか。

澄み渡る青空。陽光に照らされ、青く輝く海を船が進む。トルコ最大の都市イスタンブールの光景を、池田先生がカメラに収めた(1992年6月)
澄み渡る青空。陽光に照らされ、青く輝く海を船が進む。トルコ最大の都市イスタンブールの光景を、池田先生がカメラに収めた(1992年6月)
<名言集>
<名言集>
●思いやりの根本
●思いやりの根本
思いやりの根本は、祈りです。人間は、自分の幸福を祈り、念じてくれている人には、必ず心も開くし、好感をもつものです。(「新時代」の章、81ページ)
思いやりの根本は、祈りです。人間は、自分の幸福を祈り、念じてくれている人には、必ず心も開くし、好感をもつものです。(「新時代」の章、81ページ)
●生き方の骨格
●生き方の骨格
豊かな心を培い、また、人間としての生き方の骨格をつくっていくのが信仰です。だから、若いうちから、信心をすることが大事になる。(「鳳雛」の章、119ページ)
豊かな心を培い、また、人間としての生き方の骨格をつくっていくのが信仰です。だから、若いうちから、信心をすることが大事になる。(「鳳雛」の章、119ページ)
●使命の自覚
●使命の自覚
未来の使命を自覚した人は強い。その時、才能の芽は、急速に伸びるといってよい。(「鳳雛」の章、158ページ)
未来の使命を自覚した人は強い。その時、才能の芽は、急速に伸びるといってよい。(「鳳雛」の章、158ページ)
●信心の継承
●信心の継承
信心の継承こそが、広宣流布を永遠ならしめる道であり、一家、一族の永遠の繁栄の根本です。そして、その要諦が「一家和楽の信心」です。(「光彩」の章、236ページ)
信心の継承こそが、広宣流布を永遠ならしめる道であり、一家、一族の永遠の繁栄の根本です。そして、その要諦が「一家和楽の信心」です。(「光彩」の章、236ページ)
●仏法のための苦労
●仏法のための苦労
仏法のために苦労したことは、全部、自分の大福運、大功徳になります。だから、“大変だな”と思うことに出あうたびに、“これで、一つ福運を積めたな”“また一つ、功徳の因をつくったな”と、考えていくことです。(「光彩」の章、241ページ)
仏法のために苦労したことは、全部、自分の大福運、大功徳になります。だから、“大変だな”と思うことに出あうたびに、“これで、一つ福運を積めたな”“また一つ、功徳の因をつくったな”と、考えていくことです。(「光彩」の章、241ページ)
●真実の政治家
●真実の政治家
真実の政治家とは、民衆を支配するためにいるのではない。民衆に奉仕し、民衆のために、命をかけて働く人です。(「衆望」の章、367ページ)
真実の政治家とは、民衆を支配するためにいるのではない。民衆に奉仕し、民衆のために、命をかけて働く人です。(「衆望」の章、367ページ)
【題字のイラスト】間瀬健治
【題字のイラスト】間瀬健治