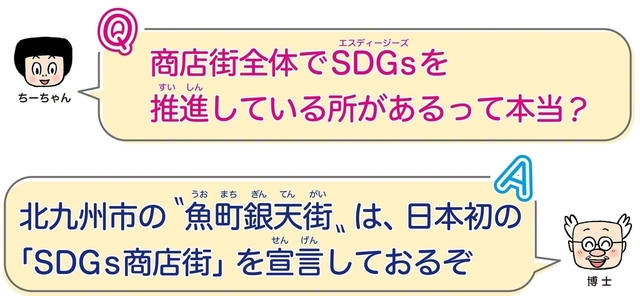〈SDGs×SEIKYO〉 事例編 北九州市・魚町銀天街 日本初の「SDGs商店街」を宣言
〈SDGs×SEIKYO〉 事例編 北九州市・魚町銀天街 日本初の「SDGs商店街」を宣言
2025年5月29日
「SDGs×SEIKYO」の事例編「ちーちゃんと訪ねる ミライの現場」。今回は福岡県北九州市の小倉北区にある「魚町商店街」の取り組みを紹介します。同商店街振興組合は、第3回「ジャパンSDGsアワード」でSDGs推進本部長賞(内閣総理大臣賞)を受賞しています。
「SDGs×SEIKYO」の事例編「ちーちゃんと訪ねる ミライの現場」。今回は福岡県北九州市の小倉北区にある「魚町商店街」の取り組みを紹介します。同商店街振興組合は、第3回「ジャパンSDGsアワード」でSDGs推進本部長賞(内閣総理大臣賞)を受賞しています。
この前、近所の商店街に買い物に行ったら、形はふぞろいだけど新鮮な野菜が、とっても安く売っていたんだよ!
この前、近所の商店街に買い物に行ったら、形はふぞろいだけど新鮮な野菜が、とっても安く売っていたんだよ!
それは良かったのお。食品ロスをなくす取り組みじゃな。
それは良かったのお。食品ロスをなくす取り組みじゃな。
父さんに聞いたら、商店街としてSDGsに取り組んでいるんだって。ほかにもこういう商店街は、あるのかなあ?
父さんに聞いたら、商店街としてSDGsに取り組んでいるんだって。ほかにもこういう商店街は、あるのかなあ?
あるぞ。福岡県北九州市の“魚町銀天街”は、日本で初めて「SDGs商店街」を宣言。店舗や地域住民、学生らと連携して、多彩なSDGsの活動を展開しているんじゃ。一緒にその取り組みを見ていこう!
あるぞ。福岡県北九州市の“魚町銀天街”は、日本で初めて「SDGs商店街」を宣言。店舗や地域住民、学生らと連携して、多彩なSDGsの活動を展開しているんじゃ。一緒にその取り組みを見ていこう!
活性化を目指した挑戦
活性化を目指した挑戦
今や、全国の商店街のシンボルともなっている「アーケード」。
その発祥の地が、“銀天街”の愛称で親しまれる、魚町商店街(福岡・北九州市)である。1951年に日本で初めて、公道上にアーケードを設置した。JR小倉駅の南側に位置し、南北に延びる400メートルほどの道沿いに約150の店舗が軒を連ねる、北九州を代表する商店街だ。
北側から歩くと、途中で小倉中心部のメインストリート・勝山通りとの交差点に行き着く。その信号を渡ると、幅いっぱいに横断幕が掲げられている。そこには、「世界の目標『SDGs』に取り組む街!」との言葉と、SDGsの17の目標が記されていた。ここは、日本で初めて「SDGs商店街」を宣言した商店街である。
今や、全国の商店街のシンボルともなっている「アーケード」。
その発祥の地が、“銀天街”の愛称で親しまれる、魚町商店街(福岡・北九州市)である。1951年に日本で初めて、公道上にアーケードを設置した。JR小倉駅の南側に位置し、南北に延びる400メートルほどの道沿いに約150の店舗が軒を連ねる、北九州を代表する商店街だ。
北側から歩くと、途中で小倉中心部のメインストリート・勝山通りとの交差点に行き着く。その信号を渡ると、幅いっぱいに横断幕が掲げられている。そこには、「世界の目標『SDGs』に取り組む街!」との言葉と、SDGsの17の目標が記されていた。ここは、日本で初めて「SDGs商店街」を宣言した商店街である。

福岡県北九州市の魚町商店街。江戸時代に魚河岸があり、鮮魚店が多かったことが名前の由来になっている
福岡県北九州市の魚町商店街。江戸時代に魚河岸があり、鮮魚店が多かったことが名前の由来になっている
――59年、JR小倉駅が西小倉から現在の場所に移転すると、“駅前”となった魚町商店街には多くの買い物客がやって来た。
当時の歩行者通行量は、1日で約3万9000人。幅が5・5メートルしかない商店街は、肩と肩が触れ合うほど混雑したという。
だが、93年ごろから、毎年10%ずつ歩行者が減少。リーマンショック後の2009年には、1万1000人にまで減った。売り上げも下がり、商店街の南側に当たる魚町3丁目地区では、空きテナント率が約3割に。商店街の人々は、活性化を目指して、さまざまな挑戦を開始した。
――59年、JR小倉駅が西小倉から現在の場所に移転すると、“駅前”となった魚町商店街には多くの買い物客がやって来た。
当時の歩行者通行量は、1日で約3万9000人。幅が5・5メートルしかない商店街は、肩と肩が触れ合うほど混雑したという。
だが、93年ごろから、毎年10%ずつ歩行者が減少。リーマンショック後の2009年には、1万1000人にまで減った。売り上げも下がり、商店街の南側に当たる魚町3丁目地区では、空きテナント率が約3割に。商店街の人々は、活性化を目指して、さまざまな挑戦を開始した。
各店舗の強みを生かす
各店舗の強みを生かす
まず10年から、商店街の遊休不動産をリノベーションで再生するまちづくり事業に取り組んだ。20件超のリノベーションが実施され、400人を超える新規起業者や雇用者が誕生。活気が生まれ、歩行者は約30%増加した。
迎えた18年4月、北九州市がOECD(経済協力開発機構)からアジアで初めて「SDGs推進に向けた世界のモデル都市」に選定された。商店街としても、持続可能な社会の実現を目指し、“買い物すること自体が社会貢献につながる”という意識を来街者に持ってもらおうと、本格的にSDGsに取り組むことを決め、「SDGs商店街」を宣言。北九州ESD(持続可能な開発のための教育)協議会と連携し、事業を進めていくことになった。
まず10年から、商店街の遊休不動産をリノベーションで再生するまちづくり事業に取り組んだ。20件超のリノベーションが実施され、400人を超える新規起業者や雇用者が誕生。活気が生まれ、歩行者は約30%増加した。
迎えた18年4月、北九州市がOECD(経済協力開発機構)からアジアで初めて「SDGs推進に向けた世界のモデル都市」に選定された。商店街としても、持続可能な社会の実現を目指し、“買い物すること自体が社会貢献につながる”という意識を来街者に持ってもらおうと、本格的にSDGsに取り組むことを決め、「SDGs商店街」を宣言。北九州ESD(持続可能な開発のための教育)協議会と連携し、事業を進めていくことになった。

竹を原料に作られた線香。小倉城の周辺に約3万個の竹灯籠をともすイベント「小倉城竹あかり」で使用された竹を再利用している
竹を原料に作られた線香。小倉城の周辺に約3万個の竹灯籠をともすイベント「小倉城竹あかり」で使用された竹を再利用している
魚町商店街振興組合の梯輝元理事長は、「日本初のアーケード設置に象徴されるように、常に先駆的な取り組みをすることが、この商店街の気概であり、メインテーマです。SDGsもまた、誰もやったことのない新しいことを始めようとの思いで、スタートしました」と語ってくれた。
最初に行ったのは、これまで商店街が推進してきたことをSDGsの視点から考察し、体系化すること。そして優先課題を選別し、取り組むべき目標を明確にすることだった。
魚町商店街振興組合の梯輝元理事長は、「日本初のアーケード設置に象徴されるように、常に先駆的な取り組みをすることが、この商店街の気概であり、メインテーマです。SDGsもまた、誰もやったことのない新しいことを始めようとの思いで、スタートしました」と語ってくれた。
最初に行ったのは、これまで商店街が推進してきたことをSDGsの視点から考察し、体系化すること。そして優先課題を選別し、取り組むべき目標を明確にすることだった。

商店街がSDGsをどのように活用するかを議論したセミナー。商店主らが参加し、活発な意見が交わされた
商店街がSDGsをどのように活用するかを議論したセミナー。商店主らが参加し、活発な意見が交わされた
また、SDGsの認知度を高めるために、横断幕や懸垂幕をアーケード内に設置し、視認性を高める工夫を凝らした。その結果、21年には来街者のSDGs認知度は80%まで上昇した。
取り組みの中で、最も力を入れてきたのは、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」だ。
また、SDGsの認知度を高めるために、横断幕や懸垂幕をアーケード内に設置し、視認性を高める工夫を凝らした。その結果、21年には来街者のSDGs認知度は80%まで上昇した。
取り組みの中で、最も力を入れてきたのは、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」だ。
取り組みの中で、最も力を入れてきたのは、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」だ。
商店主が自らの知識やノウハウを伝える「得するまちのゼミナール(通称うおゼミ)」を年に2回、開催してきた。
カレー店が「やさしいインドカレーの作り方」を教えたり、スポーツ用品店がウオーキングの体験会を主催したりするなど、毎回、約40の講座を実施。各店舗がもつ強みと独自性を生かし、学びと楽しみを提供しながら、街のにぎわいにつなげることを目指した。
取り組みの中で、最も力を入れてきたのは、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」だ。
商店主が自らの知識やノウハウを伝える「得するまちのゼミナール(通称うおゼミ)」を年に2回、開催してきた。
カレー店が「やさしいインドカレーの作り方」を教えたり、スポーツ用品店がウオーキングの体験会を主催したりするなど、毎回、約40の講座を実施。各店舗がもつ強みと独自性を生かし、学びと楽しみを提供しながら、街のにぎわいにつなげることを目指した。
愛する地域の発展を
愛する地域の発展を

公平・公正な貿易で仕入れた紅茶などのフェアトレード商品を販売する輸入食料品店
公平・公正な貿易で仕入れた紅茶などのフェアトレード商品を販売する輸入食料品店
これに応じて、各店舗が自発的にSDGsを商売に取り入れるようになる。
輸入食料品店では、余剰品を食品ロス削減のために格安で販売したり、公平・公正な貿易で仕入れたフェアトレード商品を扱ったりする取り組みを始めた。また日本茶の専門店では、普段は捨てることが多いお茶の出がらしにかけることで、それをおいしく食べられる画期的なポン酢を開発・販売するなど、これまでに30店舗がSDGsの運動に参画した。
これに応じて、各店舗が自発的にSDGsを商売に取り入れるようになる。
輸入食料品店では、余剰品を食品ロス削減のために格安で販売したり、公平・公正な貿易で仕入れたフェアトレード商品を扱ったりする取り組みを始めた。また日本茶の専門店では、普段は捨てることが多いお茶の出がらしにかけることで、それをおいしく食べられる画期的なポン酢を開発・販売するなど、これまでに30店舗がSDGsの運動に参画した。

出がらしをおいしく食べるために開発されたポン酢「お茶ぽん」(左端)
出がらしをおいしく食べるために開発されたポン酢「お茶ぽん」(左端)
商店街を挙げて、路上生活者の自立支援も実施。排除するのではなく、声かけから自立支援センターへとつなぎ、08年に400人いた路上生活者は50人を切るまでになった。
こうした商店街の取り組みをまとめた映像は、第1回「SDGsクリエイティブアワード」の最高賞を受賞。反響は大きく、全国から問い合わせが相次ぐように。
とりわけ、修学旅行の研修先として魚町商店街を選定する学校が増加。毎年、全国各地の10~15校の生徒らが、同商店街を訪問するようになった。
客層にも変化が起こった。かつては中高年の女性が多かったが、SDGsに取り組み始めてから、若年層の利用が増えたという。
不断の努力により、歩行者通行量は、一時は1万4000人まで増加。その後、コロナ禍や3度の火事に見舞われた影響で減少したが、今は1万2000人まで持ち直している。
商店街を挙げて、路上生活者の自立支援も実施。排除するのではなく、声かけから自立支援センターへとつなぎ、08年に400人いた路上生活者は50人を切るまでになった。
こうした商店街の取り組みをまとめた映像は、第1回「SDGsクリエイティブアワード」の最高賞を受賞。反響は大きく、全国から問い合わせが相次ぐように。
とりわけ、修学旅行の研修先として魚町商店街を選定する学校が増加。毎年、全国各地の10~15校の生徒らが、同商店街を訪問するようになった。
客層にも変化が起こった。かつては中高年の女性が多かったが、SDGsに取り組み始めてから、若年層の利用が増えたという。
不断の努力により、歩行者通行量は、一時は1万4000人まで増加。その後、コロナ禍や3度の火事に見舞われた影響で減少したが、今は1万2000人まで持ち直している。

NPO法人「グリーンバード」と連携して開催した清掃活動は、地域の学生が中心になって取り組んだ
NPO法人「グリーンバード」と連携して開催した清掃活動は、地域の学生が中心になって取り組んだ
魚町の挑戦は終わらない。本年6月からは、「うおゼミ」を発展させ、外部講師を招いて、「ウオマチ大学」を開始する予定だ。
梯理事長は力を込める。「目標は2030年までに2万人の通行量を回復することです。全国の商店街の衰退が叫ばれる中にあって、“商店街でも、こんなことができるんだ”と、モデルになるような活動を目指して、頑張っていきたいと思います」
“日本初”の誇りを胸に、先駆的な取り組みを続ける魚町商店街の人々。その心には、「いかなる時代にあっても、愛するわが地域を発展させていきたい」との気概があふれている。
魚町の挑戦は終わらない。本年6月からは、「うおゼミ」を発展させ、外部講師を招いて、「ウオマチ大学」を開始する予定だ。
梯理事長は力を込める。「目標は2030年までに2万人の通行量を回復することです。全国の商店街の衰退が叫ばれる中にあって、“商店街でも、こんなことができるんだ”と、モデルになるような活動を目指して、頑張っていきたいと思います」
“日本初”の誇りを胸に、先駆的な取り組みを続ける魚町商店街の人々。その心には、「いかなる時代にあっても、愛するわが地域を発展させていきたい」との気概があふれている。

輸入食料品店に掲げられた、SDGsの推進を伝えるボード
輸入食料品店に掲げられた、SDGsの推進を伝えるボード
この取り組みに関わるSDGsの主な目標
この取り組みに関わるSDGsの主な目標
ご感想をお寄せください
sdgs@seikyo-np.jp
聖教電子版の「SDGs」特集ページが閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html
ご感想をお寄せください
sdgs@seikyo-np.jp
聖教電子版の「SDGs」特集ページが閲覧できます。
https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html