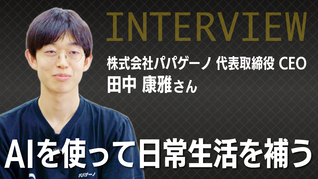分断を超える「文学」の力 今伝えたい「希望」の哲学――ボストン大学 アニータ・パターソン教授に聞く
分断を超える「文学」の力 今伝えたい「希望」の哲学――ボストン大学 アニータ・パターソン教授に聞く
2025年5月16日
- 〈識者が語る 未来を開く池田思想〉
- 〈識者が語る 未来を開く池田思想〉
身近な“一人”こそが偉大な存在である――アメリカ・ルネサンスを代表する哲人である、エマソンやソローの叫びは、仏法の思想にも通じています。ボストン大学のアニータ・パターソン教授は、エマソンらの文学と仏法の共鳴について研究し、池田大作先生の思想と実践に深い理解を寄せてきました。さまざまな分断に直面する現代社会における、「文学」と「対話」の価値について、パターソン教授にインタビューしました。
(聞き手=掛川俊明、村上進)
身近な“一人”こそが偉大な存在である――アメリカ・ルネサンスを代表する哲人である、エマソンやソローの叫びは、仏法の思想にも通じています。ボストン大学のアニータ・パターソン教授は、エマソンらの文学と仏法の共鳴について研究し、池田大作先生の思想と実践に深い理解を寄せてきました。さまざまな分断に直面する現代社会における、「文学」と「対話」の価値について、パターソン教授にインタビューしました。
(聞き手=掛川俊明、村上進)
――パターソン教授は、アメリカ文学、黒人文学などを専門とし、アメリカ・ルネサンス文学と仏教の関連も研究されています。文学と出合ったきっかけは、何だったのでしょうか。
アメリカ社会の中で、私は“人と違う”という難しさに直面しながら育ちました。というのも、母は広島県にルーツを持つ日系人で、父はロシア系ユダヤ人の子孫という、移民の家庭だったからです。
第2次世界大戦中、高校生だった母は、敵性外国人として日系人強制収容所に入れられました。母の家系にはキリスト教徒もいれば、仏教徒もいました。しかし、家族が仏教徒であったことを、私は日系アメリカ人の歴史研究に携わるようになって、初めて知りました。母は、信仰や強制収容の経験について、決して語らなかったからです。
一方で、読書好きの母は私の手本でした。母にとって読書は、文化や伝統を学び、アメリカ社会の一員として溶け込もうとする努力でもあったと思います。
このように私は、文化的にはアメリカ・日本・ロシアにルーツを持ち、宗教的にはキリスト教・ユダヤ教・仏教の背景を持った、複雑な環境で育ったのです。それゆえに、他者との距離を縮め、アメリカの伝統的な文化になじみたいという憧れが、文学に情熱を持つきっかけになりました。
――パターソン教授は、アメリカ文学、黒人文学などを専門とし、アメリカ・ルネサンス文学と仏教の関連も研究されています。文学と出合ったきっかけは、何だったのでしょうか。
アメリカ社会の中で、私は“人と違う”という難しさに直面しながら育ちました。というのも、母は広島県にルーツを持つ日系人で、父はロシア系ユダヤ人の子孫という、移民の家庭だったからです。
第2次世界大戦中、高校生だった母は、敵性外国人として日系人強制収容所に入れられました。母の家系にはキリスト教徒もいれば、仏教徒もいました。しかし、家族が仏教徒であったことを、私は日系アメリカ人の歴史研究に携わるようになって、初めて知りました。母は、信仰や強制収容の経験について、決して語らなかったからです。
一方で、読書好きの母は私の手本でした。母にとって読書は、文化や伝統を学び、アメリカ社会の一員として溶け込もうとする努力でもあったと思います。
このように私は、文化的にはアメリカ・日本・ロシアにルーツを持ち、宗教的にはキリスト教・ユダヤ教・仏教の背景を持った、複雑な環境で育ったのです。それゆえに、他者との距離を縮め、アメリカの伝統的な文化になじみたいという憧れが、文学に情熱を持つきっかけになりました。

池田大作先生とロナルド・ボスコ博士、ジョエル・マイアソン博士のてい談集『美しき生命 地球と生きる――哲人ソローとエマソンを語る』(毎日新聞社)
池田大作先生とロナルド・ボスコ博士、ジョエル・マイアソン博士のてい談集『美しき生命 地球と生きる――哲人ソローとエマソンを語る』(毎日新聞社)
19世紀半ばのアメリカ・ルネサンスを代表する、エマソンやソローなどの作家を研究する中で、彼らと仏教の共鳴点に注目してきました。実際に、エマソンらは仏教の思想に強い関心を抱き、学んでいました。
当時、エマソンを中心に「超絶主義」という新しい哲学・文学運動が起こり、彼らは人間生命に偉大な力が内在するという理念に着目していました。エマソンらは1836年に「トランセンデンタル・クラブ(超絶主義の会)」というグループをつくり、後に機関誌「ダイアル」を創刊します。
エマソンはソローと共に、この機関誌で東洋の古典の翻訳を紹介しており、1844年には法華経の薬草喩品の英訳を掲載しました。薬草喩品の「三草二木の譬え」では、生きとし生けるものの多様性と、それを育む平等なる慈悲が説かれています。
エマソンの文学作品は、私の人生と家族の歴史における、文化的な隔たりを埋めてくれました。文学との関わりは、家族史の探究であり、私自身のアイデンティティー(自分が自分であることの根拠)を探す旅でもあったのです。
19世紀半ばのアメリカ・ルネサンスを代表する、エマソンやソローなどの作家を研究する中で、彼らと仏教の共鳴点に注目してきました。実際に、エマソンらは仏教の思想に強い関心を抱き、学んでいました。
当時、エマソンを中心に「超絶主義」という新しい哲学・文学運動が起こり、彼らは人間生命に偉大な力が内在するという理念に着目していました。エマソンらは1836年に「トランセンデンタル・クラブ(超絶主義の会)」というグループをつくり、後に機関誌「ダイアル」を創刊します。
エマソンはソローと共に、この機関誌で東洋の古典の翻訳を紹介しており、1844年には法華経の薬草喩品の英訳を掲載しました。薬草喩品の「三草二木の譬え」では、生きとし生けるものの多様性と、それを育む平等なる慈悲が説かれています。
エマソンの文学作品は、私の人生と家族の歴史における、文化的な隔たりを埋めてくれました。文学との関わりは、家族史の探究であり、私自身のアイデンティティー(自分が自分であることの根拠)を探す旅でもあったのです。
■エマソンの「自己信頼」と仏法の「大我」の生き方
■エマソンの「自己信頼」と仏法の「大我」の生き方
――アメリカの池田国際対話センター(マサチューセッツ州ケンブリッジ市)が開催してきたフォーラムにも、パターソン教授は何度も参加し、文学が持つ力や価値について語ってこられました。
同センターのイベントを通して、池田博士の著作を学び、大きな啓発を受けてきました。博士は常々、スピーチや著作で文学作品を引用し、文学の力で多くの人々を励まされました。
私も、人生の最もつらく苦しい時期に、文学が持つ力を実感した一人です。90年代半ば、私が研究者として独り立ちした頃、姉が自ら命を絶ったのです。それは、筆舌に尽くしがたい悲しみでした。
悲嘆の中で、文学は人生にいかなる影響を与えるでしょうか。私はそれ以来、さまざまな問題にぶつかる現代社会において、文学が持つ力がどのようなものかを研究してきました。
エマソンをはじめ、アメリカ・ルネサンスの思想には、普遍的な自我の肯定があり、人間の精神を再生させる英知の源があり、人生の意味を教えてくれます。
――アメリカの池田国際対話センター(マサチューセッツ州ケンブリッジ市)が開催してきたフォーラムにも、パターソン教授は何度も参加し、文学が持つ力や価値について語ってこられました。
同センターのイベントを通して、池田博士の著作を学び、大きな啓発を受けてきました。博士は常々、スピーチや著作で文学作品を引用し、文学の力で多くの人々を励まされました。
私も、人生の最もつらく苦しい時期に、文学が持つ力を実感した一人です。90年代半ば、私が研究者として独り立ちした頃、姉が自ら命を絶ったのです。それは、筆舌に尽くしがたい悲しみでした。
悲嘆の中で、文学は人生にいかなる影響を与えるでしょうか。私はそれ以来、さまざまな問題にぶつかる現代社会において、文学が持つ力がどのようなものかを研究してきました。
エマソンをはじめ、アメリカ・ルネサンスの思想には、普遍的な自我の肯定があり、人間の精神を再生させる英知の源があり、人生の意味を教えてくれます。
それは、仏教の思想にも通じるでしょう。1993年、池田博士はハーバード大学での講演で、エマソンの「あらゆる部分や分子が平等に結びつく普遍的な美、永遠の〈一なる者〉」(『エマソン論文集』下、酒本雅之訳、岩波書店)という言葉を紹介されました。このエマソンの「大霊」の考え方と共鳴するものとして、博士は他者への深い共感と理解を持ち、同時に「他に紛動されず、自己に忠実に主体的に生きよ」と促す、仏教の「大我」の生き方を語られました。
エマソンは、社会の風潮に流されない人が偉大であると訴え、「汝自身を信頼せよ」という自己信頼を教えました。私は人生の最も暗い時期に、このエマソンの著作『自己信頼』を読んだことで、困難を乗り越えることができました。エマソンを読み続ける中で、自分の人生を、より大きな文脈の中で捉えられるようになったと感じます。
そして池田博士は、仏教の「大我」の生き方を通して、一人の人間が偉大な人格を備え、自己自身を主体的に生きられることに言及しました。博士がつづった詩や著作は、いつも私を勇気づけ、生きる力を与えてくれました。それは、博士が言うように、自己の内面を深く見つめる経験でもありました。
アメリカ社会の中で、私の両親は移民として苦労しました。その娘である私にとって、文学は人生の意味を見いだし、人間として再生する力を与えてくれたのです。
それは、仏教の思想にも通じるでしょう。1993年、池田博士はハーバード大学での講演で、エマソンの「あらゆる部分や分子が平等に結びつく普遍的な美、永遠の〈一なる者〉」(『エマソン論文集』下、酒本雅之訳、岩波書店)という言葉を紹介されました。このエマソンの「大霊」の考え方と共鳴するものとして、博士は他者への深い共感と理解を持ち、同時に「他に紛動されず、自己に忠実に主体的に生きよ」と促す、仏教の「大我」の生き方を語られました。
エマソンは、社会の風潮に流されない人が偉大であると訴え、「汝自身を信頼せよ」という自己信頼を教えました。私は人生の最も暗い時期に、このエマソンの著作『自己信頼』を読んだことで、困難を乗り越えることができました。エマソンを読み続ける中で、自分の人生を、より大きな文脈の中で捉えられるようになったと感じます。
そして池田博士は、仏教の「大我」の生き方を通して、一人の人間が偉大な人格を備え、自己自身を主体的に生きられることに言及しました。博士がつづった詩や著作は、いつも私を勇気づけ、生きる力を与えてくれました。それは、博士が言うように、自己の内面を深く見つめる経験でもありました。
アメリカ社会の中で、私の両親は移民として苦労しました。その娘である私にとって、文学は人生の意味を見いだし、人間として再生する力を与えてくれたのです。
■文学は“旧友”と語らうような「心の対話」
■文学は“旧友”と語らうような「心の対話」
――2023年9月、池田国際対話センターで開かれたフォーラムのテーマは、「心の対話――内なる変革と平和を育む文学の役割」でした。同フォーラムで、パターソン教授は基調講演を務められました。
池田博士はフォーラムに寄せたメッセージの中で、大乗仏教の視点から、分断と対立の原因が思想や精神性の乱れにあると指摘されました。そうした状況を乗り越えるためには、人間自身の「内なる変革」が重要であり、生命の内奥に広がる“宇宙的大我”にいざなう翼こそ「文学の力」であると述べられました。さらに、それぞれの国が誇る文学に学び、感動を分かち合うことが内なる変革と平和を育む「心の対話」に連動すると強調されたのです。
私は、文学から教訓を引き出す、池田博士のアプローチに感銘を受けてきました。私たちは文学を通して、自分とは異なる文化や考え方とも「対話」ができます。
――2023年9月、池田国際対話センターで開かれたフォーラムのテーマは、「心の対話――内なる変革と平和を育む文学の役割」でした。同フォーラムで、パターソン教授は基調講演を務められました。
池田博士はフォーラムに寄せたメッセージの中で、大乗仏教の視点から、分断と対立の原因が思想や精神性の乱れにあると指摘されました。そうした状況を乗り越えるためには、人間自身の「内なる変革」が重要であり、生命の内奥に広がる“宇宙的大我”にいざなう翼こそ「文学の力」であると述べられました。さらに、それぞれの国が誇る文学に学び、感動を分かち合うことが内なる変革と平和を育む「心の対話」に連動すると強調されたのです。
私は、文学から教訓を引き出す、池田博士のアプローチに感銘を受けてきました。私たちは文学を通して、自分とは異なる文化や考え方とも「対話」ができます。

池田大作先生と語り合う、ジョエル・マイアソン博士㊧とロナルド・ボスコ博士㊥。3人の語らいは、てい談集『美しき生命 地球と生きる――哲人ソローとエマソンを語る』(毎日新聞社)に結実した(2001年5月、創価大学で)
池田大作先生と語り合う、ジョエル・マイアソン博士㊧とロナルド・ボスコ博士㊥。3人の語らいは、てい談集『美しき生命 地球と生きる――哲人ソローとエマソンを語る』(毎日新聞社)に結実した(2001年5月、創価大学で)
かつて、池田博士は長編詩「世紀の太陽よ昇れ」の中で、エマソンやホイットマンと“旧友”として語り合ったとして、「若年の昔より 座右に親しみ/共に語り 心を通わせし/エマソン ホイットマン……」と、つづっています。
この部分は、英語版では「心の対話」として翻訳されています。文学との触れ合いは、民族や文化、宗教などの違いを超えた“開かれた心による対話”であると表現されているのです。
池田博士は、この心の対話にソローも含めます。ロナルド・ボスコ氏、ジョエル・マイアソン氏とのてい談集(『美しき生命 地球と生きる――哲人ソローとエマソンを語る』毎日新聞社)の冒頭で、池田博士は「人間精神の新しき凱歌」との詩をつづっています。
「ラルフ・ウォルドー・エマソン/ヘンリー・デイヴィッド・ソロー/そして/ウォルト・ホイットマン/深く尊敬し合う友のように/並び屹立した精神の大樹たちよ!/大自然の香気に満ちた/大らかな魂の呼び声を/人類の大空へ送り続けてやまぬ/『アメリカ・ルネサンス』の/誇り高き旗手たちよ!」
かつて、池田博士は長編詩「世紀の太陽よ昇れ」の中で、エマソンやホイットマンと“旧友”として語り合ったとして、「若年の昔より 座右に親しみ/共に語り 心を通わせし/エマソン ホイットマン……」と、つづっています。
この部分は、英語版では「心の対話」として翻訳されています。文学との触れ合いは、民族や文化、宗教などの違いを超えた“開かれた心による対話”であると表現されているのです。
池田博士は、この心の対話にソローも含めます。ロナルド・ボスコ氏、ジョエル・マイアソン氏とのてい談集(『美しき生命 地球と生きる――哲人ソローとエマソンを語る』毎日新聞社)の冒頭で、池田博士は「人間精神の新しき凱歌」との詩をつづっています。
「ラルフ・ウォルドー・エマソン/ヘンリー・デイヴィッド・ソロー/そして/ウォルト・ホイットマン/深く尊敬し合う友のように/並び屹立した精神の大樹たちよ!/大自然の香気に満ちた/大らかな魂の呼び声を/人類の大空へ送り続けてやまぬ/『アメリカ・ルネサンス』の/誇り高き旗手たちよ!」

2023年9月、アメリカ・池田国際対話センターで開かれたフォーラムで登壇するパターソン博士(壇上左端)
2023年9月、アメリカ・池田国際対話センターで開かれたフォーラムで登壇するパターソン博士(壇上左端)
文学は、私たちを隔てる、さまざまな違いを乗り越えるのを助けてくれます。ゆえに私は、池田博士の「心の対話」という考え方に深い共感を覚えるのです。
時に人生には、朝が来ても起き上がれないような日が訪れます。文学と対話は、苦難の時にこそ、価値を発揮します。それは、人生の意味をもう一度生み出し、他者とのより良い関係を築き、自身の存在を高めてくれます。
そして、人生と社会に希望を感じることができれば、世界は私たちにとって、意味あるものとして輝き始めます。そうすれば、どんなに困難な状況に陥ったとしても、自分と他者の幸福のために貢献したいと思える一人一人に成長していくことができるはずです。
文学は、私たちを隔てる、さまざまな違いを乗り越えるのを助けてくれます。ゆえに私は、池田博士の「心の対話」という考え方に深い共感を覚えるのです。
時に人生には、朝が来ても起き上がれないような日が訪れます。文学と対話は、苦難の時にこそ、価値を発揮します。それは、人生の意味をもう一度生み出し、他者とのより良い関係を築き、自身の存在を高めてくれます。
そして、人生と社会に希望を感じることができれば、世界は私たちにとって、意味あるものとして輝き始めます。そうすれば、どんなに困難な状況に陥ったとしても、自分と他者の幸福のために貢献したいと思える一人一人に成長していくことができるはずです。
■現実の「生活」の中に平和の種を植える
■現実の「生活」の中に平和の種を植える
――現代社会には、多くの深刻な対立が生じています。分断が深まる時代にあって、文学や対話といった実践には、どのような価値があるとお考えですか。
今、世界には「希望」が欠けているのではないでしょうか。人々は、民主主義への信頼を失ってきているように見えます。そのことが私を苦しめているのです。
アメリカでは1960年代にかけて、アフリカ系アメリカ人が人種差別の解消を求めた、公民権運動が起こりました。あの頃も、戦争や経済格差、差別といった社会的分断は存在していましたが、当時は身近な人たちが、民主主義への信頼を抱かせてくれました。具体的には、投票や市民的不服従、抗議といった行動が、より良い社会へ変革する有効な手段であるという希望を植えてくれたのです。
――現代社会には、多くの深刻な対立が生じています。分断が深まる時代にあって、文学や対話といった実践には、どのような価値があるとお考えですか。
今、世界には「希望」が欠けているのではないでしょうか。人々は、民主主義への信頼を失ってきているように見えます。そのことが私を苦しめているのです。
アメリカでは1960年代にかけて、アフリカ系アメリカ人が人種差別の解消を求めた、公民権運動が起こりました。あの頃も、戦争や経済格差、差別といった社会的分断は存在していましたが、当時は身近な人たちが、民主主義への信頼を抱かせてくれました。具体的には、投票や市民的不服従、抗議といった行動が、より良い社会へ変革する有効な手段であるという希望を植えてくれたのです。
しかし今日の世界では、独善的な「怒り」と「党派性」によって、異なる人同士が対話することが難しくなっています。こうした現状について、あるメディアは“怒りの伝染病”と表現しました。怒り、そして対話の欠如が、現代社会の至る所で深刻な影響を与えているのです。
そこで私は、池田博士の思想と実践を思い起こします。博士が、より良い地球社会の構築のために貢献されてきたことの中で、最も重要で印象的な洞察の一つが「希望」の概念です。
池田博士は、“希望とは決意である。人間にとって最も重要な決意である。私たちの人生からはじまり、希望はすべてを変革する。希望こそ、理想を実現するための行動力の源泉である”と訴えました。現実社会は“希望と絶望の闘争”であり、博士は希望が勝つことこそが平和であると教えているのです。
マーチン・ルーサー・キング牧師の盟友であり、歴史学者のビンセント・ハーディング博士との対談集(『希望の教育 平和の行進』第三文明社)で、池田博士は「『夢』を失わないかぎり、『希望』は生き続ける」と訴えました。
教育者である私の目標は、この「希望」の哲学を学生たちに伝えることです。
しかし今日の世界では、独善的な「怒り」と「党派性」によって、異なる人同士が対話することが難しくなっています。こうした現状について、あるメディアは“怒りの伝染病”と表現しました。怒り、そして対話の欠如が、現代社会の至る所で深刻な影響を与えているのです。
そこで私は、池田博士の思想と実践を思い起こします。博士が、より良い地球社会の構築のために貢献されてきたことの中で、最も重要で印象的な洞察の一つが「希望」の概念です。
池田博士は、“希望とは決意である。人間にとって最も重要な決意である。私たちの人生からはじまり、希望はすべてを変革する。希望こそ、理想を実現するための行動力の源泉である”と訴えました。現実社会は“希望と絶望の闘争”であり、博士は希望が勝つことこそが平和であると教えているのです。
マーチン・ルーサー・キング牧師の盟友であり、歴史学者のビンセント・ハーディング博士との対談集(『希望の教育 平和の行進』第三文明社)で、池田博士は「『夢』を失わないかぎり、『希望』は生き続ける」と訴えました。
教育者である私の目標は、この「希望」の哲学を学生たちに伝えることです。
大学での文学の講義では、学生の歴史的自己認識を育むことを重視します。文学を通して歴史的な発展を学ぶことは、文化・人種・階級といった溝を埋める第一歩になります。
例えば、アフリカ系アメリカ人の文学を学ぶと、奴隷制と人種差別の負の遺産を知り、それが社会の現状にまでつながっていることが分かるようになります。
困難な政治的問題に直面すると、異なる見解は衝突しがちです。けれど、教室で文学作品を通して対話することで、直接的な衝突を避けながら、開かれた心で見解の違いを話し合うことができます。
文学と対話は、私たちには他者から学べることがもっとあると感じさせてくれるのです。他者との親密さを生む対話――それは日常生活で、自分自身と他者への深い気付きや認識を育むために、不可欠な実践です。私は、そこにこそ「平和構築」のプロセスに通じるものがあると考えます。
2004年の「SGIの日」記念提言において、池田博士は「平和といっても、決して日常を離れたところにあるものではない。一人ひとりが現実の『生活』の中に、また『生命』と『人生』に、どう平和の種を植え、育てていくか。ここに、永続的な平和への堅実な前進がある」と、つづっています。
博士の著作や生き方を学ぶたび、新たな希望の生命が、私の中に吹き込まれるのを感じます。創価学会の皆さまが続けてこられた、地道な対話の実践こそが、現代社会を先導する重要な意味を持つと思います。そうした運動が実を結び、池田博士のビジョンを現実のものとしていくことを願ってやみません。
大学での文学の講義では、学生の歴史的自己認識を育むことを重視します。文学を通して歴史的な発展を学ぶことは、文化・人種・階級といった溝を埋める第一歩になります。
例えば、アフリカ系アメリカ人の文学を学ぶと、奴隷制と人種差別の負の遺産を知り、それが社会の現状にまでつながっていることが分かるようになります。
困難な政治的問題に直面すると、異なる見解は衝突しがちです。けれど、教室で文学作品を通して対話することで、直接的な衝突を避けながら、開かれた心で見解の違いを話し合うことができます。
文学と対話は、私たちには他者から学べることがもっとあると感じさせてくれるのです。他者との親密さを生む対話――それは日常生活で、自分自身と他者への深い気付きや認識を育むために、不可欠な実践です。私は、そこにこそ「平和構築」のプロセスに通じるものがあると考えます。
2004年の「SGIの日」記念提言において、池田博士は「平和といっても、決して日常を離れたところにあるものではない。一人ひとりが現実の『生活』の中に、また『生命』と『人生』に、どう平和の種を植え、育てていくか。ここに、永続的な平和への堅実な前進がある」と、つづっています。
博士の著作や生き方を学ぶたび、新たな希望の生命が、私の中に吹き込まれるのを感じます。創価学会の皆さまが続けてこられた、地道な対話の実践こそが、現代社会を先導する重要な意味を持つと思います。そうした運動が実を結び、池田博士のビジョンを現実のものとしていくことを願ってやみません。
〈プロフィル〉 Anita Patterson ボストン大学英文学部教授。専門分野はアメリカ文学、モダニズム(現代主義)、黒人文学であり、それらについて国境を超えた文化間の対話に重点を置いてアプローチしている。近年は、アメリカをはじめとする西洋諸国の文学に東洋思想が与えた影響などを研究。ハーバード大学卒。英文学博士。
〈プロフィル〉 Anita Patterson ボストン大学英文学部教授。専門分野はアメリカ文学、モダニズム(現代主義)、黒人文学であり、それらについて国境を超えた文化間の対話に重点を置いてアプローチしている。近年は、アメリカをはじめとする西洋諸国の文学に東洋思想が与えた影響などを研究。ハーバード大学卒。英文学博士。
●ご感想をお寄せください。
メール kansou@seikyo-np.jp
ファクス 03-5360-9613
●連載「識者が語る 未来を開く池田思想」の過去の記事は、こちらから読めます(電子版の有料会員)。
●ご感想をお寄せください。
メール kansou@seikyo-np.jp
ファクス 03-5360-9613
●連載「識者が語る 未来を開く池田思想」の過去の記事は、こちらから読めます(電子版の有料会員)。
音声読み上げ