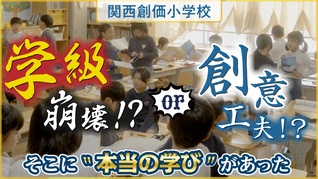〈フォーカス 平和運動〉 今回のテーマ:核兵器廃絶
〈フォーカス 平和運動〉 今回のテーマ:核兵器廃絶
2025年4月17日
平和創出に向けて社会が直面する課題や学会の取り組みを深掘りする「フォーカス 平和運動」が、今月から始まります。ここでは、池田先生の箴言や各界の識者による解説、学会が実施する諸行事をクローズアップする記事、課題解決へ一歩を踏み出すためのツールなどを紹介していきます。今回のテーマは「核兵器廃絶」です。
平和創出に向けて社会が直面する課題や学会の取り組みを深掘りする「フォーカス 平和運動」が、今月から始まります。ここでは、池田先生の箴言や各界の識者による解説、学会が実施する諸行事をクローズアップする記事、課題解決へ一歩を踏み出すためのツールなどを紹介していきます。今回のテーマは「核兵器廃絶」です。
【池田先生の言葉から】
【池田先生の言葉から】
全宇宙の
あらゆる宝よりも
尊いものがある。
それは
私たちの生命である。
だから
生命を傷つける魔物は
断じて許さない。
生命を奪う悪魔とは
断固と戦うのだ。
全宇宙の
あらゆる宝よりも
尊いものがある。
それは
私たちの生命である。
だから
生命を傷つける魔物は
断じて許さない。
生命を奪う悪魔とは
断固と戦うのだ。
※2006年10月に池田先生が贈った長編詩「平和を! 平和を! そこに幸福が生まれる」からの抜粋。
※2006年10月に池田先生が贈った長編詩「平和を! 平和を! そこに幸福が生まれる」からの抜粋。
【学生部主催のピーストークから】
【学生部主催のピーストークから】
核兵器禁止条約の理念と挑戦
日本反核法律家協会 山田寿則理事
核兵器禁止条約の理念と挑戦
日本反核法律家協会 山田寿則理事
今年初めの時点で、世界には約1万2300発の核弾頭が存在するといわれています。7万発以上といわれた冷戦期をピークに減ってきていましたが、再び増えており、核軍拡が進んでいくのではないかと懸念されています。
こうした状況下でいかに核軍縮を進めるか。一番大きな枠組みは「核兵器不拡散条約(NPT)」と呼ばれる条約です。この条約は核兵器をいきなり“ゼロ”にするのではなく、核軍縮交渉を進めるという内容ですが、近年、各国の意見が大きく対立し進展がみられない現状があります。これではどうしようもないということで、NPTに参加している一部の国々が中心となって進めてきたのが、2017年に採択された「核兵器禁止条約」です。
核兵器禁止条約は、核兵器を持ってはいけない、もらってもいけない、使ってもいけない、使うと脅してもいけない、そうした活動をしている国を援助することもいけないとしており、核兵器を包括的かつ全面的に禁止する内容になっています。
今年初めの時点で、世界には約1万2300発の核弾頭が存在するといわれています。7万発以上といわれた冷戦期をピークに減ってきていましたが、再び増えており、核軍拡が進んでいくのではないかと懸念されています。
こうした状況下でいかに核軍縮を進めるか。一番大きな枠組みは「核兵器不拡散条約(NPT)」と呼ばれる条約です。この条約は核兵器をいきなり“ゼロ”にするのではなく、核軍縮交渉を進めるという内容ですが、近年、各国の意見が大きく対立し進展がみられない現状があります。これではどうしようもないということで、NPTに参加している一部の国々が中心となって進めてきたのが、2017年に採択された「核兵器禁止条約」です。
核兵器禁止条約は、核兵器を持ってはいけない、もらってもいけない、使ってもいけない、使うと脅してもいけない、そうした活動をしている国を援助することもいけないとしており、核兵器を包括的かつ全面的に禁止する内容になっています。
条約支える二つの根拠
条約支える二つの根拠
この条約に参加する国々は、どのような理由で核兵器の禁止を訴えているのでしょうか。
1点目は、「非人道性」という問題です。核兵器の使用は極めて悲惨な結末をもたらします。そのことに着目して核兵器をなくそうというのが、核禁条約の基本的な考え方です。
核兵器の非人道性と聞いて、どんなイメージを持たれるでしょうか。よく“核兵器を使えば世界は消滅する”とか“人類は終わりを迎える”などといわれますが、核禁条約の形成過程では、そうした抽象的な議論で終わらせず、具体的な検証が行われてきました。
例えば、オスロやウィーンに核兵器が落とされた場合、どれだけの人が亡くなるかというシミュレーション結果などが報告されてきました。また、爆発によって大気に飛び散った粉塵が太陽光を遮ることで世界の平均気温が下がり、穀物や作物の収穫量が減る。その結果、飢餓が生じ、数十億人が飢え死にする恐れがある――というデータも紹介されています。
このように、核兵器の使用がもたらす非人道的な結末を具体的に繰り返し検証し、確認してきたのです。
2点目は、「戦争で使われるリスク」の問題です。核兵器が実際に戦争で使用されたのは広島と長崎のみで、以来、使われていません。しかし、歴史を振り返ると危機的な状況は何度もありました。キューバ危機(1962年)は象徴的ですが、整備中に誤って核兵器を発射してしまった事例などもあります。日本でも、かつて沖縄に置かれていた核兵器が誤射されていたことが分かっています。そうした人為的ミスや機械の故障等で核兵器が使われるリスクは残っています。
核禁条約は主にこの二つの根拠に基づいてつくられ、賛同する国が参加してきました。
この条約に参加する国々は、どのような理由で核兵器の禁止を訴えているのでしょうか。
1点目は、「非人道性」という問題です。核兵器の使用は極めて悲惨な結末をもたらします。そのことに着目して核兵器をなくそうというのが、核禁条約の基本的な考え方です。
核兵器の非人道性と聞いて、どんなイメージを持たれるでしょうか。よく“核兵器を使えば世界は消滅する”とか“人類は終わりを迎える”などといわれますが、核禁条約の形成過程では、そうした抽象的な議論で終わらせず、具体的な検証が行われてきました。
例えば、オスロやウィーンに核兵器が落とされた場合、どれだけの人が亡くなるかというシミュレーション結果などが報告されてきました。また、爆発によって大気に飛び散った粉塵が太陽光を遮ることで世界の平均気温が下がり、穀物や作物の収穫量が減る。その結果、飢餓が生じ、数十億人が飢え死にする恐れがある――というデータも紹介されています。
このように、核兵器の使用がもたらす非人道的な結末を具体的に繰り返し検証し、確認してきたのです。
2点目は、「戦争で使われるリスク」の問題です。核兵器が実際に戦争で使用されたのは広島と長崎のみで、以来、使われていません。しかし、歴史を振り返ると危機的な状況は何度もありました。キューバ危機(1962年)は象徴的ですが、整備中に誤って核兵器を発射してしまった事例などもあります。日本でも、かつて沖縄に置かれていた核兵器が誤射されていたことが分かっています。そうした人為的ミスや機械の故障等で核兵器が使われるリスクは残っています。
核禁条約は主にこの二つの根拠に基づいてつくられ、賛同する国が参加してきました。

女性平和委員会ユース会議が主体となって、各地で取り組んでいる被爆体験の聞き取り(2023年11月、都内で)
女性平和委員会ユース会議が主体となって、各地で取り組んでいる被爆体験の聞き取り(2023年11月、都内で)
抑止の論理に挑戦する試み
抑止の論理に挑戦する試み
ただ、こうした議論では納得しない国々が一部にあり、今、新たな取り組みが進められています。それが3番目、「核抑止の誤り」という問題です。
核抑止とは、核兵器を撃ってきたら核兵器を撃ち返すという構えを事前に見せておくことで、相手に核兵器の使用を思いとどまらせようという概念です。こうした考え方を持つ人や政策を取る国々から見れば、非人道性は必ずしも核兵器を否定するものではない。核兵器がもたらす影響がひどければひどいほど脅しとして意味を持つわけで、抑止の効き目が高くなると考えられるからです。
核禁条約の加盟国の間では近年、こうした考え方にどう向き合うか議論が重ねられてきました。その内容について、今年3月に開かれた核禁条約の第3回締約国会議でも報告がありました。その中で、核抑止は有効性の確証がなく、失敗の可能性があると述べられています。
現時点で核兵器が使われていないということは、核抑止が効いていると言えるかもしれない。ただ、他の要因で使われていない可能性もある。つまり、核抑止は効いているとする決定的な立証はできないというわけです。一方で、まかり間違って核兵器が使用されてしまえば、多くの国を巻き込んで甚大な被害をもたらしてしまう。
こうした事態を踏まえて核禁条約に加盟している国々は、核抑止は本当に効いているのか、それに依存して国の安全保障を考えることは妥当なのかと、科学的な証拠を示しながら問題提起していこうとしているわけです。
核兵器が非人道的な兵器であることは極めて重要な点であり、忘れてはいけません。その上で、核抑止の考え方に依存する国や人々に対し、その依って立つ根拠をいかに揺さぶっていくのかが今、重要な取り組みになっているのです。
ただ、こうした議論では納得しない国々が一部にあり、今、新たな取り組みが進められています。それが3番目、「核抑止の誤り」という問題です。
核抑止とは、核兵器を撃ってきたら核兵器を撃ち返すという構えを事前に見せておくことで、相手に核兵器の使用を思いとどまらせようという概念です。こうした考え方を持つ人や政策を取る国々から見れば、非人道性は必ずしも核兵器を否定するものではない。核兵器がもたらす影響がひどければひどいほど脅しとして意味を持つわけで、抑止の効き目が高くなると考えられるからです。
核禁条約の加盟国の間では近年、こうした考え方にどう向き合うか議論が重ねられてきました。その内容について、今年3月に開かれた核禁条約の第3回締約国会議でも報告がありました。その中で、核抑止は有効性の確証がなく、失敗の可能性があると述べられています。
現時点で核兵器が使われていないということは、核抑止が効いていると言えるかもしれない。ただ、他の要因で使われていない可能性もある。つまり、核抑止は効いているとする決定的な立証はできないというわけです。一方で、まかり間違って核兵器が使用されてしまえば、多くの国を巻き込んで甚大な被害をもたらしてしまう。
こうした事態を踏まえて核禁条約に加盟している国々は、核抑止は本当に効いているのか、それに依存して国の安全保障を考えることは妥当なのかと、科学的な証拠を示しながら問題提起していこうとしているわけです。
核兵器が非人道的な兵器であることは極めて重要な点であり、忘れてはいけません。その上で、核抑止の考え方に依存する国や人々に対し、その依って立つ根拠をいかに揺さぶっていくのかが今、重要な取り組みになっているのです。
【プロフィル】国際反核法律家協会理事、日本反核法律家協会理事。明治大学法学部兼任講師、公益財団法人政治経済研究所主任研究員。
【プロフィル】国際反核法律家協会理事、日本反核法律家協会理事。明治大学法学部兼任講師、公益財団法人政治経済研究所主任研究員。
音声読み上げ