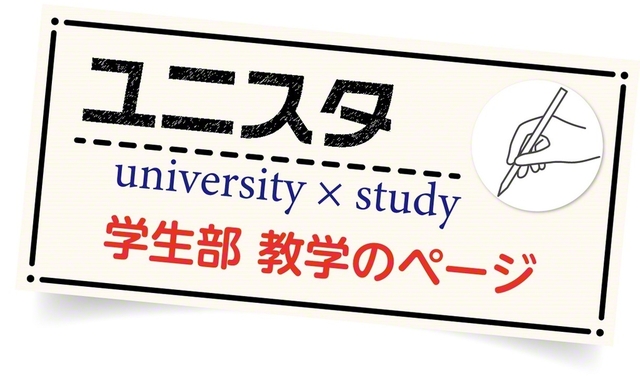〈ユニスタ 学生部教学のページ〉兄弟抄⑥
〈ユニスタ 学生部教学のページ〉兄弟抄⑥
2025年7月22日
- 「智慧」と「勇気」の題目が境涯を開く
- 「智慧」と「勇気」の題目が境涯を開く
学生部教学のページ「ユニスタ(university×study)」では、前回に続いて「兄弟抄」を研さんする。三障四魔の乗り越え方を学び、行学錬磨の夏を勢いよく駆けよう。併せて、学生部リーダーが行った教学の取り組みを紹介する「教学アクション」を掲載する。
学生部教学のページ「ユニスタ(university×study)」では、前回に続いて「兄弟抄」を研さんする。三障四魔の乗り越え方を学び、行学錬磨の夏を勢いよく駆けよう。併せて、学生部リーダーが行った教学の取り組みを紹介する「教学アクション」を掲載する。
範囲
範囲
御書新版:1477ページ13行目~1480ページ8行目
御書全集:1086ページ9行目~1088ページ6行目
御書新版:1477ページ13行目~1480ページ8行目
御書全集:1086ページ9行目~1088ページ6行目
御文
御文
行解既に勤めぬれば、三障四魔、紛然として競い起こる乃至随うべからず、畏るべからず。(新1479・全1087)
行解既に勤めぬれば、三障四魔、紛然として競い起こる乃至随うべからず、畏るべからず。(新1479・全1087)
【通解】修行が進み、仏法の理解が進んでくると、必ず三障四魔が入り乱れて競い起こる。(中略)だが、これに随ってはならないし、恐れてもならない。
【通解】修行が進み、仏法の理解が進んでくると、必ず三障四魔が入り乱れて競い起こる。(中略)だが、これに随ってはならないし、恐れてもならない。
御文と池田先生の指導を学び、
次の点について語り合おう!
☆三障四魔を乗り越えた経験
☆夏休みの目標と、達成するために越えるべき壁について
御文と池田先生の指導を学び、
次の点について語り合おう!
☆三障四魔を乗り越えた経験
☆夏休みの目標と、達成するために越えるべき壁について
父から法華経の信仰への猛反対を受けていた池上兄弟に宛てて、日蓮大聖人が認められたお手紙が「兄弟抄」である。今回の範囲では、前段に続き故事を例に挙げ、重ねて兄弟に励ましを送られる。
父から法華経の信仰への猛反対を受けていた池上兄弟に宛てて、日蓮大聖人が認められたお手紙が「兄弟抄」である。今回の範囲では、前段に続き故事を例に挙げ、重ねて兄弟に励ましを送られる。
●広布に大難は必然
●広布に大難は必然
まず大聖人が示されているのが、中国唐代の『大唐西域記』に記された「隠士と烈士の故事」である。
――月氏(インド)にいた隠士は、烈士と協力して仙人の方術を成就しようとした。ところが、成就を目前にして、烈士が魔によって心を惑わされてしまったため、失敗に終わる――
大聖人は、法華経の行者に「三障四魔」が競い起こる原理を説く導入として、この故事を引かれた。仏法以外の法ですら、成就しようとすれば魔が競う。まして、法華経の行者に大難が起こることは必然である。
前回紙面(6月24日付)で確認したように、池上兄弟もまた、法華経の信仰ゆえに、大きな試練に直面していた。兄・宗仲が父・康光から勘当されたため、弟・宗長にとっては、信仰を捨てれば、兄に代わって家督相続権が譲られるという状況になっていたのだ。
兄を勘当して、弟に家督相続の誘惑をする。明らかな魔の離間策である。まさに、広布を阻む魔の本質は“分断”にあるといえよう。
分断をたくらむ魔を打ち破るには、「異体同心」の団結で、強盛な信心を貫く以外にない。
大聖人はこの故事を通して、兄弟二人が心を合わせて信心に励み、団結して苦難に打ち勝っていくよう、重ねて激励されていると拝せる。
池田先生はつづった。
「広宣流布の前進を阻む壁が、どんなに厚かろうとも、異体同心の団結をもって、堅実な信行学の実践を積み重ね、粘り強い前進をお願いしたい。たとえ、一歩でも半歩でもよい。執念をもって、前へ、前へ、前へと進んでいってこそ、道を開くことができる」
いかなる魔が競い起ころうと、信心根本に不屈の前進を貫く限り、私たちが行き詰まることはないのだ。
まず大聖人が示されているのが、中国唐代の『大唐西域記』に記された「隠士と烈士の故事」である。
――月氏(インド)にいた隠士は、烈士と協力して仙人の方術を成就しようとした。ところが、成就を目前にして、烈士が魔によって心を惑わされてしまったため、失敗に終わる――
大聖人は、法華経の行者に「三障四魔」が競い起こる原理を説く導入として、この故事を引かれた。仏法以外の法ですら、成就しようとすれば魔が競う。まして、法華経の行者に大難が起こることは必然である。
前回紙面(6月24日付)で確認したように、池上兄弟もまた、法華経の信仰ゆえに、大きな試練に直面していた。兄・宗仲が父・康光から勘当されたため、弟・宗長にとっては、信仰を捨てれば、兄に代わって家督相続権が譲られるという状況になっていたのだ。
兄を勘当して、弟に家督相続の誘惑をする。明らかな魔の離間策である。まさに、広布を阻む魔の本質は“分断”にあるといえよう。
分断をたくらむ魔を打ち破るには、「異体同心」の団結で、強盛な信心を貫く以外にない。
大聖人はこの故事を通して、兄弟二人が心を合わせて信心に励み、団結して苦難に打ち勝っていくよう、重ねて激励されていると拝せる。
池田先生はつづった。
「広宣流布の前進を阻む壁が、どんなに厚かろうとも、異体同心の団結をもって、堅実な信行学の実践を積み重ね、粘り強い前進をお願いしたい。たとえ、一歩でも半歩でもよい。執念をもって、前へ、前へ、前へと進んでいってこそ、道を開くことができる」
いかなる魔が競い起ころうと、信心根本に不屈の前進を貫く限り、私たちが行き詰まることはないのだ。
●三障四魔との闘争
●三障四魔との闘争
大聖人は続いて、天台大師の『摩訶止観』を引用し、断じて魔に負けてはならないと訴えられる。
『摩訶止観』は、天台大師が講述し、弟子の章安大師が筆録したもの。その第5巻には、「一念三千の法門」が説かれている。一念三千とは、法華経の万人成仏の思想の真髄を示す、法理と実践を表しており、天台の教えの核心である。
大聖人は、「この法門を申すには、必ず魔出来すべし」(新1479・全1087)と仰せになり、魔が競い起こることは正法を正しく実践している証明だと強調されている。
そして、『摩訶止観』を引用した別掲御文が続く。
「行解既に勤めぬれば」とは、正しい仏法の実践と、経典に対する理解の深まりを表している。私たちに即せば、真剣に「行学の二道」に励んで信心の確信を深め、いよいよ本物の決意に立って戦いを起こす時、必ず魔が現れるということだ。いわば魔の出現は、広布前進の証しといえよう。
「随うべからず、畏るべからず」とあるように、この魔に打ち勝つためには、魔に隷属することなく、恐れず立ち向かう“勇気”が必要不可欠である。その根本が、強盛な信心であることは言うまでもない。
大聖人は「門家の明鏡」「未来の資糧とせよ」(新1479・全1087)と仰せになった。いかなる障魔にも臆せず、信心根本に勇気を持って挑んでいく――その姿が、未来にわたって広布の模範となり、“常勝の方程式”と輝くのである。
続けて大聖人は、「三障四魔」の具体的な様相について、妻子や国主、父母の姿で現れると仰せになっている。しかし、煩悩や、妻や夫、子、父母そのものが、初めから障魔であるということではない。これらに引きずられる弱い生命にとっては、三障四魔となるのだ。ゆえに、どこまでも強き信心に立つことが肝要なのである。
今回の研さん範囲の結びで、三障四魔が競い起こっている者は、大聖人御自身と弟子を除いて、いないではないかと述べられた。
現代において“分断の魔性”との闘争を貫いてきたのが、大聖人直結の創価三代の師弟である。人類の宿命転換のため、対話によって人間と人間を結び、善の連帯を広げてきた。その精神を継ぎ、広布の大道を歩んでいるのが私たちなのである。
強き信心に立ち、苦難を恐れずに、勇気の一歩を踏み出していく。その地道な挑戦が、師の平和闘争に連なる、現実変革の確かな歩みであることを深く確信し、誇り高く進みたい。
大聖人は続いて、天台大師の『摩訶止観』を引用し、断じて魔に負けてはならないと訴えられる。
『摩訶止観』は、天台大師が講述し、弟子の章安大師が筆録したもの。その第5巻には、「一念三千の法門」が説かれている。一念三千とは、法華経の万人成仏の思想の真髄を示す、法理と実践を表しており、天台の教えの核心である。
大聖人は、「この法門を申すには、必ず魔出来すべし」(新1479・全1087)と仰せになり、魔が競い起こることは正法を正しく実践している証明だと強調されている。
そして、『摩訶止観』を引用した別掲御文が続く。
「行解既に勤めぬれば」とは、正しい仏法の実践と、経典に対する理解の深まりを表している。私たちに即せば、真剣に「行学の二道」に励んで信心の確信を深め、いよいよ本物の決意に立って戦いを起こす時、必ず魔が現れるということだ。いわば魔の出現は、広布前進の証しといえよう。
「随うべからず、畏るべからず」とあるように、この魔に打ち勝つためには、魔に隷属することなく、恐れず立ち向かう“勇気”が必要不可欠である。その根本が、強盛な信心であることは言うまでもない。
大聖人は「門家の明鏡」「未来の資糧とせよ」(新1479・全1087)と仰せになった。いかなる障魔にも臆せず、信心根本に勇気を持って挑んでいく――その姿が、未来にわたって広布の模範となり、“常勝の方程式”と輝くのである。
続けて大聖人は、「三障四魔」の具体的な様相について、妻子や国主、父母の姿で現れると仰せになっている。しかし、煩悩や、妻や夫、子、父母そのものが、初めから障魔であるということではない。これらに引きずられる弱い生命にとっては、三障四魔となるのだ。ゆえに、どこまでも強き信心に立つことが肝要なのである。
今回の研さん範囲の結びで、三障四魔が競い起こっている者は、大聖人御自身と弟子を除いて、いないではないかと述べられた。
現代において“分断の魔性”との闘争を貫いてきたのが、大聖人直結の創価三代の師弟である。人類の宿命転換のため、対話によって人間と人間を結び、善の連帯を広げてきた。その精神を継ぎ、広布の大道を歩んでいるのが私たちなのである。
強き信心に立ち、苦難を恐れずに、勇気の一歩を踏み出していく。その地道な挑戦が、師の平和闘争に連なる、現実変革の確かな歩みであることを深く確信し、誇り高く進みたい。
池田先生の指導
池田先生の指導
三障四魔は、不意を突き、こわがらせ、誘惑し、嫌気を誘い、疲れさせ、油断させる等、紛然たる策動を働かせてくる。(中略)結論を言えば、「智慧」と「勇気」が勝利への根幹です。魔に従わず、魔を魔と見破る「智慧」。魔を恐れず、魔に断固立ち向かっていく「勇気」。要するに、南無妙法蓮華経の唱題行が、魔を破る「智慧」と「勇気」の源泉となるのです。妙法の力用が、「無明」を即「法性」へ転じ、「難来るを以て安楽」(全750・新1045)という境涯を開いていくからです。(中略)
大難は、法華経の行者の生命を強くします。大難に雄々しく立ち向かってこそ、仏界の生命は、いやまして光り輝いていくのです。(『勝利の経典「御書」に学ぶ』第2巻)
三障四魔は、不意を突き、こわがらせ、誘惑し、嫌気を誘い、疲れさせ、油断させる等、紛然たる策動を働かせてくる。(中略)結論を言えば、「智慧」と「勇気」が勝利への根幹です。魔に従わず、魔を魔と見破る「智慧」。魔を恐れず、魔に断固立ち向かっていく「勇気」。要するに、南無妙法蓮華経の唱題行が、魔を破る「智慧」と「勇気」の源泉となるのです。妙法の力用が、「無明」を即「法性」へ転じ、「難来るを以て安楽」(全750・新1045)という境涯を開いていくからです。(中略)
大難は、法華経の行者の生命を強くします。大難に雄々しく立ち向かってこそ、仏界の生命は、いやまして光り輝いていくのです。(『勝利の経典「御書」に学ぶ』第2巻)
[教学アクション]総千葉 第7千葉総県野田第1部部長 中野秀徳
[教学アクション]総千葉 第7千葉総県野田第1部部長 中野秀徳
学会の会合だけでなく、メンバーの家を訪問した際に、玄関先でも一緒に楽しく御書を拝せたら……そう考えていた時、思い出したのは、幼い頃に熱中したカード集め。どんなカードが当たるだろうとワクワクしていた気持ちもよみがえりました。早速、「御書カード」を作ってみることに。表面に御文と通解、裏面に背景と大意、池田先生のご指導を書きました。この準備が思った以上に大変で(笑)。どう話せば伝わるかと考えながら研さんし、手のひらサイズのカードにまとめました。
いざ、カードを持ってメンバー宅へ! 「この5枚の中から選んで」と伝えると、大学1年生のメンバーが手にしたのは、「兄弟抄」の一節。その場で一緒に拝読して、“今の苦労が自分を磨く”ことを確認し合いました。思いのほかメンバーも喜んでくれ、信心の確信を自然と伝えることもできました。
せっかくならと、不在の部員宅にもカードを投函。すると、「深く信心を発して、日夜朝暮にまた懈らず磨くべし。いかようにしてか磨くべき。ただ南無妙法蓮華経と唱えたてまつるを、これをみがくとはいうなり」(新317・全384)との御文のカードを投函したメンバーから、後日、連絡が。闘病中の友人を、どう励ますべきか悩んでいたそうですが、御文を胸に唱題に挑戦し、友人に心からの励ましを送れたようです!
僕自身、悩むたびに読み返す御文は、数年前に先輩から教わり、線を引いていた御文です。何が発心のきっかけになるかは分かりません。いつの日か、メンバーが御文と“再会”することを祈って、いろんな形で激励・研さんを続けていきます。
学会の会合だけでなく、メンバーの家を訪問した際に、玄関先でも一緒に楽しく御書を拝せたら……そう考えていた時、思い出したのは、幼い頃に熱中したカード集め。どんなカードが当たるだろうとワクワクしていた気持ちもよみがえりました。早速、「御書カード」を作ってみることに。表面に御文と通解、裏面に背景と大意、池田先生のご指導を書きました。この準備が思った以上に大変で(笑)。どう話せば伝わるかと考えながら研さんし、手のひらサイズのカードにまとめました。
いざ、カードを持ってメンバー宅へ! 「この5枚の中から選んで」と伝えると、大学1年生のメンバーが手にしたのは、「兄弟抄」の一節。その場で一緒に拝読して、“今の苦労が自分を磨く”ことを確認し合いました。思いのほかメンバーも喜んでくれ、信心の確信を自然と伝えることもできました。
せっかくならと、不在の部員宅にもカードを投函。すると、「深く信心を発して、日夜朝暮にまた懈らず磨くべし。いかようにしてか磨くべき。ただ南無妙法蓮華経と唱えたてまつるを、これをみがくとはいうなり」(新317・全384)との御文のカードを投函したメンバーから、後日、連絡が。闘病中の友人を、どう励ますべきか悩んでいたそうですが、御文を胸に唱題に挑戦し、友人に心からの励ましを送れたようです!
僕自身、悩むたびに読み返す御文は、数年前に先輩から教わり、線を引いていた御文です。何が発心のきっかけになるかは分かりません。いつの日か、メンバーが御文と“再会”することを祈って、いろんな形で激励・研さんを続けていきます。