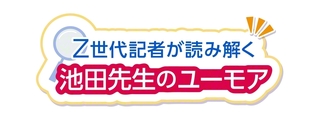2975D8AB15DF019ED11CCAB3F2DFB9C7
〈ストーリーズⅡ 池田先生の希望の励まし〉第16回 若鳥よ 中国飛びゆけ
〈ストーリーズⅡ 池田先生の希望の励まし〉第16回 若鳥よ 中国飛びゆけ
2025年8月31日
- 一生のすべての体験が生きてくるのだ。
- 何ひとつ、塵も残さず、無駄はなかったことが分かる
- 一生のすべての体験が生きてくるのだ。
- 何ひとつ、塵も残さず、無駄はなかったことが分かる

池田先生が安来会館を初訪問。友の真心が込められた展示物を観賞。この日の夜、携わった友へ「ありがとう。“どじょう”が元気に動いていました」と伝言を贈った(1991年9月9日)
池田先生が安来会館を初訪問。友の真心が込められた展示物を観賞。この日の夜、携わった友へ「ありがとう。“どじょう”が元気に動いていました」と伝言を贈った(1991年9月9日)
垣根なき師弟の世界
垣根なき師弟の世界
鳥取・米子文化会館を出発した車が、池田大作先生を乗せて、初訪問となる島根・安来会館へと向かった。1991年9月9日の夕刻。道中の家々に三色旗が掲げられていた。病院の一室にも旗が見えた。先生は、その窓の方へ向かって手を振った。
車中で和歌を詠んだ。
「あの道に また この道に 三色旗 友の笑顔を 見るが如くに」
車の窓をいっぱいに開け、先生が三色旗を振りながら安来会館に到着。出迎えた友に、「おめでとう」「いい雲だね。素晴らしい!」と声をかけた。
館内に入ると、宍道湖のシジミや隠岐のカキの殻を使った飾り絵が置かれていた。そこには太い文字で「よう来てごしなって だんだんね」と。「だんだん」は出雲・伯耆地方の方言で「ありがとう」との意味。師への感謝を込めて同志が作製した作品だった。
安来節の踊り手をかたどった、“顔出しパネル”も用意されていた。先生は、香峯子夫人と共にそこから顔を出して笑顔に。友の心に応えた。
島根県の県長を務めていた井上公男さん。「“日本一”の拡大を目指した戦いをやりきり、島根の同志の心は喜びでいっぱいでした」と振り返る。
島根県代表幹部会に出席した先生はスピーチを。
「今回の訪問は、天も地も、希望の光に満ちあふれた素晴らしい一日一日であった。朝も昼も輝いている。夕暮れも美しい。気温もさわやかである。きょうは大山も“こんにちは!”といわんばかりに、秀麗な姿を現していた。皆さまの真心と、信心のけなげさを、そのまま映し出したような美しさであった」
続いて、車中で詠んだ歌を紹介する。
「山光と たれがつけたか この光彩 日日の輝き 山陰消えたり」
そして、「数々の苦労を乗り越え、広宣流布の行動に徹しておられる“山光”の皆さまに、最大の尊敬と感謝を込めて贈らせていただく」と。
さらに、戸田先生が年末に、よく安来節を踊っていたことを述懐。共に踊った思い出などを語った。一人一人の笑顔が弾けた総会。先生は最後にユーモアを込めて、「この次お会いする時は、一緒に『安来節』を踊りましょう」と。会場に爆笑の渦が起こり、拍手が鳴り響いた。上下の隔てなどない、垣根なき師弟の世界――その空気が安来会館いっぱいに広がった。
かつて島根県の婦人部長を務め、当時は中国婦人部長だった宮井和子さんにとっても、最高の思い出のひとときに。幾多の宿命に涙を流してきた人生だった。しかし師匠と出会い、語り合い、笑い合う中で、心は明るく照らされていった。
鳥取・米子文化会館を出発した車が、池田大作先生を乗せて、初訪問となる島根・安来会館へと向かった。1991年9月9日の夕刻。道中の家々に三色旗が掲げられていた。病院の一室にも旗が見えた。先生は、その窓の方へ向かって手を振った。
車中で和歌を詠んだ。
「あの道に また この道に 三色旗 友の笑顔を 見るが如くに」
車の窓をいっぱいに開け、先生が三色旗を振りながら安来会館に到着。出迎えた友に、「おめでとう」「いい雲だね。素晴らしい!」と声をかけた。
館内に入ると、宍道湖のシジミや隠岐のカキの殻を使った飾り絵が置かれていた。そこには太い文字で「よう来てごしなって だんだんね」と。「だんだん」は出雲・伯耆地方の方言で「ありがとう」との意味。師への感謝を込めて同志が作製した作品だった。
安来節の踊り手をかたどった、“顔出しパネル”も用意されていた。先生は、香峯子夫人と共にそこから顔を出して笑顔に。友の心に応えた。
島根県の県長を務めていた井上公男さん。「“日本一”の拡大を目指した戦いをやりきり、島根の同志の心は喜びでいっぱいでした」と振り返る。
島根県代表幹部会に出席した先生はスピーチを。
「今回の訪問は、天も地も、希望の光に満ちあふれた素晴らしい一日一日であった。朝も昼も輝いている。夕暮れも美しい。気温もさわやかである。きょうは大山も“こんにちは!”といわんばかりに、秀麗な姿を現していた。皆さまの真心と、信心のけなげさを、そのまま映し出したような美しさであった」
続いて、車中で詠んだ歌を紹介する。
「山光と たれがつけたか この光彩 日日の輝き 山陰消えたり」
そして、「数々の苦労を乗り越え、広宣流布の行動に徹しておられる“山光”の皆さまに、最大の尊敬と感謝を込めて贈らせていただく」と。
さらに、戸田先生が年末に、よく安来節を踊っていたことを述懐。共に踊った思い出などを語った。一人一人の笑顔が弾けた総会。先生は最後にユーモアを込めて、「この次お会いする時は、一緒に『安来節』を踊りましょう」と。会場に爆笑の渦が起こり、拍手が鳴り響いた。上下の隔てなどない、垣根なき師弟の世界――その空気が安来会館いっぱいに広がった。
かつて島根県の婦人部長を務め、当時は中国婦人部長だった宮井和子さんにとっても、最高の思い出のひとときに。幾多の宿命に涙を流してきた人生だった。しかし師匠と出会い、語り合い、笑い合う中で、心は明るく照らされていった。

岡山での会合に出席した翌日、池田先生は初訪問となる松江へ。途中、岡山の新見駅で車窓越しに友を激励。到着後、松江支部結成大会で勇気ある信心の大切さを訴えた(1961年4月23日)
岡山での会合に出席した翌日、池田先生は初訪問となる松江へ。途中、岡山の新見駅で車窓越しに友を激励。到着後、松江支部結成大会で勇気ある信心の大切さを訴えた(1961年4月23日)
「祈るらむ 君が心の 幸の海」
「祈るらむ 君が心の 幸の海」
松江駅に電車が滑り込んでくる。幼い日の宮井さんは、自宅から見える線路をただじっと眺めていた。
父・浜崎巌さんは酒乱で、母・ゆき江さんは心を病み、争いの絶えない家庭だった。中学校では放課後は教室に残り、帰りたくない気持ちを隠していた。“なぜ自分は生まれてきたのだろう”。そんな苦悩が渦巻いていた。
57年、母が創価学会に入会。2カ月後、家族も続く。父は生き方を改め、一家で信心に励むようになっていく。
浜崎巌さんが信心によって蘇生した姿は、人々の心へ希望を広げた。島根・松江を池田先生が初めて訪れた1961年4月23日。支部長を務めることになった浜崎さんの自宅へ、先生が足を運んだ。「来たよ!」。精悍なまなざし、力強い声。宮井さんは思った。“先生についていけば、私は必ず幸せになれる!”
迎えた松江支部結成大会。読み書きのできない父のため、宮井さんはひらがなとカタカナで原稿を書いていた。その原稿で、父は1週間前から練習を重ねる。だが、本番では緊張で声が出ない。沈黙が続く会場に、同志の題目が響く。父は声を絞り出し、最後に「よろしくお願いします!」と叫んだ。
「名演説だね」
そうたたえたのが、隣で見守った池田先生だった。大会後、先生は父に「声佛事」と記した色紙を贈り、「もう大丈夫だ。必ず幸せになるんだよ」と語った。
一家に光が差し込んだ。信心に生き抜く決意が固まり、宮井さんも女子部として前進を始めた。やがて岡山の中国文化会館(当時)で職員として働き、後に泰良さんと結婚。山口での新生活を送る。
78年5月、先生が山口へ。環境が変わり、思うように学会活動ができないことに、宮井さんは悩んでいた。
「今思えば、だらしない信心だったと思います。先生から、“小鳥のような境涯ではいけない”と厳しく指摘をいただきました」
師匠からの叱咤に、中途半端な自分を改めようと決めた。数日後、先生から句をしたためた原稿用紙が届く。
「若鳥よ 中国飛びゆけ 広布旅」
新たな一歩を踏み出した。だが、翌年の春、試練が襲う。42歳の夫が不眠と過労が重なり、情緒不安定に。入院を余儀なくされた。
夫婦で苦しんでいた79年4月21日、先生からの句が届く。
「祈るらむ 君が心の 幸の海」
「ひたすら君の全快を誰よりも待っています」の一文も。3日後、先生は会長を辞任。激動のさなかでの出来事に、夫婦で報恩の人生を固く誓った。
先生の激励は続く。同年11月、宮井さんは神奈川研修道場で先生と懇談する機会があった。先生は、生活のことを気にかけ、励ましを送った。さらに、夫への伝言を託した。
「松江に行った時は、二人で一晩中語りあかそう」
たび重なる師の深き慈愛。夫婦は涙の再出発を果たす。
その後、宮井さんは島根県の婦人部長に。84年5月21日、11年ぶりに先生が島根を訪れる。前年の豪雨災害を乗り越え、出雲での文化祭を大成功で終えた同志をたたえるために、日程を変更しての訪問だった。完成して間もない島根文化会館(当時)に着いた時の思いを、先生は随筆につづっている。
「そこには、見違えるような、喜びに輝き、誇らかに胸を張った同志が待っていてくれた。いうなれば、沈黙的に思われている島根の天地は、新しい人間が、新しい呼吸をしながら、その大地より、新しい笑顔の花が咲き香っていた。東屋があった。無数の菖蒲の花に包まれていた。誇り高き同志の真心がまぶしかった」
来館者のため、設営の責任者を務めていたのが、宮井さんの夫だった。先生は約束を果たし、夫婦を励ました。
松江駅に電車が滑り込んでくる。幼い日の宮井さんは、自宅から見える線路をただじっと眺めていた。
父・浜崎巌さんは酒乱で、母・ゆき江さんは心を病み、争いの絶えない家庭だった。中学校では放課後は教室に残り、帰りたくない気持ちを隠していた。“なぜ自分は生まれてきたのだろう”。そんな苦悩が渦巻いていた。
57年、母が創価学会に入会。2カ月後、家族も続く。父は生き方を改め、一家で信心に励むようになっていく。
浜崎巌さんが信心によって蘇生した姿は、人々の心へ希望を広げた。島根・松江を池田先生が初めて訪れた1961年4月23日。支部長を務めることになった浜崎さんの自宅へ、先生が足を運んだ。「来たよ!」。精悍なまなざし、力強い声。宮井さんは思った。“先生についていけば、私は必ず幸せになれる!”
迎えた松江支部結成大会。読み書きのできない父のため、宮井さんはひらがなとカタカナで原稿を書いていた。その原稿で、父は1週間前から練習を重ねる。だが、本番では緊張で声が出ない。沈黙が続く会場に、同志の題目が響く。父は声を絞り出し、最後に「よろしくお願いします!」と叫んだ。
「名演説だね」
そうたたえたのが、隣で見守った池田先生だった。大会後、先生は父に「声佛事」と記した色紙を贈り、「もう大丈夫だ。必ず幸せになるんだよ」と語った。
一家に光が差し込んだ。信心に生き抜く決意が固まり、宮井さんも女子部として前進を始めた。やがて岡山の中国文化会館(当時)で職員として働き、後に泰良さんと結婚。山口での新生活を送る。
78年5月、先生が山口へ。環境が変わり、思うように学会活動ができないことに、宮井さんは悩んでいた。
「今思えば、だらしない信心だったと思います。先生から、“小鳥のような境涯ではいけない”と厳しく指摘をいただきました」
師匠からの叱咤に、中途半端な自分を改めようと決めた。数日後、先生から句をしたためた原稿用紙が届く。
「若鳥よ 中国飛びゆけ 広布旅」
新たな一歩を踏み出した。だが、翌年の春、試練が襲う。42歳の夫が不眠と過労が重なり、情緒不安定に。入院を余儀なくされた。
夫婦で苦しんでいた79年4月21日、先生からの句が届く。
「祈るらむ 君が心の 幸の海」
「ひたすら君の全快を誰よりも待っています」の一文も。3日後、先生は会長を辞任。激動のさなかでの出来事に、夫婦で報恩の人生を固く誓った。
先生の激励は続く。同年11月、宮井さんは神奈川研修道場で先生と懇談する機会があった。先生は、生活のことを気にかけ、励ましを送った。さらに、夫への伝言を託した。
「松江に行った時は、二人で一晩中語りあかそう」
たび重なる師の深き慈愛。夫婦は涙の再出発を果たす。
その後、宮井さんは島根県の婦人部長に。84年5月21日、11年ぶりに先生が島根を訪れる。前年の豪雨災害を乗り越え、出雲での文化祭を大成功で終えた同志をたたえるために、日程を変更しての訪問だった。完成して間もない島根文化会館(当時)に着いた時の思いを、先生は随筆につづっている。
「そこには、見違えるような、喜びに輝き、誇らかに胸を張った同志が待っていてくれた。いうなれば、沈黙的に思われている島根の天地は、新しい人間が、新しい呼吸をしながら、その大地より、新しい笑顔の花が咲き香っていた。東屋があった。無数の菖蒲の花に包まれていた。誇り高き同志の真心がまぶしかった」
来館者のため、設営の責任者を務めていたのが、宮井さんの夫だった。先生は約束を果たし、夫婦を励ました。

松江支部結成大会の後、池田先生は浜崎支部長宅へ。「ものが言えないんです」「どうやって指揮をとればいいか」との浜崎さん㊥の話を聞き、「声佛事」と色紙につづった(1961年4月23日)
松江支部結成大会の後、池田先生は浜崎支部長宅へ。「ものが言えないんです」「どうやって指揮をとればいいか」との浜崎さん㊥の話を聞き、「声佛事」と色紙につづった(1961年4月23日)

11年ぶりの島根訪問。松江市の旧・島根文化会館の玄関には、1000本のハナショウブが彩り豊かに。この日、池田先生は歴史的な「山光提言」を発表した(1984年5月21日)
11年ぶりの島根訪問。松江市の旧・島根文化会館の玄関には、1000本のハナショウブが彩り豊かに。この日、池田先生は歴史的な「山光提言」を発表した(1984年5月21日)
難との戦いで境涯を開く
難との戦いで境涯を開く
この84年の先生の鳥取・島根訪問は、両県の広布史において、ひときわ輝きを放つ。先生が「山陰」を「山光」と呼んではどうかと提案したのである。
「山陰地方は、東京より、初夏の日没は約30分遅い。また冬は寒く、雪も降るが、山の頂上からふもとまで雪で終日銀色に輝いている。さらに山の幸、海の幸も、都会より新鮮に味わうことができる。こうした意味からも、光り輝く地、つまり『山光』と申し上げたい」
後に「山光提言」と呼ばれる、このスピーチに、鳥取・島根の友は、「気持ちが百八十度変わる」ほどの勇気をもらった。
91年9月8日、先生が出席して第1回「山光総会・音楽祭」が米子文化会館で開催された。同年6月、鳥取が聖教新聞の拡大で日本一を達成。翌7月には、島根が日本一を成し遂げた。
先生は「戦い切った力強さ、境涯を感じた」と語った。さらに、「難来るをもって安楽と意得べきなり」(新1045・全750)との御聖訓を拝し、「“難との戦いで、私は境涯をこんなにも開いた”と言い切れる自身の歴史を」と訴えた。
その指導のままの人生を、宮井さん夫婦は進んだ。宮井さんは松江駅を基点に中国各県を激励に回った。宮井さんの妹の小山潮子さん、下垣みどりさんも、共にリーダーとして友に尽くす。3姉妹の姿を、両親は誰よりも喜び、支えてくれた。
2003年2月。母・ゆき江さんが見たこともないほどうれしそうな表情で、宮井さんに言った。病で入院している父が、こう語ってくれたという。
「わしはな、あんたと一緒になって、ほんに幸せだった。いい子どもたちに恵まれて、ほんに幸せだった」
宮井さんが、見舞いに訪れ、これから上京することを伝えると、父は満面の笑みでこう語った。「先生に、どうかくれぐれもよろしく言っちょいてごせよ」と。数日後、老衰で旅立った。
母はその後、さらに10年間を生き抜いた。亡くなる直前の施設では、浮かない表情だったスタッフの女性に、「悩んでいる顔しているね。南無妙法蓮華経って唱えてごらん。絶対解決するよ」と語った。彼女は信心に消極的な学会員だった。ゆき江さんのにじみ出る優しさに触れ、以来、学会活動に励むようになった。
ある時、先生は宮井さんに語った。「順調ではなかったことがよかったんだよ」。全ての出来事が幸福を深める糧になったと宮井さんは実感する。池田先生が会合で紹介した戸田先生の言葉を心に置いて、今も広布に生きる。
「一生のすべての体験が生きてくるのだ。何ひとつ、塵も残さず、無駄はなかったことが分かるのです。これが妙法の大功徳です」
山光の友は、師の提言を胸に地域に信頼を広げ、歴史を築いてきた。各界の識者からも“山光”という名称への称賛の声が寄せられる。2009年には、島根・隠岐の島町に「山光久見トンネル」が開通した。
先生がともした「山光の精神」は、地域を潤し、未来を歩む世代へと受け継がれている。
この84年の先生の鳥取・島根訪問は、両県の広布史において、ひときわ輝きを放つ。先生が「山陰」を「山光」と呼んではどうかと提案したのである。
「山陰地方は、東京より、初夏の日没は約30分遅い。また冬は寒く、雪も降るが、山の頂上からふもとまで雪で終日銀色に輝いている。さらに山の幸、海の幸も、都会より新鮮に味わうことができる。こうした意味からも、光り輝く地、つまり『山光』と申し上げたい」
後に「山光提言」と呼ばれる、このスピーチに、鳥取・島根の友は、「気持ちが百八十度変わる」ほどの勇気をもらった。
91年9月8日、先生が出席して第1回「山光総会・音楽祭」が米子文化会館で開催された。同年6月、鳥取が聖教新聞の拡大で日本一を達成。翌7月には、島根が日本一を成し遂げた。
先生は「戦い切った力強さ、境涯を感じた」と語った。さらに、「難来るをもって安楽と意得べきなり」(新1045・全750)との御聖訓を拝し、「“難との戦いで、私は境涯をこんなにも開いた”と言い切れる自身の歴史を」と訴えた。
その指導のままの人生を、宮井さん夫婦は進んだ。宮井さんは松江駅を基点に中国各県を激励に回った。宮井さんの妹の小山潮子さん、下垣みどりさんも、共にリーダーとして友に尽くす。3姉妹の姿を、両親は誰よりも喜び、支えてくれた。
2003年2月。母・ゆき江さんが見たこともないほどうれしそうな表情で、宮井さんに言った。病で入院している父が、こう語ってくれたという。
「わしはな、あんたと一緒になって、ほんに幸せだった。いい子どもたちに恵まれて、ほんに幸せだった」
宮井さんが、見舞いに訪れ、これから上京することを伝えると、父は満面の笑みでこう語った。「先生に、どうかくれぐれもよろしく言っちょいてごせよ」と。数日後、老衰で旅立った。
母はその後、さらに10年間を生き抜いた。亡くなる直前の施設では、浮かない表情だったスタッフの女性に、「悩んでいる顔しているね。南無妙法蓮華経って唱えてごらん。絶対解決するよ」と語った。彼女は信心に消極的な学会員だった。ゆき江さんのにじみ出る優しさに触れ、以来、学会活動に励むようになった。
ある時、先生は宮井さんに語った。「順調ではなかったことがよかったんだよ」。全ての出来事が幸福を深める糧になったと宮井さんは実感する。池田先生が会合で紹介した戸田先生の言葉を心に置いて、今も広布に生きる。
「一生のすべての体験が生きてくるのだ。何ひとつ、塵も残さず、無駄はなかったことが分かるのです。これが妙法の大功徳です」
山光の友は、師の提言を胸に地域に信頼を広げ、歴史を築いてきた。各界の識者からも“山光”という名称への称賛の声が寄せられる。2009年には、島根・隠岐の島町に「山光久見トンネル」が開通した。
先生がともした「山光の精神」は、地域を潤し、未来を歩む世代へと受け継がれている。

青と緑の雄大な自然美を臨んで。松江市で4200人の同志との記念撮影を終えた後、池田先生は枕木山へ(1972年9月17日)。中海や名峰・大山などを眺望し、二つの句を詠んだ。「勝鬨を あげたくなるや 枕木山」「右に湖(うみ) 左に海の 青き風」
青と緑の雄大な自然美を臨んで。松江市で4200人の同志との記念撮影を終えた後、池田先生は枕木山へ(1972年9月17日)。中海や名峰・大山などを眺望し、二つの句を詠んだ。「勝鬨を あげたくなるや 枕木山」「右に湖(うみ) 左に海の 青き風」
ご意見・ご感想をお寄せください
【メール】 history@seikyo-np.jp
【ファクス】 03-5360-9618
ご意見・ご感想をお寄せください
【メール】 history@seikyo-np.jp
【ファクス】 03-5360-9618
音声読み上げ