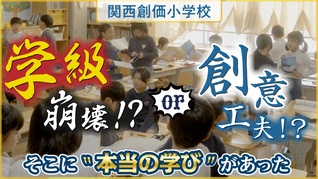【創価学園NAVI】東京創価小学校 「小4の壁」克服の取り組み
【創価学園NAVI】東京創価小学校 「小4の壁」克服の取り組み
2025年3月13日
- 児童の自己肯定感を高める教育
- 「遊び」から「学び」の意欲を伸ばす
- 児童の自己肯定感を高める教育
- 「遊び」から「学び」の意欲を伸ばす
「小4の壁」をご存じだろうか。「9歳の壁」「10歳の壁」ともいわれるこの時期は、心身が大きく成長する一方、学習内容でつまずいたり、友達と自分を比べて、劣等感を抱きやすくなったりする。小4の壁を乗り越えるには、自己肯定感やコミュニケーション力、問題解決力などの「非認知能力」を伸ばすことが重要だと指摘されている。東京創価小学校(小平市、国分寺市)では、この壁に挑む、工夫した取り組みが行われていると聞き、同校を訪れた。
「小4の壁」をご存じだろうか。「9歳の壁」「10歳の壁」ともいわれるこの時期は、心身が大きく成長する一方、学習内容でつまずいたり、友達と自分を比べて、劣等感を抱きやすくなったりする。小4の壁を乗り越えるには、自己肯定感やコミュニケーション力、問題解決力などの「非認知能力」を伸ばすことが重要だと指摘されている。東京創価小学校(小平市、国分寺市)では、この壁に挑む、工夫した取り組みが行われていると聞き、同校を訪れた。

東京創価小学校の取り組み「asobiゼミナール」の一こま。ビー玉はゴールにたどり着くかな? ワクワク!――自分たちで作った「からくり装置」を見つめる児童たち
東京創価小学校の取り組み「asobiゼミナール」の一こま。ビー玉はゴールにたどり着くかな? ワクワク!――自分たちで作った「からくり装置」を見つめる児童たち
ある日の下校前のホームルーム。4年生の教室には、児童の笑顔が広がっていた。
「○○さんは、いつも笑顔でクラスの太陽だよ!」
「○○さん、仲間思いだし、尊敬しています」
一人の児童へ、クラスメートから順番に褒め言葉がかけられていく。照れながらも、ニコっと笑みがこぼれる児童。その後、全員からの励ましの言葉がつづられた手紙が、プレゼントとして贈られた。
これは「褒め言葉のシャワー」(※)と呼ばれる取り組み。褒められる側の児童の自己肯定感が高まるとともに、褒める側の児童も友達の長所を見つけられるようになる。
ある男子児童は、クラスメートから「優しい」「頼りになる」といった、褒め言葉をもらった。「そんなふうに思われているなんて、気付かなかった。うれしくて、自信になりました」と振り返る。
4年生の学年主任の殿崎誠治郎教諭は語る。
「周りと比較して自信をなくし、友達とトラブルを起こしたり、親子関係に変化が現れたりする『小4の壁』は、健全な発達の過程であり、成長のチャンスでもあります」
ある日の下校前のホームルーム。4年生の教室には、児童の笑顔が広がっていた。
「○○さんは、いつも笑顔でクラスの太陽だよ!」
「○○さん、仲間思いだし、尊敬しています」
一人の児童へ、クラスメートから順番に褒め言葉がかけられていく。照れながらも、ニコっと笑みがこぼれる児童。その後、全員からの励ましの言葉がつづられた手紙が、プレゼントとして贈られた。
これは「褒め言葉のシャワー」(※)と呼ばれる取り組み。褒められる側の児童の自己肯定感が高まるとともに、褒める側の児童も友達の長所を見つけられるようになる。
ある男子児童は、クラスメートから「優しい」「頼りになる」といった、褒め言葉をもらった。「そんなふうに思われているなんて、気付かなかった。うれしくて、自信になりました」と振り返る。
4年生の学年主任の殿崎誠治郎教諭は語る。
「周りと比較して自信をなくし、友達とトラブルを起こしたり、親子関係に変化が現れたりする『小4の壁』は、健全な発達の過程であり、成長のチャンスでもあります」
非認知能力を育む
非認知能力を育む
9歳以降の特徴への対応について、文部科学省では「自己肯定感」「自他の尊重と他者への思いやり」「集団における役割の自覚」などを育むことを重視している。
こうした「非認知能力」を伸ばす上で、東京創価小学校では「褒め言葉のシャワー」に加え、2年前から「asobiゼミナール」(遊びゼミ)という活動を行っている。
遊びゼミは月に1度の高学年登校日(土曜)の2時限を使い、遊びを通して、主体的に学びを深めていく取り組みだ。
学年全体で、①鉛筆転がしゲーム②からくり装置作り③昔遊び④泥遊び⑤世界の遊び、に分かれて行う。
遊びゼミには、次の四つのルールが設定されている。
①「いいね」「なるほど」が合言葉(否定しない)
②失敗も大切な学び。全てを楽しもう
③みんなで考え、みんなで楽しむ
④一人も置き去りにしない
――これらは、児童が遊びを楽しみながら、互いの意見や役割を認め合い、協働して課題に取り組むために、大切な約束事だ。
遊びゼミが始まると、児童同士で“どんな遊びができるのか”“どうすればおもしろくなるのか”を話し合い、計画を立てて実行する。
その間、教員たちはあまり口を出さず、見守ることに努める。企画した大城威教諭は「子どもは遊びの天才です。楽しく遊ぶ中で、自然と自尊心と探究心が育まれ、対話が生まれる場をつくりたかったんです」と語っていた。
9歳以降の特徴への対応について、文部科学省では「自己肯定感」「自他の尊重と他者への思いやり」「集団における役割の自覚」などを育むことを重視している。
こうした「非認知能力」を伸ばす上で、東京創価小学校では「褒め言葉のシャワー」に加え、2年前から「asobiゼミナール」(遊びゼミ)という活動を行っている。
遊びゼミは月に1度の高学年登校日(土曜)の2時限を使い、遊びを通して、主体的に学びを深めていく取り組みだ。
学年全体で、①鉛筆転がしゲーム②からくり装置作り③昔遊び④泥遊び⑤世界の遊び、に分かれて行う。
遊びゼミには、次の四つのルールが設定されている。
①「いいね」「なるほど」が合言葉(否定しない)
②失敗も大切な学び。全てを楽しもう
③みんなで考え、みんなで楽しむ
④一人も置き去りにしない
――これらは、児童が遊びを楽しみながら、互いの意見や役割を認め合い、協働して課題に取り組むために、大切な約束事だ。
遊びゼミが始まると、児童同士で“どんな遊びができるのか”“どうすればおもしろくなるのか”を話し合い、計画を立てて実行する。
その間、教員たちはあまり口を出さず、見守ることに努める。企画した大城威教諭は「子どもは遊びの天才です。楽しく遊ぶ中で、自然と自尊心と探究心が育まれ、対話が生まれる場をつくりたかったんです」と語っていた。

泥遊びに夢中になる児童たち。スコップで砂を掘り、山を作っていると、「ここに穴を掘ってみない?」と、遊びがさらに広がる
泥遊びに夢中になる児童たち。スコップで砂を掘り、山を作っていると、「ここに穴を掘ってみない?」と、遊びがさらに広がる
ある男子児童は、遊びゼミを通して、協力することの大切さを実感した。特に印象に残っているのは、泥遊びでの出来事だという。
初めは、皆で大きな砂山を作ることに夢中になっていた。さらに試行錯誤を繰り返すうち、“水路を作ったほうが、もっと皆で楽しめるんじゃないか”と思うようになり、グループで話し合って、計画を変更。「あんなに協力できたのは初めて」と、うれしそうに話してくれた。
彼は、遊びを通して学ぶ意欲も高まったと言う。
「算数や図工、道徳など、授業で学んだことが遊びゼミでは生かせるんです。だから、日頃の勉強も、もっと頑張ろうと思うようになりました」
ある女子児童は友達と、からくり装置作りに取り組んでいた。
「みんなで協力して、ビー玉をゴールまで転がすコースを完成させた時は、大きな達成感がありました。遊びゼミで、他のクラスにたくさん友達ができて、うれしかったです!」
友達と連携を取り、一つのものを作る過程で、役割分担の大切さを学んだという。
「みんなで一緒に何かをやろうとすると、混乱することもあります。でも、自然と役割分担ができていき、スムーズに進むようになりました。遊びゼミでも、委員会活動などでも、役割分担は大切だと気付きました」
彼女が入学した4年前はコロナ禍のため、一部、オンラインで授業を行うなど、学校生活が制限されていた。
その分、他のクラスの児童と直接交流を深める遊びゼミの経験は、大きな喜びになっている。
「毎日、学校に行くのが楽しみです!」と満面の笑みだった。
ある男子児童は、遊びゼミを通して、協力することの大切さを実感した。特に印象に残っているのは、泥遊びでの出来事だという。
初めは、皆で大きな砂山を作ることに夢中になっていた。さらに試行錯誤を繰り返すうち、“水路を作ったほうが、もっと皆で楽しめるんじゃないか”と思うようになり、グループで話し合って、計画を変更。「あんなに協力できたのは初めて」と、うれしそうに話してくれた。
彼は、遊びを通して学ぶ意欲も高まったと言う。
「算数や図工、道徳など、授業で学んだことが遊びゼミでは生かせるんです。だから、日頃の勉強も、もっと頑張ろうと思うようになりました」
ある女子児童は友達と、からくり装置作りに取り組んでいた。
「みんなで協力して、ビー玉をゴールまで転がすコースを完成させた時は、大きな達成感がありました。遊びゼミで、他のクラスにたくさん友達ができて、うれしかったです!」
友達と連携を取り、一つのものを作る過程で、役割分担の大切さを学んだという。
「みんなで一緒に何かをやろうとすると、混乱することもあります。でも、自然と役割分担ができていき、スムーズに進むようになりました。遊びゼミでも、委員会活動などでも、役割分担は大切だと気付きました」
彼女が入学した4年前はコロナ禍のため、一部、オンラインで授業を行うなど、学校生活が制限されていた。
その分、他のクラスの児童と直接交流を深める遊びゼミの経験は、大きな喜びになっている。
「毎日、学校に行くのが楽しみです!」と満面の笑みだった。
楽しく自然に
楽しく自然に
児童のコミュニケーション力や学習意欲などを育んできた遊びゼミ。さらに昨夏、遊びゼミの発展形となる「夏期教室」を実施した。
4年生対象の宿泊行事で、2日間かけて、おにごっこ、プール遊び、肝試し、花火、校内かくれんぼなどを行う。布団の準備など、生活も共にする中で、児童は友情を深め、協調性を育んだ。
児童は口々に語る。
「夜の学校に泊まるのは初めてで、最初は少し不安でしたが、友達と一緒だったので大丈夫でした」
「肝試しは怖かったけれど、みんなで力を合わせてクリアできた時は、最高の気分でした。花火も、一緒にできて、うれしかったです」
夏期教室が「楽しくて、一年で一番忘れられない思い出になりました」と言う児童も少なくない。
殿崎教諭は「遊びによって生まれる自然な会話や試行錯誤の中から、子どもたちは多くのことを学び取っていると感じます。表情が豊かになり、発言も積極的になったのはもちろん、友達との関わり方も前向きに変わりました」と振り返る。
児童のコミュニケーション力や学習意欲などを育んできた遊びゼミ。さらに昨夏、遊びゼミの発展形となる「夏期教室」を実施した。
4年生対象の宿泊行事で、2日間かけて、おにごっこ、プール遊び、肝試し、花火、校内かくれんぼなどを行う。布団の準備など、生活も共にする中で、児童は友情を深め、協調性を育んだ。
児童は口々に語る。
「夜の学校に泊まるのは初めてで、最初は少し不安でしたが、友達と一緒だったので大丈夫でした」
「肝試しは怖かったけれど、みんなで力を合わせてクリアできた時は、最高の気分でした。花火も、一緒にできて、うれしかったです」
夏期教室が「楽しくて、一年で一番忘れられない思い出になりました」と言う児童も少なくない。
殿崎教諭は「遊びによって生まれる自然な会話や試行錯誤の中から、子どもたちは多くのことを学び取っていると感じます。表情が豊かになり、発言も積極的になったのはもちろん、友達との関わり方も前向きに変わりました」と振り返る。

昔遊びの羽根突きに挑戦! 「頑張れ」「ナイス!」――羽根を打ち合うたびに児童たちの仲が自然と深まっていく
昔遊びの羽根突きに挑戦! 「頑張れ」「ナイス!」――羽根を打ち合うたびに児童たちの仲が自然と深まっていく
創立者・池田先生は、学校教育の在り方について述べている。
「人間の成長にとって重要なことは、自らの力で考え、豊かな価値を創造しゆく、知性と人格の力を培うことです。その意味で、子どもたちが楽しく生活しながら、そうした力を自然のうちに身につけることのできる学習の場が、学校でなくてはならない」
東京創価小学校の教員は、遊びゼミなど、小4の壁への対策を考えるに当たり、こうした先生の指針を形にしようと模索してきた。
殿崎教諭は力を込める。
「“どうすれば子どもの可能性を引き出せるのか”を絶えず教員同士で議論しながら、取り組んでいきます」
「子どもの幸福」を第一とする人間教育の実現へ――東京創価小学校は、一人一人の無限の可能性を輝かせる教育に挑んでいる。
【※褒め言葉のシャワー】 教育実践研究家の菊池省三氏が提唱する取り組み。各地の小学校で導入され、児童の自己肯定感を高める効果が報告されている。
※ご感想をお寄せください。
kansou@seikyo-np.jp
※創価学園NAVIのバックナンバーが無料で読めます(会員登録は不要です)
https://www.seikyoonline.com/rensaimatome/gakuennavi.html
創立者・池田先生は、学校教育の在り方について述べている。
「人間の成長にとって重要なことは、自らの力で考え、豊かな価値を創造しゆく、知性と人格の力を培うことです。その意味で、子どもたちが楽しく生活しながら、そうした力を自然のうちに身につけることのできる学習の場が、学校でなくてはならない」
東京創価小学校の教員は、遊びゼミなど、小4の壁への対策を考えるに当たり、こうした先生の指針を形にしようと模索してきた。
殿崎教諭は力を込める。
「“どうすれば子どもの可能性を引き出せるのか”を絶えず教員同士で議論しながら、取り組んでいきます」
「子どもの幸福」を第一とする人間教育の実現へ――東京創価小学校は、一人一人の無限の可能性を輝かせる教育に挑んでいる。
【※褒め言葉のシャワー】 教育実践研究家の菊池省三氏が提唱する取り組み。各地の小学校で導入され、児童の自己肯定感を高める効果が報告されている。
※ご感想をお寄せください。
kansou@seikyo-np.jp
※創価学園NAVIのバックナンバーが無料で読めます(会員登録は不要です)
https://www.seikyoonline.com/rensaimatome/gakuennavi.html