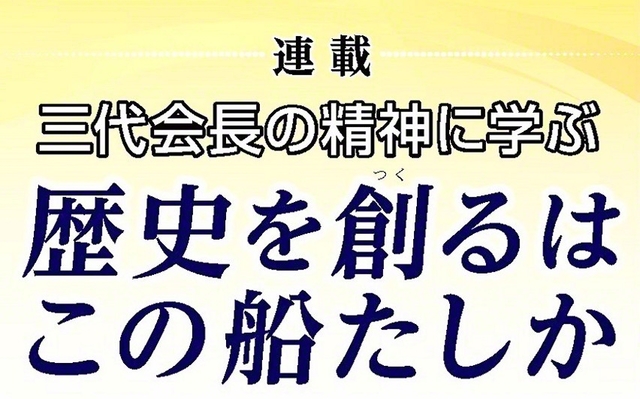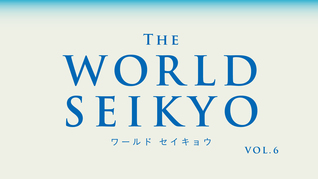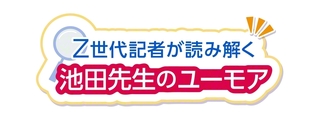〈連載 三代会長の精神に学ぶ〉第42回 池田先生「第1回SGI世界青年部総会」でのスピーチ㊦
〈連載 三代会長の精神に学ぶ〉第42回 池田先生「第1回SGI世界青年部総会」でのスピーチ㊦
2025年9月2日
- 《歴史を創るは この船たしか》
- 創価ルネサンスの運動で世界広布が前進
- 仏の生命は“凡夫の振る舞い”の中で輝く
- 《歴史を創るは この船たしか》
- 創価ルネサンスの運動で世界広布が前進
- 仏の生命は“凡夫の振る舞い”の中で輝く
(㊤はこちら)
池田先生が東欧に足を運んだのは、ソ連への初訪問(1974年9月)に先駆けること、10年も前の出来事であった。
東欧に続き、東側陣営の中心だったソ連に第一歩をしるすに当たり、どれだけの覚悟をもって臨んだのか――。
池田先生は、ソ連崩壊の翌年(1992年9月)に行われた第1回SGI世界青年部総会で、当時の真情をこう述懐した。
「経典では、現代では旧ソ連の一部が含まれるとも考えられる北方の地域(鬱単越。古代インドの世界観で須弥山を中心とした四大洲のうち北方の世界)は、仏法には縁がないとされていた。
しかし、私は確信していた。――大聖人の仏法は、全世界、全宇宙の大法である。大聖人の大慈悲は、全世界の民衆へ、もれなく向けられているはずだ、と」
「私には揺るがぬ信念があった。
ソ連にも人間がいる。人間がいるかぎり、私は行く。民衆がいるところ、すべて私の法戦の舞台だ、と。ゆえに、まず第一歩を踏み出した。そして信義を貫いた――」
この総会でのスピーチで池田先生は、「大聖人の弟子として初めて、ソ連に行った」と万鈞の重みを持つ言葉を述べているが、1964年10月に東欧諸国を初訪問した時の覚悟も全く同じだったに違いない。
当時、ハンガリーの首都ブダペストには、動乱での市街戦によって傷ついた建物が残ったままだった。その建物に目を留めた池田先生は車から降りて、いくつもの弾痕が刻まれた石壁をじっと見つめた。
共産圏の国に滞在できたのはわずか2日余りだったが、現地の視察を通じて人類の平和共存を築くための方途について思索を深めた池田先生は、東欧諸国の民衆の幸福と安穏を願い、ホテルの一室で長時間にわたって唱題を続けたのである。
(㊤はこちら)
池田先生が東欧に足を運んだのは、ソ連への初訪問(1974年9月)に先駆けること、10年も前の出来事であった。
東欧に続き、東側陣営の中心だったソ連に第一歩をしるすに当たり、どれだけの覚悟をもって臨んだのか――。
池田先生は、ソ連崩壊の翌年(1992年9月)に行われた第1回SGI世界青年部総会で、当時の真情をこう述懐した。
「経典では、現代では旧ソ連の一部が含まれるとも考えられる北方の地域(鬱単越。古代インドの世界観で須弥山を中心とした四大洲のうち北方の世界)は、仏法には縁がないとされていた。
しかし、私は確信していた。――大聖人の仏法は、全世界、全宇宙の大法である。大聖人の大慈悲は、全世界の民衆へ、もれなく向けられているはずだ、と」
「私には揺るがぬ信念があった。
ソ連にも人間がいる。人間がいるかぎり、私は行く。民衆がいるところ、すべて私の法戦の舞台だ、と。ゆえに、まず第一歩を踏み出した。そして信義を貫いた――」
この総会でのスピーチで池田先生は、「大聖人の弟子として初めて、ソ連に行った」と万鈞の重みを持つ言葉を述べているが、1964年10月に東欧諸国を初訪問した時の覚悟も全く同じだったに違いない。
当時、ハンガリーの首都ブダペストには、動乱での市街戦によって傷ついた建物が残ったままだった。その建物に目を留めた池田先生は車から降りて、いくつもの弾痕が刻まれた石壁をじっと見つめた。
共産圏の国に滞在できたのはわずか2日余りだったが、現地の視察を通じて人類の平和共存を築くための方途について思索を深めた池田先生は、東欧諸国の民衆の幸福と安穏を願い、ホテルの一室で長時間にわたって唱題を続けたのである。

池田先生の東欧訪問60周年を祝賀して、昨年10月に開催された欧州SGIの新世紀第1回東欧リーダー研修会(ウィーンのオーストリア文化センターで)
池田先生の東欧訪問60周年を祝賀して、昨年10月に開催された欧州SGIの新世紀第1回東欧リーダー研修会(ウィーンのオーストリア文化センターで)
大聖人の弟子として東欧の地で深い祈りを捧げた日から28星霜――。ハンガリーやチェコスロバキアの友も迎え、1992年6月にドイツで行われた「中欧・東欧・ロシア合同会議」で、池田先生は和歌を贈った。
「東欧の
友と相見る
不思議さは
大聖人の
たしかな子等かと」
この時のヨーロッパ指導において、池田先生が重ねて訴えたのは、“仏とは普通の人間と別の存在ではなく、仏法の世界には特別な権威も階級もない”との点だった。
合同会議の前日に開催されたヨーロッパ代表者会議では、弟子の阿那律のために針に糸を通した釈尊の逸話に触れながら、次のように呼びかけた。
「仏法の教団は本来、釈尊を中心とした、いわば『人間教育の集団』であったと考えられる。特別な権威とか階級とか形式とかではなく、みずみずしく、ともに成長していく“人間錬磨の広場”であった、と。
一次元からいえば、後世、聖職者によってゆがめられた教団を、そうした原点の姿に立ち返らせ、人間尊厳の連帯をつくろうとされたのが、日蓮大聖人であられたと拝される。その御精神をまっすぐに受け継いでいるのが、わがSGIである」
また、イタリア青年部総会では、“支配も服従も必要としない人間が幸福で偉大である”と強調した文豪ゲーテの言葉を通して、こう語った。
「人を『支配』し、苦しめもしない。人に『支配』され、苦しめられたままでもない。自分は自分らしく、人々と平等に、楽しく、そして仲良く価値の世界を広げていく。その人こそ偉大であり、幸福である。これがSGIの心でもある」と。
大聖人の弟子として東欧の地で深い祈りを捧げた日から28星霜――。ハンガリーやチェコスロバキアの友も迎え、1992年6月にドイツで行われた「中欧・東欧・ロシア合同会議」で、池田先生は和歌を贈った。
「東欧の
友と相見る
不思議さは
大聖人の
たしかな子等かと」
この時のヨーロッパ指導において、池田先生が重ねて訴えたのは、“仏とは普通の人間と別の存在ではなく、仏法の世界には特別な権威も階級もない”との点だった。
合同会議の前日に開催されたヨーロッパ代表者会議では、弟子の阿那律のために針に糸を通した釈尊の逸話に触れながら、次のように呼びかけた。
「仏法の教団は本来、釈尊を中心とした、いわば『人間教育の集団』であったと考えられる。特別な権威とか階級とか形式とかではなく、みずみずしく、ともに成長していく“人間錬磨の広場”であった、と。
一次元からいえば、後世、聖職者によってゆがめられた教団を、そうした原点の姿に立ち返らせ、人間尊厳の連帯をつくろうとされたのが、日蓮大聖人であられたと拝される。その御精神をまっすぐに受け継いでいるのが、わがSGIである」
また、イタリア青年部総会では、“支配も服従も必要としない人間が幸福で偉大である”と強調した文豪ゲーテの言葉を通して、こう語った。
「人を『支配』し、苦しめもしない。人に『支配』され、苦しめられたままでもない。自分は自分らしく、人々と平等に、楽しく、そして仲良く価値の世界を広げていく。その人こそ偉大であり、幸福である。これがSGIの心でもある」と。

1992年6月、フィレンツェのイタリア文化会館で行われた第1回イタリア青年部総会。フィレンツェは、14世紀以降に広がった文化運動であるルネサンスの発祥の地。池田先生は、冷戦後の欧州の新たな前進を祝福しながら、「本日の総会は『創価ルネサンスの勝利』の歌を、世界へ、そして万年の未来へ轟かせゆく歴史的な意義をもっている」とスピーチ。総会に集った青年たちを激励した
1992年6月、フィレンツェのイタリア文化会館で行われた第1回イタリア青年部総会。フィレンツェは、14世紀以降に広がった文化運動であるルネサンスの発祥の地。池田先生は、冷戦後の欧州の新たな前進を祝福しながら、「本日の総会は『創価ルネサンスの勝利』の歌を、世界へ、そして万年の未来へ轟かせゆく歴史的な意義をもっている」とスピーチ。総会に集った青年たちを激励した
その上で、池田先生が日本に帰国した後、仏法の人間主義を巡る指導の一つの集大成として語ったのが、同年9月に行われた第1回SGI世界青年部総会でのスピーチだった。
「御本仏日蓮大聖人は、『人間』そのもの、『凡夫』そのものの御振る舞いであられた。だからこそ偉大なのである。釈尊も人間そのものであった。だからこそ偉いのである」
「仏というと、何か特別の金ピカに光る絶対者のようなイメージが広められているが、それは後世の人が、仏の偉大さを強調するなかで、つくられていった表現であり、一つの象徴といえよう。
ゆえに仏法者は、『偉大なる凡夫』をめざして生きていくことが正しい。神秘めかして自分を特別な存在のように見せかけるのは、そのこと自体、にせ者の証拠なのである」
偽りの権威に惑わされて、生き方を誤ることがあってはならない。一人一人が「偉大なる凡夫」として人生を歩み抜き、悩める友のために仏界の生命を涌現させて希望と勇気を灯していくことに、創価学会とSGIの根本精神があると、池田先生は高らかに宣言したのだ。
冷戦終結後、池田先生の指導を源泉にして進められた「創価ルネサンス」の運動――。
その歓喜と確信あふれる信仰実践を通じて、世界広宣流布は力強く前進し、当時115カ国・地域だったSGIの陣容は、192カ国・地域にまで大発展を遂げたのである。
その上で、池田先生が日本に帰国した後、仏法の人間主義を巡る指導の一つの集大成として語ったのが、同年9月に行われた第1回SGI世界青年部総会でのスピーチだった。
「御本仏日蓮大聖人は、『人間』そのもの、『凡夫』そのものの御振る舞いであられた。だからこそ偉大なのである。釈尊も人間そのものであった。だからこそ偉いのである」
「仏というと、何か特別の金ピカに光る絶対者のようなイメージが広められているが、それは後世の人が、仏の偉大さを強調するなかで、つくられていった表現であり、一つの象徴といえよう。
ゆえに仏法者は、『偉大なる凡夫』をめざして生きていくことが正しい。神秘めかして自分を特別な存在のように見せかけるのは、そのこと自体、にせ者の証拠なのである」
偽りの権威に惑わされて、生き方を誤ることがあってはならない。一人一人が「偉大なる凡夫」として人生を歩み抜き、悩める友のために仏界の生命を涌現させて希望と勇気を灯していくことに、創価学会とSGIの根本精神があると、池田先生は高らかに宣言したのだ。
冷戦終結後、池田先生の指導を源泉にして進められた「創価ルネサンス」の運動――。
その歓喜と確信あふれる信仰実践を通じて、世界広宣流布は力強く前進し、当時115カ国・地域だったSGIの陣容は、192カ国・地域にまで大発展を遂げたのである。
<語句解説>
ソ連崩壊 冷戦終結に伴い、ソ連を構成する共和国の間で独立を求める動きが強まる中、1991年12月、エリツィン大統領が率いるロシアなどが中心となり、独立国家共同体(CIS)を創設。ソビエト共産党の解体や、ソ連のゴルバチョフ大統領の辞任を経て、1922年の建国以来、69年間に及ぶソ連の歴史が幕を閉じた。
阿那律 釈尊の十大弟子の一人。眠りを断って修行を続けたために失明したといわれる。ある時、阿那律が衣のほころびを縫おうとして、“だれか、私のために針に糸を通してくれる者はいないであろうか”とつぶやいた。その際、釈尊が近づいてきて針に糸を通したという話が、仏典に記されている。
<語句解説>
ソ連崩壊 冷戦終結に伴い、ソ連を構成する共和国の間で独立を求める動きが強まる中、1991年12月、エリツィン大統領が率いるロシアなどが中心となり、独立国家共同体(CIS)を創設。ソビエト共産党の解体や、ソ連のゴルバチョフ大統領の辞任を経て、1922年の建国以来、69年間に及ぶソ連の歴史が幕を閉じた。
阿那律 釈尊の十大弟子の一人。眠りを断って修行を続けたために失明したといわれる。ある時、阿那律が衣のほころびを縫おうとして、“だれか、私のために針に糸を通してくれる者はいないであろうか”とつぶやいた。その際、釈尊が近づいてきて針に糸を通したという話が、仏典に記されている。
※次回(第43回)は10月6日に配信予定
※次回(第43回)は10月6日に配信予定
池田先生 「第1回SGI世界青年部総会」でのスピーチ (1992年9月)
仏とは、最高の「人間」である。決して「人間」以上の存在なのではない。(中略)
大聖人は、弘安元年(一二七八年)、身延の山で、「今年は異常に寒い」とおっしゃり、土地の古老たちにたずねてみたら、八十、九十、百歳になる老人も「昔から、これほど寒かったことはありません」と言っていたと書かれている。
山の中の庶民と、何のへだてもなく「寒いね」「こんなことは、いまだかつてありません」と、和やかに語らっておられる。これが御本仏の世界なのである。(中略)
釈尊も、旅から旅への布教の人生の最後に、ある村(ベールヴァ村)で病気になり、侍者の阿難に、私の体は、もうボロボロなんだよ、と告げている。ありのままの人間の姿であり、行動であった。
仏というと、何か特別の金ピカに光る絶対者のようなイメージが広められているが、それは後世の人が、仏の偉大さを強調するなかで、つくられていった表現であり、一つの象徴といえよう。
◇
経典では、現代では旧ソ連の一部が含まれるとも考えられる北方の地域(鬱単越。古代インドの世界観で須弥山を中心とした四大洲のうち北方の世界)は、仏法には縁がないとされていた。
しかし、私は確信していた。――大聖人の仏法は、全世界、全宇宙の大法である。大聖人の大慈悲は、全世界の民衆へ、もれなく向けられているはずだ、と。
ゆえに、私は、大聖人の弟子として初めて、ソ連に行った。(中略)
ソ連にも人間がいる。人間がいるかぎり、私は行く。民衆がいるところ、すべて私の法戦の舞台だ、と。ゆえに、まず第一歩を踏み出した。そして信義を貫いた――。
あれから十八年。今や、ロシアをはじめ旧ソ連にも、仏法への理解と共感は大きく広がった。(中略)
どうか決してあせることなく、朗らかに皆をリードし、楽しく進んでいっていただきたい。末法は万年である。悠々と進んでいきましょう!
(『池田大作全集』第81巻)
池田先生 「第1回SGI世界青年部総会」でのスピーチ (1992年9月)
仏とは、最高の「人間」である。決して「人間」以上の存在なのではない。(中略)
大聖人は、弘安元年(一二七八年)、身延の山で、「今年は異常に寒い」とおっしゃり、土地の古老たちにたずねてみたら、八十、九十、百歳になる老人も「昔から、これほど寒かったことはありません」と言っていたと書かれている。
山の中の庶民と、何のへだてもなく「寒いね」「こんなことは、いまだかつてありません」と、和やかに語らっておられる。これが御本仏の世界なのである。(中略)
釈尊も、旅から旅への布教の人生の最後に、ある村(ベールヴァ村)で病気になり、侍者の阿難に、私の体は、もうボロボロなんだよ、と告げている。ありのままの人間の姿であり、行動であった。
仏というと、何か特別の金ピカに光る絶対者のようなイメージが広められているが、それは後世の人が、仏の偉大さを強調するなかで、つくられていった表現であり、一つの象徴といえよう。
◇
経典では、現代では旧ソ連の一部が含まれるとも考えられる北方の地域(鬱単越。古代インドの世界観で須弥山を中心とした四大洲のうち北方の世界)は、仏法には縁がないとされていた。
しかし、私は確信していた。――大聖人の仏法は、全世界、全宇宙の大法である。大聖人の大慈悲は、全世界の民衆へ、もれなく向けられているはずだ、と。
ゆえに、私は、大聖人の弟子として初めて、ソ連に行った。(中略)
ソ連にも人間がいる。人間がいるかぎり、私は行く。民衆がいるところ、すべて私の法戦の舞台だ、と。ゆえに、まず第一歩を踏み出した。そして信義を貫いた――。
あれから十八年。今や、ロシアをはじめ旧ソ連にも、仏法への理解と共感は大きく広がった。(中略)
どうか決してあせることなく、朗らかに皆をリードし、楽しく進んでいっていただきたい。末法は万年である。悠々と進んでいきましょう!
(『池田大作全集』第81巻)
音声読み上げ